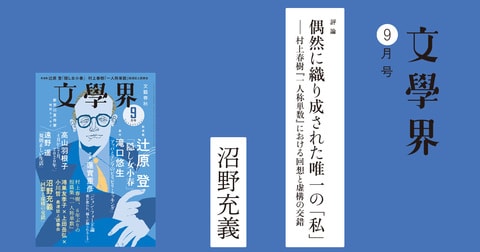三島由紀夫の戯曲は(あるいは小説は)なぜ上演され続けているのか。作品の固有性をひとまず無視して身も蓋もない言い方をしてしまえば、それはおそらく三島の言葉が「かっこいい」からだろう。
意地の悪い見方をするならば、ひとたび言葉を発することさえできてしまえば「格好がついてしまう」三島作品は俳優を見せるのに都合がいいのだ。三島の言葉には自立する強度があり、格調高い言葉を舞台上で朗々と発する俳優はそれだけで十分に見るに値するだろう。だが、言葉を発するというただそれだけのことが何と難しいことか。三島の言葉の前にあえなく敗北し、見るに耐えない無残な結果に終わる上演は無数にある。それだけにより一層、舞台で三島の言葉を発するという挑戦は取り組みがいのあるものとなり、観客はそれを成し遂げた俳優を称賛をもって迎えることになる。だが、ここに一つの罠がある。
三島作品の上演は「かっこいい」だけではダメなのだ。三島作品ではしばしば登場人物が相反する二極――たとえばエロスとタナトス――のあいだで引き裂かれるさまが、あるいはそれらが対立し、ときに止揚に至るさまが描かれる。このとき重要なのはもちろん相反する二極のあいだに生じる運動であり、その先に到来する決裂や止揚のカタルシスなのだが、「かっこいい」だけの舞台では、相反するはずの二極が均質な「かっこよさ」のなかに塗り込められてしまう。なるほど、それでも俳優によって語られる言葉のなかには相反する二極の対立が、決裂が、止揚があるだろう。だがそれはあくまで言葉でしかない。概念でしかない。ならば戯曲なり小説なりを読めば済む話だ。
あるいは、並外れた技量を持つ俳優によって発せられることによってこそ、それらは舞台の上に立ち上がるのだという主張もあろう。しかし三島の言葉に正面から取り組むならば、それを発する俳優がその格調の高さから逃れることはほとんど不可能である。ここに三島作品を上演することのジレンマがある。三島作品の上演を成功させるためには、俳優はまず大前提としてその言葉を十全に発するという困難を成し遂げなければならない。だが一度それが成された途端、俳優はその磁場に取り込まれ、自らもまたある種の「格調の高さ」をまとい、それは上演の全体を覆うトーンとなる。相反する二極のあいだに生じるはずの苛烈なまでの葛藤はこうして「かっこよさ」のオブラートに包まれ、結果、安全な見世物となる。だから三島作品の上演は退屈なのだ。
いかにしてその退屈な「かっこよさ」から逃れるか。そこにあるはずの複雑さをいかに舞台に立ち上げるか。観客を安全圏から引きずり出すか。近年の三島作品の上演からいくつかのケースを見ていきたい。