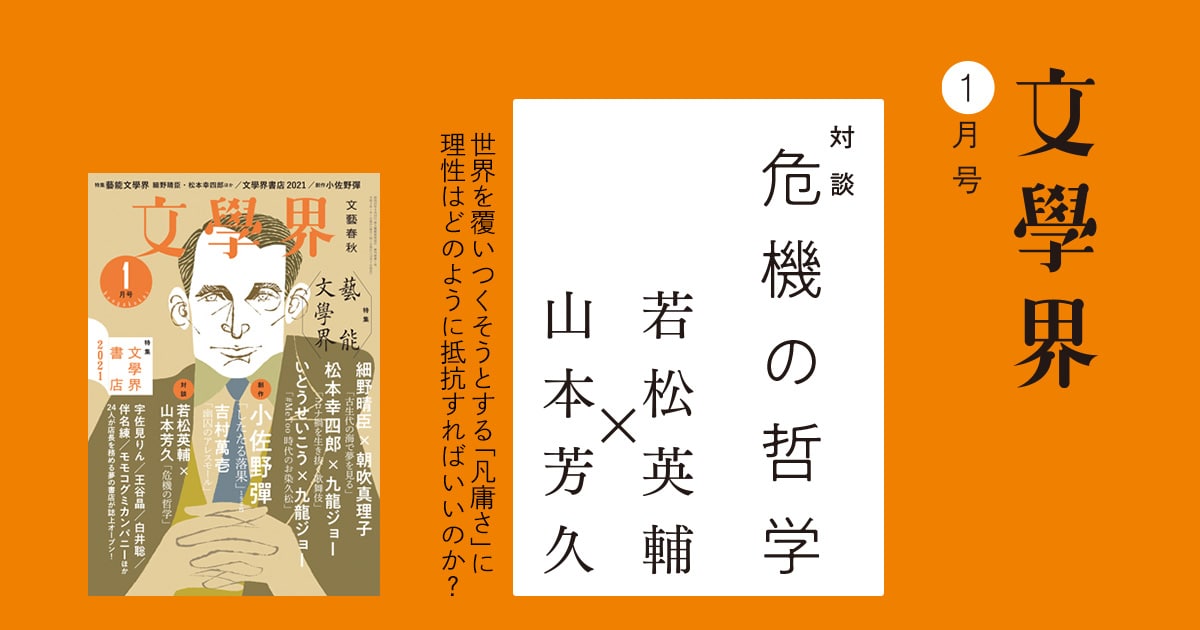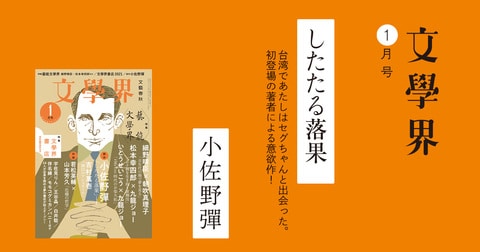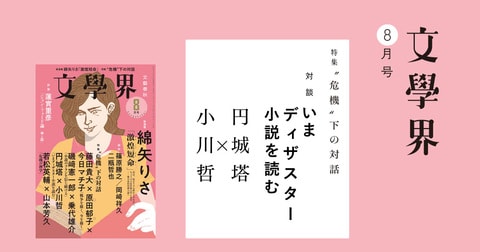世界を覆い尽くそうとする「凡庸さ」に、理性はどのように抵抗すればいいのか。
『キリスト教講義』のコンビが再び結集し、ハンナ・アーレントをはじめとする哲学者たちの言葉から叡智を汲み取る。

アウグスティヌスとアーレント
山本 前回の対談(文學界八月号)は、危機の神学というテーマで『新約聖書』の「ルカ福音書」から「善いサマリア人」のたとえ、『旧約聖書』の「出エジプト記」から「神の名」についてのテクストを紹介して、「危機の中でもともにいてくださる神」という神観が一貫しているという話をしました。また、半分ぐらいは、西ローマ帝国における蛮族の侵入という危機的状況を背景に執筆されたアウグスティヌスの『神の国』と、彼の個人的な危機についての有名な記述が見出される『告白』について論じました。
若松 今回「危機の哲学」を語る上でも、アウグスティヌスはキーパーソンのひとりになると思っています。彼は、神学と哲学の間に立つ人であり、後世においてその両方に、さらには文学にまでも大きな影響力を与え続けた人でもある。
さらに、今、彼の言葉を読むことが重要なのには、もう一つ理由があります。危機の時代にとても重要なのが、「凡庸なる悪」という言葉を残したハンナ・アーレントの哲学です。ご存知のとおり、彼女の初期の重要な仕事である博士論文が、『アウグスティヌスの愛の概念』(一九二九年)です。
私たちは今、とても凡庸さが際立った時代に入ってきている。凡庸なるものへの対処が十分でないとき、あることを契機に容易に状況は「悪」に飲み込まれていく。「悪」は凡庸な事象を飲み込みながら肥大化していくというべきかもしれません。アーレントはそこに警鐘を鳴らした。彼女はこんな言葉を残しています。「〈より小さな悪〉を実行した人は、すぐに自分が悪を選択したことを忘れてしまう」(「独裁体制のもとでの個人の責任」『責任と判断』中山元訳)
哲学は理性の責務だけではなく、理性の限界を探り当てようとする責務もまた担っている。しかし現代哲学は、人間理性の可能性をどこまでも追求し、理性で世界を覆い隠そうとしてきた。理性を超えるものを緩やかに排除さえしていった。その結果、人間の愚劣さが際立つかたちで残ったともいえる。
『アウグスティヌスの愛の概念』の中心的問題にあるのが愛と永遠、さらには隣人の問題です。こうした主題を論究することは現代ではとても難しくなってきています。しかし、愛も永遠も隣人も、その重みはやっぱり変わらない。
山本 アウグスティヌスはまさに、神学と哲学の接点にいて、両方に対して現代に至るまで大きな影響を与え続けている巨人です。哲学において、特に危機という観点から、彼が与えてきた大きな影響を見るうえで糸口になるのはやはり、『告白』の第四巻、親友が亡くなる箇所です。「この〔友を亡くした〕かなしみによって、私の心はすっかり暗くなり、目につくものはすべて死となってしまった」(山田晶訳、中央公論社、一九六八年)。その結果、「いまや、自分自身が、自分にとって大きな謎となってしまいました」。アーレントのアウグスティヌス論では、序文をはじめとして、この言葉が複数回引用されています。アウグスティヌスの原体験を取り出そうとすると必ずこの一文に行かざるをえない。