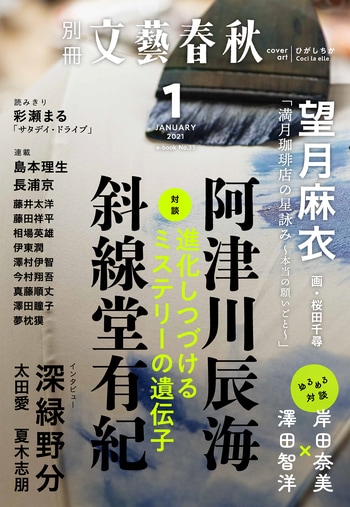彼らは、英語の難問奇問を出すことで知られている大学の過去問題を持ってきて「ちょっと読んでくれんかい」などと安永に頼むのだ。いくら英語圏で育ったとはいえ、つい先日まで中学生だった安永が、受験英語をすらすらと読めるわけもない。しかも部屋に持ち込まれる英文は難解そのもの。読めなくてつっかえる安永を表向きは慰めて帰る三年生たちが、内心で彼を馬鹿にしていることは明らかだった。
安永は、彼らよりずっと恵まれている。
日本どころか、九州の中心からも離れた鹿児島の、さらに周辺部から集まってきた寮生たちは、街から離れた寮に閉じこもって、毎日五時間も、無言で受験勉強に打ち込んでいる。相性がいいわけでもない他の学年の学生と部屋を共有し、勉強に関係のない私物は全て、畳一枚分の二段ベッドの枕元に押し込んでいる。二年生、三年生になれば少しは楽になるとはいえ、こんな生活に耐える理由は、大学に行くためなのだ。
過疎化の進んだ郡部や離島にある高校の学力低下は深刻だ。倍率が1.0を下回る高校では、就職に向けて三桁の掛け算や分数の足し算をやり直す。そんな教室では、大学受験に必要な三角関数や微分積分は学べない。
彼らが直面している事態は、学力の格差だけではない。
マモルもまた、ここに来た理由がある。
鹿児島の周辺部では比較的マシな高校のある指宿市出身のマモルが、南郷高校の理数科を選んだのは、経済的な理由からだった。父が経営していたホテルは、四年前の感染症流行で経営破綻してしまった。廃業の処理すらできず、解雇されてもなお出勤してくるホテルマンたちと部屋を片付けていた一家を助けてくれたのは、東京資本のホテルチェーンだった。
看板をかけ直したホテルは、夏から始まった政府のキャンペーンのおかげで息を吹き返し、以前よりも部屋は埋まるようになった。
しかし、雇われ経営者になった父の収入は激減し、マモルの将来も変わってしまった。
父はマモルを東京の私大に、それも語学に強い学校に行かせたいと言っていた。そこから中国に留学させて、増えつつあった中国人観光客向けにホテルを生まれ変わらせるつもりだった。小学生だったマモルは、そんな父の言葉を裏付けるかのように、日々増えていく中国からの観光客を見ながら、いずれ自分の手でホテルを経営するのだろうと考えていた。
だが、もうそんな夢を見ることはできなくなった。サラリーマンの子は、家を出なければならないのだ。
父の収入は、マモルを進学塾に行かせる余裕もないほど下がっていたので、残されていた選択肢は多くなかった。自宅から通える地元の高校で、厳しく自分を律して成績トップを維持し、年に一人か二人しか入れない鹿児島大学を目指すか、学区制限のない南郷高校の理数科に入って、九十名の寮生たちと国公立大学を目指すかのどちらかだ。父は後者を勧め、マモルも賛成した。