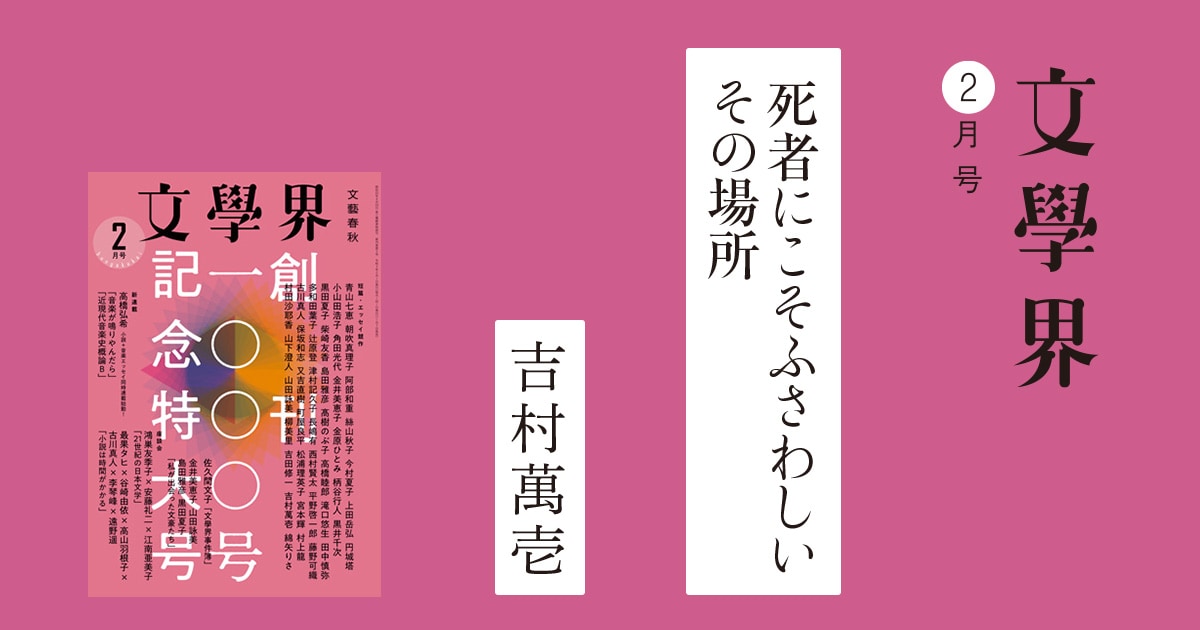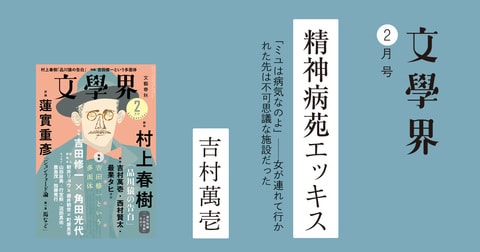秋祭りが近付くと、他の町同様に折口山町の献灯台にも灯が灯り、だんじり小屋からは篠笛、鉦、太鼓といった鳴り物の練習の音が流れてくる。嘗て夜に気勢を上げて街中を疾走していた青年団の走り込みは、騒音や車の通行に配慮して近年は自粛傾向にあるが、本番が迫るに連れて町全体が熱を帯び、否応なく血が騒ぎ始める町民は徐々に浮き足立ってくる。「捨て身祭り」の異名を取る秋祭りは迫力あるだんじりの曳き回しが見もので、曲がり角を直角に曲がる場面ではだんじりが横滑りしたり横転したりして、時に圧死者も出た。折口山町を含む十五町のこの過剰とも言える熱狂振りは二百五十年に亘って受け継がれてきたが、自分達の中に流れている血潮の源を正確に知る者は一人もいない。それでもしきたりは厳格に守られ、盆を過ぎると各家の表札や門扉や軒下には人型の護符が束となってぶら下げられた。護符には目玉が一つずつフリーハンドで描かれていて、強風に吹かれて一斉にはためくとそれはまるで多くの目が忙しなく瞬きをしているかのように見えた。千切れた護符の目は風に運ばれて町のあちこちに散らばり、町民が祭りに捨て身になっているかどうかを見極める監視の役割を果たすと言われていた。従って秋祭りの季節になると、子供から老人までが道に落ちた護符を見付けては、突然秋祭りの掛け声を叫んだり、手近な物を手に取って鉦のリズムを叩いたりして浮かれ出すのである。
町の中には当然のことながら、このような熱狂を心の底から忌み嫌う人間が存在した。夕方になると聞こえてくる鳴り物の音に耐えかねて、傾き始めた夕陽に背を向け、自分の影に導かれるようにしてその男が目指すのは、彼にとっては馴染みの場所である町外れの植物園であった。植物園へと続く車道は住宅街へと続く抜け道になっていたが、雑木の枝のアーチに覆われていて昼間でも薄暗く、鳴り物の音を含めた町の喧騒を完全に遮断して静まり返っている。時に行き交うのは車ばかりで、人通りは殆どなかった。やがて右手奥にだだっ広い敷地と古びた建物が見えてくると、男は車道から逸れてスッとそちらの方へと吸い込まれていった。それは一瞬、この世に現れた冥府の口に呑まれたかのようにも見えたが、よく見ると男の他にも、朽ちた建物や泉水を縫うように何人かの黒い影が亡者のように移動しているのだった。彼等はこの場所を好んで散歩する常連達で、互いに決して知り合おうとせず、どこまでも見知らぬ者同士として存在することを暗黙の了解事項としている者達だった。
あちこちに点在する大小の泉水の中でも植物園の正面に位置する大泉水は一際堂々としていて、ここに来た誰もが一旦は立ち寄っては縁越しに中を覗き込んだ。そして蓮の葉を浮かべた漆黒の水にじっと見入ったり、小石を投げ入れたり、或いはがっかりしたような表情を浮かべては、また夫々思い思いの方向へと立ち去っていくのである。
男は大泉水の周りを、縁に沿ってゆっくりと移動した。
まだ歳若く、目を細めて周囲を覗うその顔は、狐のようだった。
狐男は目についた人間の顔をジロジロと見た。それは人定めをしているようにも、相手を挑発しようとしているかのようにも見えた。他人を避けるためにのみここに集い、離れて眺め合う以上のことはせず、目が合えばどちらからともなくそっと逸らすような遠慮がちな人々の中にあって、その目は場違いな輝きを帯びていた。
大泉水の縁に両手を突いて前屈みになって黒い水面を眺めていた女は、ふと視線を上げ、大泉水の反対側から自分の顔をじっと見ている狐男に対して、体を起こして背筋を伸ばし、コオロギに似た顔を真っ直ぐに対峙させた。まだ学生であろう狐男は、三十代と思しきコオロギ女のきつい視線に気圧されて一瞬伏し目がちになったが、すぐに気を取り直して再び視線を彼女に合わせた。大泉水を挟んで、二十代の学生風の男と、三十代の、一見すると痩せて見えるがしかしゆったりしたワンピースの下の胸や腰周りにはかなりの肉が詰まっていそうな大人の女とが、十数秒間見詰め合う格好になった。それが可能だったのは、彼等の距離が大泉水によって充分に隔てられていたことに加え、夕闇の薄暗さも加わって互いの表情が不鮮明であったことが影響しているかも知れなかった。
この続きは、「文學界」2月号に全文掲載されています。