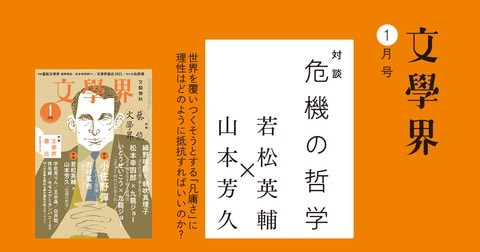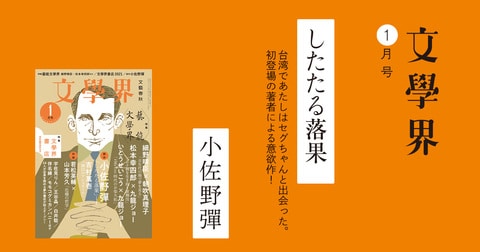第一の事件簿 「近代の超克」と日本の「n・r・f」
「文學界」の長い歴史で、くりかえし言及されるという点で最大の事件と言っていいのが、昭和一七年一〇月号に掲載された「近代の超克」をめぐる大座談会である。
「近代の超克」がたびたび論議の対象になってきたことについてたとえば柄谷行人は、「それはその座談会の歴史的意味を問うということを意味するだけではなかった。むしろそれを問うことがその都度その時期の状況を映し出すというかたちになっていたと思うのです」と、『〈近代の超克〉論』を書いた哲学者廣松渉を招いた座談会で発言している(「〈近代の超克〉と西田哲学」=「季刊思潮」平成元年四号)。
戦後の思想史を研究する上で、日本のみならず、海外の研究者からも言及されるのが、「文學界」の同人が開いたこの座談会だった。
大座談会というのは、同人が編集していた「文學界」のひとつの名物だった。
学生時代から寄稿していた中村光夫が、「あのけんかみたいな座談会」(「『文學界』五十年のあゆみ(戦前篇)」昭和五八年一〇月号)とふり返って言うように、呉越同舟と言われるほど考え方の異なる同人が集まっていたからこそ、徹底的に討議する必要も意味もあった。
ここで「文學界」の歴史を簡単にふりかえっておこう。
創刊は昭和八(一九三三)年十月。プロレタリア作家の武田麟太郎が、小林秀雄、林房雄に声をかけ、川端康成も加わった。宇野浩二、広津和郎といった少し年長の作家も参加を承諾した。
ほぼ同じ時期に、「文藝」「行動」といった文芸誌も創刊され、そうした動きが「文芸復興」とうたわれた。うたわれた、というより作家みずからがそう位置づけたと言ったほうが正しい。プロレタリア作家への弾圧が激しくなり、武田によれば、「満洲事変以後、私たちの上に重苦しく押っかぶさって来た鉛色の曇天に対する作家的反発からであったと思う」(「文芸時評」=「文學界」昭和一一年七月号)という背景があり、大衆文芸がさかんになるなかで純文学を守る意図もあった。
武田や林といったプロレタリア系の作家と、川端、小林ら芸術派が手を結び、そこに宇野ら四十代の作家まで加わったことで、「文學界」は「呉越同舟」と評された。のちに何度かの改組を経て同人の数が増えたときには「文壇強者連盟」と高見順に揶揄されたこともある。
実力派作家が集結した感のある「文學界」だったが、経営は厳しく、「文藝」や「行動」と比べても原稿料が安かった。一年目は一枚五十銭、それもすぐに出なくなり、橋善という新橋の天ぷら屋での会食が原稿料の代わりになった。