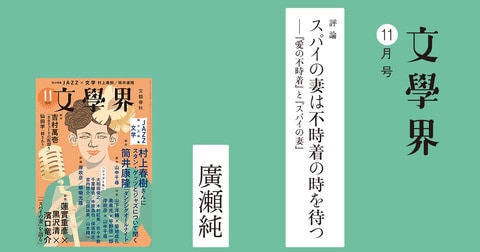俺は俺自身を、純粋で完全な全音符にしたいと思った。
幼少期から、俺は楽曲の最後の全音符が好きだった。一際大きく鳴らされた最後の音が、ゆっくりと消えたのちに訪れる静けさ――、あの静寂は無音ではない。豊かな音楽が俺の体内には残っていて、それはときに小節を進む最中の音楽を超える。
俺は俺の中の音楽を、好きなように楽しむことができる。多くの場合、体内の音楽は視覚をもたらした。窓辺に差す日光が格子柄の絨毯の上を移ろっていく光景、日没間近の雲の腹が赤く染まりその下で電線や電柱や家並みが影絵に見える光景、小川の畔を漂う蛍の尾のエメラルド色の灯りが少しずつ夜の闇に紛れていく光景――、どうやら音楽は、俺の少年期と深く結びついているらしい。旋律が連れてくる言葉がどこか感傷的なのはそのせいだろう。言葉はときに抽象的な詩を形成し、ときに具体的な散文詩を形成し、形になれなければ断片となる。俺に選択権はない。あなたの作品なのに選択権がないとはどういうことでしょう? 君たちは得意の質問で訊くだろう。選択権を持つのは常に音楽だ。その点で、俺は音楽に誠実であったし、同時に音楽の奴隷でもあった。
音楽が変わってしまったのか、俺が変わってしまったのか、今となってはもう分からない。少なくとも俺は、汚れた手で音楽に触れようとは思わない。ある親しいサックス奏者は、音楽は本来楽しむべきものだと俺に忠告した。反吐が出る。ある親しい売人は、君はもっと楽天的に生きるべきだと俺に警告した。クソくらえ。音楽は楽しむものではないし、ならば人生も同じだ。ときに俺は聴衆にさえもそれを望んでしまうが、果たしてそれは傲慢だろうか――。
今、この一室には音楽が流れている。第一音で産声をあげた音楽は、いくつかの緩急を経て、最期には終止線を迎える。すべての音楽に、必ず終止線は引かれるのだ。俺は君たちに随分とサービスをしてきたし、これまでの馬鹿げた問答も、すべてが虚構であったわけではない。最後は俺の好きにさせてもらう。同時にそれは君たちが、最も望む結果になる。明日になるか、明後日になるかは知らないが、君たちは新聞紙面に、面白い見出しを見つけるだろう。そして色々な理由を探すだろう。それもまた、君たちには上等な娯楽になることだろう。
(Recording on Aug 11)