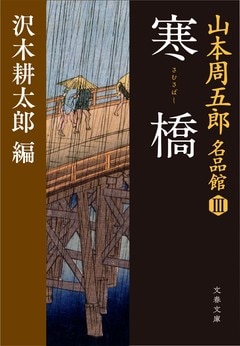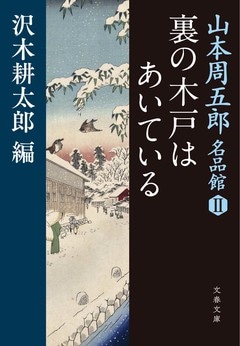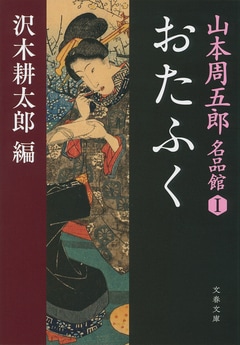I
地下のバーに流れる音楽は、J・D・サウザーの「ユア・オンリー・ロンリー」からビリー・ジョエルの「オネスティ」に変わった。
カウンターの隣に座る沢木耕太郎の声は、騒がしい酒場の中で穏やかに聞こえた。
「僕はいつも相手と対等で在りたいと思い続けてきた。もちろん相手のことを好きになること。あとは……そうだね、相手に対して誠実であることかもしれない」
誠実という言葉が背後に響く歌の名前に重ねたものなのか、偶然の符合によるものなのかを、私は推(お)し量(はか)ることができなかった。
平成二十二年十二月二日、渋谷での夜。二十三時を回っていた。
彼は大切なことをいくつも教えてくれた。子供に読み聞かせた絵本のこと。高倉健に宛てた脚本のこと。ロバート・キャパが残した謎のこと。私が少し前にした羽生(はぶ)善治へのインタビューで『深夜特急』の話になったと伝えると、彼は静かに笑った。
ふと井上陽水の話題になった。
「一昨日会ったんだ。お互い歳を取ったね、なんて随分と長く懐かしい話をしたよ」
ふたりの出会いが描かれた作品を思い出した私は「初対面の井上さんに向かって、なぜ、興味がない、なんて言えたんですか?」と聞いた。
「若かったし、陽水なら面白がってくれるんじゃないかという僕なりの計算もあった」
私は前年のライヴで陽水の「積み荷のない船」を聴いていた。ドラマ「深夜特急」の主題歌はアンコールで語るように歌われた。
「僕との約束だったんだ。一度、コンサートで歌ってくれないかって。聴いたことがなかったんだ。僕が行った時も歌ってくれた。あの歌がすごく好きなんだ」
ステージでの陽水のヴォーカルを追想する。
積み荷もなく行くあの船は 海に沈む途中 港に住む人々に 深い夜を想わせて
深い夜、沢木耕太郎との約束──。少し酔いの回った意識の底で、私は五年前のことを思い出していた。
十七年夏、沢木とカシアス内藤へのそれぞれのインタビューで同じ質問をした。
「真っ白い灰に燃え尽きる『いつか』という刻(とき)を、あれから迎えることはできたのでしょうか」
二十五歳の沢木が「クレイになれなかった男」の終幕に書いた文章は、二十五歳になった私の心に再び反響していた。
人間には、燃えつきる人間と、そうでない人間と、いつか燃えつきたいと望みつづける人間の、三つのタイプがあるのだ、と。
望みつづけ、望みつづけ、しかし「いつか」はやってこない。内藤にも、あいつにも、あいつにも、そしてこの俺にも……。
十四歳の時に初めて読んでからずっと、何かを語り掛けてくる言葉だった。「あいつ」のリフレインの果てに俺もいるんだ、と十代の青さで考えていた。望み続け、望み続けても「いつか」のやってこない者として。
遠い月日が経過した後の答えを聞きたかった。
「E&Jカシアス・ボクシングジム」を開いた直後だった内藤は真新しいリングの中央に座ったまま言った。
「これが俺の目指したいつかだった。あとは自分の手で世界王者をつくること。それが俺の新しいいつか」
代表作になる『凍』を発表したばかりの沢木は少し考えた後で言った。
「うん……宿題にしとくね。でも、いずれは提出することを君と僕との約束にしよう」
音楽はスティーブン・ビショップ、ボズ・スキャッグスと移っていく。
あの時の約束を果たしてもらうには、うってつけの夜だと思った。
日付が変わる。時間がない。席を立つ前に、五年前の問いをもう一度投げ掛けた。
沢木は考えていた。不思議なくらい静かに、別れる前の時間は過ぎていった。
彼はI・W・ハーパーのストレートを折り目正しい手つきで口元へと運び、おそらくは歩んだ日々について思いを巡らせていた。
「……ふたりで目指したいつかには、ついに辿り着かなかった。そして僕自身も……いつかと思える刻を迎えることはできなかったのかもしれない」
返す言葉などどこにもなかった。
酔客の喧騒も、懐かしい音楽ももう聞こえなかった。
暖色の光がカウンターを照らしていた。
私は何も言えず、ただ彼の横顔を見つめた。
II
『敗れざる者たち』は昭和五十一年、二十八歳の沢木耕太郎が発表した二冊目の著作である。同世代の先駆者たちを追った『若き実力者たち』から三年。初めてのスポーツノンフィクション短篇集として勝負の世界を生きる者たちの陰影を描いている。
燃え尽きることなく翳(かげ)りゆくボクサー、英雄を頂点に運命を交錯させる三人の打者、夭折(ようせつ)する栄光の長距離走者、良血馬たちとの一度限りの決戦に臨むサラブレッド、戦いの舞台から降りてなお狂気を放つ名選手、無謀と嘲笑された挑戦へと疾走する元王者───。ヘミングウェイの短篇に重ね、沢木が「The Undefeated」と定義した主人公たちは孤独に屹立(きつりつ)しているようで、夜空に瞬(またた)く星座のようにひとつの世界を造形している。星々の光度は異なるが、集合体としての不思議な光を闇に浮かび上がらせている。
スポーツノンフィクションは経年への耐久性を厳格に問われる。ある勝負をめぐるレポートなら一年後より一週間後に読んだ方が迫真性は高いに決まっているからだ。ところが、刊行から四十五年が過ぎた今も本作には全く色褪せることのない力がある。一九七六年の読者に与えた夢を、二〇二一年の若者にも届けるだろう。経年はむしろ「不変」という付加価値に導く武器として機能している。
『敗れざる者たち』の個性はいくつかの角度から語ることができる。通底しているのは、書き手と主人公の青春が同時に描かれていること。大抵の場合において、スポーツについて書くことは青春について書くことと同義だが、本作では青春が併存し、時に交錯することで高純度の結晶のような何かを生み出している。
さらに、異なる競技を横断する短篇集という形式を支えるのはアマチュアの視点からプロフェッショナルを見ていること。リング上でのボクサーの技術を詳述する時でもなお、どこか専門性を表明しない姿勢が作品に普遍性をもたらしている。スポーツノンフィクションと窮屈にカテゴライズするより「スポーツに賭ける個の軌跡を描いたノンフィクション」と語る方が相応(ふさわ)しいだろう。
そして何よりも、沢木耕太郎の圧倒的な作家性である。対象の選び方、対象への関わり方、どのように取材するか、どのように自らがシーンを生きるか。得た素材を作品化する際の方法、構成、文体、文章、言葉。さらにタイトルやエピグラフ、あとがきに至るまで、二十代半ばの書き手が残したものは、以降の半世紀で多くのスポーツライターが挑み、届かなかった水準に到達している。将棋という勝負の世界を伝え、時にノンフィクションとして書いている四十一歳の私にとっては、少し信じ難い作品である。
読者は燃え尽きることのない自己を主人公たちに投影する。あるいは、たとえ真っ白い灰にならなくとも、信じた道で燃え尽きることを望む主人公たちに憧憬(しょうけい)を抱く。風変わりな読み手の中には「自分も書き手になってこんな物語を書いてみたい」と願うようになる者さえいる。私くらいかと思っていたが、スポーツの名を冠したメディアで過ごしてきた十八年間に、同類の同業者と数多く出会ってきた。『深夜特急』を読んで長い移動に焦がれ、本当に出発した多くの旅人たちのように。
令和二年十一月、沢木耕太郎に『敗れざる者たち』について聞いた。
彼は「まあ……そうだね、人を動かす力はあるのかもしれないね」と微笑した。
「当時、まだ先行例がなかったものを、という思いはあったのかもしれない。アメリカの『スポーツ・イラストレイテッド』に掲載されているようなノンフィクション、あるいはゲイ・タリーズがニュージャーナリズムで書いた作品を最初は翻訳で読んで、もっと読んでみたいなと思って原書も辞書を引いて訳してみた。するとね、僕が書きたいな、と思うものは原稿用紙にすると六十枚くらいは必要なんだな、ということが分かった。ゲイ・タリーズの短篇集『The Overreachers』もそれぞれ六十枚くらいで。日本の雑誌で一般的に求められるのは三十枚くらいだから、新しいものが生まれたとは思った」
走り始めた若いルポライターに勝負の世界という強烈なイメージを与えたのは、ルポルタージュ「儀式─ジャンボ尾崎、あるいはそれからの星飛雄馬(ひゅうま)」だった。後に「巨象の復活」として改稿され『若き実力者たち』に収録される作品である。
「本当に取材というのは面白いなと思えたし、尾崎将司さんの人生はとても面白かった。あとは自分と同世代の人を書く中で、自分には他の人には見えない面白さを抽出できる能力があるかもしれないと思えたことと、方法が手に入ったこと。彼の試合の流れの中で彼の人生について書いていくことで、極端なことを言えばもう何でも書けると思ったんだ」
「儀式」で手にした方法の力に導かれ、書かれたのが本作の「イシノヒカル、おまえは走った!」だった。沢木自身が今になっても「どうして書けたのか分からない」と振り返るのは、ラストシーンの「ひと塊りの黒い馬群が、四コーナーを回り切った」から「イシノヒカルは、長い直線を必死に走った。差はつまらない」までの十数行である。ある律動の中に馬群の蹄音と歓声が響いている。
「どうして書けたのか、という文章は少ないけれど、あのイシノヒカルの数行だけは書くことの不思議さを感じた。リズムと思いが籠(こも)って、あれ以前の僕にも、あれ以降の僕にも書けないものが書けた。何度か読み返したけど、心が高揚するものがあった。どうして書けたのかは本当に分からない」
書き手の端くれとしては最後の夜のシーンも「どうしてこんな三行が書けたのか」と唸らされるエンディングである。「イシノヒカル」のみならず『敗れざる者たち』全六篇のラストセンテンスには沢木耕太郎の書き手としての神髄が表出している。物語を包括する余韻、残響であり、本を読む幸福の象徴に他ならない。
III
才能も個性も、将来の夢さえもなかった中学二年の時、沢木の『一瞬の夏』を偶然読み、何かと出会えた気がした。誰かと会い、話を聞き、書くこと。こんなふうに生きることが出来たら、と初めて思えた。
片端から著作を追った。沢木耕太郎という人は、今までの自分が知り得ていた世界、あるいは想像し得た世界にいる誰とも似ていなかった。会いたい人に会うこと。行きたい場所に行くこと。書きたい何かを書くこと。誰とも群れず、何にも属さず、しかし、あらゆる世界や人々と柔らかく繋(つな)がっている。私立探偵のように何らかの発端を得て、人や出来事に深く関わり、ある時間を共に過ごし、去っていく。何かが残れば作品として発表する。
人より先に一報を伝えるためでもなく、論客を論破するためでもなく、政権を打倒するためでもなく、無限の自由の中で行動し、脳裏に浮かぶ地図を燃やしながら移動する。最高の試合を目撃し、酒場で誰かから何かを学び、異国のバスに乗って車窓の風景を眺める姿は生きる上での最良のモデルに映った。私は時々、想像するようになった。今、自分が生きている瞬間、世界のどこかを旅している書き手の存在を。級友たちがアスリートやアーティストを想うように。
大学三年になり、どこかへ向かって歩き始めたいと思った。バスケットボール部を辞め、講義は全て欠席した。「SWITCH」編集部に何度も履歴書を送り、アルバイトとして日夜働くようになった。私にとって「SWITCH」は夢の雑誌だった。編集部員が対象と並走し、共に旅をした成果としてのロングインタビューを美しい誌面で表現していた。沢木耕太郎を追い続けている雑誌でもあった。
編集部に赴いた初日のこと。編集長の新井敏記に「君は誰にいちばん会いたいの?」と聞かれた。「沢木耕太郎さんです……」と正直に告げると「じゃ、これから沢木さんへのお使いはお前が行けよ」と笑顔で言われた。えっ、と思った。何の気なしに言ってくれたであろう言葉だったが、私には新しい可能性への開示として聞こえた。自分は昨日まで生きてきた場所とは明らかに異なる世界に半歩足を踏み入れたのかもしれない、という確かな感覚があった。
当時はまだフィルムカメラが中心の時代で、現像所でプリントされた写真を各所に届けるのが任務のひとつだった。スイッチ・パブリッシングが出版した沢木の写真集『天涯』に関連する写真を抱えて、何度も駒沢大学駅前の喫茶店に行った。
目の前に沢木耕太郎がいるという体験は二十歳の私にとって革命的な出来事だった。当然、通常のお使いは「御苦労様」で終わるが、彼だけはいつも学生アルバイトのためにコーヒー一杯分の時間をくれた。私は彼が聞く価値のある話など何ひとつ持ち合わせていなかったが、相手をしてくれた。今夜の天気はどうか、次号の特集は誰が飾るのか、私がどのような夢を抱いている若造か。
現実の沢木耕太郎も、今まで会った誰とも似ていない人だった。年齢や性別、地位も立場も関係なく相手を受容し、肯定するような人だと思った。だからこそ、あのような作品の数々を生み出してきたのだと。
卒業後もライターとして編集部に残りたいと思っていたが、悩み抜いた末、辞めて就職することを決めた。私はどこかで怖かったのだ。あまりに凡庸な二十年を生きてきた人間が今までとは全く別の世界へと船出することが、どこかでずっと怖かった。
平成十二年十二月三十日、最終出勤日の夜。
校了を終えて静かになった編集部で、私は最後の訪問者を待っていた。
十九時を過ぎた頃、ノックの音に気付く。
「こんばんは」
沢木耕太郎がドアを開けた。
写真集『天涯』のサイン本をつくる作業だった。彼が署名していく扉のページに、私はインクが滲まないように一枚ずつ半紙を挟んでいった。銀色のフェルトペンで書かれていく「酒杯を乾して 沢木耕太郎」の文字を私は見つめた。
「さようなら。また来年もよろしく」
音を立ててドアが閉じられてから数秒後、破裂するような衝動が胸を襲った。
気が付くと、私は外へ飛び出して走り始めていた。
元麻布の方向に見える彼もなんと走っている。
「沢木さん!」
彼は何事かという顔で振り返った。
「どうしたの?」
「あの……僕、実は今日で辞めるんです。本当に有難うございました」
「ああ、そうなんだ……辞めちゃうのか」
「あの……でも、僕の夢は文章を書くことなので、これから頑張ります」
「そうか……ねえ、君は僕の仕事場の連絡先分かる? 年が明けたらどこかでコーヒーでも飲みながら話をしようよ」
私は今でも時々、あの夜の一瞬のことを思い出す。
あの時の沢木耕太郎の言葉と表情を。あの後、編集部まで全力で走った時のアスファルトの硬さ、頬に受けた冷気、高鳴り続けていた鼓動のことを。
IV
『敗れざる者たち』について考える時、背景に見据えたいのは旅との関わりである。沢木は「イシノヒカル、おまえは走った!」と「クレイになれなかった男」を発表した後の昭和四十九年、後に紀行『深夜特急』として発表するユーラシアへの一年に及ぶ旅に発っている。作品化する際、大きな役割を担うことになる金銭出納帳の片隅に書いたのが「敗れざる者」という文字だった。
当時、まだスポーツノンフィクションというジャンルは確立されていなかったが、勝負の世界を巡る物語のみで短篇集を編むイメージは異国での移動中に構想されていた。
帰国後、立て続けに発表された「三人の三塁手」「さらば宝石」「長距離ランナーの遺書」「ドランカー〈酔いどれ〉」は、旅人がラワール・ピンディーやイスファハンの安宿の夜に夢想した何かの結実だと思うと、本書の読み味はより重層的なものになる。
ボクシングをテーマにした「クレイ」と「ドランカー」を読み比べた時、書き手が纏(まと)う空気にはわずかな変化があるように映る。後者では、旅を終えた青年が精悍な強度を手にしているように私には思えるのだ。
『敗れざる者たち』を経た沢木耕太郎は、若い書き手としての絶頂期を迎えることになる。わずか二年後の昭和五十三年、山口二矢(おとや)による浅沼稲次郎暗殺事件をニュージャーナリズムの手法で描いた初の長篇『テロルの決算』を発表する。さらに昭和五十六年には、その後のカシアス内藤と並走しながら「見たもの以外は書かない」私ノンフィクションのスタイルで書いた長篇『一瞬の夏』を刊行する。いずれも、本書の過程で力を手にしたライターが「方法の冒険」に挑み、辿り着いた作品である。テーマも技法も異なるが、出発点は『敗れざる者たち』での格闘にあった。
長い歳月の中で沢木作品を読み続けると、あることを思うようになる。ノンフィクション、エッセイ、紀行、小説、写真、絵本とあらゆる表現を横断し、連動しながら、彼は「沢木耕太郎」という名の長篇を書き続けているのではないか、と。
「そのようなイメージが僕にもある。沢木耕太郎という人生を生きる中で関わった人や事象について文章にする。でも、文章にすれば完結してしまうのではなく、僕の人生に人や事象は存在し続ける。数十年でも影響を受け続けて、影響を与え続けているのかもしれない。そのような人や事象について、もしかしたら新しい作品は生まれないかも知れないけど、生まれるかもしれない。関わってさえいれば、いつも『今』なんだと思うんだ。どんなに古めかしい関係でも。強引な主張なんだけどさ。カシアス内藤君にしても、息子の律樹にも僕は関わっていく。すごく大きな物語から派生している物語だから、どんなふうに決着がつくかは現実だから分からないけど」
連動性の志向は、例えば『敗れざる者たち』のエピグラフにも表明されている。
「あっしは闘牛士なんでさ」
と、マヌエルは言った。
A・ヘミングウェイ
勝負の予兆を鮮やかに想起させる短文のスタイルは、平成元年に刊行されたスポーツノンフィクション短篇集の第二作『王の闇』に継承されている。
「わたしにあって、あなたにないもの」
道化が王に謎をかけた。
B・セルバンテス
十三年の時間を繋ぐ三行に隠した秘密を、沢木は明かしてくれた。
「ヘミングウェイはErnestだからE・ヘミングウェイとするべきなんだけど、引用する時にちょっと語呂が悪いな、と思ったので文章を少し弄(いじ)ったんだ。僕が勝手に弄ったわけだから、EではなくAとした。あえてAとしたのは、これから次々と書いていくであろうスポーツノンフィクション短篇集の一作目であることを示そうと思ったから。『王の闇』に書いたものはセルバンテスの引用ですらなくて、ありもしない文章を僕が勝手に書いた。セルバンテスはMiguelだから全然Bじゃないよね。だから二冊目という意味のBなんだ。当初は次々とスポーツノンフィクションの短篇集を発表していくつもりだったからC・誰々、D・誰々と出していけば、ああそういうことか、と分かってもらえるなと思っていたけど、僕の関心が長篇に向いていったこともあって、AとBだけで止まってしまったんだ」
『王の闇』が世に出て三十二年が経過してもなお、読者は続篇の予感を抱く。
「もしかしたらCは存在しないかもしれないけど、あり得るかも知れない。ちょっとDはないかもしれないけど、Cはあるかもしれないと思ってる。だからA・ヘミングウェイという不思議な名前を通します。もちろん、短篇集を出すくらいの材料は現時点でもあるけど、古いままの作品を集めてもしょうがないから、新しいものを一本でも付与できるなら出してもいいかもしれないね。どこかでまだCはあり得るかもしれないって思ってるんだ」
エピグラフの一文字を通巻のノンブルにする発想は、エッセイ集『ポーカー・フェース』収録の一篇「ゆびきりげんまん」の中でも記しているが、実は同書のタイトルにも沢木らしい仕掛がある。
「当然、本来なら『ポーカー・フェイス』だよね。でも、同じようなスタイルのエッセイ集はナカグロを挟んで前後に音引きがある形で揃えたかった。どうでもいいようなことだけど」
第一作は『バーボン・ストリート』、第二作は『チェーン・スモーキング』。つまり「ー・ー」のルールを継がせているのだ。
『敗れざる者たち』の最後を飾る傑作「ドランカー〈酔いどれ〉」は『王の闇』において、同じく輪島功一を追った「コホーネス〈胆っ玉〉」という対の続篇を得る。
カシアス内藤との発端の作品「クレイになれなかった男」は代表作『一瞬の夏』に繋がる。内藤は沢木のキャリアの中で無二の対象になっていく。
「駄目な奴だなあ、とどれだけ思っても、手を差し伸べる時があったとしても、彼は一人きりでリングに向かっていく。僕とは隔絶された世界に向かっていく人に対する敬意がある。彼には何かが欠けていた。でも、欠けている彼は僕でもある。燃え尽きることのできない彼は僕なんだと思ったんだ。あの『いつか』は何らかの経験を得たり努力して辿り着ける『いつか』ではないと思う。青春の時代に輝く幻のような何かかもしれない。多くの人は手に入らないけど、稀に手にする人もいるよね」
カシアス内藤を巡る物語には、未刊の続篇『冬の戴冠』が眠っている。
「句読点を打てる時が来たら書く必要があると思っているし、書きたいと思っている」
V
令和二年十一月二十一日、後楽園ホール。
東洋太平洋スーパーライト級タイトルマッチ十二回戦は沈黙の中で行われた。
見えざる敵の脅威も漂う会場で、マスク姿の観客はリング上への賛辞を歓声ではなく拍手で表現した。カシアス内藤が釜山(プサン)で聞いた群衆の叫びも、輪島功一が両国で聞いた狂熱もなかった。
王者の内藤律樹は挑戦者の同級四位・今野裕介を初回から翻弄(ほんろう)する。父と同じサウスポーのボクサーファイターは精巧な技術者を思わせる戦いを貫いた。
七回、今野がアクシデントに襲われる。左肩を故障してガードを上げられない。リングに沈める好機を得た王者だったが、一発の右を警戒してインファイトには持ち込まない。九回終了後、続行不能と判断されるテクニカルノックアウトで内藤は四度目の防衛を果たした。敗北の可能性を徹底的に削(そ)いでいった完璧な勝利だった。
私は想像した。もしリングサイドにいたなら、エディ・タウンゼントは「殺すのよ!」と叫んだだろうか。二十五歳の沢木耕太郎は「やれよ!」と夢を託しただろうか。あの静寂の戦いを、沢木ならどのようなスタイルと言葉で書くだろうかと。
沢木耕太郎は「夢の作家」である。
ノンフィクションの系譜の中では「方法の作家」と語られる。正確な評価だろう。彼が続ける「スタイルの冒険」はノンフィクションの持つ可能性を拡げている。
でも、とも思うのだ。「方法」という個性の前には「夢」があるのだと。
沢木耕太郎は自分の夢を生きる。そして人に夢を与える。
『敗れざる者たち』の物語は続いている。
私は『冬の戴冠』を、そして「C」の短篇集を想っている。
望み続け、望み続け、やってくる「いつか」のノンフィクションとして。
引用出典
「積み荷のない船」(1996) 作詞・井上陽水 作曲・井上陽水/浦田恵司