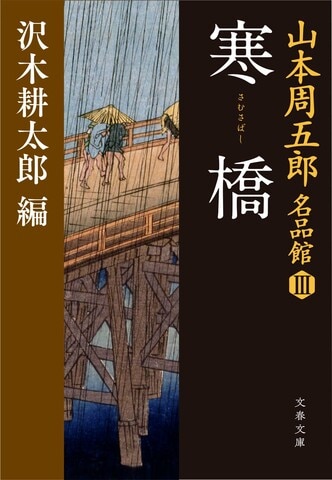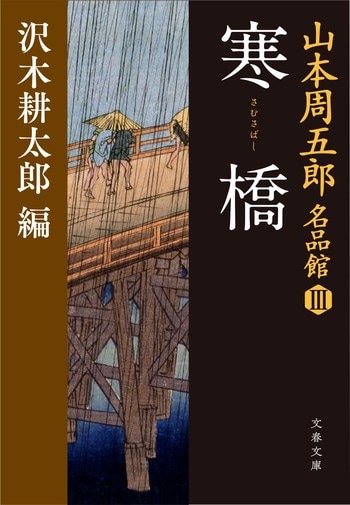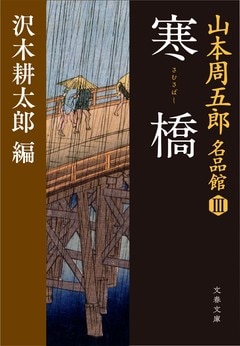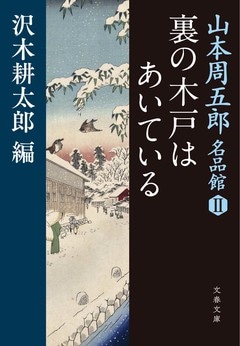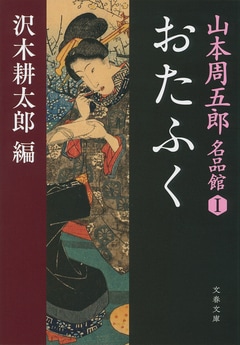私の父は、二十年前に八十九歳で死んだが、その晩年の一時期、熱心に俳句を詠んでいた。もちろん、素人俳句の域を出ていなかったが、二つ三つは私にも悪くないと思える句があった。「聖夜なり雪なくばせめて星光れ」とか、「差引けば仕合はせ残る年の暮」とかいった句は、その季節になると、ふっと口をついて出てきそうな気がするくらい親しいものになっている。
その父の句の中に、こんな一句がある。
樟脳を纏ひし母の冷たさよ
これだけではよくわからないかもしれない。だが、その句については、父が所属していた結社の句誌に載せた短い文章が残されており、それを読むと、なるほどそういう句だったのかとわかる仕組みになっている。
そこでは、まず齢をとればとるほど幼少期の記憶が鮮明になってくるらしいという前振りがあったあとで、次のように記されているのだ。
《冒頭の句は、そうした私の句なのである。私も又、幼少期の方が思い出すのにより愉しくもあるし、鮮やかでもある。一例を挙げれば、時間を決めて家に来る髪結いに、小さな鏡台に向かって髪を上げさせている若い母の横顔は、鬢付け油の匂と共に昨日の事のようにはっきり思い出す。そして樟脳を──外出しようとする母の晴着から舞い昇る樟脳のひいやりとした匂と、絹物の持つ特有の冷たい肌触り、しゃんと身仕舞した外出姿の何か普段とは違った取り付きにくさ──を纏いし母の冷たさよである》
父は幼い頃に母親を亡くしている。その樟脳の匂いが、幼かった父が母親について記憶しているわずかなもののうちのひとつだったのだろう。
もちろん、父の幼い頃に亡くなっているのだから、私の祖母にあたるその人を私は知らない。美しい人だったと聞かされているが、古い写真ではその美しさを正確に認識することはできない。ただ、父のその句からは、なんとなく幼い父と美しかったという母親のいる空間が想像できるような気がする。
六畳くらいの日本間に小さな鏡台が置いてある。そこに向かって座っている母親の背後には髪結いの女がいる。髪を結ってもらっている若く美しい母親の姿を幼い男の子が不思議な面持ちで眺めている。髪が結い終わり、外出着に着替えようとしている母親のところから樟脳の香りが漂ってくる。その香りは、羽織っている絹の着物の質感と、母親のちょっと取り澄ましたような顔の表情とがないまぜになって、幼い男の子には「冷たさ」と記憶される……。
その情景が展開されたのは、父の年齢から考えると、大正の初期だったと思われる。しかし、その部屋の雰囲気は、明治をさかのぼり、江戸時代にまでつながっているような気がしないでもない。
ところで。
山本周五郎に「寒橋」という短編がある。私は、それを読んで二つのことに驚かされた。
ひとつはタイトルの読み方である。実際に中身を読むまで、私はそのタイトルの読み方がわからなかった。かんばし? かんきょう? さむばし? どれも違うように思われる。そのため、私は、読めない字が現れたときによくそうするように、「寒橋」という文字を頭に入れたまま「読むこと」を停止して、放置してあった。
そして、あるとき、「山本周五郎小説全集」に収録されていた「寒橋」を読んでいくと、次のような一節に出くわすことになった。
《寒橋というのは小田原町から築地明石町へ渡したもので、京橋堀と見当堀が大川へおちるおちくちにあった。汀に大きな石のごろごろした、吹きさらしの、「さむさ橋」という俗称のぴったりする観景である》
まず、寒橋は「さむさばし」と読むのであるらしいということに驚かされた。寒橋の「寒」を「さむさ」とはなかなか読めないが、しかし、そう教えられると、寒橋は「さむさばし」としか読めなくなってしまう。
そしてもうひとつの驚きは、その「さむさばし」が小田原町にあるということだった。寒橋だけでなく、主人公のお孝が住む家も小田原町にあるらしい。
小田原町!
私の父が、所属する俳句の結社の句誌に書いたもうひとつの文章の中に、次のような一行がある。
《本願寺の裏を流れる築地川と、将に東京湾に注ぎ込もうとする隅田川に挟まれた小さな島のような小田原町が、私の生まれて十まで育った所だ》
そう、私の父は、小田原町で生まれ育ったのだ。