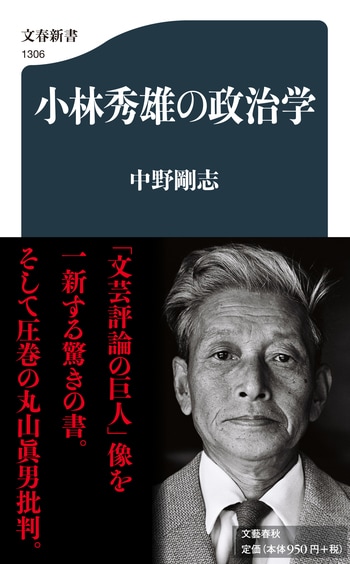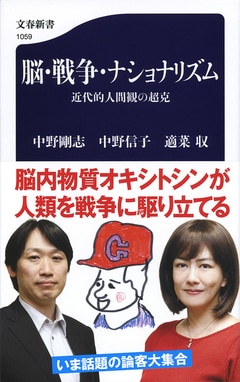注目すべきは、小林がドストエフスキーの『作家の日記』を重視し、「ドストエフスキイの生活」の中の一章を当てていることである。江藤淳は「この章は『ドストエフスキイの生活』中でも小林の主張がむき出しになつている部分で、そのために評伝としての均衡はかえつて大きく崩れているという感をおおいがたい(※3)」と評している。評伝としての均衡を歪めてまで、小林が描き出そうとしたものとは何だったのか。それは他でもない、ドストエフスキーの政治論であった。
※3 江藤淳『小林秀雄』(講談社)、1965年P166。
小林は、ドストエフスキーの『作家の日記』について、これは政治論文集であり、「文学者の政治に対する態度が、膨大な論集を通じ、一貫してまことに鮮やかに現れてゐる」(「政治と文学」〔昭和二十六年〕、第九巻P60-61)だけでなく、「ドストエフスキイといふ人間を知る上には、恐らく最適の、少くとも必須の作品」(「ドストエフスキイの生活」〔昭和十~十二年〕、第五巻P154)とみなしていた。要するに、ドストエフスキーという人間の本質は、彼の政治論にあると小林は見ていたということだ。
そのドストエフスキーが「殆ど唯一の思想の淵源」であったと言うからには、小林の思想に政治学が欠けていたはずがない。政治に対する深い理解がなければ、ドストエフスキーを掘るどころか、近づくことすらできないはずだからだ。
また、小林は、日華事変が勃発した昭和十二年には、「戦争について」を書いている。戦争とは、クラウゼヴィッツを引くまでもなく、政治の延長であるから、この随筆はれっきとした政治論だと言ってよい。
日華事変は、次第に戦線が拡大して泥沼化し、昭和十三年には国家総動員法が公布されるなど、総力戦の様相を呈していった。昭和十四年に第二次世界大戦が始まり、昭和十六年には大東亜戦争(太平洋戦争)へと突入した。
こうした非常時の中で、小林は、戦争、政治あるいは歴史について、深く思索を巡らせた随筆を少なからず書き、昭和十七年の「近代の超克」座談会に参加し、文芸銃後運動にも協力していた。そうした随筆や講演を具体的に列記すると、次のようになる。
昭和十二年:「戦争について」「宣伝について」
昭和十三年:「現代日本の表現力」
昭和十四年:「満洲の印象」「クリスティ『奉天三十年』」「慶州」「事変と文学」「外交と予言」「神風といふ言葉について」「学者と官僚」「イデオロギイの問題」
昭和十五年:「アラン『大戦の思ひ出』」「欧洲大戦」「処世家の理論」「事変の新しさ」「ヒットラアの『我が闘争』」「マキアヴェリについて」「文学と自分」「『戦記』随想」
昭和十六年:「モオロア『フランス敗れたり』」「『歩け、歩け』」「沼田多稼蔵『日露陸戦新史』」
昭和十七年:「戦争と平和」「『ガリア戦記』」
昭和十八年:「ゼークトの『一軍人の思想』について」「文学者の提携について」
さらに昭和十七年発表の「無常といふ事」「平家物語」「西行」や、昭和十八年発表の「実朝」もまた、政治、戦争あるいは歴史に深くかかわる随筆であると言える。
例えば、平家物語は、平安末期の大乱にあって「古いものの死と新しいものの生との鮮やかな姿を、驚くほど平静に、行動の世界のうちに描き出してみせた」(「実朝」〔昭和十八年〕、第八巻P57)ものだと小林は書いている。また、西行は「陰謀、戦乱、火災、饑饉、悪疫、地震、洪水、の間にいかに処すべきかを想つた正直な一人の人間の荒々しい悩み」(「西行」〔昭和十七年〕、第八巻P33)を抱いた歌人として描かれている。そして実朝もまた、頼朝亡き後の陰謀と暗殺が繰り返される中を生き、そして自らもその犠牲となった悲劇の主人公である。
昭和十七~十八年といえば、戦局が悪化し、敗戦へと向かっていった頃である。当時の戦局の事実は大本営が隠蔽していたから、一文学者がその状況を正確に知っていたはずもあるまい。にもかかわらず、小林は、この時期に、まるで滅びの運命を予感していたかのように、「無常といふ事」を書き、平家物語、西行、実朝を読んだ。