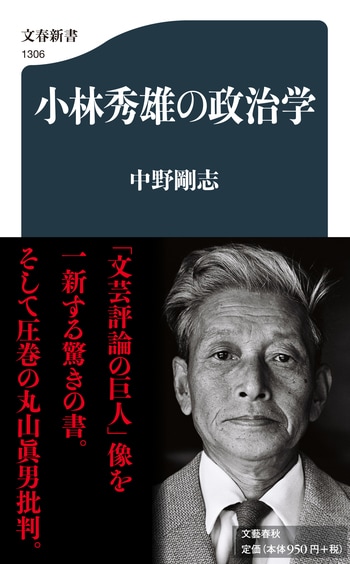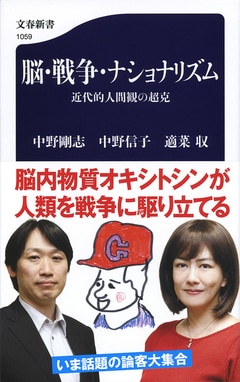序(※1)
※1 本書において、小林秀雄の著作や対談を引用する「全集」は、『小林秀雄全集』(新潮社、1967~68年。第十三巻と別巻は1979年のもの)、である。なお、旧かなはそのままとし、旧字は新字に改めた。
小林秀雄の政治学。
このタイトルを見て、訝しく思った人は多いだろう。小林秀雄と言えば、政治嫌いの文学者として知られているからだ。
確かに小林は、「政治と文学」において、「政治といふものは虫が好かない」(「政治と文学」〔昭和二十六年〕、第九巻P60)と吐露していた。それどころか、「私は長い事かゝつて政治への不信を育てて来た。格別な事を企図した訳ではない」(「感想」〔昭和二十六年〕、第九巻P146)とまで言っていた。
初期の作品である「Xへの手紙」には、すでにこう書かれている。「俺は人間の暴力を信ずるが物質の暴力を信じない。だから俺は政治の理論にも実践にもなんの積極的熱情を感じないのだ。俺はどんな党派の動員にも応じない。俺は人を断じて殺したくないし人から断じて殺されたくない。これが唯一つの俺の思想である」(「Xへの手紙」〔昭和七年〕、第二巻P98)。
ここまで言い切っている小林秀雄になお政治学を求めるのは、ローマ法王に軍事戦略を乞うような無理ではないか。そう思われるかもしれない。
しかし、実際に小林の全集を繰ってみると、意外にも、政治や社会についての言及が多いことに気づかされる。それも、かなり初期の段階からである。
例えば、小林の批評家としての出発点となった昭和四年の「様々なる意匠」について見てみよう。
そもそも「様々なる意匠」は、プロレタリア文学の全盛期に書かれたということもあって、マルクスについての言及が少なくない。小林は、昭和六年には「マルクスの悟達」なる随筆も著している。実は、亀井秀雄が明らかにしたように、若い頃の小林は、マルクスの『哲学の貧困』『経済学批判』『ドイツ・イデオロギー』を読み、深く理解していたのである(※2)。このようにマルクスに高い関心を寄せ、深く理解していた小林が、政治について無関心であったとは思われないのである。
※2 亀井秀雄『小林秀雄論』(塙書房)、1972年、第一章。
小林が批評家としての活動を開始した昭和初期という時代背景に目を転じてみよう。
昭和三年、第一回普通選挙が実施され、大衆民主化が始まった。そして、昭和四年の「様々なる意匠」の発表後、間もなくして、世界恐慌が起きた。その翌年には、昭和恐慌が起き、浜口雄幸首相が狙撃され、翌々年には満洲事変が勃発した。それに、昭和七年の血盟団事件、五・一五事件と続き、昭和十一年には二・二六事件が起きている。
このように、日本の政治が大衆民主化すると同時に不安定化し、戦争への道へと転落していくのと並行して、小林の批評活動は始められ、進められたのである。この当時の危機的な政治情勢が、鋭敏な小林の批評にまったく影響しなかったとは考え難い。
また、小林は、昭和八年から同三十九年の長きにわたって、ドストエフスキーについて論じ続けたが、ドストエフスキーは、極めて政治色の強い作家である。
周知の通り、ドストエフスキーは、政治犯として官憲に逮捕され、死刑判決を受けるも恩赦によりシベリア流刑となったという経歴をもち、この時の経験を、後の作品に反映させたと言われている。また、ネチャーエフ事件(秘密結社を組織したセルゲイ・ネチャーエフが組織内の学生を殺害した事件)をモデルにして『悪霊』を書いてもいる。そういうドストエフスキーについて、小林は「久しい間、ドストエフスキイは、僕の殆ど唯一の思想の淵源であつた。恐らくは僕はこれを汲み尽さない。汲んでゐるのではなく、掘つてゐるのだから」(「『ドストエフスキイの生活』のこと」〔昭和十四年〕、第五巻P226)とまで言っていた。