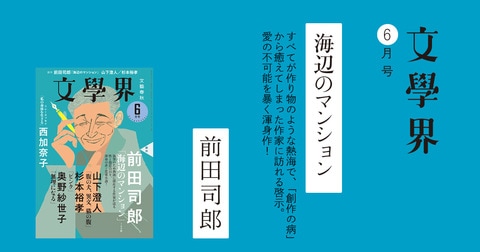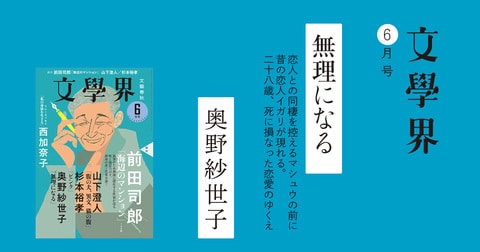リヴィングにみなれない絵が飾ってある。スタインウェイ越しの白い壁面に、その身幅とほぼかわらない横長の額縁がかけられ、そのなかは一面に黒い。たしか昨晩までは別の作品が飾られていたはずである。小振りの海景だった。近寄ってみると、絵をおおう透明なアクリル板に起き抜けの中年顔が映りこむ。いや、初老の顔と言うべきか。
アラームが鳴る。小走りにキッチンへと戻り、きっかり十五分のあいだ沸騰させた湯をマグに注ぐ。有機のにんじん、りんごとレモンはすでに専用のスロージューサーで絞ってある。盆にグラスとマグを二つずつのせてダイニングテーブルのうえに移し終えたとき、ちょうど瞑想を済ませて寝室から出てきたデイヴィッドの手がわたしの背に触れた。
「君はまるでドイツ人だな」
挨拶代わりにそう言うと、なぜ? と彼はうえからわたしの顔を覗きこむ。
「日本人だって時間に正確だろう?」
「彼らは臆病だから十分前には待機しているよ」
彼ら(They)、ね。デイヴィッドは、英語教師のように舌をうえとしたの歯にこれみよがしに挟ませて、ゆっくりと発音してみせる。
テーブルを挟んで腰をおろすと、わたしたちはまずマグに入った白湯をゆっくりと時間をかけて啜っていく。それが終わると、野菜ジュースの入ったグラスを一息にあおる。数年まえに人間ドックでともにコレステロールの値を指摘されて以来、デイヴィッドの提案で取り入れたファスティングと呼ばれる朝食メニューだった。同じものを朝に晩に食べてきた二人の血が同じように劣化し、そしていま断食によってともに浄化されていくというのは至極シンプルでまっとうなことのように思える。
「ところであれはどうしたの?」
わたしはまだ湯気のたつ白湯を少しばかり口に含みながら、黒い絵に目線を送った。
「このまえ出張で上海に行ったときにみつけたんだよ」
それから彼はたまたま西岸地区で開催されていたというアートフェアに出展していたローカルの有力ギャラリーから新進の中国人アーティストを売り込まれたときのことをわたしに話して聞かせた。熱中するあまり、手が止まっている。いや、彼は猫舌だから、まだ熱くて白湯が飲めないのだろう。
「ぼくらの部屋の雰囲気にとても合っている」
だろう(You see)? 手まえにある漆黒のグランドピアノの存在感と相まって、朝日のなかで眺めるそれはいかつい要塞めいてみえなくもないが、夕食後にダウンライトの光量を絞ってワイングラス片手に彼が鍵盤に指を這わせれば、ちょっとしたライブハウスのようにみえるかもしれない。自信ありげにこちらの顔をみつめてくる彼に軽い調子で訊ね返す。絵はインテリアではないよ? すると彼は知ってるとばかりに頷いてから、あくまで投資対象、といつものように応える。反論する代わりに、わたしは絵の感想を素直にこぼした。
「それにしてもいまはこういうのが流行りなんだね」
「こういうのって?」
「なんというか、糞みたい(shitty)な絵さ」
そう言うと、彼は小さく吹き出す。
その一面に塗りこまれた黒の油絵の具には、それを制作したアーティストである彼女の――思い出せないのか、異邦人には発音が難しいのか、具体名に一度も言及することなく彼は人称代名詞を用いた――生存する親族全員の体毛が練りこまれているらしい。その制作意図についてわたしが訊ねると、彼はとにかくタイトルは『希望』というらしいよと笑ってお茶を濁すばかりである。けれども作品の価値が跳ねあがるのも時間の問題だと熱弁するところをみる限り、おそらく彼は出張のついでに絵を買ったのではなく、絵を買うついでに出張したというのが実際のところなのだろう、そんなことを確信していると、
「ここに本物の糞(real shit)を飾るよりはマシだろう?」
彼の言うそれが特定の美術作品を指していることはすぐにわかった。YBAs(ヤングブリティッシュアーティスト)のひとりとして名高い、デイヴィッドと同じナイジェリアをルーツにもつその現代美術家は、象の糞を絵の台座あるいは絵の具そのものの原料に用いることで知られている。
この続きは、「文學界」6月号に全文掲載されています。