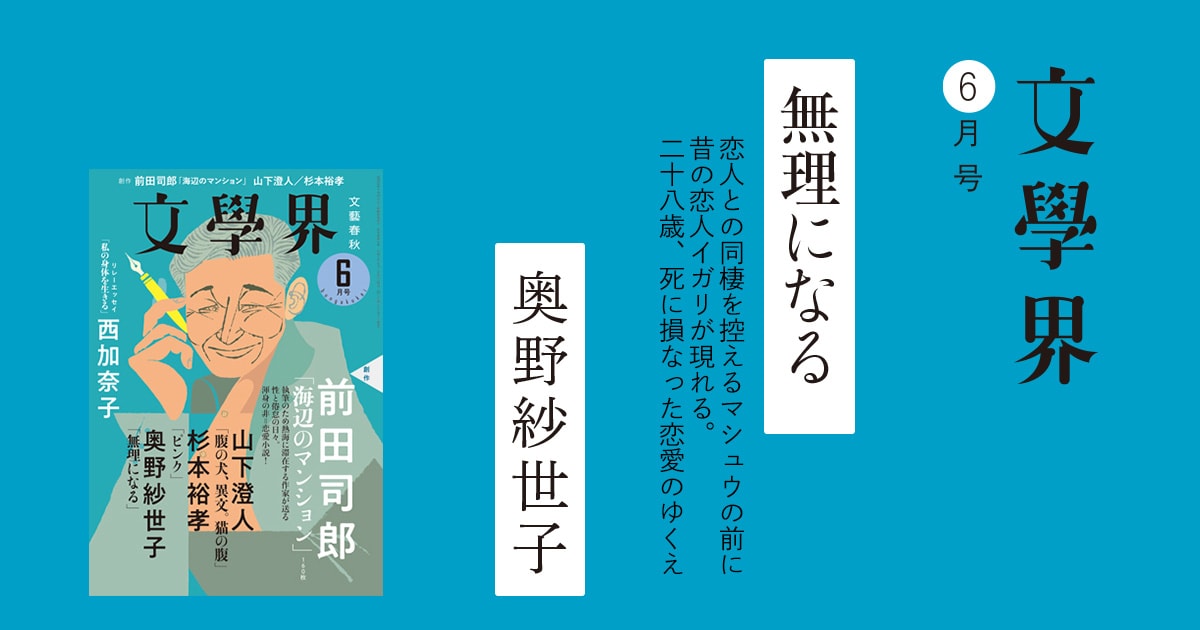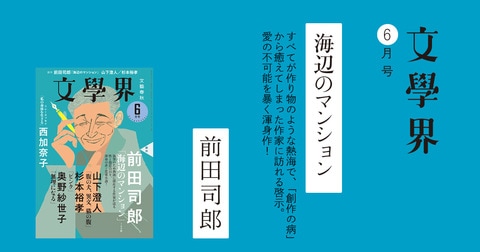辛味チキンを持って来た店員が去り際に向かいの席を見た。もたれるように置かれたトートバッグから熊手がのぞいている。
先月の酉(とり)の市(いち)で買ったものだ。わたしは千円くらいので良かったけど、それは稲穂が垂れ下がっているだけで物足りない感じだった。迷っていたら店のおじさんが二千五百円のやつを二千円に負けてくれたのだ。おかめと小判と開運招福の札がついている。
イズミは五千円のエビスと鯛と造花が盛ってあるデコラティブな熊手を買った。来年から独立してフリーランスになるから気合が入っているのだ。
どうせ同居するのだし、合算して八千円くらいのやつを買ったほうが良かったかもしれない。熊手は年々グレードアップさせるものらしいから、いつか靴箱の上に七福神が総動員された御輿のようなやつが鎮座する時が来ると思うとがぜん同棲の感じが盛り上がってくる。
このサイゼリヤにもう来ないかもしれないと思うと名残惜しい。調布にもサイゼリヤはあるけど広すぎて落ち着けない。ここはいつ来てもわりと空いているし、二人掛けのソファ席が多いこともあって好きだった。すでに千円以上注文しているわたしはこの店に別れを切り出しつつあるのかも知れない。
イズミと付き合いだした時、バシエリは珍しく祝ってくれた。知り合ったのが銀行員のタマキの結婚式だったことも縁起がいいらしい。
「イズミくんいいよ。いちばんちゃんとしてるし」
バシエリはわたしがいままで付き合った男がシーシャ屋の店員とDJと変なミュージシャンだと知っている。
いつもwebカメラ越しに進捗を報告している。ヘアバンドで髪をあげたバシエリには眉毛がない。通話しながらテーブルの上に林立した様々な大きさの青い瓶の中身を手に取ってはどんどん顔につけていく。
「それはそうかもしれないけど、なんか不安だよ」
大学生の時に二年ほど人と住んだことがあった。あれのことを同棲と呼ぶのかわからない。いつまでも人の部屋にお邪魔しているような忍び足の感覚が抜けることなく、あっけなく関係が解消されてしまった。わたしはどうにもあの部屋を出た足取りのまま、いまに至っているような気がしている。
「意外とどうにかなるもんじゃないの?」マイク越しにあきれたような息遣いを感じる。
「そうかなぁ」
三十二歳で、映像制作会社で働いている、すこしオシャレな男。実のところわたしはイズミをそれくらいでしか認識できていないのではないだろうか。イズミもまたわたしのことをそれくらいしか知らないのかもしれない。
「善は急げじゃない?」
わたしはバシエリのことを学年で最初にアイプチを使い出したときからずっと尊敬している。いまでも、とろいわたしの方を振り返ってなにか教えてくれるような気がしていた。
「善って男女交際でも急いでいいの?」
「二十八歳にはそのくらいのスピード感が必要じゃない?」
それから話題はバシエリがオンライン会議のために女優ライトを買うかどうかに変わった。
サイゼリヤではいつもペペロンチーノに青豆の温サラダを乗せて食べる。粉チーズをかけて半熟卵をかるく混ぜると、ニンニクの向こうからカルボナーラが現れる。ペペロンチーノな上に、カルボナーラ。もはや完全栄養食である。
右手にフォーク、左手にiPhoneの終わりスタイルで麺をすする。Twitterを開くと、kulsko onlineが[新進気鋭のマルチプレイヤー石垣まいとベテラン猪狩務がタッグを組んで放つ問題作『curve causers』!]という記事をツイートしていた。わたしが取材した記事である。カルチャー誌のkulskoは七年前に廃刊になり、いまはwebマガジンとして展開されている。
二千三百人のフォロワーに向けて「猪狩務さん(@t_igari)と石垣まいさん(@isgk_maimai)にインタビューさせていただきました! 衝撃の傑作「curve causers」! 濃厚な内容です! ぜひご覧ください!」と宣伝する。
本当はまったく濃厚な内容とは言えない。猪狩務は終始歯切れが悪かった。
この続きは、「文學界」6月号に全文掲載されています。