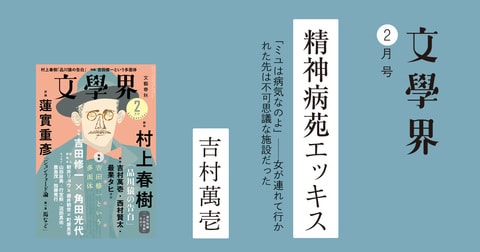街角や駅の構内あるいはパーティ会場などで不意に人から声をかけられることがある。その顔は大抵笑みや驚きに満ちていて、目のまえの奇遇を全身で祝福しているようにみえる。知っている。わたしはこの人と以前なんらかの関わりをもったことがある。けれどもそれが具体的に何だったのか、すぐには思い出せない。そういうとき、わたしは一拍の遅れをとりながらも相手の表情を鏡像のようにして自分の顔に繕い、当たり障りのない挨拶をおそるおそる交わしながら向こうの出方を待つ。相手の口から繰り出される言葉の端々に神経を張り巡らせて、思い出すための糸口をなんとかみつけようとする。それが記憶力の問題なのか、それとも交友関係が日々目まぐるしく積み重ねられ更新されていくことの必然なのかはわからない、間宮潤一が職場を訪ねてきたときも、そのような状況とどこか似たような感覚にわたしは捉われた。――やあ。――久しぶり。――元気そうだな、お前も。彼が学生時代の同窓であることは当然わかっていた。けれどもかつてどのような親密さと距離感で接していたのだったか、そしていまどのような親密さと距離感で接するべきなのかを、一階の受付フロアに降りてきたわたしの姿をみとめるなり笑顔で近づいてきた彼の口から繰り出される台詞をそのように殆ど鸚鵡返しにしながら、わたしは繕った笑みのしたでどうにか見極めようとしていた。――お前も全然変わらないな。そしてまた彼と同じように感嘆の声を漏らす。口角と眉をやはりまた鏡うつしにもちあげてみせながら、おそらくはおよそ十年振りに再会する彼の顔やスーツに包まれた体躯を、わたしは幾らかの警戒心を胸に眺める。