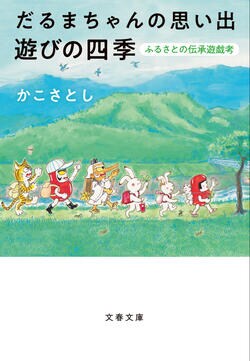
新型コロナに怯えて自宅籠りのこのごろ、子供の書棚に、昔読んだ絵本を見つけて読み直す大人の方もいるだろう。かこさとし作の『だるまちゃんとてんぐちゃん』や『からすのパンやさん』がその中にあるかもしれない。
平成30年(2018)、92歳で他界した、かこさとし(加古里子・本名中島哲)さんは、今挙げたような童話絵本の名作のほか、子供が科学や工学の世界に親しむための絵本も数多く手がけ、幅広いレパートリーを持つユニークな絵本作家として知られる。その人が多忙な絵本の制作のかたわら、生涯かけて取り組んだのが、子供の遊びの世界の調査と記録である。
加古さんは大正15年(1926)福井県今立郡国高村に生まれ、武生町(現・越前市)に転居、7歳で東京に移るまでこの地に育った。本書『だるまちゃんの思い出 遊びの四季』は、“当時は他と比較して、とりたてて自慢できることも少ない、北陸の一つの田舎町だった”と氏が回想する武生で体験した四季の遊びのさまざまを、絵入りで再現したものである。
タンポポやペンペン草など、さまざまな野の花とたわむれた「春」の遊び。丈高い草を敵に見立て、手ぬぐいで小魚を掬う「夏」の遊び。彼岸花の茎を割いて輪をこさえ、はだしで駈ける子供の脚を引っかける草わなつくりの「秋」の遊び。やかんの湯気で曇ったガラスに指でラクガキし、雪を使ってあらゆることをする「冬」の遊び――豊かな自然の四季の移り変わりと、それに敏感に反応する子供の遊びが本書の主題だが、相撲ごっこ、鬼ごっこ、パチンコ遊びなど、季節を問わず行われる遊びも加えられ、総数合わせて46項に及ぶ。
加古さんが武生で生活したのは7歳までだった。最初の数年間を差し引けば、その間の遊びの体験の豊富さに驚かされる。草花や昆虫の名前、遊びの仕方まで、こと細かく記録され図解されている。我が子に遊びを教える父や母の面影までそこに加わる。遊びの相手となる草花や虫を歌った全国のわらべ歌がさりげなく添えられている。女の子の遊びも、自分自身がそこに加わったかのように詳しい。その頃の自分になりきった加古さんの思いが絵と文で伝わってくる。
*
私が加古さんと知り合ったのは、川崎古市場の東大セツルメントで、1954年ころだったと記憶する。加古さんは当時、毎週日曜に開かれる、セツルメント子供会のリーダーを務めていた。近所の化学工場に勤める技師でありながら、自らつくったプロはだしの見事な紙芝居をその都度持参して、子供たちを魅了していた。あなたたちも一つ作ってはどうかと、加古さんに言われ、宮沢賢治の童話をもとに、友人と共に苦心して作って見せた。だが加古さんの作品を見慣れている子供たちには通用せず、残念な結果に終わったことを懐かしく思い出す。
時が経ち、生まれた子供のための絵本を店で探していると、かこさとし『だるまちゃんとてんぐちゃん』が見つかった。絵本作家として活躍を始めた加古さんを知って嬉しかった。
さらに時が過ぎた2005年の暮れ、私は藤沢のあるセミナーの教室で、氏の講演を聴いた。後でふれる『伝承遊び考』の内容を要約したようなお話に続き、社会が子供から遊びの場を奪い、豊かな発想力を奪っている現状を激しく批判し、それから紙芝居を実演された。新聞紙ほどの大きな画面の後ろに顔を隠してゆっくり話される。それは、インドの古い実話を取り上げたもので、幼い子をつれた白象の母親が、山火事に遭って逃れられないと悟り、自らの体で子を覆う、親は焼け死ぬが子は助かる、というストーリーだった。子連れの母親は涙を流して見ていた。
加古さんは視力が以前から悪く、講演のときはそれがさらに進んでいた。それを知らなかった私は、久しぶりの対面が嬉しくてサインを求めると、応じて下さった。「かこさとし」の「し」の後半が、真横の直線を長く引いている、その直線が機械で引いたような鋭いものとなっているのに、エンジニア出身の加古さんの、愚直なまでの真面目さ、誠実さを見る思いがした。
*
話を本書のことに戻そう。“出来るだけその当時の自分に立ちかえって、その心と立場から遊びの面白さとよさを記すようにした”と「まえがき」しながら、同時に子供は“生存や生活や人間関係やらの、さまざまな悩みや葛藤の渦まく生きた社会の中で「遊んでいた」はずである”とも書かれている。子供の遊びを理想化し、それを美化することによって、現実から逃避する態度を戒める氏の姿勢がここに見られる。
氏が武生で遊んだのは、日本が軍国化され、戦争に突入する直前の時期だった。この本の中にも「兵隊ごっこ戦争ごっこ」が扱われている。そこでは、戦争ごっこに夢中になった子供の態度がひたむきに擁護される。敗戦の時、加古さんは19歳、同年配の少年が特攻隊を志願する年齢でもあった。加古さん自身も、かねてから航空隊にあこがれる軍国少年だったが、そのころすでに視力が悪く、陸軍士官学校を受験すらできなかったという。
敗戦により虚脱状態となり、大人不信に陥った加古さんにとって、荒廃の世相の中で子供の遊びの生活に寄り添い、それを守り、そこで教え教わることが新しい生き甲斐となった。「兵隊ごっこ戦争ごっこ」のところで加古さんは、子供の戦争ごっこと大人の戦争とは全く別のものだと主張する。ロングセラーとなった『未来のだるまちゃんへ』(文春文庫)の「はじめに」で、終戦と呼ばず敗戦と呼びたい、と強くいう。その気持ちは、敗戦当時13歳だった私にはよくわかる。
*
本書は、最初、じゃこめてい出版という個人的な出版社からの依頼で1975年に発行され、それが学者・評論家の坂西志保氏(1896~1976)の目にとまり、第23回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞した。著者は坂西氏の推薦に厚く感謝している。そしてその後、2018年に復刊ドットコムで復刊された。
そのような経緯の本が、今回文庫本として再刊されたことの意味は大きい。生まれ育った美しい故郷への思いと、遊びの記憶とがつづれ織りとなった本書には、氏のライフ・ワークというべき、4冊本『伝承遊び考』(2006~08・小峰書店)の雛形ともいえる部分も含まれている。「鬼ごっこ天国」「じゃんけんうた抄」「じゃんけんグリコとび」などがそれである。
加古さんが、子供の遊びに関心を持ったのは、氏が川崎古市場のセツルメントに入った1950年の頃だった。子供たちが地面に絵や図形を描いて遊ぶ様を氏は、いっしょに遊びながら熱心に記録した。その作業は以後、半世紀余り続けられ、全国から集めた資料は29万点に及んだ。その成果が『伝承遊び考』に実を結ぶことになるのだが、満を持していたのだろうか、氏の子供の遊びについての本が出たのは、1975年初版の本書が最初であり、それも、幼い自分の体験した遊び、という限定を付けてである。その中に、『伝承遊び考』の原形があることはすでに述べた。
膨大な資料を綿密に整理し、正確な記録を意図して描かれた『伝承遊び考』の記号的な図に対し、この本では、絵本作者としてすでに高く評価されていた氏の描く子供たちの姿が、のびやかで楽し気だ。大人たちの童心を呼び覚ます魅力がそこにある。














