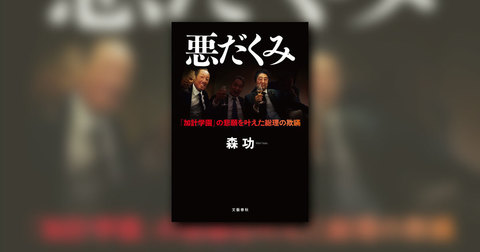私は、かつて安倍昭恵首相夫人を取材し、「安倍昭恵『家庭内野党』の真実」という記事を書いた(『文藝春秋』二〇一七年三月号)。
当時、原発の再稼働に反対するなど、夫とは真逆の意見を口にする首相夫人を一部のメディアは、「家庭内野党」、「物言うファーストレディ」と誉めそやしていた。
だが、そのような見方は正しいのか。
むしろ彼女は価値観の根底を夫としっかりと共有しており、同志的に連帯している。夫とは常に補完関係にあり、だからこそ政権も夫人に五人もの秘書をつけて、公人と変わらぬ振る舞いを許しているのではないか、と私は書いた。
すると記事の発表直後、森友問題、続いて加計問題が起こった。私は自分が昭恵夫人を取材していたという経緯もあって、この問題に強く惹(ひ)かれた。
なぜ、どうして、このような問題が起こったのか。事件の全体像や本質を知りたいと思ったのだ。ところが次第に国会での野党の追及や、メディアの報道は、誰が、いつ、どのような忖度をしたのかという一点に傾いて隘路(あいろ)に陥り、私の疑問はそのまま胸に残って解消されなかった。
だからこそ、二〇一七年十二月に本書が単行本として刊行されると、すぐさま読んだ。そして、ようやく答えを得られたと感じた。
幾重にも絡まる蔦のような人間関係、それを著者は過去にさかのぼり丹念に調べ、すべての基にある安倍首相と加計孝太郎加計学園理事長の、義兄弟のような結びつきを詳らかにしている。
ふたりが知り合ったのは四十年以上も前のアメリカ。南カリフォルニア大学での留学生仲間だった。やがて、それぞれ父親から地位と財産を受け継いだふたりは、互いに便宜を図り合う仲となる。周囲を巻き込み、「公」を蝕(むしば)むほどに。
彼らの関係性が大きく変わるのは、小泉政権下で進められた規制緩和、「教育の自由化」以降だと本書から知った。それまでの規制が取り払われ、教育事業も新規参入のできるビジネスへと変貌していく。加計理事長はこの機運を捉えて、安倍を後ろ盾とし、事業の拡大を図っていくのである。
少子化が進む日本で二〇〇〇年以降、私立大学が次々と新設されていったのも、こうした事情による。一九九五年時点で五六五校だった大学は二〇一九年現在、七八〇校。これだけ増えれば一方で、倒産する大学が続出してもよさそうなものだが、そうした話はあまり聞かれない。助成金という名の税金が投入されているからだろう。もちろん、学生の定員割れが続けば経営は苦しくなるし、私学助成金も減額される。そこで日本人学生だけでは定員を満たしきれない新設大学は、留学生をかき集めるのである。
加計理事長がやってきたことも、つまりはそういうことであった。
関東進出が長年の夢であった彼は政治力を駆使し、安倍の力も借りて、過疎化に悩む千葉県銚子市にまず千葉理科大学(現・千葉科学大学)を新設する。だが、肝心の学生が集まらない。そこで留学生を求めて海外へと手を広げていくのであるが、これを後押ししたのもまた、安倍首相夫妻だった。首相の応援が効いて、加計学園はフィリピン最大の日本語学校と業務提携することに成功している。
さらには、ミャンマーへも進出するが、ここでは安倍昭恵夫人がより大きな役割を担ったと、本書に詳しい。
昭恵夫人は、森永製菓の創業者一族という恵まれた家庭に生まれ、幼稚園から聖心女子学院に通ったが、勉強もスポーツも苦手な劣等生で系列の四年制大学には進学できず、人と自分を比べては落ち込んでいたという。内向的で政治家の妻になってからも人前に出ることが苦手だった、とも。これは私自身が彼女にインタビューをした際、本人から直接、聞いたことである。
ところが、彼女は夫が総理になり、首相夫人を経験してから大きく変貌を遂げる。自分に自信を持つようになり、自分に目覚めていったのだ。自分が動けば周囲を変えることができると感じるようになり、「私を利用してもらいたいと思った。人と人とをつなぐこと、それが私に与えられた使命だと気づいた」が持論になる。
同窓の先輩である作家、曽野綾子のアフリカにおけるボランティア活動に同行して感激した夫人は、自分も同じようなことをしたいと考え、夫の勧めもあってミャンマーを選んだという。そして、二〇〇六年から毎年、まだ軍事政権下にあった同国を足しげく訪問。夫人は「ミャンマーに貧しい子どもたちのための寺子屋を作りたい」と考えるようになるが、その夢は加計理事長の支援により、あっさりと実現する。
その後、二〇一一年にミャンマーが民主化され、二〇一二年に第二次安倍政権が誕生すると半年後、安倍首相は財界人約四十人を連れてトップセールスに赴くのだが、その政府専用機には加計理事長も同乗していたと本書は明かす。
こうした流れの中で、加計学園は他の学校法人に先駆けてミャンマー支局を設立。ミャンマー人を加計学園傘下の学校に留学生として送り込む窓口を得るのである。
一見、昭恵夫人の突拍子もない我がままに加計が協力し、その見返りを安倍首相が与えたように映るが、逆に、安倍首相が自分の立場では赴けない軍事政権下のミャンマーに先遣(せんけん)として夫人と加計を送り込み、人脈の下地づくりをさせたようにも受け取れる。本書を読み、考えさせられた部分だった。
日本国内での学生不足による赤字を補填(ほてん)するため、海外、それも発展途上国へと触手を伸ばしていく。それを日本の首相夫妻も積極的に後押しする。何よりも気になるのは留学生のその後だ。日本に赴く若者たちの夢や目的は叶えられるのか、それとも踏みにじられてしまうのか。中には多額の借金をして学費を工面した学生もいるであろう。あるいは大学には初めから期待せず、日本に入国するための手段として、学生ビザを取ることだけを目的に入学する若者もいる。そうした出稼ぎ目的の留学生たちは、入学後、大学から姿を消して、日本国内で行方不明者となる。それを承知で留学生を集めるような大学、それを許す教育行政を今、日本は推し進めているのである。
補助金を得て過疎地に大学を新設し、留学生を求めて海外にも進出した。しかし、それでも定員割れは解消できず、赤字が続いた加計学園は次の手を求める。
それが、獣医学部の新設であった。
獣医学部は「儲かる学部」と教育業界では言われている。人気漫画の影響で志望者は多く、六年制で学費を高く設定できるからだ。しかし、獣医師が増えすぎて過当競争となることを避けるために、「教育の自由化」以降も、医学部、歯学部などとならんで獣医学部は規制の対象となっており、新設は不可能とされてきた。
にもかかわらず、その固く開かぬはずの門が、加計学園にだけ開かれていく。愛媛県今治市が「国家戦略特区」に指定され、特区事業として獣医学部の新設が認められて、しかも、加計学園の申請だけが通るのである。特例中の特例であり、「総理のご意向」が働いた結果ではないか、と多くの人が疑念を持つのは至極、当然なことであった。
森友問題も、加計問題も、ともに学園を舞台にしている。
安倍政権下の教育行政では、教育も市場経済に任せればいいという新自由主義的な考えと、復古的なナショナリズムが同時に台頭した。加計問題は前者から、森友問題は後者の流れから生まれたと見ていいだろう。本書では、「森友は、第二の加計学園」であると強調されているが、これは重要な指摘だ。世間では問題発覚の順番から「加計は、第二の森友学園」と誤解されている向きがあるが、それは違う。
昭恵夫人は、森友学園の籠池理事長夫妻と知り合い、教育勅語を朗読させる教育理念に共感した。だからこそ、同学園が新設するという小学校の名誉校長になることも躊躇(ちゅうちょ)せずに引き受けたのである。籠池理事長夫妻から、「国有地の払い下げがなかなか進まない」「認可が下りない」という悩みを聞かされれば、その都度、力を貸しもした。
脇の甘い、お人よしの首相夫人がアクの強い理事長夫妻にわけもわからず搦め取られた、と説明する報道が多かったが、そのような見方は間違っていると思う。
もともと、昭恵夫人は、加計学園が経営する「御影インターナショナルこども園」の名誉園長を引き受けていた。また、なによりも夫と加計理事長の関係性を長年、間近に見続けてきた。だからこそ、森友学園が新設する小学校の名誉校長になることも問題だと思わず、夫が加計の大学新設に力を貸したように、自分もまた、官庁に働きかけて、夫の思想に沿った教育をする、夫の信奉者である籠池理事長夫妻に心から尽くそうと考えたのだろう。
首相である夫の周りには政権を支える取り巻きがいる。彼ら彼女らに引けを取りたくない、自分も夫を支える存在でありたいと張り合う気持ちも夫人にはあったのだろう。
森友問題を夫人の暴走だと片付けるのではなく、夫人を利用し、夫人にも権力を与えてきた夫や政権の責任を、より重く見るべきではないか。
男たちはゴルフ、カラオケ、酒で交友を結び、互いに利益を与え合う。そこにまた、女たちも悪びれることなく加わった。下村博文元文科省大臣夫人の下村今日子と昭恵夫人の享楽的な遊びぶり。「文科省大臣夫人」「首相夫人」の肩書で、ともに加計学園の広告塔にもなっている。本人たちは夫のため、国家のためとでも思っていたのか。
本書を読み私は、現役総理がかかわったとされるダム建設をめぐる汚職事件をリアルタイムで描いた石川達三のモデル小説『金環蝕』を思い出した。約半世紀前に書かれた作品だ。当時の日本では、ダムや原発といった公共事業に莫大な税金がつぎ込まれており、そこで政治家が口利きをし、見返りに建設会社から賄賂を受け取るといった、わかりやすい悪の図式があった。
翻って今の日本では、おいそれとダムや原発は新設できない。だが、二〇〇〇年以降、「教育の自由化」の御旗のもと、新しい形の公共事業が生まれたのではないだろうか。
もちろん、かつての建設事業と教育事業では違いもあり、昔のような現金の授受は今のところ見つかってはいない。ただ、普通の教育者では得られない、特別な「便宜」が図られたことは、どう考えても確かであろう。教育事業を行おうとする一個人が、たまたま時の権力者と近いというだけの理由で。首相夫妻、あるいはその取り巻きと親しく、インナー・サークルを作っている人たちだけが、国から優遇され、教育に乗り出せるとすれば、それは「公教育」を私的な事業に変質させてしまう。校舎の建設用地も、建設費も、そして私学助成金も、公共の名の下に負担しているのは国民であるのに。
「教育の自由化」や特区という変革を悪用して、私的な関連性を公の場に組み込ませていく。首相を中心として、べったりとした気味の悪い共同体が作られ、国家も行政も私物化されていく。首相が露骨に「お友達」を優遇するのを見て、政治家も官僚も民間人も恭順の意を示すようになる。その過程と構図を本書は、見事に暴いている。
加計学園問題の本質を知りたいと思う読者だけでなく、平成の末期、日本に何が起こったか。終わりの始まりを知りたいと思う人々によって、本書は後々まで読み継がれていくであろう。