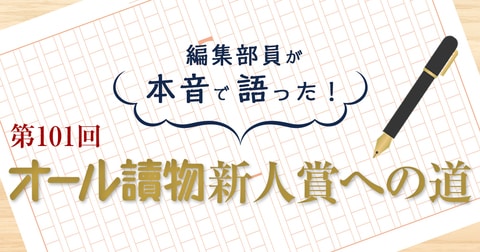第101回を迎える今期より、募集ジャンルを特化したオール讀物“歴史時代小説”新人賞。締切がひと月後に迫る中(6月20日受付締切)、昨年の第100回を時代小説「をりをり よみ耽り」で受賞した高瀬乃一さんが、受賞第1作となる「板木どろぼう」をオール讀物6月号に寄稿した。

受賞作の舞台は、文化年間の江戸浅草。女手ひとつで貸本屋を営む〈おせん〉の奮闘を描く“ビブリオ捕物帖”だった。新作も、このおせんが縦横無尽に活躍するシリーズ作。得意先の版元でおきた滝沢馬琴の新作盗難事件におせんはどう挑むのか? 江戸後期、盛りを迎えた読本文化の楽しさと、捕物帖の面白さをともに堪能できる力作だ。
◇ ◇ ◇
――新作を書き上げた心境はいかがですか。
「貸本屋おせん」をシリーズにできたらいいなと思って、一生懸命に書きました。同じ主人公が活躍するわけですから、当然、「をりをり よみ耽り」と「板木どろぼう」とでキャラクターの軸がぶれてはいけない。だけど、受賞作の世界観を引きずりすぎて、完全な“続編”を書いてしまったら、今回、初めておせんと出会う読者の方は戸惑いますよね。おせんの内面も、家族の背景も、私の中ではしっかりできているんですけど、それを書きすぎないようにセーブして、むしろ馬琴の新作を彫った板木が盗まれるという事件の面白さを書くことに心を配りました。その書き方のバランスに苦心して、何度も手を入れましたね。

――新人賞の世界では「デビューよりも書き続けることが難しい」と言われます。
言葉の意味を、日々、実感しています。最大のプレッシャーは、受賞作よりも面白いものを書かないと雑誌に載せてもらえないこと(笑)。もっともっと勉強しなきゃという焦りはつねにあります。ようやく1作書けてホッとしたのと、また次作を書かねばならない重圧と、いまは半々くらいの気持ちですね。
――青森県三沢市で暮らす高瀬さんが新人賞への応募を始めたのは、ちょうど10年前。東日本大震災が背中を押したそうですね。
40歳になる直前のことでした。たまたま三女が生まれた翌年に、東日本大震災を経験しまして。人間いつ死ぬかわからないなと感じ、ちょうど人生の折り返し地点だし、悔いのない生きかたをしようと小説を書き始めました。三沢って何もないところで(笑)、子育てで外にも出られないし、私自身もちょっと病気をして家にいる時間が長くて、時間を見つけてはパソコンに向かいました。まったくの独学で、それこそ漢数字と算用数字をどう書きわけるのかもわからないところから、ひとつひとつ自分なりに調べて書いていきました。
――オール讀物新人賞への投稿は、全部で5回だと聞きました。
最初に出したのはファンタジー作品で、これは一次にも残りませんでした。2回目に応募した、母と年頃の娘を描いた現代小説(「彼女たちのいくところ」)で最終候補(第97回)に残りましたが、評価はボロボロ(笑)。その次に、男の人が女性に騙される不倫の小説を出してまったくダメで、急転直下、舞台を明治に変えた「ひとぼしごろ」で2度目の最終候補(第99回)に。その翌年、時代小説の「をりをり よみ耽り」で賞をいただいたという流れです。
――作風や題材をどんどん変えているのはなぜですか?
深い理由はなくて、書いてダメだったから違うものにしようと。別の主人公を書いてみよう、思い切って時代を変えてみよう、とチャレンジしていったわけです。
最終候補に残ると、選考委員の先生に選評を書いてもらえるじゃないですか。「彼女たちのいくところ」では、池井戸潤さんの選評が印象に残っていて、「読みにくい」「文章表現にしても、凝りすぎて意味がわからない」「もっとわかりやすく」と、要するに、全然ダメということなんですけど(笑)。当時の私は、純文学とエンタメの区別が存在することも知らずに応募原稿を書いていまして、けっこう小難しい比喩とか使ったり、感情を延々と説明したりしてたんですね。指摘されて初めて、もっともっと簡潔に、伝わる文章を書かないといけないんだな、とわかった。読む人の気持ちを考えるようになったのが、ひとつの転機になったかなと思います。
また、時代小説を書くきっかけをもらったのは、編集者のアドバイスでした。「彼女たちのいくところ」が落選した後、いまオールの編集長をなさっている川田さんからメールをもらいまして、
『宇喜多の捨て嫁』の木下昌輝さんは最初は現代ものを書いていたが、歴史小説に路線を変えて活躍されている。高瀬さんもそういう道を考えてはどうですか?
こういう趣旨の言葉をもらったんですね。何かしら私の書く文章の中に時代小説に通じるものがあったのかなと思い、「挑戦しよう」という気持ちになりました。そんな折、たまたま地元紙の「デーリー東北」で、「糠部三十三観音」を特集した連載記事を読んだ。明治期のちいさい祠がいまも残っているというエピソードに惹かれ、資料を調べて、あっというまに「ひとぼしごろ」の構想を思いつきました。
――明治時代を舞台にするのは難しくなかったですか。
考証的なことはまったく自信がありませんでした。ただ、私は青森に住んでいるので、主人公たちの言葉使いとか、土地の空気を伝えられれば御の字かなと。田舎は閉塞的なところなので、そこから飛び出す女の子の気持ちを描きたい。それだけでしたね。
この「ひとぼしごろ」で2度目の最終候補に残ったけれど、やっぱり「説明的」だという評がありましたし、(選考委員の)村山由佳さんの「主人公の染色に懸ける想いをもっと深く描いてくれていたら」との選評はこたえました。「をりをり 読み耽り」で江戸時代にチャレンジするとき、主人公のおせんがどうしてそういうふうに行動するのか、その「想い」をしっかり書こうと心がけました。
――江戸を書くにあたって、どんな準備をしましたか。
若い頃から時代小説を好きで読んでいたり、テレビで時代劇を見たりしていたので、そんなにハードルは高いと思ってなかったです。言葉遣いや生活様式など、わからないことは書店で資料を買ってごく基本的なところだけ勉強して……という感じです。
東京の地理になじみがないので、具体的な町の描写が難しかったですね。書いた後で「あ、この地名、間違ってた」と気づくことが何度もありました。当時の江戸文化の中心は日本橋だろうから、日本橋を中心に地名を調べていって……いちばん役だったのは地図です。大きな古地図をAmazonで買って、ことあるごとに眺めるようにしました。家の本棚にある藤沢周平さんの小説を読んで、『獄医立花登手控え』の主人公・立花登が歩く道筋を古地図で見たりしていると、なんとなく浅草から日本橋はこれぐらいの距離感で歩けるんだなとわかってくる。北原亞以子さんの作品もよく主人公が歩くので、その道のりを古地図で辿ってみたりもしています。
貸本屋に関する資料も、たくさん買うには買ったんですが、しっかり読んでいるものはまだ多くありません。日本史の基本的な知識さえあまりなくて、徳川家康から慶喜までの将軍の順番もあやしいくらい(笑)。いま、人生でいちばん本を読んで勉強しているところです。

――新作の「馬琴の板木が盗まれる」事件はとても魅力的ですが、アイデアはどうやって思いつくのでしょう。
題材はすぐ見つかるんですよ。当時の資料を読んでいても思いつくし、テレビニュースでも新聞記事でも、面白そうと思ったら、すぐに調べて想像を膨らませていきます。
この間も、まだちいさい子どもを持つお母さんが、ママ友に洗脳されてわが子を……というショッキングなニュースがありましたよね。江戸でこんなことが起きてしまったらどうなるだろう、と考えます。
この春、娘が独立して東京の学校へ進んだのですが、我が子を青森から東京へ送り出すのも、昔だったら今生の別れですよね。電話もSNSもない時代だったら、親子の別れはどういうふうになるだろう――と、私自身、3人の娘をもつ母親なので、まず母親としての気持ちを想像してしまいます。人の心は江戸の昔もいまも変わりません。これからも身近なところからヒントをえて、小説を書き続けていきたいと思っています。
◇ ◇ ◇