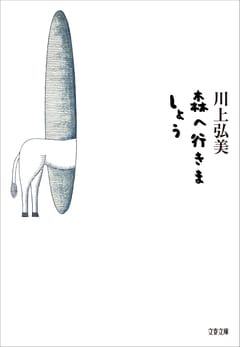二〇一五年、多和田葉子は、「変身」という日本語訳で広く読まれてきたフランツ・カフカの小説Die Verwandlung(一九一二年)に、「かわりみ」というルビをふった新訳を含む『ポケットマスターピース01 カフカ』(集英社文庫ヘリテージシリーズ)を編んだ。その解説にあたる「カフカ重ね書き」の中で、多和田は、精神分析の先駆者、ジグムント・フロイトの「マジック・メモ(ドイツ語ではWunderblock)」という概念を紹介している。「タブレット端末」のディスプレイを凝視していても、その向こうに別のデータが透けて見えることは決してないが、フロイトの「マジック・メモ」の場合、ボードの上にシートを重ねて何かを書いてからシートをめくれば、いったん、消えたように見えても、透かしてみれば、「文字の圧力でできた微かな痕跡」が残り、ボードに線が刻まれるという。フロイトがいうような「マジック・メモ」には幾筋もの線が浮かびあがり、読書の記憶も、「重層構造」を持つことになる。一度、書きつけられた線が織りなす像は、もう一度、読みなおしてみることによって、別の像として重ね読みされる。
本書『穴あきエフの初恋祭り』には、二〇〇九年から二〇一八年にかけて、「文學界」に発表された七篇の小説が収められている。長い期間を経て生まれた短篇集は、それぞれの人生の段階や社会状況の変化の中で、かつての読書で結んだ像とは異なる像を新たに刻んでゆく。カフカの小説がそうであるように、『穴あきエフの初恋祭り』に収録された小説も、重層的な読書経験をくれる。それだけではなく、近年、多和田葉子の文学について書かれた多くの批評や研究を重ね読みすることによっても、『穴あきエフの初恋祭り』はさらに豊かさを増してくるだろう。
『穴あきエフの初恋祭り』の単行本から文庫化されるまでの三年ほどの間にも、英語での論集Tawada Yoko : On Writing and Rewriting(ダグ・スレイメーカー編、レキシントンブックス、二〇二〇年)、震災後文学の視点から多和田作品について論じた論文が多く収められた『世界文学としての〈震災後文学〉』(木村朗子・アンヌ・バヤール=坂井編著、明石書店、二〇二一年)、多和田の文学について縦横無尽に思考をめぐらせた室井光広の『多和田葉子ノート』(双子のライオン堂、二〇二〇年)などが刊行されている。また、劇作家ハイナー・ミュラーについて書いた多和田の修士論文「ハムレットマシーン(と)の〈読みの旅〉――ハイナー・ミュラーにおける間テクスト性と〈再読行為〉」の日本語訳が収録された論集『多和田葉子/ハイナー・ミュラー――演劇表象の現場』(谷川道子・山口裕之・小松原由理編、東京外国語大学出版会、二〇二〇年)や『多和田葉子の〈演劇〉を読む――切り拓かれる未踏の地平』(谷川道子・谷口幸代編、論創社、二〇二一年)が刊行され、「演劇人としての多和田葉子」にも、光があてられている。『穴あきエフの初恋祭り』に収録された小説を初出で読んだ人も、単行本で読んだ人も、改めて文庫版を重ね読みしてほしい。そこに重ね書きされた像は思いもよらない模様になるかもしれない。
「胡蝶、カリフォルニアに舞う」(初出「文學界」二〇一八年七月号)は縦書きで書かれることが「慣例」となっている日本語の近現代文学を問う小説である。一〇年のあいだ、アメリカに留学した後、日本での就職面接のために帰国した「I」と、空港に迎えにきてくれた「優子」を軸にした小説は、「Iは優子のマンションで目を覚ました」という一文からはじまる。縦書きの小説の読み方に慣れている読者は、「I」を誰かの名前の頭文字だと思いながら、読みはじめるだろう。しかし、就職面接にむかう電車に乗っていた「I」は、「複数の線路」の「交差」に差しかかったとき、どの進路を選べばいいか迷う。英語と日本語の「複数の線路」の「交差」を思わせるこの場面の後で、「英語ならIも一人称になるかもしれないが、中央線の中ではそれはただの頭文字に過ぎない」と書かれている。読者は、この瞬間、日本語の縦書きという慣習にしたがって読み進めてきた自らの読み方に転換を迫られる。英語の一人称代名詞としては認識されなかった「I」は、頭文字「I」と一人称代名詞「I」の両方の意味内容を担うことになる。「I」というひとつの記号は、頭文字「I」と一人称代名詞「I」のあいだで、宙吊りにされる。だが、ふたつの言語を切り換えることは簡単にはできず、「正面衝突」したり、「脱線」するかもしれない危険に「I」はさらされている。また、この場面で、「そもそも日本語で思考する時さえ、自分自身のことをIという三人称で呼ぶIは、自分から逃げているのだ」と書かれている点も見逃せない。「その日、わたしはあなたに永遠の乗車券を贈り、その代わり、自分を自分と思うふてぶてしさを買いとって、「わたし」となった。あなたはもう、自らを「わたし」と呼ぶことはなくなり、いつも、「あなた」である。その日以来、あなたは、描かれる対象として、二人称で列車に乗り続けるしかなくなってしまった」という『容疑者の夜行列車』(青土社、二〇〇二年)の一節を思い出せば、「I」は頭文字になることで、「主体」となることを回避しようとしているともいえる。一方で、「I」の物語に乗せられないでいるのが「優子」だ。「優子のゆ」を「英語のユーかも知れないね。君のこと、ユーって呼んだらおかしいかな」と「I」がいうと、「優子」は、きっぱりと、「おかしいわよ」と答える。言語という虚構の列車、そして、その言語によってつくられた物語に乗るか、乗れるか、乗らないか。「胡蝶、カリフォルニアに舞う」は、言語によって対象化することでしか、自らについて把握できない「I」が、頭文字「I」として「主体」になることを迂回し、その後、「I」という、性別を持たない一人称代名詞によって女性へと変身してゆく変身物語でもある。日本語の一人称代名詞のジェンダー規範の強さを「I」という英語の一人称代名詞が解きほぐす。
「文通」(初出「文學界」二〇一八年一月号)は、作家、翻訳家の谷崎由依の書評「不在の穴を駆け抜ける」(『群像』二〇一八年一二月号)で指摘されているとおり、「源氏物語」の「宇治十帖」と重ねたくなる小説。しかし、「源氏物語」の登場人物である「浮舟」という名前は、「文通」では、浮子と舟子に分裂している。谷崎が書評で、「「浮舟」を連想する人物名だが、王朝時代の貴族よろしく交わす浮子との手紙は、恋文というよりむしろ恋愛を成就させないための文」であり、「ロマンスではなくその解体」を目論んでいると書いているが、うなずける。四一歳の誕生日が迫った頃、高校の同窓会が開催されることを知った陽太は小説を書く仕事をして生計を立てている人物。「源氏物語」の薫と匂宮は嗅覚にまつわる名前を持っているが、陽太は光や暖かさと結びつく名前であり、感覚が互換されている。通信手段が増える時代において、メールアドレスを公開していない陽太は、同窓会の知らせも、「葉書ルート」で受けとる。同窓会が開かれる日になると、現在の恋人である舟子との通信に用いている携帯電話の調子が悪くなり、「手書きのアドレス帳」に書いていた電話番号に電話をかけても、「この電話番号は現在使われていません」という機械の声。英文学者、評論家の武田将明が、「手紙や郵便という旧来の通信手段を登場させ、誤配に可能性を見出している」(「・言葉・によって世界に・穴・を穿つ七つの短篇集」「週刊新潮」二〇一八年一一月二九日号https://www.bookbang.jp/review/article/561081)と指摘するように、「文通」では、確かに「誤配」が起こっている。また、「文通」は、名前をめぐる小説でもある。特に、女性たちの名字。「源氏物語」の時代には、「女君」、「姫君」、「○○の娘」といった抽象化された存在だった女性たち。しかし、二〇二一年の現在においても、結婚するとき、ひとつの名字しか選べず、別姓が選べない状態は続いている。陽太が浮子に手紙を送るとき、「四文字の漢字」、つまり、明かされてはいない名字の存在が示唆される。陽太は名字と名の統合によってはじめて、浮子の姿の総体を見た気になるが、あくまでも、それは言葉でしか結ばれない像であることも示されている。「文通」は、浮子との手紙のやりとりが途切れるまでの出来事が、実は、「全国学生小説コンクールの恋愛小説部門」の「佳作」に入選した「小説」だったことが明かされて終わるが、現実と虚構の境目がわからなくなり、登場人物たちの言語交通回路では、「誤配」が起こりつづける。
「鼻の虫」(初出「文學界」二〇一二年二月号)は、新型コロナウィルス感染症拡大のさなかにある二〇二一年に読み返すと、それまでとは異なる印象を抱く小説。ドレスデンの衛生博物館で、「体の中の異物」という展示が行われる。それを見て以来、鼻の中にいるという寄生虫「鼻の虫」に興味を惹かれた語り手の「わたし」は、携帯電話を梱包する工場の課長として、安全を管理する仕事をしている。職場のひとつである包装部をはじめ、「わたし」が住む海辺の町は生物の影が見えない無機質な場所。「わたし」は、そこで、「鼻の虫」のことを思い出す。生きものの気配が消えてしまったかのような街に住む中で、「一度彼岸花を眼にしてしまったら、夢幻に墓場を訪れる度にその花を無視することができないのと同じで、一度博物館に足を踏み入れた者はもう眼には見えない寄生虫を見て見ぬふりをすることはできない」という、「わたし」の言葉は重みを持っている。もちろん、寄生虫である「鼻の虫」と新型コロナウィルスを同一視することはできないし、新型コロナウィルス感染症拡大は、政府の対応、国際協調、科学的知見への信頼、人権や個人の私権の尊重といった要素と切り離すことができない問題だ。それでも、新型コロナウィルスによって、人間が「異物」というべきものたちとともに生きていたことが浮き彫りになったことは確かだろう。多和田は、二〇二〇年一〇月に開催された「朝日地球会議2020」で、生命誌研究者の中村桂子とオンラインで対談し、「つねに人間が住んでいる文化、文明というのが危機なのであるということを自覚して、それを忘れないで、それについて考えつづけることを可能にしてくれるのが文化」であると話した。新型コロナウィルス感染症拡大で、多くの人々が亡くなり、日々の生活が立ち行かなくなった人々もたくさんいる。便利さを求めるあまり過酷な労働環境をつくりだし、社会福祉や医療の予算を削り、新自由主義の経済体制へと舵を切ってきた政治そのものが問われているといえるだろう。「鼻の虫」の最後の方で、「甘い蜜のにおいのする植物に囲まれて眼を閉じて深く息を吸う。ああ、この香りは、どこかにもう一つの魂が存在している、そういう香りだ」という言葉がある。決して、楽観はできないが、それでも、「見て見ぬふりをすることはできない」無数のものたちと共に生きてゆくための社会や環境のつくり方を考えてゆくことはできるだろう。現状を包み隠さず明らかにする言葉、そして、社会や環境のあり方を話すための言葉が求められている。
「ミス転換の不思議な赤」(初出「文學界」二〇一四年三月号)を読むために、一九九九年に東京外国語大学で行われた国際シンポジウムでの多和田の言葉を参照したい。多和田は、「『言語』の二一世紀を問う」と題されたシンポジウムの報告の中で、「文字を聞くというのは、文字を見えなくしてしまうような聞き方をするのではなくて、逆に文字の身体を耳でとらえる聞き方のことです」(「文字を聞く」『境界の「言語」――地球化/地域化のダイナミクス』荒このみ・谷川道子編著、新曜社、二〇〇〇年、一一二頁)と述べている。そして、「同音異義語」について触れて、「ワープロが普及したおかげで、いろいろ変換ミスが起こり、これまで気がつかなかったことに、いろいろ気がつくようになりました。コンピューターのよいところは、なかなか人間には真似のできないような面白いミスをすることで、そのミスによって、言葉の隠された可能性が見えてくることです。これが最新技術のもたらす変化の中で一番意義のある面かもしれません。もちろん、新しい可能性に気がつくのは機械ではなくて人間のほうなので、ハイテクの世界でこそ、わたしたちはどんなポエティックなチャンスも見逃さないように、たえず耳を傾け、目を大きく開けていなければいけません」(同書一一八頁)と指摘している。ここで追究されている「同音異義語」の「変換ミス」こそ、「ミス転換の不思議な赤」の肝になる部分だ。「脳」の「司令局」という言葉の連なりは、「脳の死霊曲」となり、「魂」という言葉は「玉Cさん」と変換される。だが、「ミス転換の不思議な赤」は、多和田がこれまでにも追究してきた「魂」と「身体」をめぐる問題がさらに前景化した小説のように思えてならない。近代の科学では、身体のあり方を、脳や神経系、筋肉の動きなど、医学的な言葉によって表現することが多い。しかし、それだけでは説明がつかない「魂」の問題について考えずにはいられない。自分の中にあるようでいて、生きている間にも、「離魂」することがある「玉Cさん」。同じ美術部員ではあるが、登場人物の緋雁と語り手の「わたし」の間に成立していたのは、他者の内面をのぞくこともできず、他者になることができないという、交換不可能な二者の関係である。しかし、不意の出来事によって、緋雁の「魂」が身体から離れてゆく場面に遭遇した「わたし」は、緋雁のうちにあった「魂」が外在化する場面に出会ったことになる。倒れた緋雁の眼鏡を拾った「わたし」は、緋雁の身体の内側にあった「血」にも触れる。交換不可能な「わたし」と緋雁のあいだで、「魂」と「身体」のうちとそとが反転して滲み出し、「脳」の中の現象としてだけでは説明できない「魂」の存在が外在化する。言語によって知ることができるのはどこまでなのか。世界そのものに触れることはできるのか。「ミス転換の不思議な赤」にはその問いが鮮烈に描かれている。
「穴あきエフの初恋祭り」(初出「文學界」二〇一一年一月号)は、魚籠透、那谷紗、「わたし」の・三人関係・が魅力的な小説。キエフを舞台にして、古い街並みを取り壊し、新しいマンションやビルを建設する会社に抵抗するため、言葉遊びやユーモアが政治運動と結びついて活性化する様子が描かれる。二〇一四年に、下北沢の本屋B&Bで、多和田と、「朗読、笑い、お話――反対運動におけるユーモアの住処としての身体と言語」という催しをしたことがある。そのときに、多和田の文学における「反対運動」を探してみたところ、『ヒナギクのお茶の場合』に収録されている「雲を拾う女」では、「同性カップルの税金の額を、既婚者と同じ額に下げろって言うデモ」が起こっていた。エッセイ集『溶ける街透ける路』(日本経済新聞出版社、二〇〇七年)では、奴隷解放運動や女性解放運動の先駆けとなったイサカというアメリカの町のことや、エストニアのタリンで、政治体制が資本主義へと転換するのにともなって、喫茶店の前の広場が駐車場に変えられたのに対して行われる駐車場反対運動が描かれており、多和田文学には、案外、反対運動やデモが多く顔を出している。そのときに重要になるのが、言葉遊びやユーモアによって既存の価値観を揺さぶるような笑いの存在だ。シアターXでのレパートリー劇場公演やドイツ文学者の松永美穂がコーディネートしてきた早稲田大学での公演&ワークショップで、多和田とともに言葉と音楽のコラボレーションを行っているピアニストの高瀬アキは、エッセイの中で次のように書く。
笑う、戯れるということは単なる表面的な可笑しさからだけ生まれるわけではない。
そしてユーモアには多くの想像力や表現能力も必要だ。何か常識という枠を超えた中にふと浮かび上がって来た時の笑いが私には面白い。(『多和田葉子の〈演劇〉を読む』一五〇頁)
高瀬が書くように想像力と表現によって常識の枠を壊すようなユーモアこそ、「穴あきエフの初恋祭り」をはじめとする多和田の小説の特徴の一つであり、政治運動と言葉遊びはお互いを活性化させる。
「てんてんはんそく」(初出「文學界」二〇一〇年二月号)には、「照子(=テルコ)」、「青江(=アオエ)」、「アリス」という三人の登場人物が出てくる。二〇一八年に京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)で行われた「朗読と講演」(聞き手・森山直人、http://realkyoto.jp/article/tawada_moriyama/)の中で多和田が明かしているように、三人の名前は、ドイツの電話会社テレコム、大手インターネットサービス会社AOL(ドイツ語読みで「アー・オー・エル」)、そして、もう潰れてしまったという電話会社「アリス」に対応している。一種の擬人化小説だが、通信速度が加速し、通信会社の競争が激化する時代において、強迫的(あるいは脅迫的?)なまでの「販促」が行われる様子は切実だ。しかし、離れているからこそ、魂が身体を離れてしまうほどにあくがれることも起こるのだろう。「こがれる、あこがれる、遠くを思うとたまらなく息が苦しくなる。届かないものに語りかけ、ふりむいてほしいとひたすら願う」という輾転反側(眠れないで寝返りをうってばかりいる状態)は、そういうときにこそ起こる。
「おと・どけ・もの」(初出「文學界」二〇〇九年一月号)は、まさに、物流や労働環境が大きく変化し、人々がその流れに飲み込まれている時代の文学。しかし、不思議なほど、坪内逍遥や二葉亭四迷らが翻訳文学をとおして近代の日本文学をつくった時代を思い起こさせる文体。体言や連用形や助詞でとめる文章の連続は、一〇〇年以上前の文学世界から届いた「おと・どけ・もの」のよう。「世の中ではどんどん単語が死んでいくけれども、小説というのはそう早く書けるものではない」という言葉は、まるで、この小説そのものについてあらわしているようだ。二〇〇九年から届いた「おと・どけ・もの」。
多和田葉子は、「文學界」二〇二一年二月号に、「陰謀説と天狗熱」という短編小説を発表した。この短編小説も、未来において、短篇集に収められて届けられるだろうか。まだまだ先が見えない状況は続きそうだが、穴のむこうに見える未来の頭文字はエフだ。「穴あきエフ」にどんな未来を見出すのかは私たちにかかっている。決して、未来のその手を離さないようにしなければならない。