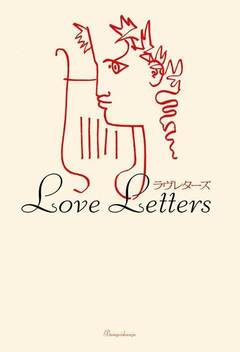奇想天外な物語を紡ぎ続ける皆川博子さん。長篇小説『U(ウー)』刊行にあたり交わされた、“幻想小説の女王”と彼女を愛してやまない三人の作家との、現実を軽々と超えていく “虚構”についての往復書簡。
綾辻行人さんの手紙
皆川博子さま
清秋の候、お変わりなくお過ごしでしょうか。──というふうにお手紙を書くのも、すごく久しぶりのことになります。ある時期以降はメールのやりとりばかりですものね。それをこうして改まって……というのはやっぱり緊張してしまうので、改まるのはやめにして、いつものメールの調子で書かせていただきます。
初めて皆川さんとお会いしたのは、今からもう二十六年ほども前。元講談社の故・宇山秀雄さんのセッティングで、綾辻のほかに竹本健治さんや谷山浩子さんも交えてのお食事会で、でしたっけ。その少し前に一度、やはり宇山さんの取り持ちでお会いする約束があったのに、当日ちょうど僕が高熱で寝込んでしまい、実現しなかったのでしたよね。あのときは失礼しました! けれどもあのときの体験をもとに皆川さんは、のちに「湖底」という幻想味あふれる短編をお書きになったのでしたね。その意味では、お役に立てて幸いでした。思い返すと大変に懐かしい話です。
ところで、先ごろ拙作『十角館の殺人』の〈限定愛蔵版〉にエッセイを寄せてくださいましたが(ありがとうございます!)、そこで三十年前のこの国のミステリーは「リアリズムの鎖に雁字搦(がんじがら)めになって」いたとお書きになっています。皆川さんが当時、経験された「雁字搦め」の具体的なエピソードを伺ってみたい気もします。また、皆川さんご自身はそのような状況からどのようにして脱け出し、本来お書きになりたかったものを書かれるようになったのでしょうか。その契機となった作品は何だったのでしょうか。
僕が初めて皆川作品を読んだのは、一九八八年に刊行された『聖女の島』をリアルタイムで、でした。何て凄まじくも美しい幻想ミステリーなのだろう、と感じ入った記憶が鮮やかに残っています。いちばん好きな作品は今でも、九七年の『死の泉』なのですけれどね。お送りいただいたあの本を徹夜で一気読みしたときの興奮と陶酔感、そして歓びは、いまだにまったく色褪せないのです。
その後も現在に至るまで、ますますパワフルにさまざまな方面で傑作をものしておられますが、そんな皆川さんの、創作の原動力はいったい何なのでしょうか。──ともすれば自分が見失ってしまいがちな問題なので、少しでも皆川さんの秘密を知りたいなあ、と思います。
二〇一七年十月某日
綾辻行人拝
綾辻行人様
お手紙を拝読して、懐かしく、思い出しています。本格ミステリ指向の若い方たちを後援しようと、宇山さんも燃えていた時期でしたね。
雁字搦めの鎖の具体的なエピソードですが、書くのをちょっとためらったのです。昔の繰り言めいて、じとじとするので。でも、あのころの雰囲気を伝えるために、当時、担当の編集の方々などから言われたことを書きますね。
私は小説誌の新人賞受賞でデビューしたのですが、その選考委員のお一人のスピーチ。
「作者は家庭の主婦だというが、なぜ、主婦の話を書かないのか」
各社の編集諸氏。
「僕はリアリズム以外はわかりません」
「どんな作家が好きですか」
ドノソ、シュルツ、マンディアルグ、澁澤、中井……
「変なのが好きなんですね」
「皆川さんが書きたいものは、書かないでください。こんなつまらないものは書きたくない、と思うようなものを書いてください。そうすれば、読者は楽に読めます」
「二時間ですらすら読めて、読んだ後は内容を忘れるようなものを書いてください。読者はまた同じようなものを買ってくれます」
書くのをやめようかと思いました。
『聖女の島』は、編集者の注文はホラーでしたが、無視して、禁じられている〈書きたいもの〉を書いてしまいました。
本当に書きたいものを書けるようになったのは、早川書房の『死の泉』以降です。外国を舞台に、翻訳物のような仕掛けをした作品を、ハヤカワさんなら受け入れてくださると思いました。自分の好みに偏した作なので、ごく一部のかたにしか読んでいただけないだろうと思ったのですが、予想外に好評で、それ以後、のびのび書けるようになりました。『死の泉』は小説の賞をいただいたのですが、選考委員の中には、「日本人が、日本人の登場しない外国の話を、なぜ、書くのか。必然性があるのか」と、非難する方もおられました。
書き続けずにはいられない原動力は、虚構の中にいるのがすきだからでしょうね。もう一つは、好奇心かな。興味を惹かれたことは調べたくなる。その世界の中に身をおきたくなる。
綾辻さんは、社会派リアリズム全盛の時期に、本格再興の道を切り開いてこられたのですから、周囲の非難をはねかえして書き続けるのに、並ならぬ気力が要ったのではと思います。本格復興三十年! 仲間と共に、よく進んできたよね。