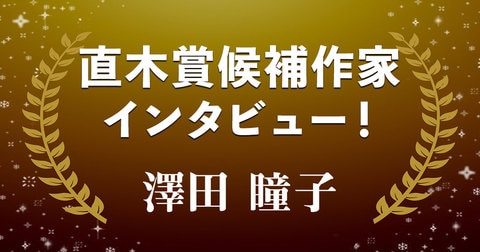李琴峰は、二〇一七年に群像新人文学賞優秀作を受賞した「独舞」(二〇一八年に刊行された単行本では『独り舞』に改題)を発表して以来、新たな試みの小説を次々に発表してきた。『独り舞』を自ら中国語に翻訳した『獨舞』(聯合文學出版社、二〇一九年)や、『独り舞』の中国語から英語への翻訳も現在進行中(二〇二二年刊行予定)であり、複数の言語が重なりあう地点で、さまざまなジェンダーやセクシュアリティの登場人物たちの生を描いている。
本書は、彼岸花が咲く島にひとりの少女が打ち上げられる場面からはじまる。隔絶されたその〈島〉で暮らす少女游娜によって宇実と呼ばれることになる少女のからだには、無数の「傷跡」が刻まれており、それは、「鋭いもので切られたような傷口」や「鈍器で殴られたような暗い紫色の痣」として表現されている。そこには暴力の痕跡がある。宇実は記憶をなくしており、なぜ、島に流されてきたのかについての記憶は、断片的である。宇実の記憶の断片から明らかになるのは、女性同士が唇を重ねることが「何か決定的な出来事」となり、迫害されたということ。女性を愛する女性への憎悪や暴力の痕跡は、痛みをともなった傷口として、宇実に刻まれている。だが、この小説は、宇実と游娜という二人の少女が出会い、お互いがかけがえのない存在だと知ってゆく物語でもある。
大海原に浮かぶ〈島〉は、ガジュマルや蒲葵に覆われ、海岸はほとんどが断崖絶壁。孤絶したような〈島〉の描写は物語の緊張感を高めてゆく。しかし、東崎、西崎といった地名は、太陽が昇る場所と沈む場所を示唆しているようであり、〈島〉の環境とそこに生きる人々の生活が浮かびあがってくる。米、芋、砂糖黍がとれる山あいや平地の田んぼと畑、〈東集落〉、〈西集落〉、〈南集落〉という三つの集落への分散居住など、〈島〉の生活は明確なイメージを持った風景の中で活写される。
〈島〉では、「ニホン語」が話されており、それとは別に、「〈島〉の歴史を受け継ぎ、未来へ伝えていくための言語」である「女語」が女性たちだけに伝承されている。〈ニライカナイ〉と呼ばれる海の向こうの島からやってきた先祖たちは、なぜ、この〈島〉へ逃れてこなければならなかったのか、そして、この〈島〉でどのような罪を犯したのか。物語が進むにつれ明らかになるのは、〈ニホン〉、〈タイワン〉、〈チュウゴク〉と呼ばれるほかの島や国々のあいだで翻弄されてきた〈島〉の歴史であり、自らも犯した罪である。この歴史は、もちろん、領土をめぐり、侵略を繰り返してきた現実の歴史とも重なる。男性たちがつくってきた歴史は戦と暴力の歴史であり、この〈島〉では、それを繰り返さないように、女性たちに歴史が移譲された。「〈島〉の指導者」である「ノロ」は、全員が女性で、「女語」によって歴史を担い、祭礼をとりしきる司祭でもある。宇実は「外」からやってきたが、「女語」を流暢に用いることができることもあり、この島に残ることができたのである。
この小説を読みながら、私は、李の連作小説『ポラリスが降り注ぐ夜』(筑摩書房、二〇二〇年)に登場する、新宿二丁目のバー〈ポラリス〉の店主・夏子が、二丁目に行ったことのある人なら記憶にあるだろう「卒塔婆の群」を見ながら、次のように思う場面を思い出す。「歴史の中で、いつだって女は男の影にいる。戦争の歴史も、経済成長と破綻の歴史も、同性愛者の歴史でさえも、そう。それについて夏子はもう怒りを感じるほどの元気はない。しかし、「彼ら」とは違う「わたし」の、「わたしたち」の歴史も、この地にはきちんと刻まれるべきだと、夏子は常に思っている」(前掲書一六三頁)。『ポラリス』の中で夏子が思い描いた歴史が『彼岸花が咲く島』では展開されているように思う。卒塔婆のかたわらに彼岸花が咲き乱れていて、何おかしいことがあろう。だが、『彼岸花が咲く島』を読む中で、私が胸をしめつけられたのは、「男の子」として周囲の人々から見なされ、「女語」を誰よりもよく見聞きし、知っているにもかかわらず、ノロにはなれない拓慈の存在だ。戦に明け暮れ、血に染まった〈島〉の歴史。そして、それを繰り返さないために「女語」で伝えられる島の秘密。自分のことを「私」という一人称代名詞で呼びつづける拓慈の存在を私は「女語」への「跨性別(トランスジェンダー )」として捉えた。
『彼岸花が咲く島』は、不均衡な男性と女性の歴史を問う。同時にクィア・ヒストリーの可能性の萌芽がある。世界中であげられてきた無数の周縁化された者たちの声、それらを含めた歴史の可能性。この試みは、異性愛中心、シスジェンダー中心の男性たちの「男語」によって語られてきた歴史を問い直すだろう。さらには、ゲイ男性中心の歴史の問い直しでもある。本書において追求された問いを引き継ぎながら、さらに、根源的に歴史を開いてゆくとどうなるのか。「昔のことを知っている人間は、常に先のことを考えながら生きていかねばならんからな。それは決して楽なことじゃあない。覚悟が求められることだ」という言葉は、自分自身も迫害され、〈島〉にたどり着いた大ノロの言葉である。この〈島〉は虐殺を行った上に成り立っている。男女というジェンダーの二元制度も堅固である。だが、それらがいかにして瓦解したり、変容するのか。あるいはそれが困難なのはなぜか。拓慈に歴史を教えたあと何が起こるのか。宇実と游娜はその答えをどう引き受け、年を重ねてゆくのか。私は、宇実と游娜の決断を信じたい。「女語」への「跨性別(トランスジェンダー )」である拓慈を信じたい。私が生きているこの世界においても、クィア・ヒストリーは端緒についたばかりだ。それでも、その試みを行う意義は大きい。だからこそ、私は、本書の結末からはじまる物語を読みたいと強く願わずにいられない。宇実、游娜、拓慈はどんな未来を生きているだろう。成熟し、新しい社会をつくってゆく彼女たちが生きる未来で、私は彼女たちと再会したい。信じて待つには歳月が必要だ。その間、予めの排除をしないこと。この本はそのための約束なのである。