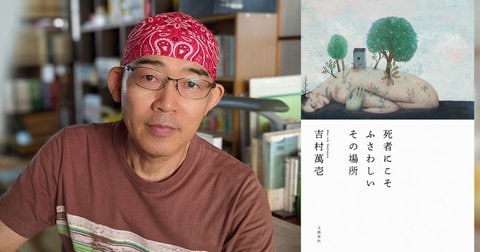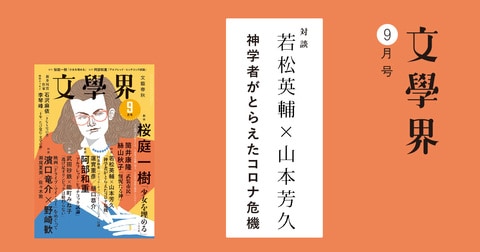現代版『森の生活』(ヘンリー・ソロー)というべき著書『土になる』が刊行される。作家、建築家、画家、音楽家など数多くの顔を持つ坂口恭平の活動すべてに通底する思想とは。
絶対に揺るがないものが失われつつあるコロナ禍で、「土」について語るということ。
ロングインタビューの前編です。
坂口恭平インタビュー後編「土、ドゥルーズ、石牟礼道子」はこちら
聞き手●九龍ジョー 構成●辻本力 撮影●松本輝一

■まっすぐ言葉を吐く
――新刊『土になる』は、前作『躁鬱大学』同様、「note」での投稿連載が元になっています。これは毎日、原稿用紙30枚程度の原稿を推敲なしで掲載する、という破格の速度で書かれたものでした。
坂口 そのほうがいい意味で力が抜けるんですよね。今回は、漢字をひらがなに開く/開かない、みたいなこともまったく考えず、ただただ書き連ねていきました。これまでの執筆を踏まえて、訓練してきたことの結果、そういう素直な書き方に辿りついた、ということでもあると思う。
――表現の技巧や見せ方に気をとられないようになった、と。
坂口 「見せ方を気にしていない」という見せ方は、とても気にしていますけどね。そこは意識的にやらないとできない。だから、その手前までの、実際に「見せ方を気にしない」というところまで持っていくということが、修行の結果かな。今回の『土になる』も文章上の作為はふんだんに満ちているはずなんですけど、直感で書かれているようにしか見えないと自分でも思い込むくらいの状態にまで持っていくことができた。
保坂和志さんの書き方なんかもそうですよね。根っからまっすぐに書いているように見えて、実はそうではない。作為的に言葉をまっすぐ吐く、みたいなところがあって、すごく参考にさせてもらいました。
より遡れば、ツイッター上で反射的に書きなぐりをしている状態と、長編小説『現実宿り』などで試した、自分でも何を書いているんだか分からないんだけど、らせん状にぐいぐいとものを書いていける状態とが、今回の本でシームレスに繫がった感じ。喩えて言うなら、山下清とジル・ドゥルーズが頭の中で同時に動き続けている状態というか(笑)。
最近は「文体という自我」の消失という言い方もしている。自分の文体を持たずに書けるようになってきたという感触があるんですよ。
――文体という自我、ですか。
坂口 結局、文体というのは自我の塊だから。今の若い作家とか、僕と同年代の作家とかを見ていても、どこかしら作品の中でそういうものを作り出そうという意思を感じるんですね。でも、それがかえって読者の理解を妨げているようなことがあって、考えようによってはもったいないと思うんです。
本当に今、さまざまな言葉が人の生活に侵入していることを実感するから、できるかぎり直に、率直な言葉を投げかけた方がいいと思う。素直に、まっとうに言葉を吐く、というか。そんな素直表明術を、書くものを通して提示したいんです。僕はそれをツイッターで学んできたような気がする。
■「一瞬の熟考」という抵抗
――文体について、ツイッターから学んだ、と公言する作家もなかなかいないと思います(笑)。同じ意味で、坂口さんはよく「今日は何十枚書いた」という内容のツイートをされますが、その枚数の中にはツイートの文字数も含まれていますよね。
坂口 僕は言葉を分けませんから。というか、そこを分けていたらダメじゃないかと思うんですよ。だって同じ言葉じゃないですか。よく作家のツイッターアカウントで、「どこそこでサイン会をやります」みたいな情報をスタッフが代理で書いているのを見ると、「そこは自分で書けよ」と思ってしまう。情報だって言葉なんだから、作家ならそこまで責任持ってくれよ、って。まあ、僕が潔癖症すぎるのかもしれませんが。
――たしかに、そのきらいはありますね(笑)。
坂口 でも、やっぱりツイッターへの投稿だって、僕の原稿なんですよ。それも、推敲しない、書き直しなしの原稿。より原液に近いという意識でいます。
僕は文芸というのは芸の道で、だから、推敲する前の初稿が勝負だと思っているところがあるんです。極論ですけど、推敲をするのはズルというか(笑)。芸である以上、原稿を汚してはいけないと思うんです。消しゴムだってキレイなままで。
――ミュージシャンで言うスタジオ一発録りに近い美学を感じますね。でも一方で、スタジオで音を重ねて、綿密に組み立てていくような作り方もあるわけですよね。
坂口 もちろんその違いは分かるんですけど、作り込むやり方はあくまで商品であって、芸術とはまた別のものだと思うんです。商品を否定するわけではないですよ。ポストプロダクションが必要な時もありますし。
でも一方で、今この瞬間に表現しなければならない、という状況があると思うんです。政治やそれに伴う社会を見ていると、まさに言葉がピンチですよね。例えば菅首相の何を言っているか本人すらよくわかっていないんじゃないかという言葉の使い方。悪い意味での直感主義、直情主義にしか見えないんです。これは明確に言葉の危機ですよ。だからこそ作家は、推敲で手直しとかしている暇があるなら、言葉を奪還するための言葉を早急に発してほしい。
といっても、むやみやたらに言葉を撒き散らせばいいと言いたいわけではない。作家としての目で、世界や社会状況を捉えて、頭脳もフル回転させて、という前提を踏まえた上での話ですけどね。今はSNSで簡単に炎上してしまうので、警戒するのもわかるんです。どんな短い文でも投稿する前に「これは書いてもいいことか」を一瞬考えてから投稿しますよね。みんなのそういう仕草を感じて、逆に、僕は思ったことをその瞬間にできるだけそのままツイッターに書こうと思ったんです。
ただ、そのためには世の中のNGワードについても理解しなくてはならないし、情報収集も必要。なぜそんなことをするかと言うと、書く上で迷わないためなんですね。言葉の速度を速めるため。
これも今までの言葉の訓練の成果を信じているからこそ、なんです。僕にとっては、言葉を発するのに三秒間くらい考え込んだり、躊躇してしまうことのほうが危険。なぜなら、それによって言葉が完全に硬直してしまうから。本来はそうして硬直した言葉をマッサジすることこそが作家の仕事じゃないですか。それができなかったら、存在する意味がない。僕がしつこく言っているのはそのことなんです。書き直しとかどうでもいいから、すぐに言葉を発しなければならない。
このインタビューが掲載されるのは「文學界」ですが、あえて言わせてもらえば、文芸誌の発行ペースに合わせて言葉を出す、というのでは遅すぎる。もちろん、商業媒体でハイクオリティなものを作るには必要な時間だとは思います。でも、言葉って一日一日でも変わっていくじゃないですか。政権のお偉いさんなんて、言っていることが毎日コロコロ変わっていくわけでしょう?
あんなデタラメな発信に対抗していくには、一瞬の熟考で言葉を練ることができる作家の力が必要なんです。一見、直感で言ってるようでいて、実は完全に意識化された、しかも自分に対しては素直であるという声を上げることが。そうでないと、このヤバイ現実に太刀打ちできませんから。
――やはり「素直」というのが鍵ですか。
坂口 先ほど訓練でそこに辿りついたと言いましたけど、同時に、僕には、幼い頃はまっすぐ言葉を吐けていたというたしかな感覚もある。そういう自分のルーツに対する感謝も常にあるんですね。そういう意味では『土になる』は、小説『幻年時代』のような幼少期の記憶とも結びついた、自分そのものの言葉とも関係しているのかもしれない。
――幼少期の言葉で、例えばどんなことを記憶していますか。
坂口 四歳の時、僕は砂としゃべることができたんです。山口県宇部の砂さんが、僕が生まれ育った熊本まで風で運ばれてきたので、「あなたたちはどうやって帰るの?」って聞いたんですね。すると砂が、「こうやって」とばかりに目の前で竜巻を起こしてみせた。これは、ほとんど僕の妄想か創作だと思うけど、少なくとも四歳くらいの時には、そうしたことが起こった、という実感がある。
今になって思うと、そんな幼年時代の記憶が僕の創作のベースになっているということがよくわかる。
そこでふと思い出したのが、ドゥルズの「地下茎」という言葉です。地下茎って、いわゆる根っこではなくて、その手前、土の中に埋まっている茎の部分なんです。地下茎は土の中にあっても、根などとは違って、暴れるんですよね。そうした運動の結果、どこからどこまでが地上茎で、どこからが地下茎なのかがよく分からなくなってくる。それが、どこまでが自分で、どこからが自分の外側なのかがわからなくなるような自己の在りようとも繫がってくる――みたいなことを彼は書いているんですけど。
そういうことを、形式的に整然と捉えなくても、畑をやって、土をいじっていると、シンプルにさらっと得心できてしまう。そういう感じがそもそも自分の中にはあるからというのもあるけれど、『土になる』は書いていて本当に気持ちがよかった。
■コロナを描かぬコロナ禍文学
――『土になる』の執筆プロセスは、ある意味で劇場型でもありました。まず起床して、「これから執筆します」と投稿。数時間後、書き上がったそばからnoteで無料公開し、ツイッターで告知。すぐさま読者の感想も返ってくるので、それを作者本人ががんがんリツイートする。こうした一連のプロセスの可視化は、作品に影響を与えていますか。
坂口 影響も何も、読者の声はすごく参考にしています。『週刊少年ジャンプ』の読者アンケートと同じですよ。ジャンプでは、あのアンケートを参考にして、作家と編集者がその後の展開を考えるわけでしょう?
ただ、僕の場合、受け入れるのは、自分にとってインスピレーションになりうるフィードバックだけです。批判を遮断するということではないですよ。むしろネガティブな意見がインスピレーションになることも多い。
――インターネットやSNSという場所については、どうお考えですか。
坂口 ライブ感があって面白い。可能性しかないですよね。作品発表の場としてネットを下に見る向きもありますけど、僕は「ネットの何が悪いんだ?」と思いますね。
もちろん『土になる』も、最終的には活字の本という形になるわけですけど、本でなければダメだとは思わない。もちろん本には本のヤバい楽しみ方がある。それはMP3音源とレコードとの違いと一緒です。MP3音源だと気楽にダウンロードできるけど、レコードはレコード屋に行って買うしかない。でも、その経験と物としての手触りは替えがきかない。今回やったのは、ネットと本という二つの世界の秘境まで桃源郷を探しに行くルポルタージュのつもりでもあります(笑)。
――本作は、二〇二〇年五月から連載が開始されています。時期的には、新型コロナウイルスの流行が新たな世界的危機として捉えられ、まさに猛威を奮い始めた時期にあたります。興味深いのは、世界中が先行きの見えない不安な状況にある中で執筆されているにもかかわらず、その影が直接的にはまったく書き込まれていないところです。
坂口 それは、僕がナチス時代の詩人たちに影響を受けているからじゃないでしょうか。彼らの詩には、圧倒的な自然の美が描かれていたりするけれど、その裏では虐殺の銃声が鳴り響いていた。そうした二重性が、常に僕の書くものにはあるかもしれない。
――例えば、畑の先生であるヒダカさんと「東京、大変ですね」といった日常会話をするようなことが、実際にはあったりしなかったんですか。
坂口 まったくないですね。国の新型コロナ対策に不平不満を漏らす、ということもなかった。ただ、ヒダカさんは、過去の戦争の話のときだけ、ぶちギレるんですよね。沖縄玉砕があった日に、いつも温厚なヒダカさんが唯一怒りの感情を見せた。
――作中にも出てきますね。戦争で亡くなった人たちがいたからこそ、今自分たちはこうして生きていられる、とヒダカさんが言います。だからヒダカさんは、「沖縄玉砕の日、原爆が落ちた日、終戦の日の4日は絶対に休まずに日が暮れるまで働くことにしてる」と。
坂口 その日、畑には僕らしかいなかったんですけど、ヒダカさんにそう言われて、僕も帰るに帰れなくなってしまった。あの日は「いのっちの電話」(※坂口氏は「自殺者をゼロにする」という目標のもと、死にたい人が駆け込める相談サービスとして自らの携帯電話番号を公開している。〇九〇・八一〇六・四六六六)にも出ることができなかった。
ヒダカさん曰く、「戦争で死んでいった人のことなんか、頭にないんだよ。どうして自分たちが今、生きられているかわかったら、死にたいなんか言うはずがない」。思い返しても、あれは印象的な日だった。
――やはり世の中の非常時だからこそ、ある透徹さをもって書かれた作品でもあるのかなと。
坂口 思うに、コロナ禍文学という側面はあるんでしょうね。今って、絶対に揺るがないというものが失われつつある状況じゃないですか。誰も「絶対、大丈夫」みたいなことは言ってくれない。
――自分の身は自分で守るしかない、ということが声高に言われていますね。
坂口 そこで「土」だと思うんです。あらためて読み返して、我ながらすごいなと思うのは、ヒダカさんが徹底して信頼している土という存在が、この本の中ではほとんど神様のように君臨している……いや、遍在している。その感覚があったからこそ、僕も安心して書くことができた。
キーワードは「安心感」ですね。僕は自分の表現によって、人々に本当の睡眠をもたらしたいんです。深い眠りの世界に誘いたい。そのための安心感を、創作活動によって実現したい。
――でも現実には、人がそうした安心感を手に入れることは簡単ではない。
坂口 そうですね。そういう意味で僕は、セイブ・マイセルフだから。今回の執筆の中で、自分で自分の救い方をもぎとった感覚があります。だから、ある種の幸福論でもあるのかもしれない。僕は常に幸福を求めてきたし、「幸福とは何か」を書きたいという思いが強くある。幸福を、人がきちんと手にとれるような形にしたい。それこそ作物のように、手でもぎとることができるものとして提示したい。
でも一方で、その奥を見つめたら、個人の救済をはるかに超えた、壮大な世界が広がってることに気づいた、ということでもあって。自分の歩いてきた道を振り返ってみたら、そこに無数の植物たちが群生していて、「うわぁ!」みたいな。その土から生まれた植物たちを介して、僕は別世界を知る。ニーチェが「新しい世界が発見されなければならない。一つならず、数多くの別世界が!」っていう、あれです。