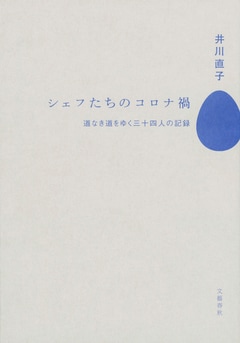有明海を望み、雲仙岳を見晴らす熊本の地で、師匠ヒダカさんの背中を見ながら畑を始めた。日々成長する野菜たちに向き合うこと。それは生命を取り戻していく過程そのものだった――。
パステル画を始め、躁鬱病を克服した著者が贈る土への感謝の本は、コロナ禍をどう生きるかという、向こう十年のヒントに満ちた一冊になりました。
『土になる』の本文冒頭公開します。

まだ畑1ヶ月目の初心者だけど、畝の裾野を見て、その畝の表面ではなく、中の湿り具合が頭に浮かぶというか、会話するというか水が欲しいのか欲しくないのかが感じられるようになった。つまり新しい言語獲得中であるような気がする。言語を覚えたての感じがある。人間以外との対話がうまくなってきてる。
土の表面を歩く、虫が僕と目が合う感じがする。目が合うとすぐに逃げているような気がする。あ、あいつがまた来た、と言っているような気がする。土は喜んでくれてる気がする。かと言って虫も僕が天敵だとは思っていない気がする。僕に殺意がないのは感じ取っているような気がする。畑の隣の廃墟の屋根や、その庭の樹木の陰にいるカラスも僕を見ている。目は合わない、合わせていないが見ている。僕は時々、畑に集中しているふりをして、パッとカラスの方をみる。カラスは、お前見てるのさっきから気づいてるよ、と突っ込んでくる。手を動かして石を投げるような意識を持つと、カラスは、それもすぐに察知してちょっと離れたところに飛ぶ。
畑に入ってしばらくすると匂いなのか音なのか僕を察知して野良猫のノラジョーンズが遠くからやってくる。しばらく黙っているが、僕が畑に夢中になっていると突っ込むように小さな声をあげた。僕がその声を無視しないのをノラジョーンズは知ってる。
土の上ではビニール袋は元気がない。自作の竹棚に張った麻紐は元気がある。その時点で麻紐は土に戻っていこうとしている。つまり僕の作業は僕だけの作業ではなく、麻紐との共同作業でもある。おかげでもっと器用な感覚に溢れる。畝の表面はそんな僕の動きをしっかりと観察し、土の中の誰かに伝えている。多分根っこに伝えてる。
農園主のヒダカさんが機械で耕しておいてくれた土を見る。ヒロミが自分で作った堆肥を30キロ、福岡から持ってきてくれた。オカラを熟成させて作った堆肥だ。なぜ突然、畑をやろうと思ったのか。疫病が流行っていたからか。もちろんそれもあるだろう。食料を獲得する場所が、誰もが同じスーパーなのはどうなのかと違和感を感じた。思い立ったら即行動である。すぐに僕は市役所に電話をした。すると、家の近くなら、近見(ちかみ)と小島(おしま)にファミリー農園がありますよ、と教えてくれた。近見と言えば、僕が通っていた小学校がある土地だ。そこなら慣れているだろうと思ったが電話をしても繋がらない。僕はいつも電話が繋がらないときは縁がないと思う癖がある。ということで、近見は諦めて小島に電話をした。ワンコールで電話に出てくれた人がヒダカさんだ。「畑は空いてますよ」とヒダカさんが言った。僕はすぐにラパンに乗って畑を見せてもらうことにした。
家のすぐ裏には花岡山がある。僕の父が育った山だ。墓もそこにある。飛鳥時代の頃は朝日山と呼ばれていた。車で山の横の細い道を抜けていく。近所だが、普段は通らない道だ。山の裏手に入った途端に、新緑の茂みがいたるところから目に入ってくる。熊本も最近は新築の高層マンションが立ち並んでいるが、山を越えるとそんな世界とは別の風景が広がっている。目の前に井芹川(いせりがわ)が見えてきた。空が突然広がり、奥には金峰山(きんぽうざん)がそびえている。僕は車の窓を開けた。風がおどかすように入り込んできた。ススキのような穂が揺れている。名前は知らない。車道の脇に畑がいくつか見えた。乾いた黒土の色を見ながら、僕はふと、自分なら何色で絵を描くかなと思い浮かべた。その途端、金峰山は青と緑と黒と灰の混じった色と形になった。太陽の光で白く輝く雲のふくらみが、無数の陰を生み出している。風景を描きたいと思ったのは何年ぶりだろうか。もしかしたら初めてなのかもしれない。
そんなことを考えながら、車を飛ばしていると、右手に楠(くすのき)の大木が見えてきた。三つ、四つ、五つといろんな緑の葉が湧くように風に揺れている。楠は風が吹くたびに新しく生まれ変わっているように見えた。風が止んでも元の色と形に戻るわけじゃなく、すっかり別の楠になるのかもしれない。感じたことをそのまますぐ何かにあらわしたいと僕は思った。ゴッホはそんなことを感じていたのではないか。今まで少しも興味を持ったことがなかった印象派の画家のことを知りたいと思った。色をそのままにあらわしたい。使う画材はパステルしかないなと思った。父からもらったファーバーカステルの70色入りパステルのことを思い浮かべた。小さな風景画をパステルで描いている自分の姿が見えた。

井芹川が坪井川に合流すると、川というよりも海の気配がしはじめる。有明海まではもうすぐだ。アオサギが大きな羽を一直線に広げて、ゆっくりと飛んでいた。この道は両親の実家のある海沿いの町、河内(かわち)につながっている。小さい頃からよく車で通っていた道だ。河内は何にもない田舎だったので、幼い僕には退屈な道だった。堤防の向こうが川なのか海なのかよくわからない。幼い頃の僕にとって海は常に危険なものと教わっていた。近づくな、と言われていた。のちに調べると、祖父母の家がある河内町白浜は1792年(寛政4年)に地震や火山活動で島原の山が崩壊したことによって、20メートル以上の津波に飲み込まれ家屋が全滅している。川沿いの国道にはいくつも苔むした神社の鳥居が見える。石碑が目に入った。
左手にずっと続く堤防の向こうにぼんやりと雲仙の姿が見える。空は晴天そのもので、青一色ではあらわせない。紫を入れたら、ぐっと奥行きが出てあの空の青を表現できるかもな、と僕は考えた。右手には金峰山の連峰が昔話みたいに佇(たたず)んでいる。
うねうねと道が曲がり始めた。ここも昔は海だったのかもしれない。2016年、熊本で大地震が起きた時、僕はすぐに家族を連れて逃げようとタクシーを捕まえて飛び乗った。祖父から教えてもらっていた、金峰山の山道を走るように運転手さんに伝えたら、国道は大渋滞だったのに、スイスイと河内まで走り抜けることができた。河内に入った途端、憑き物が落ちたように体が軽くなったことを今も体感として覚えている。おそらく地盤が市街地とは違うのだろう。金峰山は昔、山伏たちが歩いていた道だったという。山を越えたこの辺りは、全く別の世界だったに違いない。
不思議と今日は、この道も退屈には思えなかった。むしろ、豊かな山と海に囲まれた、生物にとって絶好の生息地だ。田中万十(まんじゅう)店という看板が目に入った。昔、よく祖父母の家に行く途中に立ち寄っていた饅頭屋だ。車を停めて、よもぎ団子を買って食べた。懐かしい味だ。この国道にはいくつも饅頭屋がある。なぜだろうと思いつつ、でも、おかげで僕が今、嬉しくなっているんだから、それが理由だろう。何もないところに甘いものがあるなんて、それだけで宝物屋じゃないか。
小島小学校を越えると、国道沿いにファミリーマートが見える。ヒダカさんが言ってたコンビニだ。車を左折し、手前の路地を川に沿って入っていく。ススキの草むらが見え、奥にそびえる雲仙は少し大きくなっていた。山の頂にはかつらみたいな雲が浮かんでいる。隠れている太陽が、小さな雲間の輪郭を照らしていた。強く白のパステルを押し付けたらあの光が描けるかもしれない。指を頭の中で動かしながら進んでいくと、目の前に畑が広がっていた。
畑の真ん中で青色のツナギを着た男性が鍬(くわ)で土を耕している。
彼がヒダカさんだった。

この続きは本書でお読みください。