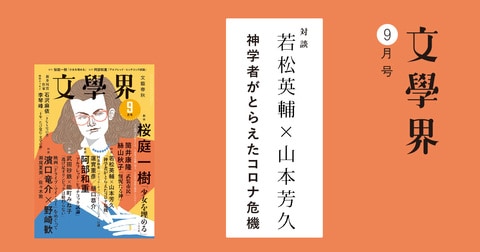現代版『森の生活』(ヘンリー・ソロー)というべき著書『土になる』が刊行される。作家、建築家、画家、音楽家など数多くの顔を持つ坂口恭平の活動すべてに通底する思想とは。
絶対に揺るがないものが失われつつあるコロナ禍で、「土」について語るということ。
ロングインタビューの後編です。
坂口恭平インタビュー前編「幸福を、作物のように、手でもぎとることができるものとして提示したい」はこちら
聞き手●九龍ジョー 構成●辻本力 撮影●松本輝一

■"軌跡”としての生と創作
――これまでは自分のペースで動こうとしてきたが、畑をやるようになってそうではなくなった、と書いています。でも、それは植物に合わせているのではなくて、いわば待ち合わせをして一緒に何かをする、という感じに近い、と。
坂口 だから、ある意味でSFなんですよ。ずっと頭の中に映画『惑星ソラリス』のオープニングシーンのイメジがありましたから。あの強烈な緑色。ああいう色を文章で出せるかな、という挑戦でもあった。奇しくも、畑とほぼ同時に始めたパステル画も「色」が重要ですから。「この空の色が描けるか?」と考える作業を、執筆と並走させていたことも大きかったと思う。
ただ、映画では芸術表現としてあの色を実現しているけど、僕はもっと生活寄りのところで同じことをやってみたかった。『土になる』は、それがとてもやりやすい器だったと思います。自分の思っていること、感じていることを素直にそのまま出せる。身の丈に合った形でできたというか。もっとも、その身の丈は、故意に作り出したものではあるんですけどね。そういう意味では、これがノンフィクションであるという実感も薄いんです。
――「小説」と呼んでも過言ではない?
坂口 だと思いますよ。それに、自分の生を小説だと思いながら生きるというのも、すごく重要なことだと思うんです。「じゃあ、すべて書くためにやったことなんですか?」みたいに言う人もいるかもしれないけど、それも違う。そういうことではなくて、描きたいものを描くということは、生きているということそのものとリンクすると思うんです。言ってしまえば、創作も生きることもみんな“軌跡”でしかないわけですよ。そのことに対してとやかく言うなよ、という感じ。だからもう、書くために生きている、それしかないでしょう? みたいな感覚なんです。
――実際のところ、この連載では、経験であれ、考えたことであれ、翌日の朝にはもう原稿に書いてるわけですしね。
坂口 ほぼオンタイム(笑)。そのまま出してますからね。僕が生きてきた軌跡を、その瞬間瞬間でどうやってもぎとるか、ということをやってみたかった。だから、これはハウツーメイクアートワークであり、創作論であり、心の安静についての研究でもあれば、土に関する考察でもある。そういう意味では、文学ではないのかもしれない。むしろ、文学で終わらせたら面白くないだろう、と思っているくらいで。
こうやって要素に分解していくと「ああ、なるほどね」となるかもしれないけど、そんな単純なものとして書いてもいない。この複雑さをどうやって読者に届けるか、ということについては腐心しながら書きました。でも僕の本の読者は、もうこの複雑さを前提として読んでくれているという手応えもある。
――坂口恭平のこれまでの作品を追いかけてきた人間は、その多岐にわたる活動や、そこから生まれた数々の創作に触れる中で、相当訓練されてきている感じはしますね。
坂口 僕が今のように書けるようになったのは、読者が僕と一緒に成長したからだと思う。例えば『現実宿り』では、文章で混沌を表現しようと、そのための手法やギミックをいろいろと考えながら書いたんですけど、今はそういうことをわざわざする必要がなくなってきた。文章の中でゴチャゴチャやらなくても表現できるし、「伝わる」という感触がすでにあるから。
■人間=声
――『土になる』の植物と猫という世界に顕著ですが、坂口恭平の中に、無人の風景が広がっている気がするんですね。多彩な活動もしているけど、実は人と交わってどうこう、という人ではない。電話番号を公開して、無償で何万人もの悩める人からの相談を受けているくらいだから、よほどの人好きな博愛主義者だろうと一見思われるけど、逆に人好きであったら、こんなにもたくさんの見ず知らずの人々からの電話に対応することなんてできないと思うんです。
坂口 そう、僕はボディにまったく興味がないですからね。人間は「声」でしかないと思っているくらい。ひいては、言葉もイコール「声」という認識です。見方を変えると、僕はずっと「声とは何なのか」を研究しているのかもしれない。人間自体が楽器という感覚もある。人間に興味がないのではなくて、「声でよくない?」という感じですかね。猫にも虫にも、植物にだって声はある。言葉は喋れなくても、出せる声がある。
――それをずっと聞いてきたと。
坂口 そうですね。ずっと、そのための修行をしてきたというか。今って、学習とか鍛錬することを軽視しがちな時代だと思うんです。そのことに対する自分なりの異議申し立てみたいな気分はあります。
――たしかに、畑や土をいじる方法はヒダカさんに学んだわけですし、思い返せば『TOKYO 0円ハウス 0円生活』の時も、隅田川のブルーシトハウスに住まう「都市の達人」こと鈴木さんに住居作りに関して教えを乞うたわけですよね。師匠を見つけて学ぶ、という姿勢はその頃から変わっていない。
坂口 でも、必ずしも人間の師匠じゃなくてもいいんですよ。モノだって先生になり得るから。僕は、たまたま友達の家で手渡されたファラオ・サンダースの『Thembi』というアルバムが忘れられなくて、長らく心に引っ掛かり続けているんです。その理由を「なぜだろう?」と考え続けることだって、僕にとっては学びなんです。いわゆる「お勉強」とも違う。学びのおかげで、「いいものを作らなきゃ」という重圧から解放されて、どんどん自由になってきている実感があります。
■「生きる」の基本に立ち返る
――先日、書店でのトークイベントで「職業としての作家」という話をしていましたが、あらためて、自らが作家であるということをどのように考えていますか。
坂口 作家であるということは、作物を育てるための土みたいな存在になることだと思っています。つまり作家は、作物が育っていく言葉を出せるようにならなければいけない。土には、自然に、あるいは人為的に種がまかれ、それを育てなければならないというプレッシャーが常にかかっている。めちゃくちゃ忙しいわけです。
自身の中から出てきたものをそのまま、変にいじくり回さず出せるようになること。これはおそらく、石牟礼道子さんから最も学んだことです。でも、そういう生々しい言葉に対しては風圧もハンパないし、危険物質を放出してしまう可能性だってある。それでもきちんと育つような地肌を育てていかなければならないので、なかなか大変ではあります。
――強靱な肉体が必要ですね。
坂口 かなりハードな肉体労働ですよ。これまでに原稿用紙換算で三万枚ぐらい書いてきましたけど、それができたのも鍛錬の結果だとは思います。僕が毎日毎日書き続けるのも、作家としての肉体強化の一環なので。
――これからの題材選びや、書く上での姿勢や方法などは、この先どんなふうになっていきそうですか。
坂口 作家として、理想的な形で作品に向き合えるようになってきた自覚はあります。ただ、やはりまだまだ考えるべきことはたくさんあって。僕の活動の真の目的は、「いい作品を書くこと」ではないはずなんです。それよりも、みんなの意識を変えることのほうが大きな目的としてある。自分の作品が、読者が社会に接続する際の指針のようなものになれば嬉しいし、さらに言えば、読者が幸せをもぎとるための契機になれば最高です。
こうした理想への欲望は、日に日に強くなってきています。あるいは僕の本を読んで、「私にも書ける」「私にも書くべきことがある」と思ってくれたら、それこそ作家冥利に尽きる。その励ましのつもりで書いているところもあるから。
――書きたい人への協力は惜しまない、とよく言ってますものね。
坂口 あとは、とにかくみんなに畑を始めてほしい。土に触れてみてほしい。知り合いに、母親が目の前で自殺してしまって、十八年間、悪夢が消えなかったという人がいるんです。でも、僕がその人と一週間くらい付き合って話をしていたら、畑をやっている幸せそうな僕を見ていて悪夢が消えた、と言っていました。
それで、彼も植物を育て始めたんですよ。二十日大根を。でも、なかなか芽が出ないので不安になって、ブツブツ文句を言うわけです。だから、「お前、自転車乗れない子どもが横におったら、『早く乗れ』って言う?」と言ったら、「そうですよね……」って。僕は、「芽さん、大丈夫だから、いつ出てきてもいいんだよ」って実際に口に出して言ってみろと言ったんですよ。口で言わんとダメだよ、って。今の人間って、本当に口に出してものを言うことを忘れてしまっている。音読を忘れている。音読って本当に大事なんです。そいつに「ちゃんと言ってみ」と言ったのも、それが言葉の練習になると思ったからで。
彼が土に向かって声を掛け始めたら、三日後に小さな芽が出ました。とても嬉しかったみたいで、今はさらに枝豆とかも育てているみたい。でも、葉が萎れたりすると心配になって、メールに写真を添付してきて、「恭平さん、これどうすればいいですか?」って聞いてくるんですよ。お前、自分の子どもがちょっと体調悪くなったくらいで、学校の先生に写真を送って「布団から出てこないんですけど、どう思いますか?」なんて聞かんやろ、と。まずは自分の頭で考えてみてください。必要な情報は植物に隠れているから、それをしっかり観察した上で、するべきことをすればいい。
■「地面」というステレオ装置
坂口 そうした視点を持つことが、生きることの基本に立ち返らせてくれるし、自分のメンテナンスにもなる。こういう当たり前のことができていないから、人はしんどくなって死にたくなったりするんですよ。
――しかし、今日もそうですが、坂口恭平のある種の放言というか、一見言いっぱなしのように見えなくもない発言の数々が作品に繫がったり、後から実を結んだりするのをこれまで何度も目の当たりにしてきました。
坂口 種をまけば作物ができる、というある種の畑感覚に近いのかもしれない。出会いみたいなものも、種なんだと思うし。偶然出会ったようなことでも、実は自分で選んでいるんですよね。建築を教えてくれた石山修武もそうだし、ル・コルビュジエもそう。僕の新政府設立計画を聞いてもまったく否定せず、むしろ「徹底してやるべきだ」と言ってくれた中沢新一さんもそう。僕が素直に歌えなくなって悩んでいた時、正直に思うところをぶつけてくれた前野健太くん。ミュージシャンはみなまっすぐ来てくれますよね。七尾旅人くん、寺尾紗穂さん、原田郁子さん、岸田繁さん、中納良恵さん、中原昌也さん。あるいはジャック・ケルアックを始めとするビート詩人、それからボブ・ディランも。後に大きな発見や実りをもたらしてくれる出会いも、意識的に選び取った結果だとは思う。
――そういえば、ディランは『土になる』の中にも登場して、その歌声がサントラのように作用していましたね。
坂口 ディランの『ブロンド・オン・ブロンド』というアルバムのつもりで書きましたからね。あのアルバムの黄金色のサウンドイメージが、畑で見た夕方の風景と重なるんです。音楽的なところでも、緩急の付け方とか、実験性のバランスとか、あるいはトラディショナルでありながら時代の求める感覚に対して敏感なところとか。
――『ブロンド・オン・ブロンド』というのはよくわかります。ルーツがすべて鳴っている現在形という。それこそ幼稚園までの通学路も、石山修武さんも、0円ハウスも、多摩川のロビンソン・クルーソーも、さらに言えば、坂口恭平が生まれる以前の熊本という大地の歴史までもが全部、『土になる』に溶け込んでいる。
坂口 それが、まさに地面というステレオ装置のなせる業わざなんでしょうね。僕が生まれ育った熊本という土地に帰ってきて、石牟礼道子という作家と出会ったことで生まれた素晴らしいオーディオのこと。以前の僕は「土地」というモチーフに触れながらも、それをどこかで創作の上でのギミックとして捉えているフシがあった。でも、今回本物の「土」とリンクしたことで、大きな変化があったんですよね。初めて僕は、文字どおり地面にしっかりと着地し、道子の詩を本当の意味で歌えるようになった。
最高の音を聴くには、アンプの調子を整えたり、音響環境を徹底させる必要がある。それは、日常の所作を見直すことにも近い。いわば「基本」の部分ですよね。だからこそ畑を軸に、自分の住む場所、生活する場所を整えることへと向かっていったんじゃないかな。それこそが「土」から考える、つまりは「足下から考える」ということの本質だと思うから。
(7月13日、文藝春秋にて収録)

坂口恭平
さかぐち・きょうへい●1978年、熊本県生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。『苦しい時は電話して』『Pastel』『お金の学校』『躁鬱大学』など著書多数。