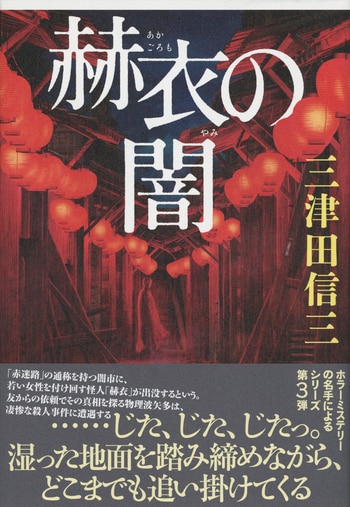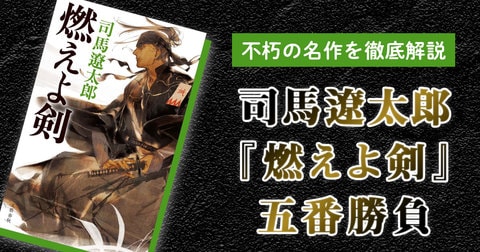闇市の怪人と猟奇殺人の謎に挑む

ホラーとミステリーを融合させた作風の著者のシリーズ探偵といえば『忌名(いな)の如き贄(にえ)るもの』などの刀城言耶(とうじょうげんや)が人気を集めている。それと対を成すのが本作で三作目の登場となる素人探偵・物理波矢多(もとろいはやた)だ。敗戦後の日本で怪異が絡む事件を追う点はどちらも同じだが、物語上の役割は大きく違う。
「作家になった時から書きたかった舞台が、遊郭・炭鉱・灯台でした。言耶を探偵役とする『幽女の如き怨むもの』で遊郭を扱い、次は炭鉱……と考えたのですが、社会から隔絶された場で内部の視点を入れようとすると、同じ探偵役では構成が似てしまう。そこで炭鉱を舞台にして“言耶ではできない事”をやるために生まれたのが、『黒面の狐』の波矢多です。就職することで当事者として事件現場にいられる役割にしたわけです。シリーズ化の予定はなかったけど、この主人公っぽい名付けからすると、心のどこかで予感していたのかもしれない(笑)」
当時は国のエネルギー源であった炭鉱での事件を解決後、波矢多は海運の要を維持する灯台守に転身する(シリーズ第二作『白魔の塔』)。本作は二つの事件の間にあたり、闇市に出没する怪人の正体究明を友人に依頼された波矢多が猟奇殺人に巻き込まれる。彼が関わる事件はすべて、戦後復興に寄与した場で起きるが、三津田さんは闇市も「自由経済の芽生えの場として」このシリーズで書きたかったという。
「闇市の資料を読んでいて一番感じたのは民衆のたくましさです。食糧備蓄はあったはずなのに敗戦のどさくさで着服され消えて、国民に分配されることはなかった。だからたとえ高値でも食べるため、生きるため、民衆が闇市を自然発生させたわけです。“お上は当てにならない”という感覚は今の日本にも通じるでしょう。同時代の記録は資料として貴重ですが、客観性の維持が難しく、どうしても偏りが生じます。現代作家が過去を書く意味の一端はここにあって、“こういう歴史が存在した”という事実を娯楽作品として残しておきたいと思っています」
戦後の混乱を具現化したような、路地が込み入り「赤迷路」と称される闇市の描写に、不安が高まる中で起きる凄惨な事件。闇市ならではの条件下で構成された“密室”を解く鍵は――。
「いつもプロットを全く立てずに書くので、どういう小説になるのか完成まで自分でも分からないのですが、『白魔~』で幻想色が強かった反動か、今回はロジックで詰めていく構成になりました。実はこのインタビュー中に次なる舞台を思いついたので、波矢多の事件簿にはまだ続きがありそうです」
みつだしんぞう 編集者を経て2001年『ホラー作家の棲む家』でデビュー。10年『水魑の如き沈むもの』で本格ミステリ大賞受賞。他に『逢魔宿り』など著書多数。