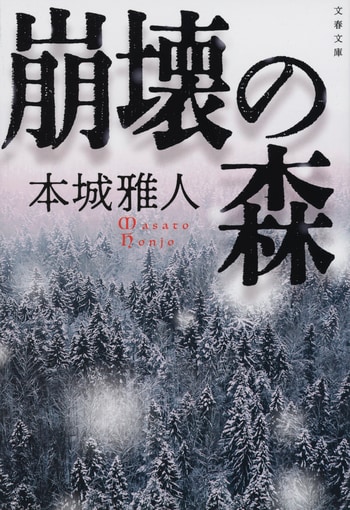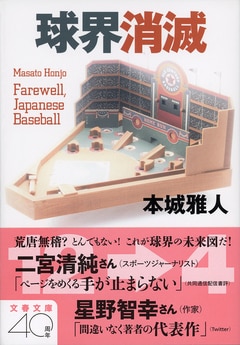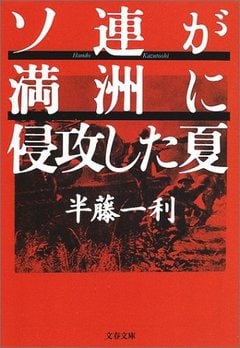一九九一年十二月二十五日にソ連のミハイル・ゴルバチョフ大統領がソ連国民に向けテレビで会見を行い「親愛なる皆さん、独立国家共同体が形成された結果、私はソビエト連邦の大統領としての活動を停止します。私は不安を残してここから去ります」と述べた。クレムリンの上に立っていた赤旗が降り、ロシア連邦の白青赤の三色旗が掲げられた。本書ではこのときの情景がリアルに描かれている。
〈──今晩、クレムリンの旗が降りるぞ。
この日の夕方、一人のウオッカ友達がそう教えてくれた。炎のように赤い地に金色の星と、鎌と槌(つち)が組み合わさった、巨大な社会主義国家「ソビエト連邦」を象徴する赤旗、それが降ろされるというのだ。土井垣はそのシーンを、日本から応援に来てくれた二人の同僚、そして妻の咲子と一緒に見たいと思った。みんなで歴史的瞬間に立ち会い、それぞれの目に焼きつける。それが将来の東洋新聞にとって大きな財産になる。
後ろから溶けた雪が跳(は)ねるような足音がすると思ったら、桑島が白い息を吐いて走ってきた。
「なんとか、間に合ったみたいだな」
「まだ大丈夫だ、桑」
「あっ、あれじゃないすか」
藤村が、手袋を嵌(は)めた指を空に向けた。
その指先を追いかけると、クレムリンの屋根に二つの人影が現れていた。
土井垣は時間を記録しておかなくてはと咄嗟(とっさ)にコートの左袖をまくった。腕時計の秒針がちょうど十二の位置を通過したところだった。二人のシルエットはドームの上までするすると駆け上がり、ポールから素早くソ連国旗を降ろして、そして白青赤の新しいロシア国旗を引き上げていく。旗が昇り切ったのを見て、時間を確認した。わずか三十五秒の出来事だった。
屋根に視線を戻した時には、二人の姿は消えていた。〉(11~12頁)
この件(くだり)を読んで私は、この現場を見ることが出来ずに悔しいと思った。当時、私は在ソ連日本国大使館の三等書記官だった。同年八月のソ連共産党守旧派によるクーデター未遂事件、その後、リトアニア、ラトビア、エストニアの沿バルト三国の独立とこれら三国と日本の外交関係樹立の業務に忙殺され体調を崩し、十一月末から日本に一時帰国し、治療を受けていたからだ。ソ連崩壊の過程は日本で新聞やテレビを通じて知ることになった。もし私がモスクワにいたならば、この物語の主人公たちと一緒に「赤の広場」で、赤旗が三色旗に替わる瞬間を見ていたと思う。
私は、九二年一月末にモスクワに戻ったが、シェレメーチェボ国際空港の国境警備隊員が押した入国印には、CCCP(ソ連)ではなく、Российская Федерация(ロシア連邦)と記されていた。
あれから三十年を経て、ロシアとウクライナの国境地帯が緊張している。連日、インターネットでロシアのテレビニュースを見ているが、三十年前、共産主義体制から解放され、ロシア人もウクライナ人も歓喜していた情況からは想像もつかないような陰鬱な雰囲気だ。私は、セルゲイ・チェシュコ(1954.1.28-2019.1.6)氏の名著『ソ連邦の崩壊:民族政治的分析』(ミクルホ・マクライ名称ロシア科学アカデミー民族学人類学研究所、一九九六年)を読み直している。同書はわずか五百部しか刊行されていないが、専門家の間では高く評価されている学術書だ。
チェシュコ氏は私の恩師でもある。私がチェシュコ氏と初めて会ったのは一九八九年秋のことだった。ブレジネフ時代にソ連では民族問題は基本的に解決されたということになっていた。実際にはアゼルバイジャンとアルメニアのナゴルノ・カラバフ紛争、沿バルト三国における文化自治強化の要求など深刻な問題が火を噴き出し始めていた。モスクワ国立大学で研修を終え、八八年六月から私はモスクワの日本大使館政務班で働き始めた。基本は雑用係で、コピー取りや書類回しの他、ロシア語の新聞や通信社報道をチェックし、重要なものを翻訳し、外務本省に公電(公務で用いる電報)で報告するのが主な仕事だった。新聞には地方紙も含まれていたが、アゼルバイジャン共産党機関紙「バクーの労働者」とアルメニア共産党機関紙「共産主義者」はナゴルノ・カラバフ問題に関する論調が正反対だった。またリトアニア共産党機関紙「ソビエツカヤ・リトアニア」やエストニア共産党機関紙「ソビエツカヤ・エストニア」には、スターリン時代の人権抑圧に関する記事が掲載されるようになった。明らかにモスクワの中央政府の統制が取れなくなっていることがうかがわれた。
私が地方紙を丹念に読んで公電で報告していると、八九年の夏に上司から民族問題を担当するようにと言われた。大使館の内政分析担当官が行うのは、まず新聞や雑誌などの公開情報を丹念に読んで、それから当該事項を担当する共産党と政府の担当官と面会して説明を受けることだ。しかし、民族問題はソ連に存在しないことになっているので、共産党にも政府にも担当部局がない。「いったい民族問題はどこで扱っているのか」とモスクワ大学時代の友人でラトビア人民戦線の幹部として活躍しているサーシャ(本名はアレクサンドル・ユリエヴィッチ・カザコフでサーシャは愛称。拙著『自壊する帝国』の主要な登場人物。現在、サーシャはプーチン大統領を支持する論客として活躍している。二〇一八年にサーシャが上梓した『北の狐──ウラジーミル・プーチンの大戦略』はロシアで話題になって直(す)ぐに三刷りとなり、二〇二一年には東京堂出版から日本語訳が『ウラジーミル・プーチンの大戦略』というタイトルで刊行された)に尋ねてみると「ソ連科学アカデミーの民族学人類学研究所(現ロシア科学アカデミー民族学人類学研究所)だ。あそこはソ連共産党中央委員会イデオロギー部と緊密な関係を持っている。国家秘密も扱う研究所なので資本主義国の外交官はアクセスできないかもしれない」と言われた。大使館から面会要請の手紙を出すと一カ月ほどして、受諾するという回答があった。八九年秋のことだった。そして、研究所の窓口となったのが、当時、三十五歳で副所長兼学術書記をつとめていたチェシュコ氏だった。チェシュコ氏はアメリカ先住民族の専門家だったが、同時にプロテスタンティズムへの関心が強かった。学術書記とは、共産党中央委員会との連絡を含む研究所の行政の責任者でもあるので実権を持っていた。私とチェシュコ氏は波長が合い、家族ぐるみで付き合うようになった(拙著『甦るロシア帝国』(文春文庫)にチェシュコ氏のことを詳しく書いた)。
チェシュコ氏はソ連崩壊後も研究所の副所長に留まった。秘密警察による外国人に対する監視が緩くなったので、二人の関係は一層深くなり、夜遅くまで台所でウオトカを飲みながら様々な議論をした。主なテーマとなったのがソ連崩壊の原因についてだ。このテーマでチェシュコ氏は九六年に博士号を取った。その論文が先に紹介した『ソ連邦の崩壊:民族政治的分析』だ。チェシュコ氏は、ソ連崩壊が歴史的必然だったという見方も、国内の敵と外国の特務機関による陰謀が成功したことによるとの見方も退ける。ソ連崩壊の原因は二つの要因が絡み合ったことによるものというのがチェシュコ氏の分析結果だった。第一はソ連の反体制派だ。ソ連体制では二級のエリートの場しか与えられなかった学者、作家、政治家などがペレストロイカ(改革)によって生じた隙間を用いて、自己の地位を向上させるために反体制的言説を展開するようになったことだ。第二は民族共和国のエリートだ。この両者が同盟を組み、反共主義的言説と民族主義的レトリックを駆使してソ連体制を攻撃した。その目的は、権力と財産を奪取することだった。乾いた分析だが説得力があった。
『崩壊の森』は小説の言葉でチェシュコ氏が学術書で書いたのと同じ内容を説明している。ソ連共産党は、西側諸国の政党とはまったく異なる組織だった。一党独裁体制の下、共産党が政府や議会、マスコミなどを指導していた。共産党は国家そのものだったのである。ゴルバチョフ・ソ連共産党書記長は、ソ連国家を強化するために共産党独裁体制を打破し、複数政党制を導入する計画を極秘裏に進めていた。一九九〇年二月五~七日に行われたソ連共産党拡大中央委員会で、共産党独裁放棄が決定されたが、それを世界で最も早く、同年二月三日にスクープしたのが産経新聞モスクワ支局長の斎藤勉氏だった。このスクープによって産経新聞は一九九〇年度の日本新聞協会賞を受賞した。
『崩壊の森』は、斎藤氏をモデルにした小説だ。東洋新聞の土井垣侑モスクワ支局長の目からソ連末期の政治動向と人間ドラマとして描いている。ちなみに私をモデルとしたと思われる日本大使館三等書記官(窪田健次郎)も登場する。私は連日、ウオトカを手にしてロシア要人の夜回りをしていた。当時、私は深夜に斎藤氏と路上で歩きながら情報交換をしたことが何度もある。あの頃の記憶が鮮明に甦ってきた。
土井垣は、モスクワに赴任したとき前任者の新堀から特ダネ禁止を言い渡される。特ダネを取ろうとしてKGB(ソ連国家保安委員会=秘密警察)に目を付けられ、国外追放にされると、東洋新聞が大打撃を受けるからだ。しかし、土井垣は、ゴルバチョフが進めるペレストロイカの深層を知ろうと、権力の中枢に食い込んでいく。そして、ソ連を根本から変化させる重大決定が近くなされるという情報をつかんだ。ついにその戦略を立案した一人(歴史学者)に行き当たる。重大決定は、次の拡大中央委員会総会で共産党が一党独裁制を放棄するという内容だった。共産党が独裁を放棄すればソ連体制は崩壊する。まさに歴史の分水嶺となる政策転換だ。この情報入手の場面がリアルだ。
〈着いたのはビジネスホテルの一室くらいの暗くて狭い部屋だった。拡大党中央委員会総会に向けて、彼が極秘で借りているようだ。机と椅子があるだけで、机の上には数枚ごとに綴じられた書類が積まれていた。これこそボリスが話していた基本大綱の原案なのだろう。
「その文書を一部、頂戴(ちょうだい)できないか」
立ったまま土井垣が言うと、彼は椅子から立ち上がって手で伏せ、「これは渡せない」と断った。
「どうしてですか」
「数に限りがあるからだ」
「だったら貸してもらうだけでいい。本日中に必ず返却する」
それでも彼は「この後、修正が行われるから現段階の文書を渡すわけにはいかない」と首を縦には振らなかった。しばらく同じやり取りを続けたが、彼は大量のコピーから一部だけを掴んだ。
「今から読み上げることをメモしてもいい。ただし私の名前は絶対に秘匿することが条件だ」
「それは約束する」
ポケットからメモ帳とボールペンを出した。クージン氏が読み始めた内容を必死に書いていく。
「頼む、もう少しゆっくり話してくれ」
メモが追いつかず、何度か言い直してもらった。想像を上回る内容に、途中から土井垣の手は震え始めた。〉(274~275頁)
土井垣が書いた記事はあまりに衝撃的なものだ。しかし誰も後追いをしない。土井垣自身も誤報ではないかと不安になったが、それは杞憂だった。
〈「土井垣さん、タス通信が動き始めました。至急報ですよ」
眼鏡を両手でかけ直した土井垣は立って走って、機械から出てくる紙を掴んだ。
《スローチュナ》──頭にそう打たれている。同時につけっぱなしにしていたモスクワ放送からも緊急ニュースが流れた。
〈ソ連共産党は二月五日からの拡大党中央委員会総会で七十年余り続いた独裁を放棄することを審議します〉
やった。思わず拳を握った。
そこで黒電話が鳴った。きっとデスクか国分部長だろう。
「土井垣です」
勇んで取ったものの〈新堀だ〉と言われて、返事に詰まった。また余計なことをして──あの冷酷無情な口調で怒られると気が滅入りそうになったが、新堀の声はこれまで聞いたことがないほど昂っていた。
〈土井垣くん、よくやったぞ。きょうのは素晴らしい記事だった〉
「は、はぁ」
〈こういう記事を書くために私や馬場さんは長い間、そこで辛抱してきたんだ。これこそモスクワの特派員がいつか書かなくてはならない記事だ。誰かに燃やされる前に、世界に向かって報道しなくてはいけない記事だったんだ。ありがとう〉
そう言うと〈じゃあ、部長に替わるな〉と電話口からいなくなった。
国分部長からも〈よくやった〉と褒(ほ)められたが、頭には入ってこなかった。〉(282~283頁)
記者冥利とはこういうことだ。土井垣は、KGBからマークされ、自宅に侵入され、車がパンクさせられるなどの嫌がらせをされた。しかし、ソ連の真実を知ろうとする土井垣にKGBのボリスが協力する。監視する立場にあったボリスの魂を開かせる人間的魅力が土井垣にあるからだ。
ちなみに現実の斎藤勉氏も人間的魅力があり、しかもそれに勇気が伴っている。二〇〇二年春、鈴木宗男疑惑の嵐に私が巻き込まれたときに、当時、産経新聞モスクワ支局長だった斎藤氏だけが、私を擁護する記事を書いてくれた。その後、私の公判も毎回傍聴し、私が作家として第二の人生を歩む手助けをリスクを省みずにしてくれた。