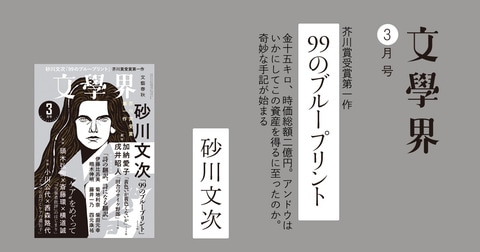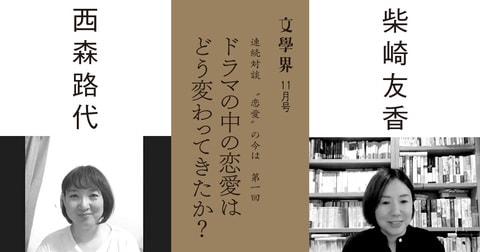西森 ときによって、その選択が変わるんですね。
小川 そうです。ウルフもこの二極で揺れた作家で、例えば『三ギニー』のような、戦争に加担していく男性たちを、平和主義を貫くために女性はどうやって止めるべきかというようなものを書いているんです。
西森 そうですよね。私は『ハイロー』の乱闘は、「おにぎり」という待つ女性のケアを持ち出した部分で、戦争ととらえられると思っているので。だからこそ、女性は参加しないでいいし、おにぎりを作って待つこともないと。
小川 だから、『三ギニー』的な立場からウルフを読むと、明らかにケアを重んじているんですよね。要するに、権力を持ったり、筋肉という力や物理的な力を持つ男性に対して、武力を持たない、権力を持たない女性たちは、アウトサイダーと呼ばれていて、でもアウトサイダーだからこそできることは何かということをウルフはずっと考え続けていたんです。ただ、他方では家庭の天使はよくないとも言っている。要するに、男性のために、おにぎりを作ったりとか、男性がやってほしいことを奉仕する女性のことも厳しく批判していたんです。そこから私は出発しているんですよね。
西森 わかります。私も、女性は乱闘に参加しないでいいし、おにぎりを作って待つこともないというのは、一見矛盾しているような気がするけれど、整合性はあると思っています。
■『マッドマックス』の女性たち
小川 『マッドマックス 怒りのデス・ロード』もマッチョな男性が暴力を使って女性を守るというお決まりの物語だと思っていたので、ずっと見ないでいたんです。でも見てよかったですね。この映画、女性はこうあらねばならないというステレオタイプに当てはめないじゃないですか。暴力を使って戦う女性もいれば、ワイブスのような存在もいて。ワイブスの中にも、イモータン・ジョーのもとに戻ろうとする女性も踏ん張って戦おうとする女性もいる。女性も多様な描かれ方をするべきだけど、これまではどちらかに振り切って描かれることが多かったんですよね。
西森 強くあるべしか、守られるべしかの二択だったかもしれないですね。
小川 でも『マッドマックス』には、多種多様な女性が描かれていて、自分がどこにあてはまるのかと考えさせられて。
西森 私も単に経済的、権力的、腕力的、あと頭脳的とかもあるかな、とにかく強い女性であれというものにも勇気づけられることはあるけれど、最近はそこからとりこぼされた女性たちも描いてほしいって思ってますね。というのも、自分が出た大学もそんないいところじゃないし、最初の就職も会社には満足していたとしても、自分は補助的な仕事だったし、東京に出てきて派遣をしても、実務は期待しないから、とにかく部内で突出しないで悪目立ちしたりトラブルを起こさなければいいからって感じで。そういう立場にいると、ケア役割というか、気遣いができなかったり空気が読めないほうが「落ちこぼれ」であり「変な人」になってしまうんです。だから、フェミニズムが「強い」女性を目指せというだけならば、その辺の人の実情が置いてけぼりになってしまうなって。
小川 私の母が専業主婦だったので、母の人生を否定しない書き物ってどういうものなんだろうとも思いますし、自分も三十歳くらいまで学生をやっていたので、あちこちでアルバイトして不当な仕事を押し付けられたりという経験もしました。
西森 どんな仕事だったんですか?
小川 塾の講師やリサーチの仕事、それに通訳などですけど、仕事量に見合わない金額で働かされたり、通訳を頼まれたはずなのにセクレタリーや付き人、カバン持ちの役割を求められることもありました。
西森 自分の年代で新卒のときは、女性の仕事って、ほぼケアだったと思いますね。今ももちろんそういう面が残っていると思います。
小川 私も通訳とは名ばかりで、ケアラー的な業務内容のほうが多いこともありましたね。だから『逃げるは恥だが役に立つ』の話もしたかったんですよ。
おがわ・きみよ●上智大学外国語学部教授。1972年生まれ。『ケアの倫理とエンパワメント』『文学とアダプテーションII ヨーロッパの古典を読む』(共編)など。
にしもり・みちよ●ライター。1972年生まれ。『韓国映画・ドラマ わたしたちのおしゃべりの記録2014~2020』(ハン・トンヒョンとの共著)など。
撮影●深野未季 構成●西森路代
この続きは、「文學界」3月号に全文掲載されています。