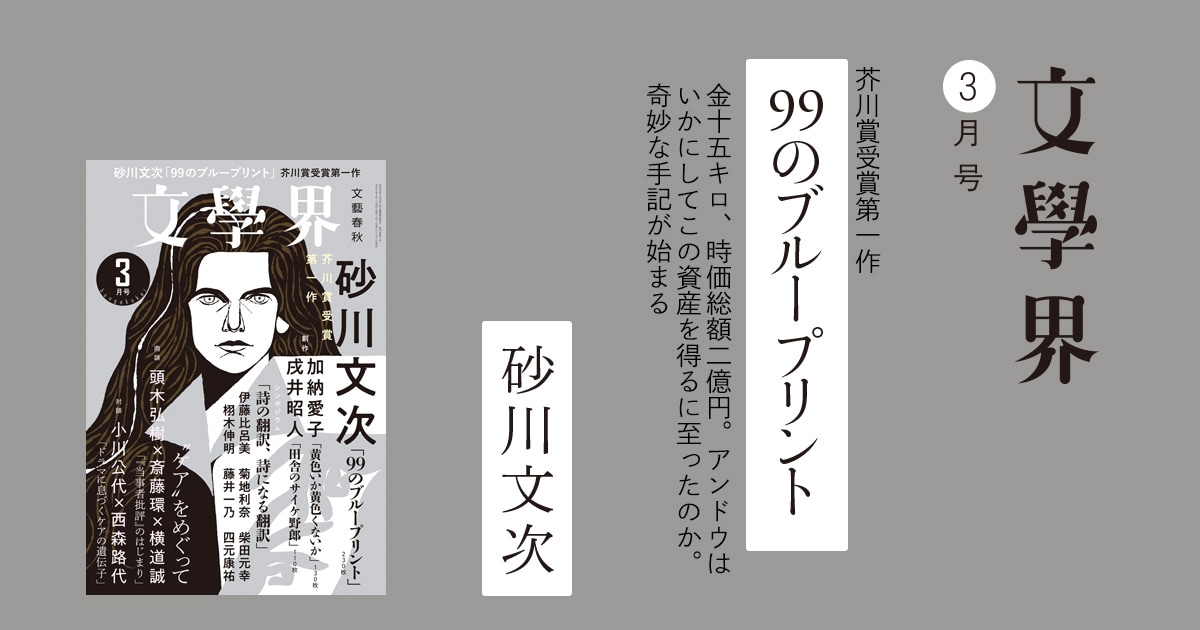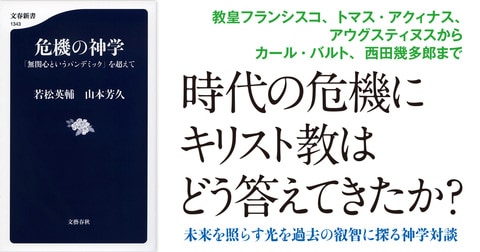自分が自分を呼称するのに、「私」や「自分」という語を用いることは、とても不合理ではないか、と思う。だからこれから起きること、起きたこと、見たものを描出するにあたっての主語は、極めて一人称に近い三人称を用いなければならない気がしている。とはいえ、自分で自分の「記号」を呼称する際に伴う違和感をやはりそのまま黙殺することはできまい。
私と他者とを区別する記号は「アンドウ」であるわけだが、これを主語に置いたからと言って、ゆめゆめ三人称などと思ってはいけない。
仮にこの文章を誰かが読むとして、一体どこまで読んでくれるだろうか。何か圧倒的な誘引が、存在が、企てが不可欠かもしれない。
アンドウはそこまで考え、一旦2in1タブレットPCの液晶に最大化されているWordを保存し、タスクバーから自分の資産のページを呼び出す。
約十五キロ。
アンドウが今現在保有している金の総重量だった。まもなく今年が終わろうとしているが、この年の中頃に巻き起こった金融危機によって金価格は前年同月比でほぼ倍になっている。円に換算すると時価二億円に迫っている。
アンドウは《これだ!》と思った。
改めてWordを開くや否や、その続きにゴールドの保有数を記載した。
これこそが誰かがこの続きを読む意味になる。十五キロ。二億円という圧倒的な意味――アンドウは、しかしこれを圧倒的と受領してしまうほどに自分を矮小化したくないと思っていた――の前に、企ての前に服従する人々は、すべてを読むか否かは別としてもその目を留めざるをえまい。かつての自分もそうだった。“あの夜”を知ってしまった自分はもうその位置まで戻ることはできない。今やすべての意味は分解されて散り散りとなっている。完全ではないにせよ。
ところでこの自分を呼称するときの違和感、居心地の悪さ、不愉快さの正体は何なのか。アンドウは考えてみたところ、結句自分が自分であることを白々しく否定してしまうことにあるのではないか、と思った。前と後との運動の数が時間である、という有名な定義を持ち出すまでもなく、自分はその総体だ。記号はその総体を表しはしていない。ただその総体らしきものの断片を指し示すだけだ。誰かが授けてくださった“皮衣”こそが総体であり、これはその点において完全に未来が定められていることから、常に未来からも自由になる。総体は点でも線でも面でもない。任意の地点に座標を定めたとき、一般的に想定される背後に過去が、眼前に未来が、というような事態も生起しない。その位置における経験はすでに済ましてしまっているからこそ任意の座標に設定できるのだから。その座標で背後や眼前という数直線的想定はもはや通用せず、当該座標における視座に死角はない。その座標が占める現在という位置も、そこへ至るまでの運動の数も、そこを出発地とする運動の数も意味がない。等化されているがために総体たりうるのだ。任意の地点から観測されるそれまでの運動数――便宜上、過去と呼ばせてもらおう――も未来も、任意地点からは振り返りや仰視という行為で見るのではなく、すでにそれらは身体に刻み込まれている。いかに没入しようともすでに前後の関係は存在せずに、ただ意味だけが残っている。当該地点に視座を置いたときに認識できるのは「全て」だ。全周にわたって意味が広がっているのだ。ばらばらになっているということは、それが依然として自分の掌中に収まっているということだ。これは一つのルールで、自分や誰か(これを仮に誰かが読むとして)の羅針盤になり得る。
アンドウは、考えるのに疲れを感じ始めていたところで“十五キロ”という数字を思い出して自分を奮い立たせた。奮い立たせるや否や、すぐにその反動とでもいうべきか、自分の存在が、総体がこのたった十五キロの反応性の低い固体金属に帰せられてしまうのか、と虚しくもなった。得も言われぬ全能感と虚無感とが一つの身体に同居していた。
十五キロを得るに至った運動を検めてみるのは、きっと何か意味があるはずだ。