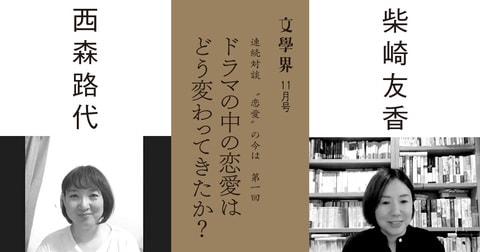気鋭の脚本家・渡辺氏の新作は、七〇年代の尾道が舞台の青春映画『逆光』。
近年は社会問題を扱うことも増えてきたという渡辺氏とともに、現代の閉塞感、ドラマにおける恋愛の描き方について語る。

■『逆光』と三島由紀夫
西森 渡辺さんが脚本を担当された新作短編映画『逆光』(2021年)は、一九七〇年代の広島は尾道を舞台に、先輩を連れて帰省した主人公と、その友人たちとの交流を描いた一夏の物語ですが、感想を一言で言い表すのが難しいですね。主人公の晃は、大学の先輩である吉岡と広島に来るわけですが、吉岡は晃が紹介した同郷の女友だち、みーこに関心を寄せるようになり、やがて彼女も吉岡のことが気になり出していく。物語的にフォーカスされるのは男性二人の関係性ですが、最終的には、吉岡とみーこの方に痛みの伴ったシンクロニシティを個人的には感じました。こうした構成は、晃を演じ、本作の監督も務めた須藤蓮さんの意向が大きかったのでしょうか?
渡辺 そのへんは、どちらかというと私の好みで押し切った感じだったように思います。この作品以前に、『blue rondo』という作品の企画があり、それは彼の実体験をベースにした物語でした。彼の脚本の中で形になり切れていない部分を私が書き直し、撮影しようとしていたところでコロナ禍に。撮影が飛んでしまい、みんなものすごくしょんぼりしていたので、元気出そう! みたいな感じで「代わりに中編を撮ればいいんじゃない?」と、気軽に言い出したことがきっかけで始まったのが『逆光』なんです。たまたま持続化給付金が私にも蓮くんにも入ったタイミングだったので、それをもとに可能な作品を尾道で撮ろうという話になり始まった、思いつきみたいな企画だったんです(笑)。
条件的に可能なラインを探っていきました。まず蓮くんが出る。蓮くんとドラマ『ワンダーウォール』で共演した中崎敏くんも出てくれると。ちょっとキャラクター性のある女性が入った方がいいだろうと思って、私が富山えり子さんを推薦しました。富山さんはお芝居がしっかりしている人なので、すごく信頼できるし、彼女もコロナで仕事が全部飛んでしまって時間があったので、出演していただくことが叶いました。
西森 みーこを演じた木越明さんはどういう経緯だったんですか?
渡辺 最初、私はその三人の話でいけると思っていたんですが、蓮くんがもう一人女性を出したらどうだろうと言い出して、それで生まれてきたのがみーこというキャラクターです。それが固まってから、尾道を舞台にした四人の若者の物語として脚本化しました。
西森 青年二人の気持ちを軸にした物語にしたのには、どんな理由があったのでしょうか。
渡辺 まず、須藤くんも私も三島由紀夫がすごく好きなんです。
――三島の『反貞女大学』が引用されたりしていましたね。
渡辺 はい。以前、二人で初めて話した時に、彼が「僕は三島の『雨のなかの噴水』という短編が好きなんですよ」と言っていて、私はその短編を読んだことがなかったので後で読んだんですけど、彼から勧められたせいか、劇中に出てくる男の子が蓮くんのイメージで読めたんですよね。雰囲気的にもピッタリだから、もし三島作品が将来映像化される際にはこの人は絶対ハマるだろうと思って。でも、文芸ものって映像化がすごく難しいから、待っていてもまず実現しない。でも、やれたら絶対いいよな、という考えがずっと頭の片隅にあって。たぶん三島というモチーフから連想されているのだと思います。
――時代設定を現代にしなかったのには、どのような理由があったのでしょうか。
渡辺 すでに失われたものの郷愁のようなものを描きたい気持ちがどこかにあったように思います。三島をモチーフにしているのもたぶん関係していて、彼の小説が若者に熱心に読まれていることがリアルに感じられる時代設定ということも考えました。それから、尾道で撮影するときに、時代を変えたほうが、衣装にせよ、言葉遣いにせよ、より美しく見せ、聴かせることができるのではないかという予感もありました。背景と人がより魅力的に見えると思っての判断ですね。また、これは蓮くんが言っていて面白かったのですが、今だと若者四人が出会ったら、すぐにLINEでグループを作って常に交流できちゃうから、彼らの迷いとか葛藤を描きづらいと。そういうのは本当につまらないし、全然ロマンチックじゃない、と言っていたのが印象に残っています。小作品だからこそ、ネットとかスマホ以前の、人がもうちょっと神秘的な存在として見えていた頃の感覚を描けるのではないか。……と、もっともらしく説明していますが、実際には私は思ったままにワーッと書いてしまうのが常なので、正確なところはわからないんですけどね。