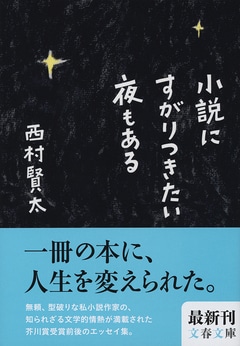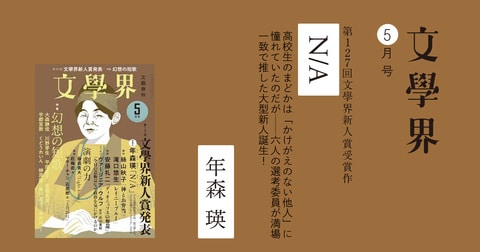先年に、藤澤淸造の老朽した木の墓標―すでに取り払われ、能登七尾の菩提寺の本堂の、その縁の下に収納されていたところの墓標そのものを懇願を重ねて譲り受け、新宿一丁目の自室に運んだキ印じみた顛末を記した内容であり、いずれは淸造の伝記中の没後項目にでも組み込むべく机の抽斗にしまっておいたものだったが、読み返してみると、キ印的とは云え、何んだか小説風でもあり、またその旨の感想を洩らしてくれる者もいたので、ならばと、も少し読み物的に書き改めて、おそるおそる『煉炭』誌に提出してみたのである。はな淸造の作品論を、と身構えたはいいが、提出期日が近付くにつれ、何やら書きあぐねてしまった状況でもあった。
「墓前生活」なる、しかつめらしい題名を付した六十枚のこの作は、たかだか十数人程度にしか読まれぬ同人雑誌上ではあるが、とあれ貫多にとっては小説まがいの文章が活字になった初めてのものとなった。
イヤ、それ以前に田中英光の研究小冊子を作っていた十年以前の頃には、二年で八冊と云うハイペースで出しているうちに書くことがなくなってしまい、仕方なしに英光風の短篇もどきを二つばかり書いて、臆面もなく載せておいたことはあるにはあるのだが、しかしこれは習作ともいえぬレベルの全くの愚文であり、元よりノートの隅の落書きじみたものだから、数のうちには入れられぬ。
で、そんなにして、何かそのときどきの目先の流れに流される格好ながらも、まずは所期の目標の一つに取っかかりを付けた貫多は、あとは初手の目論見に沿って『煉炭』誌の半年に一度の刊行毎に淸造の外伝なり作品論なりを書き続ければいいだけのことだったのだが、そこで根が案外の調子こきにできてる彼は、一寸した慾みたようなものが出てしまった。
恰度その頃に主宰者から、またぞろ頻りと先の〝半期優秀作〟と〝『文豪界』転載〟の話を聞かされた為もある。またそれを述べる先様の口ぶりに、何か引っかかるものを感じた故の反発めいた感情も確とあった。
そうだ。それはあながち根が猜疑と邪推の塊にでき、曲解と歪んだ忖度の名手にもできてる貫多の思い過ごしだけではない。かの主宰者は、それを述べる際に、「選考の人たちも、書き手が若きゃあ、なんでもいいっていうのは困ったもんだ」とか、「北町君なんかもまだ若けえんだから、この調子で書いていけば、そのうち転載されるかもしれないぞ」とか、いかにも苦々しそうに、ほき出すように言っていたことからも、その主宰者にとってトーシローはなかなかに採り上げられぬ神聖なる〝同人雑誌評〟の場で、いきなりズブのトーシローの貫多が好評を得たことは俄然面白くなかったのだ。
それが故、あの田中英光の出世作が載った『文豪界』誌に、あわよくば自分も一度創作を載せてみたい子供っぽい名誉慾に、この主宰者に対する反感が加わった貫多の『煉炭』誌第二作は、畢竟露骨なまでに〝半期優秀作〟狙いで仕立てざるを得なかった。
読み手(同人雑誌評の四名の選者のことだが)の存在をヘンに意識し、ともすれば独りよがりで鼻白まれるだけの藤澤淸造と云う特定作家に関するエレメントは一切廃すと云う、貫多なりの姑息な計算を存分に働かしたものである。
二十五歳時の最初の暴力事件によって叩き込まれた、都合十二日間の留置場体験を綴った内容で、「春は青いバスに乗って」なる横光利一の名篇をもじった題を付したところのこの作は、はな貫多としてはえらく自信満々の一作でもあった。
尤も根が文章を書くのがどこまでも不向きにできてる貫多は、この八十五枚を仕上げるのに大いに手間取ってしまい、一応設けられていた提出期日を一日過ぎただけで、かの主宰者から電話口で声を荒げられ、
「ほかの同人のみんなに迷惑がかかるのは困るっ! 『煉炭』は君を中心に活動しているんじゃないんだぞっ!」
なぞ云う陳腐なイヤ味を投げつけられながらも、間違いなくこれが年末には〝半期優秀作〟に選ばれるであろう根拠のない自信をふとこっていた彼は、尚も平身低頭で頼み込み、さらに数日を経てやっとのことで書き上げ、誠意を見せる為に原稿を千葉の検見川の主宰者宅にわざわざ持ってゆき、著者校は彼だけ印刷日の当日に、新小岩の町工場内の一隅にて行なったものだった。
そして、かような印刷所での著者校と云う〝小説家ごっこ〟的な一幕も挟んだせいか、貫多はいよいよ該作が転載作へのロイヤルロードを突き進んでいる確信を覚えていたのである。
だが、彼にとっては意外なことに、また傍目から見れば至極当然なことに、それはどこまでも馬鹿馬鹿しい錯覚にしか過ぎず、翌月だか翌々月だかの〝同人雑誌評〟で、『煉炭』誌の他の収載作は採り上げられていても、彼のその自信作はまるで黙殺されると云う、この当たり前と云えば全く当たり前の事態に、根が異常に自己評価の高い質ながら、一方の根はクールなリアリストにもできてる彼は、いっぺんに現実世界へと引き戻されてしまった。
なのでもう、身の程もわきまえぬ小説の真似事じみたものを書くのは一切やめ、やはり初手の目的のみに邁進することとした。どうで彼の束の間の〝創作意慾〟は一時の気の迷いと云うか、瓢箪から幾つ駒が出てくるかを試してみただけの、一場の遊興みたいなものだったのである。
ところで貫多のこの二作目の、ちょっとも擦りもしない見事な三振ぶりは、他の同人たちには随分とお気に召したようであり、そうなると前作を含めての悪評が彼の耳にも洩れ伝わってきた。
かの同人たちと云うのは十四、五人程度の集まりであったが、皆一様に六十歳を過ぎた高齢者ばかりで、元教職者や元銀行員なぞインテリ層のリタイア組も多く、中にはすでに数十冊の自著を持つ人物も混じっていた。
但、貫多がその多くと面識がないと云うのは、偏に月に一回行なわれている同人会に殆ど足を運ばなかったことによる。
何しろそこでの話と云えば、直近の芥川賞受賞作の批判である。現今の小説や文芸誌を全く読まず、その賞の最近の受賞者も受賞作もまるで知らぬ貫多には、その手の話柄は退屈でたまらなかったが、よし口を挟む余地があったとしても、結句は妬みと嫉みの世界だから、馬鹿馬鹿しくなってすぐにソッポを向くことになろう。仮令その同人たちが言う通り、槍玉にあげられた新人作家の作がどんなにつまらなかったとしても、少なくともその同人の作よりかは、はるかに読ませるものであるに違いない。
殆ど文盲に近い貫多の目にも、いったいに同人雑誌を主戦場にしている人たちは、文章は滅法に上手いと思う。何んとも国語の教科書通りの行文で、読み易いことも確かである。
そして『煉炭』誌もそうだが、同人雑誌全般としてもその作は圧倒的に私小説が多いらしいものの、しかし肝心の内容がさっぱり面白くないのだ。無論、これは貫多は自らのことを完全に棚上げにしての感想なのだが、内容がちっとも、ひとつも面白くないのである。
それだから会合の話題が、何んだか創作の方法論みたいなものに移っても、それらは実に安っぽい、どこかで聞き齧った言葉からの受け売りを並べ立てているものとしか聞こえず、かつ、そんな猫に小判的な議論がどうにも片腹痛くて、貫多はこんな会合ならば、とてもではないが電車で一時間以上もかけて検見川くんだりまでくる必要は感じられなかった。
で、そんな彼の内心の不遜は自ずと表情にも浮かんでいたとみえ、もともと見た目が小説なぞ読みそうもないタイプの、土方ヅラした貫多の存在は同人の間でも浮き上がり、それまでの二作中で記した「私」の冴えない経歴と、些か異常者風の作中主人公の言動から妙な色眼鏡もかけて見られたらしく、陰でイヤ味やら全否定やらを散々に囁かれていたようだ。