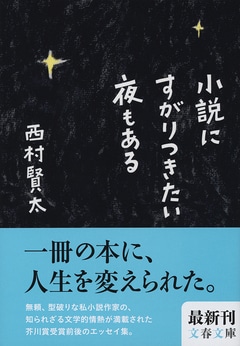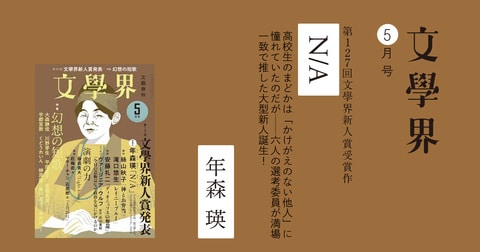「文學界」で連載され、最終回執筆中に著者が急逝したために未完となった、西村賢太さんの『雨滴は続く』(文藝春秋刊、488頁、定価2200円)が単行本にまとまりました。
後年の西村さんのキャラクターは広く知られていますが、本作に描かれているのは、それが確立される以前、小説家としてデビューする前後の北町貫多=西村賢太の姿。何者かになろうともがく貫多の、言わば”遅すぎた青春”篇です。
発売を記念して、1章を無料公開いたします。(文學界noteではさらに2章、3章、4章を公開中です。)

一
このところの北町貫多は、甚だ得意であった。
元来、と云うか、生まれついてこのかたの不運続きで、三十七歳と云う年齢を虚しく経ててきた彼にとり、それはかつて味わったことがない昂揚であり、覚えた様のない心境でもあった。
―ことの起こりは、二箇月近く前に届いた一通の葉書である。文豪春秋の文芸誌『文豪界』編輯部から届いた一通の葉書である。
その仁羽と云う編輯者によるところの短文は、貫多の作品が二〇〇四年度下半期の〈同人雑誌優秀作〉に決定したことを伝えるものであり、ついては該作を『文豪界』の十二月号に転載するので追ってゲラを送付、訂正箇所を手直しした上で早急に戻して欲しい、との意の文言が続いていた。
貫多も、この転載の〝制度〟のことは知っていた。はなは昨年の夏、同人雑誌に加入したのちに、その主宰者から知らされたのである。
何んでも現今の、いわゆる純文学雑誌五誌のうち、〝同人雑誌評〟のコーナーを設けているのは『文豪界』一誌のみだそうで、そこでは四名の選者が〝今月のベストファイブ〟として、印象に残った作を五本挙げるらしかった。
そして半年ごとに計三十本の作を〝候補作〟とし、うち一本を半期の優秀作に定めるそうであったが、するとそれは『文豪界』誌に全文転載と相成るのが長年の慣らわしになっているとの由。
更に主宰者が続けたところによれば、
「今現在、同人雑誌は小説誌だけでも全国に六百誌ぐらいあって、そのうち毎月百冊近くが『文豪界』に送られてくるらしい。一冊に平均五作が載っていたとしても月に五百作だから、ベストファイブに入るのは、これは容易なことじゃねえんだよ。その上、半年なら三千作にまで膨れ上がっから、この中で優秀作に選ばれるには、よっぽどのものを書かねえと、とてもじゃないけどね……」
と云うことだったが、このとき九十歳になる主宰者は、元は江戸川辺のペンキ職人であり、その傍ら若い頃より同人雑誌活動を継続し、昭和三十年代には『新日本文学』にも創作を発表して、今も尚、自身の雑誌に毎号短篇を書き続けている人物だった。すでに十年程前に〈同人雑誌優秀作〉にもなって転載を果たし、以降はかのコーナーのベストファイブ入りの常連組であることが何よりの誇りであるらしく、そうした自らの〝業績〟を語る際には、
「一回、優秀作に選ばれっと、あとは二度目を許してくれねえんだから、いつもこっちはよ、どんだけいい作を書いてもベストファイブ止まりなんでイヤになっちまうよ」
と、巻き舌で付け加えるのを忘れなかった。
ところがそんな話を再三聞かされたあとに、貫多がその主宰者率いる『煉炭』という雑誌に初めて載せてもらった駄作は、三箇月後の件の〝同人雑誌評〟コーナーであっさりベストファイブ入りになった。
これを妙に上ずった声による主宰者からの電話で知らされた彼は、とりあえず駅前の新刊書店へ行って、該誌を手に取り評文を読んでみたが、その時は一寸したうれしさは覚えたものの、そう得意を感じるまではいかなかった。
思わぬ高評を貰ったかたちではあるが、しかしそこでいくら褒められたところで、商業誌に転載されて、より多くの目に触れない限りは、これにはさして意味もない―と、やけに〝転載〟に重きを置くかのような考えかたをしたが、しかしながら、貫多は昔から小説―殊に私小説を読むのを何より好みながらも、自らが書き手となるのを目指そうとの、馬鹿な、或いは大それた希望はてんからしてふとこっていなかった。
子供の頃に横溝正史の探偵小説を貪り読んでいた時分は、将来は推理作家になろうかと莫然と夢想したこともあったが、それはどこまでもその以前に、日本ハムファイターズの選手以外に自分の就く職業はなしと頑なに信じ込んでいたのと大差のない、ただの囈言にしか過ぎぬ。
そもそも、貫多が同人雑誌に入ってみる気になったのは、別段小説を発表したかったわけではない。自身の敬する大正期の私小説家、藤澤淸造に関する雑文を載せてゆこうとの目的のものであった。
それより遡ること八年前の二十代の終わりの年に、自業自得の暴力沙汰で起訴された彼は、周囲からすっかり四面楚歌の状況になっていた。僅かに相手にしてくれていた者もすべて去り、見事なまでに何もなくなった苦し紛れで、以前に一度読み、それなりに魅かれるところのあった藤澤淸造の私小説を再読したところ、今度はその一言一句が異様に心に沁みてしまった。
生き恥にまみれつつ、決して上手いとは云えぬ創作を意地ずくで続け、果ては性病由来の脳梅毒で行き倒れ不様に死に恥までもを晒した該私小説家の作を、古書展や古書目録を猟り掲載誌で一つ一つ探して読むことは、往時貫多の唯一の慰めであると同時に最高の娯楽でもあった。
ダメ人間がダメ人間に魅かれる典型みたいな塩梅式で、彼はこの私小説家の〝歿後弟子〟となることを自らに課し、根が思い込みの深い質でもあるだけに、やけにその点については思い詰めた。そして勝手に思い詰めた挙句、〝師〟の無念を晴らすことだけが、向後の自身のただ一つの目標にもなっていた。他にはもう、己れの人生も含めて何に対しても熱意を持てなくなっていたのだ。
で、差しあたり貫多が〝歿後弟子〟として取りかかれることと云えば、かの私小説家の完全網羅に近い全集の自費出版と、できる限りの詳細な伝記の作成である。
共に先立つものは金であり、肉筆資料一つ入手するのも地方へ二、三日調べ事に行くのもすべて金が不可欠だから、これは完全に人生を棒にふる覚悟を固めなければ、到底成し遂げることはできぬなりゆきである。
その辺りの腹はすっかり括ることができたが、それと同時に、自らも藤澤淸造に関する文章を書き散らす必要を痛感した。該私小説家の参考文献が編まれた際に、そこに自身の淸造に関する文章が数多記録されていなくては、〝歿後弟子〟としては一寸格好がつかぬことになると思ったのだ。
それ故、貫多は本来の眼目たる伝記とは別個に、その種の文章を書きまくらなければならない焦りに駆られた。が、悲しいかな馬鹿の中卒で何んのコネも持たぬ彼には、これを散発的にも発表できる場所の当てはまるでない。インターネット上の利用は、そも彼はその操作の仕方を全く知らぬ。なれば残されたフィールドは時代遅れな同人雑誌の世界より他はなかった。
と、それだけの理由で、年間六万円もの会費を要する、かの『煉炭』に参加したのである。
先にも云った通り、主宰者は九十歳の大高齢者であったが、矍鑠として、よく神保町にも足を運んでいた。
貫多は、古書街の裏路地の一画に事務所を構えている、目録販売専門の古書肆「落日堂」で手伝いのようなことをしていたが、主宰者はここの長年に亘る常連客の一人であり、出版も手がけているこの古書肆からは、何年か前に作品集も刊行していた。
従って貫多とも顔馴染みであることから、その入会もきわめて自然な流れで認めてもらえたのだが、それから程なくして、彼が初めて提出してみた原稿は自分でも思いもかけず、小説風の体裁をとってしまったものであった。