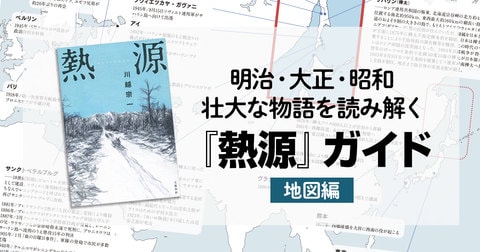「近代」が大きな波のように、地球上の多くの地域に覆いかぶさってきた時代、アイデンティティと誇りを胸に極寒の地を生き抜いた人々の、群像劇と言ってもよい作品だろう。ただし、もっとも重要な人物は二人。樺太アイヌのヤヨマネクフと、ポーランド人の民族学者ブロニスワフ・ピウスツキだ。
第一章ではヤヨマネクフの物語が、第二章ではピウスツキの来歴が、交差することもなく描かれる。
一方は大日本帝国に、他方はロシア帝国に、むりやり故郷を奪われ「臣民」に組み込まれた。奪われたのは土地や統治権ばかりではない。まず言葉、そして名前だ。
ヤヨマネクフは、日本とロシアが勝手に結んだ「千島樺太交換条約」により北海道に強制移住させられる。日本の小学校では「八夜招(ヤヨマネク)」と妙な字をあてがわれ、北海道から故郷である樺太(この地名は和名で、そのころはロシア名でサハリンと呼ばれている)に帰るために、「山辺安之助」という日本名の旅券を作らなければならない。ピウスツキは帝政ロシアによって解体させられたポーランド・リトアニア共和国出身で、やはり母語を禁じられ、自分の名をロシア風に「ピルスドスキー」と呼ばれると胸に灼けるような怒りと痛みを覚える。
ヤヨマネクフにとって最大の悲劇は、美しかった妻キサラスイを天然痘で失ったことだった。「文明」は侵略者として彼らの前に現れ、搾取し、「野蛮」「未開」と貶めたが、種痘を拒んだ妻や多くのアイヌの無学はたしかに、彼らの命を奪うものでもあった。変わらなければ生き延びられない。アイヌがアイヌであり続けるためにはどうすればいいのかと、ヤヨマネクフは苦悶する。
ピウスツキは、帝都サンクトペテルブルグの学生だったが、皇帝暗殺を企てた仲間の運動に巻き込まれ、拷問を受けた末に流刑地サハリンに送られる。最果ての地で生きる意欲も失いかけた彼にもう一度情熱をくれたのは、その地に住むギリヤークとの出会いだった。その言葉、文化に瞠目しつつ、ピウスツキは人種や民族で優劣をつけることのできない「人間」の存在に改めて気づく。
「アイヌ」はアイヌ語で「人間」。ギリヤークが自分たちを呼ぶ言葉である「ニグブン」も、ギリヤーク語で「人間」という意味だ。
ヤヨマネクフとピウスツキは、第三章になってようやく出会う。録音機を携えてやってきたピウスツキの依頼にこたえて、ヤヨマネクフはサハリン・アイヌの歌を吹き込む。そしてロシア語で語り出す。
「私たちは滅びゆく民と言われることがあります」「けれど、決して滅びません。未来がどうなるかは誰にもわかりませんが、この録音を聞いてくれたあなたの生きている時代のどこかで、私たちの子孫は変わらず、あるいは変わりながらも、きっと生きています」
川越宗一の長編第二作は、作家がタイトルに込め、作中で何度も言及した「熱」に満ちている。
最初に書いたように、これは群像劇だから、登場人物の数も多い。彼らが、極寒の地でとにかく生きる、その強さが、氷を溶かさんばかりに熱く語られる。
ヤヨマネクフの親友シシラトカ、教育者となる千徳太郎治、ともに五弦琴(トンコリ)の名手である印象的な女性、キサラスイとイペカラ、たぶん登場人物の中でいちばんかっこいいアイヌの頭領チコビロー。
結核に倒れるギリヤークの若者、インディン。
そしてロシア・パートでは、「根菜のような顔」をしたアレクサンドル・ウリヤノフ(レーニンの実兄)が印象的だ。
最初のほうに登場して鹿児島弁でしゃべりまくる西郷従道をはじめ、金田一京助、長谷川辰之助(二葉亭四迷)、大隈重信、白瀬矗と、和人(と、あえて書いてみる)の登場人物も有名人ばかりで、華やか。後半になって、これらの人々が出てくるあたりになると、ちょっと史実が多すぎて疲れるくらいだ。生真面目に石川啄木まで出してこなくてもよかったんじゃないかと、つい思ってしまったりする。
それはともかくとして、読むほうも自然にこの「熱」に引っ張られるようにして読み進んでしまう。そして、かなり長い、七十年くらいの時間の流れる、そして登場人物の多いこの物語を、むさぼるように読んでしまうことになるのだ。
作家の「熱」は、史実じたいのおもしろさに鼓舞されたところもあるだろうけれども、一貫して、一つの問いに全力で「否」を突きつけるその意志にこそ感じられる。
「文明に潰されて滅びる、あるいは呑まれて自らを忘れる。どちらかの時の訪れを待つしか、自分たちにはできないのか」
という絶望的な問いに、ヤヨマネクフは「違う」と答える。