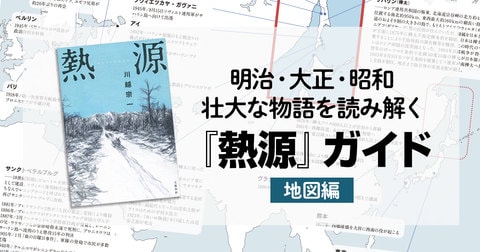かつて、幼かったヤヨマネクフの「文明ってな、なんだい」という質問に、チコビローは答えた。「馬鹿で弱い奴は死んじまうっていう、思い込みだろうな」。
そう、それは思い込みだ。別の道はある、と、ヤヨマネクフは思う。「道は自分で見つけるものだ」と。文明に潰されず、吞み込まれず、しかし、その叡智は身につけて、自分の行くべき道を選び取る。そういうことができるはずだと。アイヌを「滅びゆく民」と呼び、組み敷かれる者たちと捉えるその考え方に、「熱」をもって抗おうとする。
ピウスツキはそれを、「摂理と戦う」と呼ぶ。「弱きは食われる」というのが「人の世界の摂理であれば、人が変えられる」ものだと。こうして二人の男は自分たちの生きる厳しい氷の世界を熱源に変えようとするのだ。
とはいえ、彼らが抱え込んだ問いは、一筋縄ではいかない。
二十世紀は、「戦争の世紀」と呼ばれた。それまでの戦争とは違い、兵士だけでなく一般市民が巻き込まれる総力戦で、大量殺戮を可能にする近代兵器を擁した世界戦争が二度も戦われた。圧倒的な「力」。たとえば、第二次世界大戦では、それは核兵器という形で具現化し、その後の世界を「核による冷戦」の時代に変えた。力を持つ者と持たざる者がある。持たない者は持つことでしか生き延びることはできないという、小説中で「無くなるかもしれなかった極東の小国で、四十年近く政界をうろついていた老人」大隈重信が言い放つ論理に、二十一世紀に入ったいまも強く賛同する人々は存在する。
二〇二二年二月にロシアがウクライナに侵攻した。作中でブロニスワフ・ピウスツキが、ポーランド共和国建国の英雄となる弟のユゼフと交わす会話は、まさに、彼の地で人々が交わし、世界を巻き込んで交わされている言葉に違いない。
弟は武力を選んだ。では、兄は何を選んだのか。
ヤヨマネクフとピウスツキが選ぶのは、「人間」であること、道を自分で切り開く人間であることなのだが、そうした抽象的な言葉ではなくて、たしかに選ばれているものがある。
それは、キサラスイがヤヨマネクフに教えた五弦琴の調べだ。イペカラがヤヨマネクフの歌に合わせて奏でたものでもある。そしてピウスツキの妻となるチュフサンマが、夫の意思に反しても入れることを望んだアイヌの入れ墨だ。知里幸恵が残した『アイヌ神謡集』、千徳太郎治が書いた『樺太アイヌ叢話』、金田一京助が収集したアイヌ語そのもの。ヤヨマネクフにとっては、和人には扱えない樺太犬を率いて南極点に到達すること、でもあっただろう。ピウスツキにしても、自分にとっての第二の故郷であるサハリンの「文化」が、生涯かけて選び取るべきものの指標となった。
印象的なシーンがある。ヤヨマネクフが息子の八代吉といっしょにアイヌ伝統の刳舟を作る。北海道に移住させられ日本の小学校で教育を受けたヤヨマネクフは、自らの意思で樺太に戻ってからその作り方を覚えた。「昔からの暮らしを墨守しようとは、ヤヨマネクフは思わない。ただ樺太に帰って来たとき、古(いにしえ)から連綿と伝わる慣習や知恵を知らない自分を、恐ろしく寂しく感じた」。そして息子に語る。
「本当に帰るべき先を知りたかったからかもな」
わたしは、ある小説の背景取材で日本に住むクルド人について調べたことがある。国を持たない最大の民族と言われるクルド人たちは、トルコやシリアなどで、それこそ言葉を禁じられ、文化を禁じられ、迫害を受けて海を渡ってくる。彼らを受け入れる制度や態勢の問題は、いまは措くとして、ハッとさせられたのは、彼らが極東の地日本で、その言葉と文化を守り続けていることだった。母国では禁じられた伝統楽器やダンスが、遠く離れた日本で、演奏され、舞われる。
『熱源』はサハリン/樺太の地を題材にした歴史小説だけれど、そこで語られていることは、いまを生きているわたしたちに「故郷」について、失われていく「文化」について、人の「帰るべき先」について、考えさせる。わたしたちが知っているかのように思っている歴史を、角度を変えて見せてくれるばかりか、いま、この世界を生きていくうえで、考えなければならないことに気づかせてくれる。
そうした意味でも、『熱源』は、第一六二回直木三十五賞にふさわしい作品で、二〇一九年の文学界の大きな収穫である。