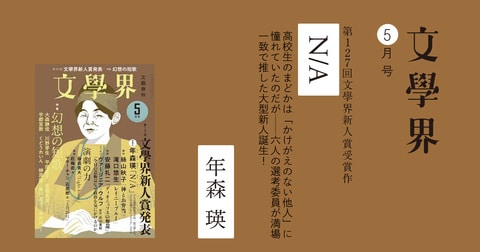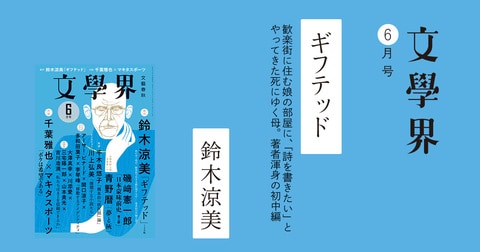ICOは孤独である。
と同時に孤独ではない。
なぜなら――
*
ICOはiPhone13の前で踊っている。
なぜなら――、
なぜなら彼女はTikTokerだから。いや正確に言えば、彼女はTikTokerでもある、というべきか。あくまでそれは彼女を説明するための一つの要素に過ぎないのだから。
しかし取り急ぎ今彼女について説明するのなら、TikTokerであるとするのがよいだろう。ICOは男性にも女性にも受ける外見を持っている。音楽に合わせて躍動する短い動画と、少しこじゃれてくだけた愚痴トークコーナーをUPし続けることで彼女は人気のTikTokerになった。
ICOはTikTokerであると同時に大学生でもあるのだが、TikTokから得られる収益だけで学費と生活費を稼ぐことができていた。まだネット上にあげていない、TikTok用の短い動画はアプリ上で下書きとして保存されるが、ICOは既にストックを300ほど作っていた。毎日同じ時間にアップロードし、たまにおまけとして、友達としゃべる件の愚痴動画をあげる。フォロワー数は50万人を超えて、半年前からは企業の商品やサービスを紹介するいわゆる案件動画のオファーが舞い込むようになって、収益は跳ねあがった。
ICOはTikTokのアカウントの名前だ。彼女は顔を出しておらず、首から下だけの動画をアップし続けた。ICOは自分のチャームポイントは体、もっと言えば胸部であると考えている。音に合わせて体を動かすことで、自身の乳房が躍動し、それを目当てにした男性視聴者を獲得できるだろう、というのがTikTokerになる前にICOがたてた基礎戦略だった。
彼女はアニメには詳しくなかったが、アルバイトで貯めた資金でそんな自分でも知っているアニメのコスプレ衣装を購入し、それを着てiPhone13の前で跳ね、TikTokを撮った。ネタが尽きると、人気がありそうな漫画やアニメのそれに移行していった。当初はよくても数百回程度だった再生数が、UPをはじめて2か月を過ぎた頃から4桁に届く動画がでだした。しばらく3桁と4桁を行ったり来たりする日々が続いたある日、動画の一つが急に一日で10万回再生され、その後も順調に再生回数は伸び、一週間後にその動画の視聴回数は200万を超えた。
ICOは観たことすらなかったが、彼女が着たコスプレ衣装のひとつの漫画作品の実写化が決まり、その宣伝用の公式Twitterアカウントが彼女の動画を紹介したことがきっかけだった。ICOはその漫画作品には何の思い入れもなかった。ただ彼女が衣装を選ぶ基準、つまり胸部を強調しているものを選んだだけだった。
TikTokをはじめてから、3か月足らずで初のバズりを経験したICOだったが、そのことに彼女は別段驚きはしなかった。なぜならそれは彼女にとって、想定内だったから。狙いを定め、機械的にこの方針を貫いていけば、いずれはバズが訪れる。それからも安定的に動画のUPを続け、女子大生の愚痴としてのYouTube動画へと誘導する。ICOは愚痴の一環として、これまでやってきた人気獲得戦略について悪びれもせず、ありのままを話した。そして、友達と二人で、女子大生として生活をする中で日々感じるストレスを画面をぼやかした動画の中で語った。
「顔を見せてないのがいいでしょ? だって、多分顔見たらがっかりするよ。フォロワーきっとバカ減りすると思う」
「ええ、でもICO顔もバカ可愛いじゃん。そんなことないと思うよ」
「や、ベスちゃんがそう言ってくれるのは嬉しいんだけど、違うんだって、可愛いとかそういうことじゃなくて、見えてないから想像がかきたてられているというか」
「ああ」
「勝手に理想の顔面想像してっからな、こいつら。人権ない生活送ってるくせに、人の顔にはうるさいんだよ」
などと友達と語る態の動画の出演者は実はICO一人だけだった。友達の名前は、スライムベスとしていたが、これはヴァーチャルな友達であって、それもICOが演じていた。ICO自体もボイスチェンジャーを使って少し声を変えていたが、スライムベスを演じる時は口調を変え、さらにボイスチェンジャーで強めに声を変えて演じ分けた。
学生にとっては莫大とも言える金を稼げるようになったが、ICOはそろそろTikTokから足を洗おうと考えている。もともとのICOの思惑としては、学費とつましい生活費が稼げればそれでよかった。ICOにとってTikTokは大学に通い、卒業するための手段に過ぎなかった。それが、大きくなりすぎて、身バレの危険性の方を強く感じる。お世辞にも裕福とは言えない環境で育った彼女が望むのはあくまで普通の上位である。馬鹿にされない街に住み、センスのいい洋服を着て街や大学を闊歩して、きちんと4年で大学を卒業し、恥ずかしくない会社に就職する結末こそが自分の望む大学生活であり、近未来であって、TikTokerとして有名になりたいわけではまったくなかった。
これまでの東京生活で彼女はさんざん屈辱を受けてきた。あの屈辱に比するならば、TikToker、ICOとしてiPhoneの前で胸をゆすることなどいかほどのことでもなかった。そう、身バレさえしなければ。
ICOがTikTokerから足を洗おうとするにはもう一つきっかけがあった。それはもう十分に資金が貯まったから。TikTokerとしてバズる前の生活レベルに戻せば、卒業までの生活費と学費は十分賄えそうだった。1LDKの部屋から、大学生らしい手狭なワンルームへと引っ越し、外食を減らし、服や装飾品の衝動買いを少し我慢しさえすれば。
しかし一度上がってしまった生活レベルを下げるのはなかなか難しいものだ。元々普通の上位を志向していたはずのICOも例外ではなかった。でもICOには妙案がある。そしてそれを実行する行動力も彼女にはある。
インターフォンが鳴って、反射的にICOはマンションのエントランス前を映したディスプレイをみる。巨大な四角なバッグを背負った若い男。彼は、ウーバーイーツの配達員だ。元の生活レベルに戻すということは、ウーバーイーツもそう頻繁には使えなくなるということだ。配達料だけでも費用がかさみ、メニュー自体も店で食べるよりも高くなるウーバーイーツを、普通の大学生が頻繁に使えるわけがない。配達料と同じくらいの金額で一食済まそうとする学生も少なからずいる。
けれどICOはでかけるのが億劫なときはすぐにウーバーイーツを利用した。好んで薄暗くしている寝室でベッドに寝ころびながら、iPhone13でアプリを起動し、おもむろに食事を選ぶのが彼女は好きだった。メニューを頼み、配達状況をリアルタイムで視覚的に伝える画面をそのままの姿勢で眺めながら、バイクや自転車のアイコンに、
「がんばれー」
「はたらけー」
「自転車こげー」
と声を掛けた。
そのICOの声はもちろん届かない。アニメのようなアイコンが地図の上を走る速度も変わらない。アイコンが、道を間違って彼女の住んでいるマンションを通り越し、行きつ戻りつしながらようやく辿り着く。
さっきインターフォンを鳴らしたウーバーイーツ配達員は、道を全く間違えなかった。通るべき道を選び、曲がるべき道を曲がった。そして今彼女の下に、フライドチキンのセットを届けようと、マンションのオートロックを潜り抜け、今まさにICOの部屋の前で再びインターフォンを鳴らした。
ドアを開けると、若い男の配達員は、小さいが聞き取りやすい声で、
「ウーバーイーツです」といつもの呪文を唱える。
ICOは配達員がにゅっと差し出してきたフライドチキンの入った袋を受け取った。
配達員は帰り際、下駄箱の上に視線を走らせた。ICOの胸が小さくうずく。そこには昼に頼んだものの結局封を開けることもなかった、ウーバーイーツで配達されたタイ料理が置いたままだった。カオマンガイと生春巻きと、あとなんだっけ? 漫然と頼んだから覚えていないけれど、頼んだ後に、なんとなくタイ料理の気分じゃなくなったんだった。
既に去ってしまったウーバーイーツ配達員は、別にICOを糾弾するつもりはなかったのかもしれない。けれど彼の視線の動きは彼女の中にわずかにあった罪悪感を刺激した。もしかしたら、あの配達員は昼にあれを運んできたのと同じ人だろうか? ICOは思い出そうとするが、昼の配達員がどんなだったか思い出せない。彼女にとってウーバーイーツ配達員はあくまでウーバーイーツ配達員であって、個人を識別する必要を感じていなかった。しかし、さっきの感情に乏しい若い男性配達員の顔、とりわけその目がなぜか脳裏に残った。
またインターフォンが鳴る。今度はウーバーイーツではなく、友達だった。仮想ではない、普通の友達である。TikTokerではないときのICOは普通の大学生であって、普通の友達が普通にいる。普通の友達はICOのことを普通の大学生だと思っている。ICOはTikTokerであることを普通の友達には明かしていないから。だから普通の友達は、彼女は普通の裕福な家の子供だと思っている。
ICOは普通の友達を自宅に招き入れる。わあ、広いねぇ、と友達はICOの部屋を見回しながら言う。そうかな、そうでもないよ、そう謙遜しながらICOは友達を招き入れる。
ウーバーイーツで頼んでおいたフライドチキンを二人で食べ、昼に頼んだものの気分が変わって食べなかったタイ料理を、「昼のだけど。問題ないと思う」と友達にことわりをいれてから、レンジで温めて食べる。塵のように胸の片隅に残っていた罪悪感がタイ料理の消失と共にすっとなくなっていく。けれど、ウーバーイーツ配達員の目は脳裏に残ったままだった。
食事を終えて、友達が持ってきた六本入りのチューハイを呑みながらしばし大学の共通の友達の噂話をする。ICOは実のところ同級生たちの動静についてはほとんど興味を持っていなかった。けれど、最大限関心を持とうと努力して話を合わせた。たまたま大学や学年、クラスが同じだっただけの人びとに多大な興味を寄せるのが、彼女が欲する普通の人びとのはずなのに、興味がもてない。
今、ICOは別のことで頭がいっぱいだった。今日友達を呼んだのには狙いがあった。彼女は話題の句切り、チューハイを飲む呼吸、相槌の感じ、そんなところまで微視的に観察して間合いを図り、切り出すタイミングを見計らっていた。
はは、と何かの話題で友達が笑い、ぐぐ、とチューハイを呷る。それから、缶を座卓に置く。そのタイミングで、ICOは友達に切り出す。
「カナッペさ、TikTok撮ったことある?」
「TikTokって、あの音楽にのせて踊ったりするやつ?」
「そそ、ま、それだけじゃないけどね」
「やったことないなぁ。あるの?」
「私もなかった。けど、なんかさ、前にうちに来た友達とね、撮ってみたんだよね。や、別にネットにあげたりとかしないよ」
「あ、そうなんだ。あげなくてもできるの? 即デジタルタトゥーでトラウマのコンボじゃん、って思っちゃった」
「ないない。撮って、見るだけ。なんか加工とかも入って自分じゃないみたいな感じで撮れるから。で、前さ、うちのおばさんともやってみたんだけど、これは令和のプリクラだな、みたいなこと言ってて。それはちゃうやろと思ったんだけど、」
と、架空のおばの話なんかを織り交ぜながら話をし、ICOは友達の気分を盛り上げていった。ICOには架空の親戚や友達をつくる癖がある。ICOの話しぶりにのせられて友達はネットに上げないのであれば、撮ってみるのもいいかなと言い出した。すかさずiPhone13でアプリを起動して、TikTok撮影する音楽を友達に選ばせる。
iPhone13のディスプレイにインカメラを通した自分たちが映る。カウントダウンが始まって、友達に説明しながらTikTok動画を撮影する。アプリが自動的にコマを省略し、少しかくかくした面白みのある動画ができあがる。ICOが友達に説明したように自動的に加工も入り、ダンス素人の友達でもそれなりにリズムに乗って踊れているように見える。
音楽にのって体を動かす自分のTikTok動画を友達は目を輝かせてみている。その隣でICOもまたその動画に集中している。ICOは友達の体を確認しているのだった。特に念入りに確認しているのは胸部の辺りだ。ICOと友達は概ね同じ背格好で、似た雰囲気だった。コマが落とされ、加工が入ったなら私たちを知っている人でも、見分けることはむずかしいのではないか。まして、顔を隠していたなら、同じ人間に見えるのではないか?
ICOはその友達が自分の身代わりになれるかどうかを確認しているのだ。TikTokから自分が足を洗った後に、こっそりTikTokアカウントを彼女に引き継ぐことができそうかどうかを。
この続きは、「文學界」7月号に全文掲載されています。