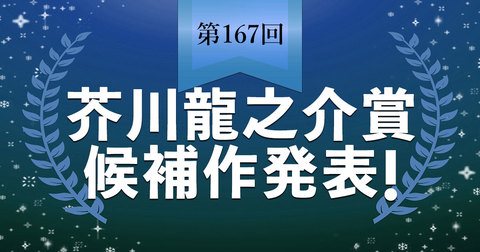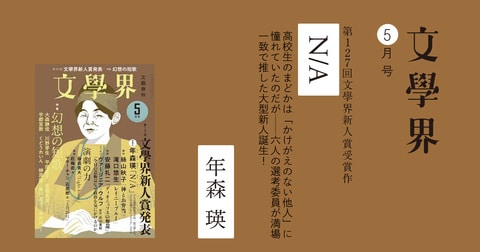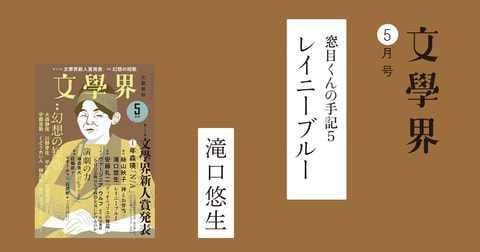「文學界 6月号」より鈴木涼美さんの初中編「ギフテッド」の冒頭をお届けします。

歓楽街とコリアンタウンを隔てる道路に面した建物の裏手に回り、駐車場の奥にある重たい扉を開けて、その扉のすぐ横の内階段を三階まで登る。階段を登り切ると再び廊下に続く重たい扉があり、そこに体重をかけて一定以上の幅まで開いたときに鳴る金属の軋むような音を必ず鳴らして、ゆっくり閉まりきる前に、今度は自分の部屋のドアの錠に鍵を差し込み左側に回して鍵の開く音を聞く。夜ごと、この二つの音を聞いて帰ってくる。その、扉の蝶番が軋んで鳴る音と、古いピンシリンダーキーの回転の途中で鳴る音の間隔が、長すぎても短すぎても安心感がない。重い荷物を一度床に置いたり、うっかり鍵を落としたりするとリズムが狂う。
夏に色々と失いすぎたせいか、秋が本格的に深まる少し前に私の部屋に越して来たいという母の要望を気軽に受け入れた。母の胃に巣食う病はいよいよ生命の維持すら困難な段階まで進み、死に場所を探しているようだった。
あと一編だけ、詩をかき上げたいの、と電話越しに母は言った。
「病院のベッドの上ではそれが無理なの。わかるでしょう」
わかるでしょう、に込められた特権的な意識を嗅ぎ取っても、私にはもう怒りも苛立ちもなかった。歓楽街の周縁にある部屋を、凡庸な病室よりは勝ると感じる母が、その感覚のまま死んでいくことを思うと、哀れにすら感じた。母はついに、彼女が望むような崇高な成功はおさめなかった。薄い詩集を何冊か出版し、その美しい顔でいくつか雑誌のインタビューに取り上げられ、地方局の朝の番組で一度、英国の詩人の詩を日本語で朗読した。それだけだった。
母が病院から直接私の部屋に移り住んだのは、その電話からたったの二日後で、もっと早く言ってくれたら私は自分の用事を済ませて、必要なものを用意できたのに、という気持ちと、母は私が彼女の居候を拒絶しないだろうと確信していたのだという安堵の気持ちは、ちょうど半分くらいだった。タクシーで到着した母は、ぶかぶかのスラックスと長袖のTシャツに辛うじてジャケットを羽織っていた。入院した日に羽織っていたのであろうその紺色のジャケットが、すでに身体を締め付けない寝巻きでしか暮らせなくなった彼女にとって、唯一かつての生活を匂わせるものだった。病院に持ち込んでいた鞄は二つだけで、母がもともと住んでいたところから他に何か必要なものを取ってこようか、と聞くと、その必要はないという。鞄の一つは二組の寝巻きと歯ブラシや櫛が詰められていたが、もう一つは私の記憶にもある母の鞄で、その中身は確認しないでもわかる。
母と同じ部屋に寝起きしていたのは八年近く前、ニューヨークでテロリストの乗った飛行機が高層ビルに勢いよく突っ込んだ頃までだが、私が十代だった二、三年を除いて、連絡を全くとっていなかった訳ではない。母の病が思いの外深刻だと気づいてからは、むしろ結構頻繁に連絡もしたし、病院や外で会うこともあった。それでも、もうずっと長いこと会わずに放置してしまった気になるのは、おそらく母が会うたびに痩せて、髪の毛も薄くなっていったからだ。若い頃は、艶があって真っ黒な髪を乳房が隠れるほど伸ばしていた。結んだりパーマをかけたりするには量が多すぎるのだと言って、少し茶色味がかった私の癖毛とは対照的に真っ直ぐ主張する黒髪を、夏でも常に垂らしていた。かき上げた前髪のバランスが悪くなると、私が通う近所の美容院とは違うサロンに行き、さらに艶を出して帰ってきた。
昨年の春頃には生き延びるつもりだと言っていた母に、そのような気概はもうないようだった。結局、仕事道具の入った鞄を開けてペンを取ることもなく、たかだか九日間私の部屋に寝泊まりしただけで、呼吸困難になって病院に戻った。半年、少なくとも数ヶ月同居するのでないのなら、毎日少しでも食べられそうなものを作って、ゆっくりお風呂に入れたり、興味がありそうな話題をたとえほとんど聞いていなくとも話しかけたりすればよかったと今思う。せめて、病院の就寝時間と同じ時刻に薬を飲んで寝る母を置いて出かけなければよかった。一緒に寝たのは、彼女が越してきた最初の夜だけだった。二日しか猶予がなかったのだから仕方ない、と母は思っているようだったけれど、実際は私が仕事で出かけている時間はほんの少しだった。
夜になって、私が出かけようとしているのを察知すると、母は薬を飲むのをわざと躊躇ったり、新聞を広げて何か無理やり捻り出した質問をしてきたりして、私を引き止めているのがわかった。行かないで、ここにいて、一緒にいようなんていう言葉は言わなかった。新聞のラテ欄を私に見せながら「何か今日寝る前に気が紛れるようなテレビないかな」とテレビのリモコンを押し付けてきた。母の腕は、しなやかで細く健康だった時に比べて数倍毛深く、皮膚があまり、人差し指から薬指までの私の指三本よりも細くなっていた。粉を吹くほど乾燥したその皮膚に、薬局で買った安い保湿クリームを塗ってあげると、少し血色がよくなり、再び「何か面白そうな番組一緒に探して」なんて言ってくる。テレビを見る習慣などほとんどなかったくせに、必死に私とたわいもない会話をしようとしてくる彼女の様子は、早く外に出なければ、と余計に私を焦らせた。
なるべく直前まで着替えず、出かける時も、いかにも夜の盛場に出かけるような服装を避けた。普段は一時間かける化粧も肌に粉をはたくところまでで止めて、あとは外に出てから仕上げるようにしていた。引き止められる時間を短くするための地味な装いは、どうしてか母の好みに合ったようだ。一度だけ、「今日の感じ、かわいい」と言われた。デニムの上にベージュのカーディガンを羽織っただけの格好だった。母に服装や容姿を褒められるのは初めてだった。でも結局、私はなるべく早く薬を飲ませるようにした上で、私といようとする母の問いかけを器用に掻い潜って毎晩外へ出た。寝落ちしかけた母を置いて出る時、外からかける鍵の閉まる音が恨めしかった。
威張っているとかお高くとまっているというようなある種の単純さがあれば、母はもう少し生きやすかったのかもしれない。身長は高くなかったが、腰の位置が高く、鼻筋が通って瞳が縦に大きかった。夏の強い日差しに当たると赤く火照る白い肌の母は、海やプールには出かけなかった。自分が美しいことをよく知っていて、その恩恵を受けてはいたが、美人などという言葉を使う世間を軽蔑もしていた。そういった性質は創作に関しても表れることがあって、母の詩を褒める一部の人間たちは、彼女の本来かけられたい言葉をかけてはいないようだった。その複雑な自尊心が表面的な気難しさのように受け止められたのも仕方のないことだと思う。短期間親しくしている人がいても、しばらくすると名前も姿も見かけなくなった。母の友人、と言われて思い浮かぶ名前は、私がすでに何年も耳にしていないものばかりだ。そのような生活が側から見てあまり孤独にも惨めにも思えないことこそ、母の姿形の最も大きな恩恵だったのかもしれない。だからこそ、痩せこけて身体は毛深く、頭髪は薄くなった姿を、私は直視しないようにしていた。
九日目の昼、私は温かい出汁をかけた麺に、九条ネギと明太子を添えて母に出した。朝まで出かけていたので、眠たかったし、何なら食べられるかという質問にいつまでも答えない母に痺れを切らせて夏の初めに買って残ったそうめんを使って勝手に作った。そうめんや鍋くらいは置いてある生活をしているが、九条ネギや明太子は母の滞在が始まってから買いにいったものだ。小さな赤いお椀を、布団の横に出した低いテーブルに置いたまま一口食べて、母はおいしいと言った。三、四回ほど口に運んで、箸を置いた。もともと少ししか入っていなかった麺は、減ったのがわからないくらい残っていた。
「こんなにおいしいものでも、もう食べられなくなった」
布団に座ったまま、量販店の安いテーブル越しに申し訳なさそうにする姿は、最期の日々、なんていう言葉からあまりにかけ離れている。使用感のある、柔らかい生地の長袖のパジャマの下には下着すら付けていない。病院の売店のものだろうか。病気で服を買いに行く元気がないからとはいえ、黄色い花柄のパジャマを母が選ぶのは不自然だ。もしかしたら、お見舞いにきた知り合いに頼んで用意してもらったものかもしれないが、少なくとも私は母の病室に誰かが訪ねてきたのをほとんど見たことがない。彼女が何度も詩の中に立ち上がらせた死や弔いのイメージをいくつか思い出して、私の胃も重くなった。
この続きは、「文學界」6月号に全文掲載されています。