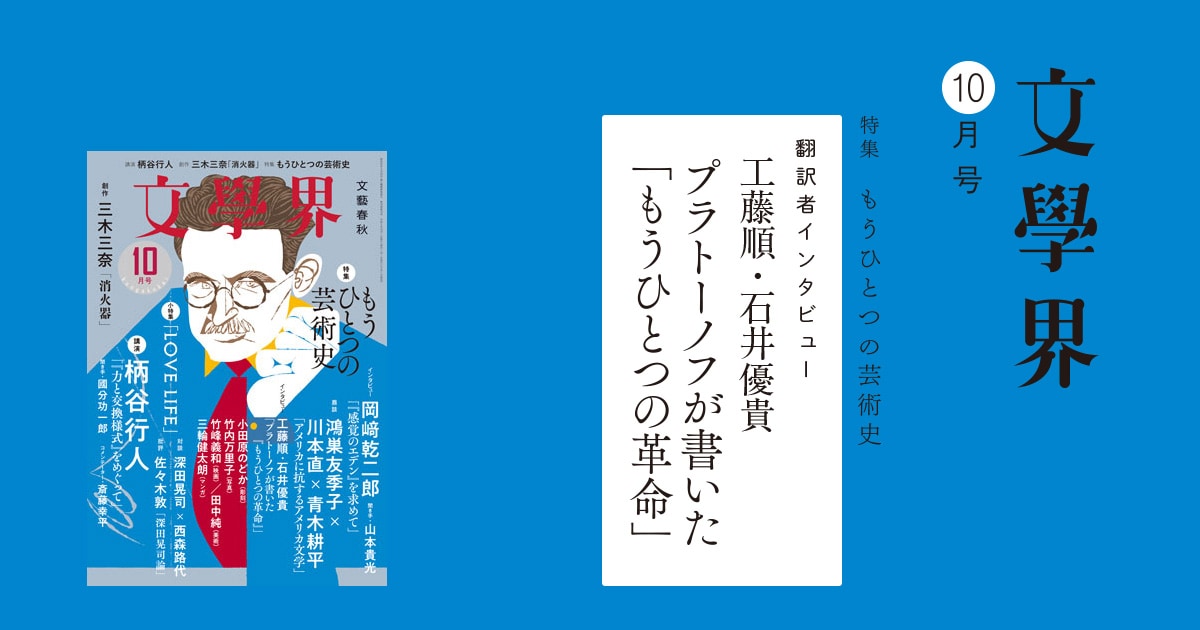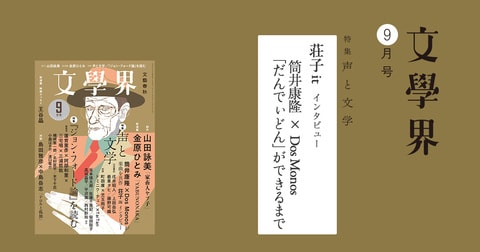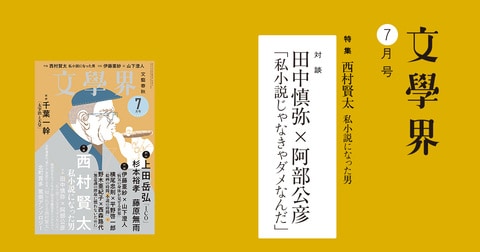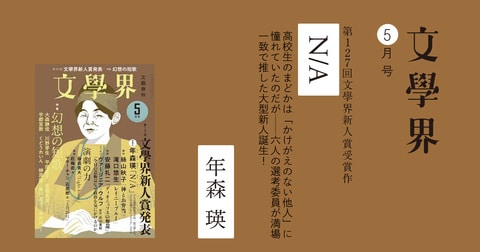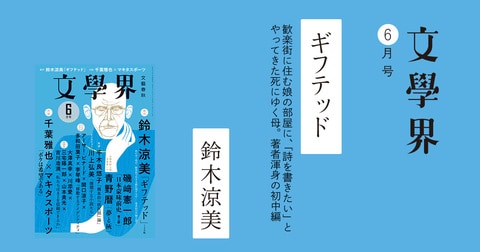二〇世紀最重要作家の代表作『チェヴェングール』がついに翻訳された。
難業に挑んだのはなぜか? プラトーノフとは何者なのか?
その作品の尽きせぬ魅力とは? 翻訳者があますところなく語った。
聞き手●編集部 写真●平松市聖

■ついに出た『チェヴェングール』
――ロシアの作家アンドレイ・プラトーノフの長篇小説『チェヴェングール』(作品社)がついに邦訳されました。プラトーノフは「二〇世紀世界文学の重要な作家のひとり」と言われながら、その代表作である『チェヴェングール』を日本語で読むことは長らくかないませんでした。翻訳されたこと自体が、「事件」だと言っていいと思いますが、本誌の特集「もうひとつの芸術史」で取り上げた理由は、二つあります。
第一は、この作品が日本の読者にロシア文学史の刷新を促すだろうことです。第二は、翻訳の解説を書かれているロシア文学者の古川哲さんの言葉を借りれば、この長篇が「あるいはそうであったかもしれないロシア革命」を描いているからです。
プラトーノフとは何者か、そして『チェヴェングール』の尽きせぬ魅力はどこにあるのかを探るべく、初めての邦訳を成し遂げたお二人に話をうかがっていきたいと思います。
プラトーノフはその高い評価とは裏腹に日本ではまだ広く知られているとは言えません。まず最初にプラトーノフはどのような作家なのかを教えていただけないでしょうか。
年譜を辿っていきますと、プラトーノフは一八九九年にロシア南西部のヴォロネジに生まれ、一九一七年にロシア革命が始まると赤軍に身を投じました。二一年に鉄道技術専門学校を卒業した後、革命政府の下でヴォロネジの土地改良事業や灌漑事業などに携わりました。二二年に詩集『空色の深淵』を発表し、二六年に妻子とともにモスクワに移住した後、二七年に発表した作品集『エピファニの水門』や二八年に刊行した作品集『秘められた人間』で作家としての評価を高めていきますが、その後、文壇や政府から批判されて、作品を発表しにくくなったそうですね。ソ連では二四年にレーニンが死に、スターリンが最高指導者になっていますが、何があったのでしょうか。
工藤 端緒は、一九二九年に発表した「疑惑を抱いたマカール」がソ連社会への批判が含まれていると強く非難されたことで、決定的だったのは、三一年に発表した「ためになる」です。スターリンが進めていた農民を強制的にコルホーズ(集団農場)へと編入する「集団化」を批判したとされ、スターリン本人からも「このクズ野郎」という罵倒を受けてしまった。それによって作品を発表することが困難になっていきました。
――『チェヴェングール』は一九二七年から二九年にかけて執筆され、二八年には、第一部にあたる「匠の生い立ち」が発表されていますが、完成した後、刊行はされたのでしょうか。
工藤 一応ゲラ(試し刷り)は出たのですが、出版の直前で差し止められてしまいました。なぜだかわかりませんが、プラトーノフは完全に出版できると信じていたみたいです。一九三〇年に書いた『土台穴』(亀山郁夫訳、国書刊行会)は、プラトーノフが実際に目にした集団化がもたらした惨状を題材としていることもあり、まったく出版の見込みが立たない状態でした。
――一九三一年の「ためになる」以後は作品の発表を完全に禁じられてしまったのでしょうか。
工藤 完全に禁止されたわけではありません。一九三六年には「三男」や「フロー」(『プラトーノフ作品集』原卓也訳、岩波文庫所収)などの短篇を雑誌に発表していますし、三七年には作品集『ポトゥダニ川』を刊行しています。第二次世界大戦時には記者として従軍した経験を基にして書いた小説が、新聞や雑誌に掲載されています。
■これからの作家
――プラトーノフは『チェヴェングール』を脱稿した後、意識的に文体を変えたと言われていますが、それはなぜだったのでしょうか。
工藤 スターリンからの批判によって作品が発表できなくなったことは非常に辛かったようで、文体を変えたことを体制にアピールして発表を認めてほしかった側面があるようです。プラトーノフ自身も手紙で「三〇年以降、根本的に文体を変えた」と述べています。実際に三〇年代以降に書かれた短篇などは、それ以前に比べると非常に文体が簡素と言いますか、わかりやすくなっています。
――それ以前のプラトーノフの文体は、スターリン体制下で正しいとされていた「社会主義リアリズム」の文体とは相容れない、新しく建設されつつある社会に貢献しないものとみなされていたのでしょうか。
工藤 プラトーノフの三〇年代以前の文体が高踏的だとは私は思いません。彼の根のところには、ヴォロネジで土地改良に携わった経験があり、すぐ隣に飢饉の危機がある農民たちの現実をつぶさに見てきたので、そこから遊離した作品を書こうとする意図は生涯なかったと思います。プラトーノフは土地改良に携わる前から文筆活動を始めていましたが、その仕事に就いたときには、今は文学のような思弁的な仕事を止め、土地改良に打ち込むべきときだ、と書き残しています。「現実から遊離していても、美しい文章を書けさえすればいい」とは、考えなかった作家だと思います。
石井 「社会主義リアリズム」という用語が実際に用いられるようになるのは一九三二年以降なのですが、それまでのソ連芸術には二つの大きな潮流がありました。一つは前衛的な「ロシア・アヴァンギャルド」で、もう一つは「プロレタリア文化」です。「プロレタリア文化」は正確に説明するのが難しいのですが、基本的には、大衆のために新しい文化・芸術を創造して、共産主義にふさわしい新しい人間や新しい秩序を組織していこうとするものでした。文学の分野ですと、後の社会主義リアリズム文学のひな型になったゴーリキーの作品やグラトコフの『セメント』などが有名です。プラトーノフ自身には「プロレタリア文化」の潮流に属しているという意識は特にはなく、私は私、という認識でいたようですが、ロシア・アヴァンギャルドの詩人マヤコフスキーなどとは根本的に立場が違います。どちらかと言えば、プロレタリア文化の側にいた作家だと位置づけられると思います。とはいえ、彼の作品は、読めばすぐにわかるように、文体も内容も当時のプロレタリア文化の中心にいた作家とは明らかに違います。
――確かに三〇年代以前に書かれた『チェヴェングール』にしても、三〇年代以降に書かれた「ジャン」(『プラトーノフ作品集』所収)などの作品を読んでも、自分が関わっている農民や共同体に寄り添って、地べたから発想していこうとする姿勢がうかがわれます。
工藤 寄り添うというよりは、無視してはいけないだろう、という意識だったのではないでしょうか。革命が起きて、今まで主体として認められていなかったような有象無象の人々が、いきなり視野に現れてきた。プラトーノフはこれまで顧みられてこなかったような社会の周縁にいた人々を描くにはどうすればいいのか、革命後の現実を反映した文学を創造するにはどうすればいいのかを懸命に考え、試行錯誤していった。その結果が、彼の文学なのだと思います。
石井 プラトーノフがプロレタリア出身で庶民階級だったことが彼の特異性を生み出したとは、よく指摘されるところです。一九世紀から二〇世紀にかけてのロシアの作家の多くは、裕福な階層やインテリ家庭に生まれていますが、プラトーノフの父は鉄道の修理工場に勤務する鉄道技師でしたし、プラトーノフ自身も最終学歴は鉄道技術専門学校で、大学は出ていません。ですから、革命を描くときも、他の作家とは目線が最初から違う気がします。
工藤 プロレタリア出身の作家は当時、非常に貴重だったので、政権も最初の頃は色々な便宜を図って、プラトーノフを特別扱いしようとしていた節があります。しかし、政権には歓迎されない作品を書いたことで、その道は閉ざされてしまった。でも、プラトーノフは少年時代に革命をわが事として受け止めたようで、基本的に生涯を通じて、反政府であったことはありません。共産党にも一回入った後に党の人と口論したかなにかで除名されているのですが、シンパではあり続けました。
――しかし、第二次世界大戦後の一九四六年に発表した「イワノフの家族」(後に「帰還」と改題、『プラトーノフ作品集』所収)が、銃後の妻が浮気をする話だったため、文壇から批判され、プラトーノフは不遇のまま五一年に結核でこの世を去ります。
『プラトーノフ作品集』を訳した原卓也さんはその解説で、ソ連でも六六年に選集が出されるまでは、書店でまったく入手できなかったと記しています。『チェヴェングール』にしても、七〇年代にパリの出版社からロシア語版が出され、各国語でも不完全な翻訳が出版されましたが、ロシア語の完全なテクストがソ連で出版されるのは、八八年まで待たなければなりませんでした。国内外で一般の読者がプラトーノフを読めるようになり、評価が高まるのは、八〇年代に始まるペレストロイカ以降と考えていいのでしょうか。
工藤 そう言っていいと思います。原卓也さんは、ロシア文学の大家ですが、同じ解説で一九六二年の時点ではプラトーノフの名前を知らなかったと書いています。プラトーノフは実に色々なジャンルの小説を書いていて、SFもあれば諷刺小説もありますし、後期になると「ポトゥダニ川」のような、ただただ胸に迫るような抒情的な作品もあるのですが、その多くはまだ邦訳されていません。未完ですが、『幸福なモスクワ』という、今ならフェミニズムで読み解いたら、絶対に面白い作品も日本語になっていません。全然これからの作家なんです。
――『土台穴』を訳した亀山郁夫さんの解説では、プラトーノフが「二〇世紀のドストエフスキー」と称えられている、と書かれているのですが、これは誰が言ったのでしょうか。
工藤 初めに言ったのが誰かはわかりませんが、そのような評価もあるようです。翻訳者としてはすこし違和感がありますが、プラトーノフとドストエフスキーのどこが似ていて、どこが違うのかを考えるのは、面白いと思います。
――『チェヴェングール』に関して言えば、壮大な全体小説を書こうとした企図の大きさは、ドストエフスキー的だと思いました。
工藤 確かに書こうとしたものの大きさや文学的野心の嵩は、ドストエフスキーに似ているかもしれませんね。『チェヴェングール』について言えば、色々な登場人物が出てきて、それを神の視点で統一しようとしないところは、ドストエフスキーに通じていると思いました。バフチンはドストエフスキーの小説を「ポリフォニー」だと表現して、そこでは小説全体を統一するような世界観や主義主張が述べられていくのではなく、登場人物それぞれの意見や思想が、ときには作者の意見や思想さえもが、対等にぶつかり合っていると論じましたが、それに近いことが『チェヴェングール』では起きていると思います。
石井 翻訳者の感想として言えば、私はドストエフスキーよりも断然チェーホフに近い気がします。
――どのようなところでそれを感じるのでしょうか。
石井 文体や取り扱っているテーマといった、表面上の類似はほとんどありません。ただ、今回の『チェヴェングール』邦訳で「虚しさ」と翻訳した「タスカー」というロシア語が醸し出す雰囲気が、チェーホフっぽいんです。チェーホフはまさに「タスカー」という小説を書いていますし(「ふさぎの虫」、「せつない」といった題名で邦訳されている)、有名な四大戯曲に通底している主題も、「タスカー」の感情に関係しているのではないでしょうか。
工藤 対象をかなり突き放して書くところは、チェーホフ的かもしれませんね。
■なぜ翻訳したのか?
――さて、いよいよ『チェヴェングール』についてお話を聞かせてください。工藤順さんは東京外国語大学でロシア語を学んだ後、現在は図書館で司書として働きながら、翻訳をされてきた。石井優貴さんはスターリン体制下でのクラシック音楽受容に関する博士論文を、東京大学大学院総合文化研究科へ提出する準備をされているところです。そのような背景を持つお二人がどのような経緯で『チェヴェングール』の翻訳に取り組まれることになったのでしょうか。
工藤 作品社で『チェヴェングール』の編集をしてくれた倉畑雄太くんとは、同じ大学だったので、在学中からの知り合いでした。石井さんとは私が二〇一三年にサンクトペテルブルクに留学したときに知り合いました。すごくお酒が強いという噂で、最初はヤバイ人だと思っていました(笑)。その後、私は二〇一五年に大学を卒業して、大学の外でも何らかのかたちで文学との関わりを保っていきたいと思い、『ゆめみるけんり』という同人誌を作りはじめたのですが、そこにときどき倉畑くんや石井さんに参加してもらい、つながりを保つことができました。
――だいぶ前から役者は揃っていたんですね。
工藤 『チェヴェングール』を翻訳する直接のきっかけは、私がプラトーノフの詩や散文を選んで訳した『不死』(未知谷)を二〇一八年に出版したことでしょうか。その刊行記念のイベントに石井さんも来ていて、けっこう酔っぱらった状態で、「工藤くん、次は『チェヴェングール』、やらなきゃいけないよね」と言われたんです。
石井 そのときはそんなに酔っていなかったよ。ワイン一本ぐらいでしょう。
工藤 そうですね(笑)。そこで「じゃあやりますか」と。といっても、私はすぐに取り掛かることになるとは思っていなかったのですが、二〇一九年に私が仕事の都合で東京から京都に移ることになって、石井さんや倉畑くんとは地理的に離れてしまうので、ここで翻訳をスタートさせておきましょう、ということになって、三人で打ち合わせをしたのが始まりですね。
――そのときはすでに刊行する出版社も決まっていたのでしょうか。
工藤 決まっていませんでした。何となく倉畑くんが出してくれないかな、という感じでした。
――翻訳を始めた後で、倉畑さんが作品社で企画を通してくれた?
工藤 そうです。
石井 『チェヴェングール』はどこそこの大学の誰々先生が翻訳していて、あと少しで出版できる状態になっているとか、色々な噂が飛び交っていて、出そうで出ないという状態が何十年も続いていました。でも、やっぱり出ないのはまずい本だとは思っていましたし、自分でも日本語で読みたいとずっと思っていました。当初はもちろん自分で翻訳をしようなどとは夢にも思わなかったのですが、自分が翻訳することになったきっかけは、やはり工藤さんが『不死』を出したことですね。私は『ゆめみるけんり』の発行など、工藤さんの文学に関係する活動を見て、ときには自分もそれに参加もしながら、すごいなと思っていました。工藤さんが仕事をしながら、文学や文化に関するイベントを開いたり、自分で作品を選んで翻訳をして出版したりする、その熱意と行動力、オーガナイザーとしての力量に尊敬の念を抱いてきました。私はそのような力がない人間だと自覚していたので、なおさら。そのような思いを持っていたので、ある日ふと、彼の力を使えば、『チェヴェングール』の翻訳を成し遂げられるのではないか、とパッと思いついたんです。それで、工藤さんに話を持ちかけた。「やってみよう」と。工藤さんも私も大学でプラトーノフを研究している専門家ではありません。ですから、このコンビで『チェヴェングール』の翻訳を出すのは、正直言って、かなり畏れ多いというか、非常に大胆な行為であるという自覚はものすごく強くありました。でも、バカなことは若いうちにやっておこうと思って。
工藤 絶対、ただ待っているよりは何かやった方がマシだ、と。
石井 翻訳の経験が少ない二人であることは重々承知した上で、それを逆手に取って蛮勇を奮い、気楽にやってしまおうと。それに若いバカ二人がポンと出してしまえば、ロシア文学界からも何かしらの反応があるのではないか、翻訳のハードルが下がって、プラトーノフの研究をしっかりされてきた方が、詳細な注釈を付けた翻訳を出すというようなことにつながるのではないか、という思いもありました。
とはいえ、翻訳を始めてみると、最初の方は訳のわからないまま完全に手さぐりで進めざるを得ず、自分で言い出しておきながら、なんでこんなに大それたプロジェクトを始めてしまったのかと後悔することもありました。でも、一頁にひとつぐらい、切なくて美しい、非常に鮮烈な文章があるんです。
工藤 そうそう、一頁に一行ぐらい輝くような文章があって、それを見つけていくことが喜びでしたね。
■特異な言語
――『チェヴェングール』の翻訳が出るぞ、出るぞと言われながら、長い間、日本語で読めなかったのは、非常に翻訳が難しいことが最大の理由ではなかったかと思います。プラトーノフの作品はいずれも翻訳者泣かせだと言われています。どこがどのように難しいのでしょうか。
工藤 ロシアのある批評家は、プラトーノフの文体を「初めてロシア語を書いたような文章」と評しました。文法的な誤りがあったり、この言葉とこの言葉は絶対結びつかないだろう、という要素同士をあえて結び付けて、新しい表現を作ったりしている。また、『チェヴェングール』を読んでいただくと理解いただけると思いますが、プラトーノフはかなり抽象的な語彙を多用しています。例えば、「自然」や「世界」のような相当抽象的な言葉がよく使われているために散文より詩を読んでいるのに近い感覚によくなりました。『チェヴェングール』は、そのような極度に抽象的な語彙に加えて、革命後に現れた民衆たちの野卑な言葉、下層の人たちが使う、すごく野蛮というか、俗っぽい言葉、ソ連が出来て初めて現れた社会主義体制に特有の言葉、官僚用語や変な略語など、そのような多種多様な言葉がグチャグチャにミックスした結果出来たような言葉で書かれています。革命が起きて、プラトーノフは新しい現実を目の当たりにして、それに対応するような言葉を一から作り出す必要に迫られたのでしょう。その結果、現実のソ連社会で飛び交う色々な層の言葉がミックスされたプラトーノフの文体が出来たんだと思います。だから、読者は「初めてロシア語を書いたような文章」を読むような、すごく新鮮な感触を得るのではないでしょうか。
石井 原理的には翻訳には完璧な正解はないわけですが、それにしても、色々なものを読み落としているのではないかという恐れを強く抱いています。ですから、崖から飛び降りるような気持ちで翻訳を出しました。
工藤 語彙が難解というのともまたちょっと違うんです。例えば、難しい哲学用語が多用されているわけではありません。一文一文を読んでいくことはとりあえずできるのですが、究極的なところで解釈が開かれていると言いますか、曖昧なところがすごく多く残る文章なんです。たぶん、私一人では自信を持って翻訳を世に送り出すことはできなかったでしょう。
――翻訳はお二人でどのように進めていったのですか。
工藤 まずおおまかにここからここまでは石井さんが担当、ここからここまでは工藤担当というふうに、おおよそ半々になるように分割して翻訳を進めていきました。それで翻訳原稿をお互いに交換して、互いにコメントを付け合いながら推敲を重ねていきました。
セリフの部分については、ほとんど石井さんにゼロから作ってもらいました。セリフの翻訳にはすごく気を遣ったからです。
――それはなぜですか。
石井 地の文とセリフでは相当に文体が違うからです。文章の質が異なるので、訳し分けなければなりませんでした。最初はどうすればいいのかわからなかったのですが、結局、自分が使っている話し言葉を応用して訳していきました。ときにはマンガのセリフの表現などを参考にして、「このくらい崩しても読める文章になるな」などと、ふさわしい日本語を探っていきました。
工藤 プラトーノフは革命後の時代に生まれてきた新しい人間たちがしゃべるような言葉を小説に落とし込もうとしたので、従来の文学的なセリフ遣いだとそのニュアンスをうまく訳せないんです。だから、新しい人間たちがしゃべるにふさわしい日本語に移し替えなければなりませんでした。例えば、革命前から生きているザハール・パーヴロヴィチのような人と革命後に生まれたプロコーフィのような人では、話している言葉が全然違うんです。女性の話し言葉の訳し方にも気を遣って、「わよ」とか「だわ」のような、今や翻訳でしか使われないような女性言葉は安易には使わないようにしていました。
石井 いわゆる女性言葉を完全に使わないようにしたわけではないのですが、これまで翻訳で使われてきた女性言葉を使うと、どうしても日本のかつての中流階級以上の女性が読者にはイメージされてしまう。でも、『チェヴェングール』に出てくる女性の登場人物は、そのイメージとは異なる存在ですし、そのような話し方はしていないんです。
工藤 石井さんが特に翻訳で力を入れていたのは、主人公のアレクサンドル・ドヴァーノフ(愛称サーシャ)の初恋の人であるソーニャとシモン・セルビノフがモスクワで出会う挿話ですね。あのソーニャ像を石井さんはかなり苦心して作り上げてくれました。革命後のロシアでは、女性を家庭から解放して、革命後の社会にふさわしい新しい女性を作っていかなければならない、という論調があったりと、女性のポジションは、社会全体の大きなテーマになっていました。プラトーノフもそのテーマに大きな興味関心を寄せていたので、ソーニャを通して新しい女性像を提示しようとしていたはずです。それに見合った翻訳をつくらなければならなかった。
石井 『チェヴェングール』が分厚くて読み通せないと思う方には、とっかかりとして、五一七頁から五四〇頁にかけてのソーニャとセルビノフの挿話を読んでいただきたいですね。
工藤 一つの短篇として読めるかもしれません。
石井 『チェヴェングール』は読んでいただくとわかるとおり、男性の視点から書かれている部分が多いのですが、前述の場面には女性のソーニャが楔のように打ち込まれていて、この挿話があるとないとでは、小説全体の印象が違うのではないか、と思わせるぐらいに重要な場面になっています。
■革命後に何を書くべきか?
――ここからは『チェヴェングール』の内容についてお話をうかがっていければと思います。
『チェヴェングール』の第一部「匠の生い立ち」では、両親を失い、孤児となった主人公アレクサンドル・ドヴァーノフ(愛称サーシャ)が成長し、大人となり、若きボリシェヴィキとしてソ連各地で共産主義建設を指導するために郷里を旅立つところまでが描かれます。
第二部「国の建設者たち」では、一九一八年から二一年の戦時共産主義から二一年に始まる新経済政策(ネップ)への移行を背景にサーシャがソ連各地を移動し、様々な人物と出会い別れながら、共産主義が今まさに建設されている現場を経めぐっていきます。サーシャはそのさなかで「チェヴェングール」という土地で共産主義によるユートピアが実現されつつあることを耳にし、そこに向かうことにします。
サーシャがチェヴェングールに進路を取るところから第三部「チェヴェングール」が始まり、サーシャが目のあたりにした共産主義建設のために奮闘する人々の姿とユートピアとはかけ離れたチェヴェングールの実態が描かれていきます。
読みはじめて、主人公であるサーシャがなかなか出てこず、孤児となった彼を引き取って育てるザハール・パーヴロヴィチの話がけっこう長く続くのに驚かされました。先ほどお二人に紹介していただいたようにソーニャとセルビノフの挿話がけっこう唐突に現れたりと三人称の多視点で描かれているので、視点人物が主人公のサーシャ以外の登場人物に自由に移り替わっていきます。
二〇世紀に入ると、トルストイが極めたような「神の視点」でたくさんの人物の主観を自由自在に描く手法に疑問が投げかけられ、『チェヴェングール』が書かれた一九二七年から二九年には、視点人物を固定して、その「意識の流れ」を微に入り細に入り描いていくウィリアム・フォークナーやヴァージニア・ウルフの小説も登場していました。そんな時代にプラトーノフがけっこう自由に野放図に三人称の視点人物が移り替わっていく形式を選んだのはなぜなのでしょうか。
工藤 それを考えるにあたってロシア文学史を振り返ってみると、ロシアでは、西欧に追いつき追いこせで西欧のような文明を築くべきだという主張と、いや西欧とは異なるロシアの大地に根ざした文明を築いていくべきだという主張の間で常に論争が行われてきました。プラトーノフの作品を読んでも、どちらかの主張に与しているとは感じられません。そのような部分は、ロシア文学の伝統からちょっと浮いていると考えられます。
それは、今言った「西か東か」という問題が、基本的には国家の問題であるからだと思います。プラトーノフが『チェヴェングール』などで書こうとしたのは、国家のような媒介がない状態での私と世界の関係で、「訳者あとがき」でも少し書きましたが、それは神話の書き方に近い。そのような意味では、フォークナーやガルシア=マルケス、中上健次といったサーガを書いた作家に近いことをやろうとしたのではないかと思います。三人称で多数の人物の視点から小説を書いたのは、ロシア革命をサーガとして語るためとも言えるかもしれません。
でも、『チェヴェングール』がいわゆるサーガかというと、それも違っているように思います。サーガや神話といえば、まずは血縁の物語ですよね。血のつながりが家族の話になり、やがて国の話になったりもする。でも、『チェヴェングール』の主人公のサーシャが孤児であるように、プラトーノフの小説では、孤児が重要な役割を果たすことが多く、プラトーノフはむしろ血のつながりを絶たれた、血縁の輪に入れないような人々を作品の中心に置こうとしていました。『チェヴェングール』は、小説の第三部に出てくる「その他の人びと」のような国家や血縁関係の外に置かれていた人々を含むかたちで新しい社会を構想することはできないだろうか、という問題意識に貫かれているように思います。
石井 『チェヴェングール』で三人称の多視点が採用されているのは、「意識の流れ」を書こうとした同時代の作家たちとは直面していた問題がまったく異なっていたからではないでしょうか。『チェヴェングール』は、革命を成し遂げたボリシェヴィズムの思想に立脚している小説で、人間の主観を掘り下げていくことは、革命が今まさに進行している時代にあっては、問題として浮上してこなかったと思われます。てんでバラバラな人々を組織して新しい秩序を作り、国家を形成したり、ひとつの芸術に結実させたりすることが喫緊の問題なので、一個人の主観を掘り下げていっても、その問題は解決できないとプラトーノフも考えていたのではないでしょうか。
工藤 プラトーノフが望むと望まざるとにかかわらず、彼が『チェヴェングール』を書いていたのは、既成のロシア社会が革命によって一度ゼロになった時代でした。西欧では小説は書くのも読むのも基本的に都会人の仕事で、都会に基盤を置いた市民社会の中の個人を描くものでした。しかし、社会が一度ゼロになった革命後のロシアでどのような小説を書けるのか、書くべきなのか。その時代を生きていたロシア作家はこの問いを誰もが突き詰めて考えていたはずです。『チェヴェングール』の文体や形式は、プラトーノフがその問題を考え抜いて出した答えだったと考えられます。
■神話のような文体
――先ほど工藤さんが『チェヴェングール』は「神話のような書き方」をされているとおっしゃっていましたが、プラトーノフの目の前で起こっていた革命後の現実が、非常に遠くから眺められ、千年後、二千年後の読者に差し出されるように綴られているように感じました。なぜそのようなことが起きるのでしょうか。
工藤 神話的だと私が一番感じるのは、やはり書き出しの部分ですね。訳文では「荒びれた森との境界が、地方の古い町のそばにはある。人は自然から抜けだし、生きるために真っ直ぐそこへやって来る。人間がひとり現れる(後略)」としましたが、冒頭の一文は「荒びれた森との境界が、古い町のそばにはあるものだ」というニュアンスで、非常に一般的な、いつでもどこでも成り立つような書き方をしています。つまり、町ってこういうものだよねと、どの町にもあてはまるような文章から始まる。そこにいきなり「人間」がひとり現れる。自然があります、町があります、で、そこに人間がポッと現れます、といった書き方をしている。そのような文体が神話や旧約聖書の創世記のような世界を読者にイメージさせるのでしょう。
――『チェヴェングール』を読むと、プラトーノフはこの小説を書きながら、どうすれば共産主義を実現できるのかを懸命にそして誠実に考えているように思いました。また、スターリンの下で進められていた、現場を知らない官僚が上意下達で理想社会を建設していくような方法では、早晩うまく立ち行かなくなるのではないかと思っていることがうかがえます。しかし、プラトーノフは対象から距離を取ってあくまで鋭い目で観察し、冷静に目の前で起きていることを叙述し、「こうすればうまくいくはずだ」とか「こうすべき」だとは声高には言わない。そのことが『チェヴェングール』を優れた小説にしていると思いました。この小説を読みながら、共産主義を実現させたい実践者と、見て書くことを仕事とする作家の分裂と矛盾を感じたのですが、お二人はそれらについてどう考えていらっしゃいますか。
工藤 先ほども言いましたが、革命によって既成の社会がゼロになり、すべての可能性が開かれたところで書かれたことが『チェヴェングール』の内容にも反映されていると思います。プラトーノフはそのような時代にどうすればよりよい社会、人間がより幸せになれる社会を築けるのかを考え、行動した。おそらくプラトーノフが理想だと思っていたのは、上の権力が強くないフラットな社会でしょう。『チェヴェングール』に出てくる「その他の人びと」のような今まで社会の他者として排除されていたような人々を包摂して、お互いに思いやることができるような社会を作りたい。お互いの思いやりのなかから、同志的な愛が生まれ、共産主義が実現されていけばいい。そんなふうに考えていたのではないでしょうか。プラトーノフは「お前はアナキストだ」という批判が投げかけられることがあり、彼は「私はボリシェヴィキだ」と否定するのですが、客観的に見ると、どうしてもアナキスト的側面は否めないと思います。
まだ邦訳されていない作品が多いのですが、プラトーノフは諷刺的な作品も多く書いていて、そこでたいていやり玉に上がっているのは、官僚主義です。官僚主義の弊害をプラトーノフは一九二〇年代に携わっていた土地改良の仕事を通じて、よく見ていたのでしょう。それを見ていたからこそ、官僚主義が人間を本当に幸せにすることはないと思っていた。
プラトーノフは対象に没入したいと思っていても、どうしても対象と距離が出来てしまう、孤独な人だったのではないかと私は思っています。私に似たところがあるから、シンパシーを抱いてしまう。
石井 『チェヴェングール』を特異な作品たらしめているのは、当時のスターリン体制に批判的な視線を投げかけつつも、革命に希望を懸け、共産主義の理想なくしては生きる意味が見いだせなかった「その他の人びと」や寄る辺なきプロレタリアートのような存在を、プラトーノフが実際に見聞きしたことを基に詳細に書き込んでいることだと思います。
工藤 プラトーノフは『チェヴェングール』でこうすれば正解だということは絶対に書かない。可能性を可能性のままに開いておき、読者に問いかけ、読者さえ事件の渦中に巻き込んでいく。
目の前の革命後のソ連社会を諷刺するような作品を書いたとしても、プラトーノフとしては、それは政権に楯突いたり、文学の力で政権を覆すためではありませんでした。方法については疑問を持っていたとしても、人々を幸せにするために共産主義を推し進めていくことは、悪いことだとは思っていなかった。プラトーノフはむしろ政権が使う用語や思想を作品のなかでそのまま使って、話を推し進めていくんです。すると、どうしても悪い未来しか見えてこない。そして、それをそのまま小説に書いてしまう。正直、政権もけっこう扱いに困る作家だったのではないでしょうか。正面から批判をしてくれれば、殺すなり何なりすればいいわけですが、プラトーノフ自身はプロレタリア出身だし、共産主義に反対しているわけでもないので、非常に位置づけにくい曖昧な作家で、政権も扱いに困っていたと思います。
石井 本当にそうですね。外から共産主義を批判しているのではなくて、その内側に入り込んで、完全にそのロジックで考えているのですが、目の前の現実を上から押しつけられた政治的な言葉だけでなく、自分の言葉で何とか語ろうとすると、政権が実現させようとしている理想と起きている現実との間の矛盾が、どうしても浮かび上がってきてしまう。当時のソ連が行っていることをすごく大真面目に取り扱ったからこそ、『チェヴェングール』のような作品になったとも言えるでしょう。ですから、諷刺に見える部分は、本当に大真面目に書いたからこその結果で、もともとの素材や対象のバカバカしさがそのまま露見してしまったのではないかと思います。
■虚しさをどう埋めるか
――第三部では、悲惨な現実が展開されていきますが、プラトーノフはこれをディストピア小説や反ユートピア小説として書こうとしたのではないことも伝わってきます。
石井 そうですね。読み終えてみると、チェヴェングールという町の失敗は、やはり必然なのではないかという気がどうしてもしてきます。他者を迎え入れると言いつつ、そもそもチェヴェングールは別の他者であるブルジョワを虐殺して作られた町です。また、チェヴェングールの建設者たちは自分たちが世界のすべてであると思い込み、外部を軽視している。そのことが遠因となって滅んでいくわけですよね。その後のソ連の予言なのではないかという気もしてしまうぐらい、チェヴェングールはユートピアとしてあまりにも出来損ないだった。でも、プラトーノフはそのことを批判したい、というわけではなく、繰り返しになりますが、やっぱり大真面目に書いていったらこの小説になった、という感じがします。
――プラトーノフが革命が成就し、共産主義が実現することを願っていることは作品からひしひしと伝わってくるのですが、それと同時に結局はダメかもしれない、すべては無駄になってしまうかもしれない、という予感と言いますか、諦念を感じさせるところもあります。その両義性がこの小説の魅力になっていると思いました。
石井 「がんばってやっているけれども、もうダメかも」は、違う言い方をするならば、「もうダメかもと思っているけど、それでもがんばる」ということです。『チェヴェングール』はそのような書き方をされている。この小説では、「虚しさ」と訳した「タスカー」という言葉が重要な役割を担っていると思うのですが、それは何か自分にとって決定的に大事なものが欠けているという悲しみです。欠けたものは埋め合わせればいいのですが、どうしても埋め合わせられない人も世の中にはいる。例えば、サーシャにとって欠落を埋め合わせてくれる唯一の存在は父親のはずですが、死んでいるので、もうどうしようもない。「その他の人びと」のような人たちは、社会から完全な他者として扱われているので、社会的に何かを得る機会を奪われてしまっている。小説では、「その他の人びと」は生きる意味を持っていないということが何度か描写されていました。今この世の中で自分にとって必要不可欠な何かが手に入れられない人は、たとえどんなに無謀であっても、欠落を埋める何か別のものを自分で作り出さなければならない。それは非常に難しいことなのですが、やらなければならないことなんです。生きる理由を獲得するには、そうする他はないのですから。
そのような問題に関して最も自覚的なのは、主人公サーシャの弟であるプロコーフィでしょう。彼はある種の賢さを持っているので、チェヴェングールを理想郷にする自分の計画が破綻しかねない、というか、破綻するだろうということに最後の方で気づきます。でも、色々な修正を施し、ある程度妥協しつつも、自らの生きる意味にしがみつく。父を永遠に失っているサーシャもまた、チェヴェングールでの共産主義の建設に邁進していく。だから、無理かもしれないけれどもがんばるということは、がんばらないと生きていけない、ということなんです。その切実さ、真面目さは、丁寧に読めば伝わってくるのではないでしょうか。
工藤 プラトーノフは一九二〇年代に書いた初期の短篇でも、「今の自分の世代は不幸でしかないかもしれない。労働してヘトヘトになるまで新しい社会の建設に邁進して、そのまま死ぬかもしれない。でも、その次の子供の世代が幸せになれるような社会が生まれるとしたら、今、私は死んでもいいだろう」というようなことを考えています。それをポジティヴと捉えるか、ネガティヴと捉えるかは人によって違うと思いますが、結末は破滅かもしれないし、みんなが幸せになれるような社会ではないかもしれないけれども、あなたはそれでもやりますか? という問いかけが『チェヴェングール』でもなされているように感じます。
石井 私はもっと情緒的に読んでいるので、そのようには捉えていないかもしれません。『チェヴェングール』には、いまここには無い何かを獲得しなければ生きていけない境遇に置かれた人が、「じゃあどうする」という問いを突きつけられたとき、どのように行動し、生きていくのかが克明に描かれている。それこそが、この小説が現代の読者にも通じる理由の一つだと思います。これからよりよい社会が実現されるとか、次の世代が幸せになるとか、そのような具体的な目標そのものはあまり重要ではなくて、とにかく今このときに、自分の欠けた心を埋めてくれる何かを得られるか否かが問題とされている小説なんだと私は考えています。だから、すごく社会的な小説であると同時にものすごく個人的な小説でもある。「共産主義の建設」というお題目に目を奪われると、現代の日本の読者にはピンと来ないかもしれませんが、「タスカー」を抱えた人が何を求めて、どう生きたかを描いた小説と捉えれば、現代の読者の心にも響くところが必ずあると思います。
とにかく、日本の読者にも「読める」ようにと二人でがんばって訳したので、ぜひ読んでほしいですね。
(7月17日、文藝春秋にて収録)
プロフィール
アンドレイ・プラトーノフ
Andrei Platonov●一八九九年、ロシアのヴォロネジ近郊ヤムスカヤ村に八人兄弟の長男として生まれる。一九二二年、詩集『空色の深淵』を発表。小説集『エピファニの水門』などで文名を高めるが、二九年にソ連を批判する小説を書いたと非難されて以降、作品を発表しづらくなっていった。五一年に他界。代表作に『土台穴』「ジャン」などがある。
工藤順
くどう・なお●一九九二年生まれ。ロシア語翻訳労働者。二〇一五年に東京外国語大学外国語学部(ロシア語専攻)を卒業。図書館に勤務する傍ら、同人誌『ゆめみるけんり』を主宰。二〇一八年、プラトーノフの詩や散文を自ら選んで訳した『不死』を上梓した。
石井優貴
いしい・ゆうき●一九九一年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期退学。スターリン体制下でのクラシック音楽受容に関する博士論文の提出を準備中。
2022年9月7日 発売