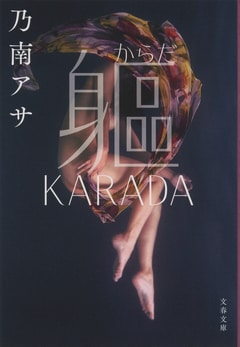著者11年ぶりの新作
「このたび、再デビューした高野です(笑)」
2011年に刊行され、山田風太郎賞、日本推理作家協会賞を受賞し、「このミス」でも1位に選ばれるなど、大きな話題となった『ジェノサイド』。以来、実に11年ぶりの新作を送り出すにあたり、冗談交じりで語る高野さん。
今作『踏切の幽霊』は、1994年の東京が舞台。下北沢の街外れにある踏切で列車の非常停止が相次ぎ、さらに心霊写真までが撮られているとあって、記者の松田は取材に乗り出す。調査を進めるうちに、彼は思わぬ真実に辿り着く――。
「いつも新作を書くときはそうですが、誰も書いたことがないものを書きたい」
そう話す著者だが、今回なぜ、幽霊小説を書こうと思ったのか。
「本好きの母親が子供にも本を読ませようと考え、児童向けの文学全集を与えたのですが、愚兄はまったく興味を示さなかった(笑)。そこで母はもっと面白そうな本はないかと考え、おばけの本を選んで次男に読み聞かせたら、こちらは見事にハマってしまったというわけです。以来、フィクションの題材としては幽霊がもっとも身近だったので、作品を書くのは自然な流れでした。その一方で、これまでにない本格的な幽霊小説にできるのではないかという感触もありました」

執筆に当たっては、既存の宗教的な考えなどは一切出さずに、人が生まれながらにして持っている死生観とは何かを考えたという。
「原始社会から現在に至るまで、おそらく人は一貫して死を怖れてきたはずで、その根源にあるのは自分が消滅してしまう恐怖ではないかと思います。
一方で、大昔から『幽霊を見た』『死んだ人間を見た』といった話がありますよね。あるいは『死んだはずの人から電話が来た』『メールが届いた』といった証言もある。幽霊が実際にいるのかどうかはともかく、いつの時代にもそうした証言があるのは不思議な感じがします。本当に死者が傍にいるのか、あるいは死んでほしくないという願望からそう思ってしまうだけなのかは分かりませんが、生きている人間が死者の存在を感じることは、何か現象としてあるのだと思います」
『幽霊人命救助隊』とは全くの別作品
高野さんの著作には、累計で33万部を超えるヒット作『幽霊人命救助隊』がある。こちらは、大学受験に失敗して自殺をした主人公ら浮かばれない4人の霊に対し、49日以内に自殺しようとする100人を救えと神から命令が下るという、笑いあり涙ありの物語。幽霊と言っても、『踏切の幽霊』はまったく異なる作品である。
「幽霊といっても完全に別ものです。『幽霊人命救助隊』の幽霊像は完璧なフィクション。幽霊という題材でフィクションもノンフィクションもないと言われそうですが(笑)、『踏切の幽霊』は現実にある証言に基づいて、様々な現象を描いています」
前作から11年も空いたことで、読者にどう受け止められるのかという不安はないのだろうか。
「それはないですね。『このストーリーで大丈夫なのか』といった不安はありましたが、それはいつものことです。毎回、過去にやったことのない話を書こうとしてますので、方法論から何から手探りで進めていくことになります」
最も苦労したのが文体
舞台は1994年なので、デジタル全盛時代よりも前、オウム真理教事件などが起こるよりも前の話である。そこで気をつけたこととは。
「まず言葉遣いが今とはちょっと違います。当時は普通に使われていたのに、今は明らかに死語になっている言葉をどうしようかと。通常は、そうした言葉は避けて書くのですが、今回はあえて使いました。たとえば『看護婦』『腺病質』、あと『アベック』なども。今の若い人にはアベックの意味が分からないらしいのですが(笑)。余談ですけど、『ヤバい』という言葉が今の意味で普及し始めたときは、自分には相当な違和感がありました。日本語は節操なく変わり過ぎるのでヤバいです(笑)。
言葉の他にも、社会の規則や習慣なども考証が必要でした。現在では病院のお見舞いに生花は持ち込めませんが、昔は問題なくできたとか」
最も苦労したのが文体だという。ノンフィクションノベルと言われたトルーマン・カポーティの『冷血』、さらにニュージャーナリズムと言われた沢木耕太郎作品など、色々と読み返してみたそうだ。
「当初は、一人称か三人称かも迷っていました。三人称にするとしても、一視点か多視点かという問題もあった。三人称多視点にしないと書けない場面が出てきてしまうのですが、そうすると主人公の個人的な心象世界からストーリーが逸れてしまう。そこでまず、ノンフィクションノベルのように書いたらどうかと考えたのですが、『冷血』などは『事実である』という前提があるから読めるのであって、純粋なフィクションであんなに書き込んだら読者は退屈してしまいます。そこでもっと情報を取捨選択して書くニュージャーナリズムのほうを研究し、『著者である私が、過去に記者をやっていた主人公に取材をして書いた』という趣向にしたらどうかとも考えましたが、伝聞という形を取ると読者と物語の距離が離れてしまいます。それで半年以上も悩んだ末に、『雑誌記者の主人公が直接経験していない場面だけを、彼が取材した内容としてニュージャーナリズム風の文章で書く』という解決策を思いついて、今の形になりました。三人称の一視点と多視点を両立させるという荒技です。読者に無駄なく物語を楽しんでいただくためには何が最上の手法か、を考えてこうなりました」
最後に、執筆中に起きた、何か幽霊と結びつくようなエピソードがないかを尋ねると、
「文藝春秋の仮眠室に幽霊が出ると聞いて見学しに行ったんです。そこでは何も出なかったのですが、別の場所で足音を聞いて振り向いたのに、誰もいなかったということがありました。一緒にいた人たちに訊いても、誰もそんな足音は耳にしていませんでした。で、その晩、家で寝ていたら、見事に金縛りに遭いまして。金縛りは医学的に説明がつくので心霊現象ではないんですが、なんて自分は感化されやすいんだろうと(笑)」
著者プロフィール

1964年生まれ。
映画監督・岡本喜八氏に師事し、映画・テレビの撮影スタッフを経て脚本家、小説家に。
2001年『13階段』で江戸川乱歩賞を、2011年の『ジェノサイド』で山田風太郎賞と日本推理作家協会賞を受賞。
他の著書に『グレイヴディッガー』『K・Nの悲劇』『幽霊人命救助隊』『6時間後に君は死ぬ』、阪上仁志との共著に『夢のカルテ』がある。