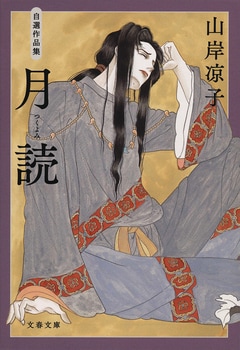はじめて触れた山岸凉子作品がホラー漫画で、しかもトラウマになるくらいの恐怖を味わったので、山岸凉子さんはホラー作品の書き手なのだと思いこんでいた。その後に『日出処の天子』『天人唐草』『パエトーン』『パイド・パイパー』『舞姫 テレプシコーラ』……と順不同に出合い、特定のジャンルにあてはめることの不可能な作家なのだと知った。
この『自選作品集 鬼子母神』におさめられている作品はいずれも、母親と子どもの関係を描いている。
「夜叉御前」は、怪奇ものと思って読んでいくと、怪奇現象よりももっとおぞましくおそろしい現実を、読み手は突きつけられる。引っ越した新居にあらわれる「恐ろしい女の人の顔」が、幽霊であってくれたほうがどれほどよかっただろうかと思わざるを得ない。
「鏡よ鏡…」では、うつくしい女優の母親と、ぽっちゃりした十四歳の娘が描かれる。母親は二十歳のときにこの娘を産んでいて、父親はだれなのかわからない。終盤になって娘は、このうつくしい母親の心の奥底からの悲鳴を聞き、「つき物が落ちたようにスーッとした気分に」なる。娘にずっと冷たかった母親の言動を理解したからである。彼女は母親の憎悪から離れ、その母を女優に育てた男に引き取られ、うつくしく変身する。
「コスモス」には、ぜんそく持ちの男の子と、彼の身を案じる母親が登場する。この母親の過度な心配は、子の支配へと通じているのではないかと思いながら読んでいると、母親の真意はそこではないことに気づかされる。母親の顔色をうかがい、その期待に応えようとするのは多くの子どもの特性でもあるが、それをコントロールできる母親という存在の、異様な力を見せつけられる。同時に、そこまで支配的になれる母親の、女性としての無力さをも。
ところで、私はこの作品に登場する料理の妙にうなった。二色そぼろごはんと見せかけて、ごはんの下にもう一色のそぼろが隠してあったり、弁当箱にくっつかないようオムレツのなかにケチャップが入れてある、といった具合に、何かを内部に隠した料理が用意され、それを子どもがよろこんで食べている、ということが、じわじわとおそろしくなってくるのである。
「ブルー・ロージス」は、無意識的な両親の支配と自己暗示について描かれている。イラストレーターとして自立している主人公が、帰省した折に、幼少期からくり返し教えこまれていた男性優位主義と、強固な暗示に気づく。
この作品にはもう一段階、先がある。皮肉なことだけれども、語り手は男性からの愛情によって、その男性優位の暗示を断ち切るのである。この中嶋さんという男性はどうしようもないやつだけれども、確実に黎子を救い、あたらしい世界に立たせるのだ。
そして表題作の「鬼子母神」。双子の男子は王子さまであり、女子は悪魔、母親は菩薩で、父親は表札│コミカルに描かれるがしょっぱなからぞっとしてしまう。家を継ぐ男の子は優遇され、女の子はその犠牲となるというストーリーを想像してぞっとするわけだが、物語はそんな単純なものではなく、予想外の展開を続ける。期待されないことによって、悪魔とされる子どもは自由を得るのである。
これらの作品が発表された八〇年代から九〇年代初頭、まだ毒親という言葉はなく、言葉がないということはその概念も存在していなかった。親は絶対的なものであり、母性はただしいものであった。家庭というあたたかい場所は万人にとって必要不可欠であり、それを否定することは反社会的な言動と等しかった。私はそれを体感として覚えている。昭和一桁生まれの私の親は、私が作家になることにも反対し、自立することにも反対し、結婚と出産こそが女性のしあわせだと言い続けていて、私がそれを旧弊な価値観だと一笑に付し、自分の言葉で反論できたのは三十代になってからだった。私が十代から二十代のとき、つまりそれは、山岸凉子さんのこれらの作品が発表された時期と重なるのだが、母親のかざす「家は絶対」論や「女のしあわせ」論を、違和感を感じながらも声高に否定することはできなかった。違和感には罪悪感が伴っていた。なぜなら、どのようなかたちであれ、親は子の幸福を本気で願っていると知っていたからだ。そして母と娘の思い描く幸福の内訳に、けっして埋められないほどの大きな隔たりがあるなどと、思いつきもしなかったからだ。