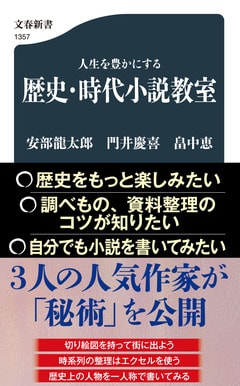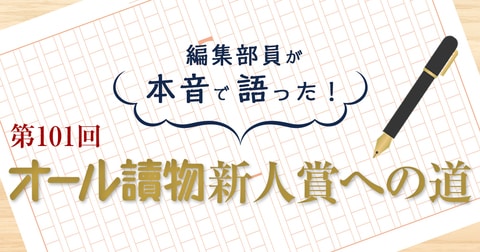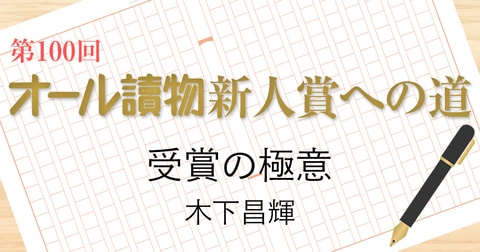四
五月になると空がどんよりと曇りがちになった。五月雨(さみだれ)の季節がやって来たようだ。夜中起きて朝寝をするという世間とずれた暮らしにも、又四郎はようやく慣れた。有難いことに、今のところ武芸の腕を振るうような事件は起こっていない。
長屋の表と裏の戸を開け放って、少々湿っぽい風に吹かれながら眠るのは何とも心地よかった。隣の赤子の泣き声も、通りから聞こえる物売りの声も子守歌に聞こえる。
日が高くなってから起き出すと、荒物屋の台所から折敷(おしき)に載せた遅い朝飯が届く。玄米飯を腹一杯搔き込んでから、腹ごなしに路地の掃除に出る。すると、どこからともなく黒猫がやって来て、長屋の住民が共同で使う厠(かわや)の塀にぴっと小便を掛けた。又四郎の顔を見ると「なっ」と挨拶して、土蔵と母屋の隙間に入っていく。
「ここまで来たなら、厠の中にしろよ」
見送った又四郎は、桶に水を汲んできて塀を流した。そこへ、「押し借りが来た」と小僧が知らせに来た。
合点承知とばかりに、店の裏口に向かう。中にいたのは、見るからに人相の悪い小男だった。銀細工の煙管(きせる)を前に置いて、主人の庄吉の方に身を乗り出している。だが、小男は又四郎の巨体を見ただけで、下卑た笑いを引っ込めた。慌てて煙管を引っつかむと、又四郎と目を合わさずに飛び出していってしまった。
「今の煙管は盗品ですよ。あの男に銀細工は分不相応です。しかし、姿を見せただけで追い払うとは、さすがでございますなあ」
庄吉が満足げに頷く。又四郎は些か肩透かしを食らったように感じたが、争う前に事を収めるのは兵法の上策だ。
「ところで、猫矢さん。一つ頼みがございます」
庄吉が手招きする。又四郎は後ろ手に戸を閉めて、主人に耳を寄せた。
「娘の飼っている黒猫ですが、あれを何処かに始末して頂けませんか」
来た、と又四郎は身構えた。お清が案じていたとおりだ。
「それは如何なものでしょう。あの猫は娘御が大層可愛がっているのではありませんか。いなくなったら、悲しむでしょう」
「それが困るのです。あの子は……まあ、いろいろあって、今は引き籠もっておりますが、私は元の朗らかな娘に戻ってほしいんです。さもなけりゃ嫁にも行けません。猫べったりで、世間からは『お清さんは猫を婿にした』とか、『あの黒猫は猫又で、娘をたぶらかしているんだ』と言われる始末。そんな噂が立つと、ますます縁遠くなっていくんです。とにかく、あの猫から引き離さないと」
「無理矢理に引き離しては、お清さんを傷付けるだけですよ。伊文字屋さんの娘を思う気持ちもわかるが、違う手立てを考えたほうがいいのではありませんか」
庄吉は深く溜息をつくと、俯いたまま言った。
「娘があんなふうになったのは、私の不徳のせいです。私の父はここで金物屋を始めましたが、お人好しが過ぎて損してばかり。かなりの借財を残して早死にいたしました。私はあんな親父にはなるまいと、扱う品物も増やして、今思えば強突(ごうつ)く張(ば)りな商いをいたしました。そのせいで恨みを買って……お清が拐かされた話はもう御存知でしょうか」
「うん……まあ、ちらりと耳にしただけだが」
「そうでしょうね。人の口に戸は立てられません。あの時、お清を捜しに駆けつけてくれたのは、かつて親父が金を用立てたまま返済を求めなかった人たちでした。皆で走り回って、あちこち捜してくれて……どんなに有難かったか。その時になって、私は親父がとてつもない宝を遺してくれたことに、やっと気付いて」
鼻をすすり上げて、庄吉が又四郎を見上げた。
「苦労を掛けた女房には報いてやれなかったけれど、お清にだけは幸せになってもらいたいんです。ですから、猫矢さん」
そう庄吉が言いかけた時、帳場の襖がしゅっと開いた。小僧の引き攣った顔が覗く。
「大変です、表で侍が斬り合ってます」
それは一大事、だが良い具合に話の腰を折ってくれた。もう一押しされたら庄吉の娘を思う親心に危うくほだされるところだった。
「店先に出るな。奥に入ってろ」
小僧に命じると、又四郎は路地に飛び出した。木戸口を出ると、荒物屋の前で若い侍二人が抜刀して睨み合っている。派手な身形からすると、旗本の倅だろうか。殺気立つ二人の間に割って入るよりも、周りに危害が及ばぬように防ぐほうがよい。
幅四間の道の真ん中で、一人は荒物屋を背に身構えている。相手が斬り込んできたら、勢いで店に飛び込むかもしれない。店先に目をやる。常連の婆様が呆然と立ち尽くしていた。巻き込まれたら大怪我ではすまぬ。又四郎は二人から目を離さずに横へ動くと、婆様の前に立った。肩越しに「下がれ」と声を掛ける。それでも婆様は棒立ちのままだったが、小僧の足音がばたばたと近づいて「奥に来て、早く」と、婆様を引っ張っていく気配がした。
侍二人が動いた。遠巻きにした野次馬がどよめく。血飛沫が上がった。まず倒れたのは斬り込んだ方の男だった。もう一人も片膝を突いて踏ん張ったが、すぐにくずおれた。
又四郎は倒れた二人を見下ろした。これ以上斬り合う力は残されていまい。店を振り返って「もう大丈夫だ」と、帳場に立つ庄吉に伝えた。
野次馬の輪が狭まって大騒ぎになった。一人はほぼ即死、もう一方も深手を負っている。戸板が持ち込まれて、遺体と怪我人を乗せた。戸板が動き出すと、野次馬がわらわらと道を開けた。又四郎はその中に見知った顔を見つけた。
着古した墨染めの衣をまとった年配の遊行僧――兎心坊だった。坊主は又四郎に歩み寄ると、静かに頭を下げた。
「またお会いできるとは、御縁がございますな」
兎心坊は沈痛な顔で遠ざかる戸板を眺め、「実は……」と話し始めた。
「先ほど、あのお侍たちが狸穴に参りまして、二人で中に入ったのです。来た時は仲が良さそうに見えたのですが、しばらくして出てくると、『おまえは心の中でおれを馬鹿にしていたのか』と怒鳴り合いになりましてね。その場は宥(なだ)めて引き取らせましたが、二人ともかなり激高していたので心配になって後を追ってきたら、やはり斬り合いになってしまって」
また狸穴か。この町に来てから、まるで又四郎を手招くように、その名が耳に入ってくる。それにしても、何故この坊主が狸穴にいたのだろう。
「坊さんも狸穴を見物に来たのか」
「ええ、噂を聞いて参りました。あれは不思議な穴で、実際に中に入ると、己の心深くに下りていくような気持ちになります。初めは苦痛ですが、それを乗り越えると穴から出る頃には生まれ変わったように清々しくなるのです。これは良い修行になると、しばらく籠もるつもりでおりました。だが、あの二人には毒になったようですな」
兎心坊は両手を合わせて念仏を唱えた。
又四郎が振り向くと、いつの間にか庄吉がそこに立っている。今のやり取りを聞いていたようで、又四郎と兎心坊を交互に見た。
「猫矢さんのお知り合いですか。坊様は近頃よくお見かけいたしますが、あの薄気味悪い狸穴にお籠もりになるとは。恐ろしゅうはございませんか」
兎心坊は穏やかな笑みを浮かべた。
「恐れていては、修行になりません」
「ほう、大したものですな……ところで坊様は魔除けの祈禱もなさるのですか」
「いいえ。拙僧には、そこまでの法力はござらぬ。先日頼まれたのは、死んだ子猫の供養でございました。施主はまだ小さい男の子で、経文を唱えると涙を流しておりました」
「猫の供養……ですか」
庄吉が縋るように兎心坊を見上げた。又四郎より拳一つ背が低いが、まずまずの大男だ。その目は力強く澄み渡り、店先に物乞いに立つような胡散臭い坊主には見えない。
「ああ、そうだ」兎心坊は思いついたように言った。「しばらく狸穴に籠もりたいので、こちらの名主様に御挨拶しておきたいと存じます。得体の知れない坊主が居着いたら、土地の者は不安に思うでしょうから」
「それでしたら、今日はもう店を閉めますから、私がお連れいたしますよ。道々御相談したいこともございますし、ちょっとの間、お待ち頂けますか」
庄吉は店に入って行くと、まだそこに立っていた婆様を丁重に送り出した。小僧と一緒になって、手際よく店を仕舞っていく。
「こちらの御主人は、困り事でもお抱えでしょうか」
兎心坊が又四郎に小声で尋ねた。
「たぶん、猫又の話だろうな」又四郎も声を潜めた。「娘の可愛がっている黒猫を始末したいんだ。だが娘の方は……」
又四郎と兎心坊の後ろで、がたんと蔀戸(しとみど)が下ろされた。
五
押し借りが来たり、斬り合いがあったりで、さすがの又四郎にも疲れが出たらしい。その晩は睡魔と闘いながら不寝番を務めた。明け方に長屋に引き揚げると、すぐさま横になった。だが、今度は逆に寝付けない。
雨の音がする。ぽつりぽつりと降り出して、やがて街道の喧噪も、隣家の赤子の声も搔き消していった。天と地に雨音が満ちる。世の煩わしさが流れて消えて、心地よい孤独だけが残った。同じ雨音をお清も聞いているだろう。
「猫を相手ではなく、猫矢と語り合いませんか」と、又四郎は独りごちて寝返りを打った。くすりと微笑むお清を思い浮かべる。もっと笑ってほしい。その笑顔に寄り添いたい……。
雨音が遠のいていった。
寝ばなを叩き起こすように声が上がる。女の金切り声だった。
目を閉じたまま耳を澄ました。荒物屋から階段を転げ落ちるような荒々しい響きが伝わってくる。ややあって店の裏口辺りで、ばたんと戸が外れて倒れる音がした。
もしや、お清に危害が――又四郎は跳ね起きると、刀を引っつかんだ。
長屋の戸口に、裸足のお清が飛び込んできた。髪を振り乱し、まさに狂女そのものだ。
「かちんが、いない。おとっつぁんが、尻尾を切るために預けたって。助けてください、かちんが死んじゃう。助けて、助けてっ」
そう叫ぶと、上がり框に倒れ込んだ。後を追ってきた庄吉が、あたふたと娘を抱き起こす。お清は口をぱくぱくして、胸をかきむしった。
「ああ、お清。こんなに取り乱すなんて。誰か医者を呼んでくれっ」
騒ぎに駆けつけた大工の女房が、赤子を背負ったまま走り出していった。又四郎は庄吉の肩を摑んだ。
「伊文字屋さん、何処に猫を預けたんだ」
「いえ、あの、籠に入れて、兎心坊さんにお布施を添えて渡してしまいました。猫又になりそうな猫がいるんだが、どうしたものかと相談したんです。そうしたら、自分が尻尾を切ってやる。万が一死んだら、きちんと供養してやろうと言ってくれたので」
昨日、お清がその猫を大層可愛がっていると耳打ちしたのに、兎心坊は何故依頼を引き受けたのか。又四郎は、お清を庄吉から引き離して抱き上げた。腕の中のお清は気を失っている。半開きの唇に目が吸い寄せられるのを堪えて、又四郎はお清を床に横たえた。
「医者が来るまで、動かさないほうがいい。兎心坊は何処にいるんだ。狸穴にいるのか」
「たぶん、そうだと思います」
庄吉は娘の顔を覗き込むと、そのまま頭を抱えて蹲(うずくま)ってしまった。庄吉の丸い背が長屋の狭い土間を塞いでいる。無礼を承知で、又四郎は庄吉をまたいで表に出た。
空はどんよりと曇っている。雨は上がっていた。
土器坂を駆け上り、飯倉四ツ辻から西へ上る坂を急ぐ。その先に、今度は南に向かって長々と下る坂道がある。坂の中ほどの崖際に、噂の狸穴が口を開けているらしい。崖下の斜面には樹木が鬱蒼と生い茂り、道から穴は見えない。又四郎は坂を下りながら、だんだんと高くなっていく崖を見上げた。木々の間に、兎心坊の姿がちらりと見えた。
「おーい」
声を掛けながら、木に手を掛けて斜面を上った。空の籠を前にして、兎心坊が苔むした石に座っていた。猫の姿はない。
兎心坊の後ろに、人一人が屈んで通れるほどの穴が開いている。又四郎は坊主頭を見下ろした。
「伊文字屋さんから、黒猫を預かっただろう。もう尻尾を切ったのか」
「いや、最初から切るつもりはない」
「それなら、何で預かるんだ。かちんは、お清さんの大事な猫だと言っただろう」
「わしが預からねば、伊文字屋の御主人は別の者を頼ったでしょう。その者は依頼どおり尻尾を切って殺すかもしれない。そうなれば娘御がどれほど傷付くか。本当にそうなる前に、あの御主人に知ってほしかった」
「荒療治が過ぎるぞ。お清さんは倒れたんだ」
医者は来てくれただろうか。あのまま狂乱してしまうのではないか。早くお清を安心させてやらなくては――又四郎は苛々と問い詰めた。
「それで、猫は何処だ。すぐに返してくれ」
「もちろんお返しいたしますが、今は中におります」兎心坊が穴を指した。「籠から出してやったら、しばらくの間、わしの足の匂いを嗅いでおりました。それから、すっと穴に。後を追ったが、出たくないと言うので、しばらくほうっておこうと」
「猫が喋るわけなかろうが」呆れ顔で又四郎は穴を覗き込んだ。「奥まで入り込んで、迷ったんじゃないか」
「そんなに深い穴ではありません。入口は狭いが、中はそこそこ広い。入って三間ほどで行き止まりになっております。迎えに行くのなら、明かりが要りますよ」
兎心坊は穴の入口に屈み込むと、火打ち石を打った。火口(ほくち)から蠟燭に火を移す。
「もし明かりが消えたら、すぐに出たほうがいい。慣れぬうちは具合が悪くなります」
又四郎は蠟燭を受け取って、穴に入った。狭い隧道(ずいどう)を膝行(しっこう)して進む。ほどなく天井が高くなった。背の高い又四郎が立ち上がると髷が天井に触れた。四角い空間は、長屋の居室よりも少し広く思えた。足元にはごろごろと丸石が敷き詰めてある。なるほど、獣の巣穴とは思えない不可思議な造りだ。腕を伸ばして蠟燭をかざすと、奥の壁際に猫の目が光った。闇に溶けるような黒い影は、紛れもなくかちんだ。
近寄ろうとした時だった。丸石に足を取られて、ぐらっと体勢が崩れた。蠟燭を持った手が空を切る。火が消えて、蠟の匂いが鼻を突いた。
漆黒の闇に包まれた。又四郎は這いつくばって、暗闇を見つめた。猫の気配どころか、何の音も聞こえない。一度外に出ようかと迷ったが、猫はすぐ近くにいるはずだ。手探りで捕まえればいいと思い直す。敷き詰められた丸石を摑んで、吸い込まれるような闇に身を委ねていると、身の内がざわざわと蠢き出した。叫びたいような衝動を堪える。全身の毛穴から細かな汗が滲み出た。頭の芯が冷たくなって、ちかちかと光が射す。低い耳鳴りが波打って、徐々に何者かの意思を象(かたど)り、言葉となって耳に届いた。
ほうっておいて。わっちは戻りません。
「えっ、かちんなのか。おまえ喋るのか。やはり、おまえは猫又になったのかっ」
違うよお。人の言葉がわかるだけ。だって、十年も人と暮らしてるんだもん。わっちらは、唇が薄くて前歯が小さいから喋れないんでごんす。
「じゃあ何故話してるんだ」
わっちは思ってるだけでごんす。
「どういうことだ。とにかく帰ろう。お清さんが心配しているぞ」ああ、抱き上げた時に、唇を吸いたかったなあ。「うわっ、何でこんな欲情が露わになるんだ」
やっぱり又四郎さんはお清さんに惚れてるんでごんすね。「にゃあにゃあ」
「やめろ、やめてくれっ」
息苦しさに喘ぎながら、又四郎は手探りで表に出た。兎心坊が顔を覗き込む。
「大丈夫ですか。顔が真っ赤で、汗まみれだ」
「気分が悪い。妙だぞ。おれが猫なのか、猫がおれなのか、わからなくなってきた」
「落ち着いて。明かりをつければ、奇妙なことは起こりませんから。さあ、蠟燭を出して」
兎心坊の差し出した手を、又四郎は振り払った。
「この穴は、いったいどうなってるんだ」
「さて、わしにも穴の正体はわかりません」兎心坊の目が穴の入口に移る。「一人闇に沈めば、己の心の声がはっきりと聞こえる。だが先ほど、わしも猫を追って入ったら、猫の心が流れ込んできた。これはどういうことだろうと、いったん表に出て考えていたところです。心が入り交じる理由はわからぬが、昨日斬り合った二人も互いの心中が露わになって、思わぬ本音に腹を立てたのでしょう」
心が入り交じるとは、何だ。理由(わけ)はともかく頭が変になりそうで、この場から離れたい。だが、かちんを助けてくれと駆け込んできたお清のためにも、ここはもう一踏ん張りしなければなるまい。戻らないと意地を張る猫を説得するには、心で話すほうが都合がいい。
「明かりは要らない。もう一度、行ってくる」
又四郎は大きく息を吸って、穴に潜り込んだ。兎心坊の声が追ってきた。
「湧き上がってくるのは、押さえつけている本音でありましょう。拒まずに素直に受け入れれば、また別のものが見えてくるはずです」
「かちん、ひとまず一緒に帰ろう」
「にゃあん」帰りたいけど、帰っちゃ駄目なの。御主人様の幸せのために身を捨てるのが猫の定めだと悟ったでごんす。
「ああ、ちょっと待て。落ち着け。落ち着くんだ。ふうーっ。よしよし」
わっちは、ここで生まれたんでごんす。母ちゃんは、まんまを探しに行ったまま帰ってこなかった。お清さんに拾ってもらわなけりゃ死んでました。お清さんは、初めは母ちゃんで、だんだん姉弟になって、今は娘と同じでごんす。だから、伊文字屋さんの気持ちがよくわかるの。わっちがいて、お清さんが幸せになれないんなら、身を引くのが恩返しでごんす。
「おまえは、なんて殊勝なんだ。だがな、このままいなくなったら、お清さんは立ち直れないと思うぞ」
わっちは、お清さんより長くは生きられないもの。いつかお別れしなきゃならないんでごんす。わっちは坊様と旅に出たって伝えてよ。わっちの代わりに又四郎さんが慰めてあげて。お嫁さんに貰ってよ。
「そんなこと、できるわけ……」
そうだなあ。こっちも訳あり、お清さんも訳あり。訳あり同士でお似合いだよなあ。
「なんて、さもしい考えをするのか、おれは」
そうなったら、嬉しいなあ。お清さんと所帯を持ちたい。隣の夫婦や飴屋の家族が羨ましいぜ。
「噓だ。おれは、家族なんて要らぬ」
親父の馬鹿やろう。あいつのせいで、家族がばらばらになった。天涯孤独の身になったのは、全て親父のせいだ。何処にいるんだ。死んだのか、生きているのか。
又四郎さん。親父なら、表にいるよう。
「何だって」
足の指のお股の匂いが、又四郎さんと同じだもん。間違いなく、親子でごんす。
かちんの首根っこを探り当てて摑むと、又四郎は穴から這い出た。心配そうな目を向けた兎心坊を睨み返したが、すぐに瞼を閉じた。頭の中を旋風が駆け巡るように、過去の日々が鮮やかに蘇る。これも狸穴の魔力なのか。
「大丈夫ですか。心の深みまで下りすぎると、しばらくは元に戻らない。少し休まれたほうがよろしかろう」
兎心坊の気遣いに、又四郎は苛立ちを覚えた。
「心配なんか要らない。それよりも、兎心坊。おれと一緒に穴に入ってくれ」
睨み付けて言うと、坊主は目をそらした。
「それは、お断りします。他人に心を覗かれたくはありません」
「おれを他人と言うか」
兎心坊の顔に懐かしさの欠片を探そうにも、又四郎には父子の間に培われた記憶は一切なかった。それでも、どんな父親だろうと思い描いたことは幾度かある。だが乱心者と聞かされてきたせいで、ろくな姿が浮かばなかった。それに比べれば、目の前の遊行僧は随分と真っ当な男に見えた。喜ぶべきか。いや、その前に、この真っ当に見える男が乱心して、友を斬り殺した理由が知りたかった。
又四郎は猫を籠に入れて蓋をした。籠目の間から覗き込むと、猫が目をこちらに向けた。
「一度、お清さんの所に帰ろう。挨拶もなく消えるのは駄目だ。身近だった者が、生きているんだか死んでいるんだか、わからないで過ごすのは辛いんだよ」
そう隣の坊主に聞こえよがしに言ってやった。兎心坊は立ち上がると、穴の入口に目をやった。
「狸穴か。人によっては真を見る穴となるのでしょうな。だが、心の上澄みに湧き上がる思いは真心ではない。それらの思いは我欲であって、人に知られれば弱みとなる。そんなものを晒すわけにはまいりません」
「わかったよ。そう言われてみれば、こちらも恥ずかしい本音を晒したくない。ただ、おれは一つだけ確かめたいんだ」
兎心坊が歯を食いしばる。その様子から見て、何を問い質されるのか薄々感づいているに違いない。それならば、一気に斬り込むだけだ。又四郎は口を開いた。
「この猫が、あんたがおれの親父だと教えてくれた。足の指の匂いが同じだから親子だと……そうなのか」
兎心坊が籠を見た。猫が「なっなっ」と頷くように鳴く。又四郎を振り向いた兎心坊の目が微かに潤んでいた。その口から途方に暮れたような、安堵したような溜息が漏れた。
「わしの妻は……不義密通を働いていました。その場を押さえたわけではありません。そんな噂があると、上役から耳打ちされたのです。相手はわしの親友だった男でした。わしはそいつを斬りました。妻子も成敗するつもりでおりました。しかし妻は生まれたばかりの子を抱いて申しました。『この子は間違いなく、あなたの息子です』と。わしは、赤子の面差しに自分と似た所を探しました。だが、わからなかった。それで、わしは妻を斬らずに逃げたのです」
又四郎は血の気が引くように思えた。
「母が……いや、あんたの妻女が不義を働いたと言うのか」
「妻は、自分は潔白だと言い切りました。だが、あの時は信じてやれなかったのです。今思えば、わしの妬心と短慮のせいで、根のない噂を丸呑みにしたのかもしれません。浅はかでした」
背を向けた兎心坊は足元を見下ろした。
「妻が実家に戻って、亡くなったのも知っております。要らぬ苦労をさせてしまいました。兵法家の内弟子になった息子を、自分に似ているかどうか幾度もこっそりと見にも行きました。でもやはり確信が持てませんでした。そうか……足の指の匂いが同じでしたか」
兎心坊は苦く笑うと、猫の入った籠を抱え上げて又四郎を振り向いた。
「その息子に許しを請うつもりはありません。憎まれて当然だからです。この話はこれで仕舞いです。猫は悪いようにはいたしません。ついてきてくだされ」
二人は坂道を無言で上っていった。まだ狸穴の力が残っているのか、又四郎の脳裏には過去の景色がちらちらと蘇る。
真冬の川で師匠の下着を洗っていた時、雨の中を使いっ走りに出された時も一人きりで泣いていた時も、あの景色の中の何処かで、この人は自分を見ていたのだろうか。
伊文字屋の店先に立った兎心坊は、中に声を掛けた。出てきた庄吉は、籠目から下がった長い尻尾を見て、安堵と失望が綯(な)い交ぜになったような顔をした。
兎心坊は厳粛な面持ちで切り出した。
「御主人。この猫だが、長年愛おしんで育ててくれた御恩に報いたいと申しておる。これからも大事にすれば、必ず魔除けの黒猫となるだろう」
「猫が喋ったのですか。それなら、こやつはやはり」
「そうだな。ぞんざいに扱えば、あるいは猫又になるやもしれぬ。だが、神仏も同じだろう。正しく祀れば御利益を得るが、粗末にすれば祟られる。もし猫又と化す気配があれば、その時は、こちらにいる猫矢又四郎殿がきっと退治してくれよう。それから」
兎心坊は諭すように続けた。
「娘御は、この猫が猫又にはならぬと言ったのであろう。まことに娘を思うなら、世間の噂より娘の言葉を信じてやってほしい。商人が世間体を気にするのもわかるが、最後に寄り添ってくれるのは苦楽を分かち合う家族だけだ。その絆を断ち切ってはならぬぞ」
庄吉に籠を渡した兎心坊は、「それでは、御免」と踵を返して去っていった。
籠の中から、かちんが鳴いた。又四郎と去っていく兎心坊を交互に見て何度も鳴く。
追い掛けなきゃ。もう戻ってこないでごんす――又四郎にはそう聞こえた。
去りゆく男を父とは認められなかった。だが断ち切り難い思いに突き動かされて、又四郎は駆け出した。土器坂を下り切った辺りで、又四郎はようやく兎心坊に追いついた。
「逃げるのか。おい、待ってくれ」
兎心坊がゆっくりと振り向く。
「わしの顔など、もう見たくもないでしょう」
「勝手に決めるな。このまま去られては悔いが残る。筆と紙を持っているか」
兎心坊が懐から矢立と小さな帳面を取り出す。受け取った又四郎は帳面の裏表紙に、「麻布飯倉町伊文字屋庄吉店 猫矢又四郎」と書き付けた。
「こうしておけば、たとえあなたが行き倒れたとしても、おれに知らせが来るだろう」
兎心坊は手にした帳面の字をじっと見据えた。やがて懐に収めると、墨染めの衣の上から手を当てた。衣越しに帳面の感触を確かめるように、その指先が微かに動く。
又四郎は、兎心坊の言葉を待った。だが坊主はくるりと背を向けると、無言のうちに歩き出した。後ろ姿が遠ざかる。振り向きもせず早足で赤羽橋を渡り切り、やがて街道の彼方に消えていった。
六
狸穴の魔力がかなり強力だったのか、又四郎は数日気分がすぐれなかった。お清の方は、かちんが無事に戻ったおかげで正気を取り戻したらしい。ただ、階段から転げ落ちたり、無鉄砲にも板戸に突っ込んだせいで、身体が痣(あざ)だらけになったと聞いた。
数日経っても顔色の冴えない又四郎を気遣って、店の小僧が箸に水飴を絡め取って持ってきてくれた。優しい甘さが身に染みる。ゆるりと味わっていると、伊文字屋庄吉の困り果てた顔が長屋の戸口から覗いて、口の中の水飴が苦くなった。
あれ以来お清が口を利いてくれないと、庄吉は泣きついてきた。
「お清さんが怒るのは当たり前ですよ。御主人なら、もっと良い知恵があったでしょう」
「猫さえいなくなれば、何とかなると思ったんです。私が馬鹿でした。お清のためというよりも、私があの黒猫を嫌っていたんです。だって狸穴にいた猫ですよ。気味が悪い」
「あの穴は確かに奇妙ですが、魔物はいませんよ」
「実を言うと、若い頃に一度入ったことがありまして。その時に、自分でもうんざりするほど小狡い思いが突き上げて、これは狐に取り憑かれたと慌てて逃げ出したんです」
「それは」又四郎は込み上げる笑いを呑み込んだ。「気の持ちようだと思うけどなあ。そうだ、今一度入ってみたらどうですか。また違う思いが湧き上がるかもしれない」
庄吉は怯え顔で首を振った。
「とんでもない。二度と御免です。ねえ猫矢さん、お清を宥めてくれませんかねえ。猫と暮らしながら、世間体を取り繕い、しかも商いがうまくいく手立てを思いついたんです。それを話したくても、お清ときたら取り付く島もなくて」
「ほう、何か思いつきましたか」
庄吉の許しを得て、又四郎は店の奥に入った。通り土間の突き当たりから右手の廊下に上がり、その奥にある急な階段を見上げた。あの騒動の時、お清はここを転がり落ちたのかと、又四郎は今さらながら冷や汗が出た。息を整えながら二階に上がると、襖の前で遠慮がちに声を掛ける。
「お清さん、ちょっとお話ししたいんだが」
ややあって、猫を抱いたお清が襖を開けてくれた。相変わらず、長い髪をぞろりと背中に流している。敷居越しに話そうとしたが、お清は「どうぞ」と部屋に入れてくれた。
「旦那さんが、ひどく後悔している。許してやってくれませんか」
「嫌です。父は根っから狡賢いんです。あの性根は直りません」
「でも、変わろうとしてますよ」
頑なにお清は首を振った。父を素直に受け入れられないのは、又四郎も同じだった。そんな自分が、父親を許せとお清に説いている。今まで父親の罪を人に話したことはない。だが、ここで明かさねば卑怯だと思った。
「実は、拙者の父は過去に罪を犯して、長らく出奔(しゅっぽん)しておりました」
その一言を言うだけで、喉がひりついた。意外な告白に、お清は呆然と又四郎を見た。
「乱心者と蔑(さげす)まれた男の倅に生まれた宿命を、どれほど呪わしく思ったか。でも先日、ふと再会して、あの人も心から罪を悔いていると知りました。子にとって親は常に正しいものと信じたいが、親もやはり間違うんだと、今さらながらに気付かされた。拙者も、あの人を父としては受け入れ難い。だが、何故か憎み切れなくなった」
額に手を当て嘆息した又四郎を見て、お清が気遣うように口を開いた。
「それが親子の絆というもので、切りたくても断ち切れないのは当たり前だと思います。それで、お父上は今は何処に」
「語り合う間もなく、また旅に出てしまいました。戻ってくるかなあ」
「もし戻ってきたら、積もり積もった恨み辛みをきっちり言っておやりなさいな。少しは猫矢様のお気持ちも晴れると思います」
「なるほど……それなら、お清さんも親父殿に恨み辛みを言ってやったら、どうですか。同じ屋根の下にいるのに、いつまでも口を利かないのは気疲れしますよ」
お清は、かちんの尻尾を弄(もてあそ)びながら頷いた。
「確かに、そうですけど、過ぎたことを言い募っても、後で空しくなるばかりで」
二人は、互いを見て頷き合った。お清はふっと笑みの交じった溜息をつく。
「でも、話さなきゃいけませんよね。二度とかちんに手を出すなって言ってやります」
「そうしてください。それと、余計なことを申しますが」と、又四郎は前置きしてから言った。「かちんを守りたいのなら、あなた自身が猫に取り憑かれたような暮らしを改めたほうがいい。猫又の噂など吹き飛ばすほど、明るく生きないと」
「そうできたらいいのですが、表に出ようとすると足がすくんでしまって」
「お清さんにはできますよ。先日もかちんを助けようと表に飛び出してきたではありませんか。もし何かあれば、この家の防ぎである拙者が、命懸けでお清さんをお守りいたします。ですから、あなたも少しずつ明るさを取り戻すように努めてほしい。失礼ながら……まずは、その乱れた髪を整えたほうがいいですよ」
あっと、お清が片手を髪に当てた。その頰がみるみるうちに桃色に染まる。恥ずかしげに俯くと、耳まで赤くなった。
「有り難うございます。お気を付けて」
店の奥から細い声が通った。
梅雨が明けて、蟬が鳴き出した。暑い盛りとなったが、お清は猫と一緒に、午後から半日だけ店の手伝いをするようになった。かちんは赤い座布団を宛がわれて、帳場の横に座っている。
「この黒猫はね、魔除けの猫です。どうです、ひと撫ですれば、旅の無事が叶いますよ」
伊文字屋庄吉は旅人の客が来るとそう吹聴した。客は、へえと半信半疑で猫を撫でていく。座布団の前に賽銭を置いていく者もいた。婆様と買い物に来た孫娘も「尻尾の先の白い毛に触ると、いいことがあるんだって」と、かちんの長い尾に手を伸ばす。かちんは尻尾をくるくる振って、触らせまいと子どもをからかう。荒物屋の店先には笑い声が溢れるようになった。
「おとっつぁん、かちんが疲れてきたから、今日はもう奥に引っ込みます」
「本当はおまえが疲れたんだろう。無理をするんじゃないよ」
襖越しにそんなやり取りが聞こえた。襖がすっと開いて、猫を抱いたお清が顔を覗かせる。紙縒(こよ)りを縒りながら、又四郎は顔を上げた。
「猫矢様、御苦労様でございます。今日はもう休んでくださいな」
「猫矢様だなんて、堅苦しく呼ばなくてもいいですよ。猫矢さんとか、又四郎さんで構いません。なんなら、猫又さんでもいい」
「やだ、猫矢様ったら」
ころころと笑うお清が眩しく見えた。親しく呼び合う仲になれればいいのにと思いながら、又四郎は微笑み返す。
「お茶を点(た)てて参りますね。おとっつぁんも召し上がりますか」
お清が振り向いた先から、ああ、いただくよと庄吉の声が返った。又四郎の膝によじのぼった猫を見て、お清は笑みを残して襖を閉めた。
「なあ、かちん」又四郎は帳場に聞こえないように声を潜めた。「お清さんは、おれをどう思ってるのだろう。おまえに何か言ってないか」
猫は大きな目で見上げたまま、首をかしげている。そのうちに、けっと声を出さずに鳴いた。
「困ったな。おまえの言葉がわからん。狸穴に入ったら、また心の内が通じ合うのだろうが、二人でここを留守にしたら、お清さんが心配するだろうし。でも、おまえ、頷くぐらいできるだろう。お清さんは、おれを……好きとまでは行かないまでも、憎からず思っているのか」
猫の耳がぴくぴく動いて、辺りの様子を窺う。又四郎が首をかしげると、焦らすようにじっと見つめ返した。
「どうなんだよ」
「にゃ」と、かちんは目を細めて笑顔を見せた。