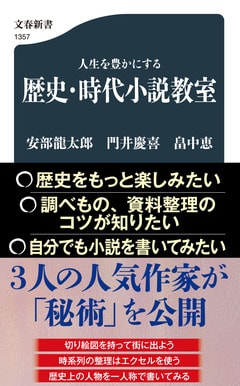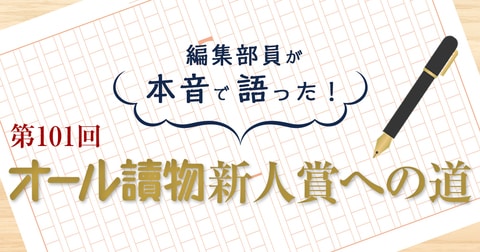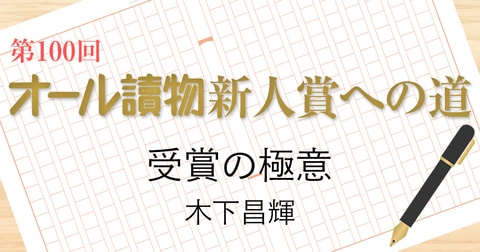「全編にわたって楽しい」(有栖川有栖)、「無条件に楽しんで読むことが出来た。ああ、面白かった」(乃南アサ)など、その独特なユーモアセンスと確かな筆致で第99回オール讀物新人賞を射止めた由原かのんさんのデビュー単行本『首ざむらい 世にも快奇な江戸物語』がいよいよ発売になりました。
収録作4篇から、「ねこまた」に続き、「よもぎの心」を一話分すべて公開します。
とある若侍が死体で発見された。下手人は河童らしく…!?
どうぞ、お仕事や勉強を終えた一日の終わり、頭を空っぽにして物語の世界を楽しんでください。

一
「河童除けのお守りになさいませ」と、女房のかめが手のひらに乗せてくれたのは、この夏に新鋳されたばかりの寛永通宝だった。
咲兵衛(さくべえ)は金色に光る銅銭を眺めた。話には聞いていたが、目にするのは初めてだ。確かに、青錆びた鐚銭(びたせん)よりは有り難みがある。だが何故、これがお守りになるのだろう。
「河童はぴかぴか光る金物が嫌いなんですよ。野っ原に出る時はお持ちくださいな」
かめの実家(さと)近くには河童が出るという。ぼさぼさ頭のてっぺんに皿があって、なりは小さく童(わっぱ)に見えるが、人や馬の腸(はらわた)を食らうから質(たち)が悪い。夕暮れに川縁には近づかないでと、かめはいつも真顔で諭す。
「河童なんぞいやしねえよ」
亭主面してそう言い捨ててはみたものの、咲兵衛はいつも懐に入れている巾着袋を取り出した。真新しい銭を巾着の紐に通して結ぶと、女房の顔に安堵の笑みが浮かぶ。同い年のかめは三十八の大年増だというのに、未だに子どもじみた物の怪を信じている。だが、そんな乙女のあどけなさを失わない古女房を、咲兵衛は可愛く思う。子宝には恵まれなかったが、もう欲は言うまい。日々息災で、女房が御機嫌な笑顔を見せてくれれば、それだけで有難い。
昇る朝日に手を合わせた後、軒下の縁台でのんびりと白湯(さゆ)をすすり、一日の仕事の算段を立てる。これが咲兵衛の朝の習いだ。薪を抱えたかめが、せわしげに前を横切る。
「今日中に菊の脇芽を摘んでくださいまし。明日は十五夜で忙しいんですから」
「そうか。朝一番に薄(すすき)を届けに行かなきゃならねえな」
咲兵衛夫婦は、大名家に花作りとして奉公している。書院や茶室に活ける旬の花は、武家の暮らしに欠かせないものだ。主家は三万石の小身大名だが、この江戸四谷(よつや)にある下屋敷はそこそこ広い。敷地の一隅にある花畑には、蕾(つぼみ)を付けた菊の群が澄んだ香りを漂わせている。その畑の前に建つ茅葺(かやぶ)き小屋が、夫婦の住まいとなっていた。
花畑と御殿を隔てる築地塀際に、萩の花が紅色に枝垂(しだ)れている。薄に添えれば、華やかな月見飾りになるだろう。
明朝に用意する花を咲兵衛が思案していると、秋草の匂う景色の中に若い侍が入ってきた。奥御殿の番士を務める佐倉兵馬(さくらへいま)だ。三年前に身重の妻が急死して以来、ちょくちょく咲兵衛の小屋にやって来ては、かめを相手に盃をあおっていた。だがこの一年ばかりは姿を見せなかった。しばらく見ぬ間に肩周りの肉が落ちて、顔色もくすんでいる。
「おはよう。ちょっと訊きたいことがあってね」
兵馬の声に振り向いたかめが、驚いたように目を瞠(みは)った。
「あら、佐倉様。お久しぶりでございます……でも、随分とお痩せになって」
兵馬は右手の指先で脇腹を軽く叩くと、咲兵衛の隣に腰を下ろした。
「ちょっと腹具合が悪くてね。時折ひどく痛む。いわゆる癪(しゃく)というやつだ」
「それは、お大事になさらないと。お白湯を持ってまいりますから、お待ちくださいな」
かめが小屋の中に姿を消すと、咲兵衛は兵馬に向き直った。
「医者には通っていらっしゃるのですか」
「麴町の岡本橘庵(きつあん)に診てもらっていたが、あまり芳(かんば)しくないのでやめた」
「あそこの御先代は評判がよろしかったが、養子に入った跡継ぎが今ひとつと聞いております。ほかの医者にも診ていただいたら如何ですか」
兵馬は曖昧に微笑んで、話題を変えた。
「ところで、花作りのおぬしなら詳しかろう。草餅に使う蓬(よもぎ)にも、花が咲くものかな」
「もちろん咲きます」
得意な話を振られて、咲兵衛は頰を緩めた。
「あれは若菜の時にみな摘んでしまうので人目には付きませんが、秋まで育てば身の丈ほどまでぼさぼさと伸びて、小豆(あずき)色の細かな花を付けます」
「ほう、ぼさぼさと伸びるか」
繁る蓬を思い浮かべたのか、兵馬は目を細めた。
「雑念多き心情を『蓬の心』というのは、秋まで育った伸び放題の蓬葉に喩えて言うのか。なるほど合点がいった」
「そんな喩えがあるんですか。こりゃ、一つ賢くなりました。蓬の花もそろそろ咲き出す季節ですから、野っ原に出た時に探しておきましょうか」
蓬葉を煎じて飲めば、腹痛にも効き目があるという。癪止めに用いるつもりだろうか。
「いや、それには及ばぬ。存じ寄りが、蓬には花が咲かぬと言い張るから、確かめてやろうと思ってね。咲くと知ったら、喜ぶだろう」
湯飲みを盆に載せて、かめが戻ってきた。兵馬に白湯を差し出すと、顔を覗き込んで遠慮がちに微笑みかける。
「しばらくお見えにならないので、心配しておりました。でも先達(せんだっ)て、佐倉様に良い御縁談が舞い込んだと小耳に挟んだものですから、ああ良かったって喜んでいたんですよ」
兵馬は白湯を一口すすると、花畑を眺めて溜息をついた。
「その縁談はお断りした。拙者も早く再婚して、跡継ぎを残さねばとは思う。だが、そのためだけに嫁を取る気にはもうなれない。心は別にあっても、家名存続のためには我が意を曲げて耐え忍ぶ。それが武家の習いと心得てはいるが」
兵馬は、脇腹を押さえて立ち上がった。
「馳走になった。約束があるから、もう行くよ」
「お加減が悪いのなら、御無理なさいますな」
気遣うかめに、兵馬は澄んだ笑みを返した。
「すぐそこの千駄ヶ谷観音に参詣するだけだよ。世話になったな。ありがとう」
歩み去る兵馬の姿が、紙切れのように薄っぺらく見えた。咲兵衛は築地塀の陰にほっそりした長身が消えるまで見届けてから、かめに目を向けた。
「佐倉様は、亡くなった御新造様を忘れられないのかな」
「そうでしょうか。私には、恋をしてらっしゃるように見えますけど」
「また、突拍子もないことを」
呆れ顔の咲兵衛を流し見て、かめは口を尖らせた。
「たった今、佐倉様御自身がおっしゃったではありませんか。心は別にあるから、惚れてもいない女子(おなご)を嫁に取りたくないって」
「そんなふうに言ったかな」
「私には、そう聞こえました。去年の話ですけど、こちらにお見えになると、色々なお菓子を購(あがな)った話ばかりなさるようになったんですよ。佐倉様御自身は甘い物がお嫌いと伺っていたので、『どなたかへの贈り物ですか』って訊いたら、ぽっと頰を染めて照れ笑って。あれは恋する男の顔です」
「そりゃ、おまえの勝手な思い込みだろうが」
「いいえ、女の勘働きに間違いはございません。そんなことがあってから間もなく、こちらにはお顔を見せなくなりました。きっと、花作りの女房よりも心許せるお方に巡り合ったんですよ。千駄ヶ谷でどなたかと会うお約束があるようですし、その方が忍ぶ恋のお相手かもしれませんねえ」
「侍が昼間っから外で逢い引きはねえだろう」
河童だの忍ぶ恋だの、かめの与太話はもういい。咲兵衛は道具箱から花鋏(はなばさみ)を取り出して、菊畝(うね)の間に屈み込んだ。余分な脇芽を摘み取り、害虫は指先で取り除く。黙々と仕事を進めるうちに、余計な話はすっかり忘れた。
秋の日が傾き、庭木の影が長く伸びていく。
咲兵衛が仕事道具を片付けていると、佐倉兵馬に仕える小者の杉蔵(すぎぞう)が花畑に姿を見せた。その名のとおり年輪を重ねた老杉のような男で、常に泰然として動じることがない。佐倉家には先代から奉公しており、兵馬にとっては親のように頼れる古参の家来だという。ゆったりと歩み来る姿には古武士の風格があり、武家の小間使いにしておくのが勿体(もつたい)なく思えた。
杉蔵は咲兵衛に会釈すると、低く通る声で話し掛けてきた。
「今朝方、こちらへ兵馬様がいらしたはずだが」
「はい。少しお話しをされた後、千駄ヶ谷観音へ参詣に行かれました」
「その後に何処かへ寄るとは、おっしゃっていなかったか」
咲兵衛が首を振ると、杉蔵は思案顔になった。
「月に二度ほど、千駄ヶ谷には御参詣になるのだが、いつもならお帰りになる時刻を過ぎても、今日はまだお戻りにならぬ。門限の暮六つにはまだ間があるから、今しばらく待ってはみるが……」
そう言い淀むと、滅多に感情を表さない杉蔵が眉間に不安を滲ませた。
屋敷内の侍長屋に戻っていく杉蔵の背に、今朝方の兵馬の後ろ姿が重なり消える。還暦過ぎの老人よりも、影が薄かったように思えた。
「かめ、ちょっと出掛けてくる」
咲兵衛は、土間で夕餉の支度をする女房に声を掛けた。
「佐倉様がお帰りにならないそうだ。今朝いらした時も顔色が良くなかったし、どうも胸騒ぎがする。千駄ヶ谷まで、ひとっ走り行ってくるよ」
目を丸くしたかめが、前掛けで手を拭きながら戸口まで出てきた。
「あら、やだ……お加減が悪くなって倒れたりしてなきゃいいけど。でも、おまえ様。日暮れまでに戻ってこられますか」
「行って帰ったところで一里もねえよ。心配するな」
「河童が出るから、川っ縁(ぺり)には近づかないでね」
いつもの一声を背に聞いて、四谷屋敷を出た咲兵衛は小走りに南へ向かった。片道半里足らずの道は、曲がっては折れて、田畑や足軽屋敷の土塀際を抜けていく。村落の先にある坂を駆け上がり、千駄ヶ谷観音聖輪寺(しょうりんじ)に着いた時には夕暮れ近くになっていた。
昼間は多くの参詣者で賑わう境内も静まり返って、かあと鳴く烏の声が杉木立から降ってくる。咲兵衛は人けのない境内を一巡りしてから、庫裏(くり)を訪ねた。出てきた寺男に急病の侍はいなかったかと訊いてみたが、知らぬと首を振る。
空が茜色に染まり、たなびく雲に藍の陰りが宿る。秋の日はつるべ落としという。そろそろ戻らないと、真っ暗になってしまう。
無駄骨を折ったかもしれない。まあ何事もなければ、それでいい。山門を出た咲兵衛は、汗を拭いながら坂を下りた。坂下に架かる橋まで来ると、小川から立ち上る冷気が火照った身体に心地よく染みる。ふうっと息をついて川下を眺めた、その時だ。
右手の岸辺に繁る薄の穂群が、ざわりと揺らいだ。
何かいるのかな――咲兵衛は橋を渡りきり、対岸沿いの道に足を向けた。川幅はさほど広くはないが、豊かな水流が怪しく揺れる穂群を隔てている。もし野犬が飛び出してきても、逃げる間はあるだろう。それでも念を入れて、斜め手前から様子を窺った。
夕日を背に何者かが立ち上がった。
咲兵衛は息を呑んだ。
朱に染まった華奢な裸体に、乱れてなびく髪。その頭上には丸い皿が見えた。片手に血の滴る短刀を握り、もう一方の手には得体の知れぬ肉塊をだらんと提げている。前髪の間から覗く鋭い眼差しが、川面を飛び越えて咲兵衛を射貫いた。
「か、河童」
腑抜けた声が漏れて、足腰が萎えた。咲兵衛は、よろけながら泳ぐように駆け出した。足取りに力が戻ると、無我夢中で巾着紐の寛永通宝を摑んだ。
二
お天道様が昇り切っても、夜具をつっかぶったまま起きようとしない咲兵衛に、土間からかめの声が掛かった。
「おまえ様。ゆうべ、夜露に当たって冷えたんじゃありませんか」
「ちょっと頭が重いだけだ。大事ねえよ」
「溜池(ためいけ)のお屋敷に、秋草を届けないといけないのに」
月見の宴は江戸城下の南、溜池の畔に建つ上屋敷で催される。今年は殿様が参勤で在府中のため、盛大に行われるという。勤めを怠るわけにはいかぬと、咲兵衛はのろのろと起き出した。
いつもなら朝飯前に一仕事こなすので、腹も程よく減る。だが今朝は、炊きたての飯と温かな味噌汁を前にしても、あれの姿がちらついて箸が進まない。かめはさっさと食べ終えて、外へと出ていく。どうやら侍長屋の様子を見に行ったらしい。すぐに暗い面持ちで戻ってきた。
「佐倉様は、まだお帰りにならないそうよ。門限破りどころか無断で他所(よそ)に泊まるなんて、お咎めが厳しくないといいけど」
「それなりの事情があればなあ」
「癪の発作で動けなくなったとか、河童に襲われたとか」
「そんなもん、いねえよっ」
思わず張り上げた声に、かめがびくっとのけぞる。気まずくなった咲兵衛は、薄と萩の花を入れた籠を背負い上げた。屋敷前の小路から大道に出れば、江戸城下に入る四谷見附はすぐそこだ。通い慣れた道だから、考え事をしながら歩いても迷いはしない。
かめの奴が、あんな話をするから幻を見たのだ。そうに違いないと、自分に言い聞かせては頷く。だが外堀に架かる見附橋に差し掛かった途端、あれの姿が鮮烈に蘇って血の気が引いた。咲兵衛は淀んだ堀水を横目に呟いた。
「堀にまで出るわけねえよ。しっかりしろ」
四谷見附から武家屋敷の間を南へ歩くと、程なく溜池の上屋敷だ。勝手門から中に入り、台所にいた茶坊主に秋草を手渡す。挨拶もそこそこに、咲兵衛は急ぎ足で引き返した。留守の間に、佐倉兵馬が戻っていればいいのだが……。奇妙なものを見たせいか、悪い予感ばかりが先に立つ。
花畑の小屋に帰ると、かめが真っ青な顔をして出迎えた。
「おまえ様、大変です。佐倉様が……お亡くなりになりました」
恐れていた知らせに、咲兵衛は返す言葉を失った。
「まだ詳しいことはわからないけど、さっき番頭(ばんがしら)様が徒士(かち)を率いてお出掛けになりました。御遺骸を引き取りに行かれたそうです」
「やっぱり、出先で具合が悪くなったのか」
「千駄ヶ谷に行くとおっしゃった時に、もっと強くお引き留めしておけばよかった」
片手を額に当てて、かめは溜息をついた。
「お通夜のお手伝いに行くにしても、御遺骸がお戻りにならないと何も始まりません。ぼんやり待っていても仕方ないから、いつもどおり働きましょうよ。気も紛れますから」
かめに促されて、咲兵衛は花畑の草むしりを始めた。だが昨晩の寝不足が祟ったのか、あくびが止まらない。強い眠気に、しゃがんでいるのも辛くなった。結局、仕事を早めに切り上げて、軒下の縁台に座り込んだ。傍らで、かめが鉈(なた)を振るって薪を割る。こん、こんと調子よく響く音が、子守歌のように聞こえた。
陽が落ちるのと入れ替わりに、満月がさやかに昇る。上屋敷では月見の宴もたけなわだろう。夕餉の後、咲兵衛は温めた茶碗酒を手に表に出た。縁台に腰を下ろして、ちびりと酒を含む。いつもどおりの十五夜なら、夫婦水入らずで月見酒と洒落込(しゃれこ)むはずだった。だが今年は、そうもいくまい。かめは、「侍長屋の方で、佐倉様のお帰りを待ちます」と言い残して、出ていったきりだ。
咲兵衛一人だけ、呑気に月見を楽しんでいるわけではない。昨夕から滅多に起きない出来事が重なって、一杯飲まずにはいられなかっただけだ。しかし川縁の怪異も、兵馬の死も、酒が五体に染みるように容易には受け入れられなかった。
四半刻ほどして、かめが帰ってきた。
「今しがた、番頭様たちが佐倉様の御遺骸を運んでこられました。でも、お通夜の手伝いは要らないそうです。何だか訳ありのようで、御葬儀も地味になさるんですって。後ほどお線香を上げに参りますと、杉蔵さんに伝えておきました」
「訳ありとは、どういうことだ」
「さあ」と、かめは首をかしげた。
慌ただしさが収まる頃合いを見計らって、咲兵衛夫婦は萩の花を抱えて弔問に赴いた。
江戸在府の家士たちが住まう侍長屋では、通夜の佐倉宅だけに明かりが灯っていた。声を潜めて訪(おとな)うと、応対に出た杉蔵が奥の間に通してくれた。ほのかに漂う線香の香りの中に、物言わぬ骸が横たわっている。杉蔵が遺骸の顔に掛けられた布をそっと外す。咲兵衛の後ろから、かめの嗚咽(おえつ)が漏れた。
兵馬の死顔は夢を楽しむように安らかだった。口元には微笑みさえ浮かべている。病苦の痕跡はない。いったい何があったのだろうか。
かめが涙ぐみながら、死者の枕頭に萩を活ける。咲兵衛は隣の間に端座する杉蔵に向き直ると、弔辞を述べてからおもむろに切り出した。
「千駄ヶ谷へお出掛けになると伺った時に、お加減が悪そうにお見受けいたしました。お引き留めすればよかったのですが、約束があるとおっしゃっていたので」
「寺近くに懐いている子どもがいるらしく、干菓子を土産に持っていかれた。昨日もお出掛けの時は、常と変わらぬ御様子に見えたが……」
朝になってから主人を捜しに出た杉蔵は、千駄ヶ谷観音坂下近くの川縁に烏が群がっているのを見たという。草を搔き分け近づいてみると、佐倉兵馬の変わり果てた姿があった。みぞおち辺りを深くえぐった傷があり、烏に腸を食い荒らされて酷(むご)たらしい有様だったらしい。
「腸を……」
思いも寄らぬ顚末(てんまつ)に、咲兵衛の背筋に戦慄が走る。兵馬の無残な死に様を思い浮かべたからではない。遺骸があったという川縁は、あれを見た場所の近くではないか。
目を閉じた杉蔵が、淡々と話を続けた。
「おそらく御切腹なされたのであろう。検分された番頭様も、そう断じられた。自害であるから事を荒立てぬようにと、村方とも話を付けた。あの辺りは寺領ゆえ、後ほどその寺にも、挨拶に伺わねばならぬ」
杉蔵は指先でそっと涙を拭った。
「近頃は癪の発作を起こされると、病で死ぬより、いっそ腹を切ってしまおうかとおっしゃるようになった。余程お辛かったのだろう。代われるものなら、この年寄りが癪の苦しみを引き受けて死にとうござった」
「まことに御自害なのですか」
咲兵衛は震え声で尋ねた。
「そう考えるしかない。ただ、お腹を召されるのに使ったであろう脇差しが、鞘(さや)ごと見当たらぬ。川に落ちたか、どさくさに紛れて誰かが持ち去ったか……だが、盗まれたという確たる証もない。他人(ひと)様の御領地に迷惑を掛けた上に、失せ物捜しまではできぬ」
「何かと争いになって、脇差しを奪われたとか」
杉蔵の目に怒りが浮かんだ。
「ひとたび争いとなれば、抜刀して渡り合うのが武士の心得。大刀は鞘に収まったまま御遺骸の下にあった。武士がむざむざと刀を奪われるなど不名誉の極みぞ。無礼を申すな」
「も、申し訳ございません」
あたふたと咲兵衛が頭を下げると、杉蔵もふうっと息をついて肩の力を抜く。
「いや、わしもつい声を荒らげてしまった。そなたが兵馬様を大切に思ってくれるのは承知している。実は、わしもすべてを得心したわけではない。だが、あれこれと詮索して、亡き主人に無用の恥をかかせたくない。どうか、このまま収めてほしい」
目を伏せた杉蔵に、咲兵衛はもう一つだけ確かめずにはいられなかった。
「佐倉様が亡くなられた所は、千駄ヶ谷観音の坂下にある橋の近くでしょうか。もし通りがかることがあったら、せめて冥福を祈りとう存じます」
「橋から右岸を三、四十歩川下に行った草むらだ。入る道はないから、対岸の通りから手を合わせるといい」
やはり、あれがいた所だ。兵馬の脇差しを奪って腹を裂き、腸を摑み出したに違いない。姿形といい、酷い所業といい、あれはまごう事なき「河童」なのだ。
佐倉様は河童に殺された――喉元まで出かかった言葉を、咲兵衛はぐっと呑み込んだ。
それが、たとえ突拍子もない事実であっても、今この場で言い出すのは憚(はばか)られる。杉蔵からも、このまま収めてくれと言われたばかりではないか。
小屋に帰る途中も帰り着いてからも、かめは何やら話し続けているが、まったく耳に入らない。もう寝ると言って、咲兵衛はさっさと夜具に潜り込んだ。
「おまえ様、具合が悪いんですか」
「……さっさと寝ちまいたいだけだよ」
目を閉じても、河童の鋭い眼差しが蘇る。咲兵衛は眠れぬまま朝を迎えた。
翌日の弔いは、控えめに行われた。佐倉兵馬は出先で癪の発作に見舞われて頓死、これ以上の詮議は無用と家中に言い渡された。佐倉家は跡継ぎなく断絶となった。
三
杉蔵が佐倉兵馬の遺灰を持って長屋を去ると、また平穏な日常が戻ってきた。兵馬の一件はこれにて落着――としていいのだろうか。咲兵衛は、喉に引っ掛かった塊を飲み下せずにいた。
咲兵衛は囲炉裏端で粥をすすりながら、戸外の花畑を眺めた。夜来から降り出した小雨に濡れて、菊の蕾がだいぶ膨らんでいる。今年は、うまい具合に重陽(ちょうよう)の節句の頃が花時になりそうだ。女房一人に仕事を任せて、いつまでも気鬱で伏せっている暇はない。
だが、いくら振り払っても、あの不気味な姿が蘇ってきて、その度に心の臓が跳ね上がる。杉蔵のように肝の据わった男になれなくても、せめて悠々と野原を歩ける元の自分には戻りたい。そのためには逃げずに闘うのだ。もちろん、武士の兵馬でさえ敵わなかった河童と、取っ組み合って勝つ自信はない。だが弱みの一つでも握っておけば、次に出くわしても逃げ切れるだろう。
咲兵衛は、桶に水を汲んで戻ってきた女房に声を掛けた。
「なあ、かめよ。河童ってえのは侍よりも強そうだが、どこか急所はあるのかい。たとえば頭の皿とか」
一瞬きょとんとしたかめは、くすっと笑った。
「おまえ様から河童の話をするなんて珍しいですね。河童は光る金物が嫌いですから、お侍が刀を抜いた途端に逃げてしまいますよ」
「ほう、刃物も苦手なのか。それならどうやって腸を取るんだろう」
「お尻の穴から手を入れて、ごぼっとつかみ出すそうですよ」
尻から腹の辺りにざわざわと寒気が走った。腰をさすった咲兵衛は、おやっと首をかしげた。あの河童、恐れるはずの刀を手にしていたではないか。
咲兵衛は、思い出すまいと押しやっていた河童の姿を瞼の裏に浮かべた。気が動転した上に西日が眩しくて、すぐに目をそらしてしまった。しかし、よくよく思い返してみると、姿形は人の子に近い。あの河童から血刀と肉塊を引いて、夕日の赤みを消してみれば、ありきたりの子どもになるのではないか。
そういえば、兵馬に懐いている子どもがいたと、杉蔵から聞いた。もし、その子だとしても、なぜ裸で草むらにいたのか。夏の盛りならまだしも、秋風の中を裸で出歩くのは合点がいかぬ。だいたい歴とした侍が、小童(こわっぱ)に殺(や)られるとは思えない。切腹で果てた後に、腸を抜き取ったのか。いったい、何のために。何もかもが、尋常な子どもの所業とは思えない。
「もしや河童は、子どもに化けるのか」
独りごちた言葉に、かめが振り向く。
「河童は、不幸な死に方をした子どもの生まれ変わりなんですって。だから、人の子に化けるのなんて、お茶の子さいさいですよ」
その言葉で、いったん遠ざけた河童の影が再び忍び寄ってくる。
河童が子どものふりをして兵馬に近づく。隙を狙って好物の腸を頂戴する――結局、河童の仕業でけりをつけたほうが、収まりがいいような気がしてきた。そう観念しかけて咲兵衛は、ちらりとかめを見た。いっその事、河童を見たと打ち明けてみようか。いや、やはりそれは出来ない。河童に怯える女房をたしなめていたのに、実はその女房よりも臆病な男だったなんて知られたら、亭主として立つ瀬がない。
額に手を当てて俯いた咲兵衛を、かめが心配そうに覗き込んだ。
「ねえ、お医者様に診てもらいなさいな。佐倉様から癪をうつされたのかもしれないし」
「癪はうつる病じゃなかろう。頭がこんぐらかるから、もう変なことは言わんでくれ」
「でも、一度診てもらってくださいませ。この年で寡婦(やもめ)になったら、誰も貰ってくれません。老い先もまだ長いのに一人きりで……」
「いきなりおれを死なせて話を進めるな」
声を荒らげた咲兵衛は、かめの陰った眼差しにたじろぐ。
「わかった。診てもらうから心配するな。近くだと、麴町の岡本橘庵先生かな。あまり評判は良くねえが、ちょいと診てもらうだけなら……」
「ああ、あそこはだめだめ」
かめが百足(むかで)でも見たように首を振る。先代より腕は劣ると聞いているが、代替わりの後には得てしてそんな噂が立つものだ。だが、かめが言いたいのは、そこではないらしい。
「見立てはともかく、人情のない医者にかかってほしくありませんよ」
「医者としての器量があるなら、それでも構わねえと思うが」
「薄情どころじゃない、ひどい話を聞いたんですよ」
かめは咲兵衛の隣にどんと腰を据えて、岡本橘庵宅の内輪話を語り出した。
子のいなかった岡本家の先代は養子夫婦を迎えて医業を継がせたが、晩年になってから召使い女との間に男子を儲けた。赤子だけを岡本家が引き取って、母親はよそに嫁がせたという。
「御隠居様としては、血を分けた我が子に跡を継がせたいと思うのが人情でしょう。でも、もうその時には、御養子の橘庵さんが跡を取って、子どもまでいたものだから、せっかく生まれた我が子を置く場所がなくて。せめて将来は医者にしてくれと頼んで、橘庵さんの末子として育てることになったんですって」
御隠居の実子は賢く育ち、橘庵の息子たちよりも出来が良かった。これは良い医師になるだろうと、御隠居は我が子の将来に期待しつつも、養子家族との確執を気に掛けていたらしい。
「去年の秋に御隠居様がお亡くなりになる時も、最後の最後まで息子を頼むと、橘庵さんに言い遺したそうです。なのに、結局追い出してしまったんですよ。ねえ、ひどい話でしょう」
「それだけ聞くと、恩ある養父の遺言に背いたように見えるが、ほかにも事情があるんだろう。誰が聞いても眉をひそめるような仕打ちをする裏には、それなりに訳があるはずだ。噂で人の良し悪しを決めるもんじゃねえよ」
かめはふんと鼻を鳴らす。
「噂じゃなくて、岡本家に奉公していた私の叔母から直に聞いたんです。叔母は御隠居様の味方をしていたせいで、坊やが追い出された時に一緒に暇を出されたんです」
「坊やってことは、まだ小さいのか」
「十かそこらですよ。御隠居様がお灸を据えたら子どもができたから、艾(もぐさ)にちなんだ名前を付けたとか。ええと、もすけじゃなくて……そうそう、蓬だわ」
灸に使う艾は、夏まで育った蓬の葉を陰干しにして、石臼で挽いて作る。草餅や艾、煎じて飲んでも薬効のある蓬葉は、花を咲かせる前にほとんど摘み取られてしまう。蓬にも花が咲くのか――兵馬と最後に交わしたやり取りを、咲兵衛はふと思い出した。
小さく溜息をついた咲兵衛を他所に、かめの話は先へ進んでいく。
「蓬に助けられて生まれた子だから蓬助(ほうすけ)って名付けたんですって。お医者になったら蓬庵(ほうあん)と名乗れって、御隠居様が言い遺したそうですよ。だのに、橘庵さんの子どもらが『花も咲かない蓬の子、さっさと枯れてしまえ』って、いじめたとか。そりゃ橘よりは地味ですけど、ちゃんと咲きますよね。私が蓬助ちゃんに会えたら、そう教えてあげるのに。花が咲くと知ったら、きっと喜びますよ」
咲兵衛の中で、かちんと何かが嚙み合った。
「咲くと知ったら喜ぶ……か」
佐倉兵馬が、あの朝に言った言葉だ。存じ寄りが蓬には花が咲かぬと言い張るが、咲くと知ったら喜ぶ、と。あの時は、そんなつまらない話で喜ぶものなのかと奇妙に思った。だが、もし兵馬の言う「存じ寄り」が蓬助だとしたら、筋が通るのではないか。
「その蓬助という子は、どこにやられたんだ。まさか、千駄ヶ谷村じゃねえよな」
「もうちょっと遠くですよ。たしか渋谷の手前の穏田(おんでん)村のほうに」
穏田村は、河童を見た小川の川下にある。千駄ヶ谷から半里先だから、子どもでも歩いてこられるだろう。蓬助と兵馬の繫がりは、医家の息子とそこの患者というだけだ。だが蓬の話を加えてみると、何らかの付き合いがあったように思えてくる。
あの物の怪の正体が蓬助だったら、とりあえず河童の呪縛からは解き放たれる。そこで咲兵衛は一計を案じた。
「その子がどこに住まっているのか詳しく訊いてきてくれないか。おれがひとっ走り行って、蓬にもちゃんと花が咲くと教えてやるよ。聞いてみりゃ可哀想な子じゃねえか。少しでも喜ばせてやりてえし」
「あら、そうしてくださいな。私もその蓬の話でやきもきしてたんですよ」
かめの笑顔に後ろめたさを感じながら、咲兵衛は話を進める。
「それからな、佐倉様も橘庵先生にかかってたんだが……」
「あらま、そうなんですか。ほかの医者に行けばいいものを」
かめがまた一くさり、橘庵の悪口を並べるのを辛抱強く聞いてから、咲兵衛は口を挟む。
「まあそれはともかく、佐倉様と蓬助って子が顔見知りだったかどうか、叔母さんに訊いてみてくれないか。佐倉様が最後に来た時、蓬にも花が咲くのかって訊かれたんだよ。蓬の花なんてめったに話題にならねえのに、近いところで二回も聞くなんて妙だろう。二人が知り合いで、蓬助がいじめられた話を打ち明けたとしたら、合点がいく」
かめは頷いた後で、首をかしげた。
「もし知り合いなら、千駄ヶ谷観音で会う約束をしていたのは、その子でしょうか。子どもと会った後に、切腹なさったと……何だか変な話ですね」
「まだ知り合いと決まったわけじゃねえよ。おれが気になるだけだから、ちょっと確かめてくれるだけでいい。ただ、こちらから佐倉様の名前は出すな」
「御家の内輪事は漏らしません。そのくらいは弁(わきま)えております」
今さら騒ぎ立てたくはないが、あれこれ考え込むよりも、糸口があるなら辿ったほうがいい。そうでもしなければ、身も心も疲れ果てて、本当に癪を病みそうだった。