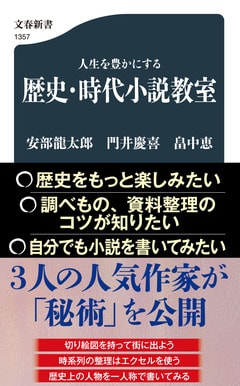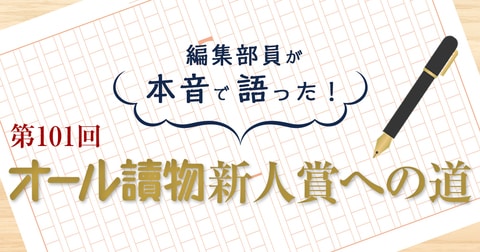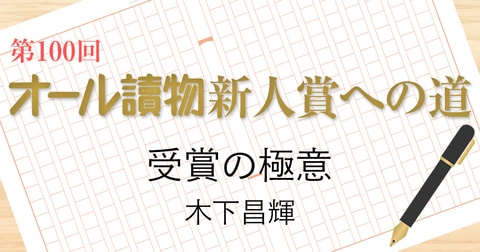「全編にわたって楽しい」(有栖川有栖)、「無条件に楽しんで読むことが出来た。ああ、面白かった」(乃南アサ)など、その独特なユーモアセンスと確かな筆致で第99回オール讀物新人賞を射止めた由原かのんさんのデビュー単行本『首ざむらい 世にも快奇な江戸物語』がいよいよ発売になりました。
収録作4篇から、「ねこまた」を一話分すべて公開します。
荒物屋の用心棒に雇われた浪人・猫矢又四郎が出会ったのは、“ねこまた”に憑かれた娘で……。
どうぞ、お仕事や勉強を終えた一日の終わり、頭を空っぽにして物語の世界を楽しんでください。

一
江戸城虎ノ門から、相州平塚に向かう道を中原街道という。東海道の脇往還として便も良く、行き交う旅人や荷駄が引きも切らない。道沿いには武家屋敷や寺社が並び、芝増上寺(しばぞうじようじ)の西にある赤羽橋の辺りまで、江戸城下からこぼれ出た屋並みが続いている。
赤羽橋手前の町並みは代官支配の村落になるが、誰言うとなく飯倉(いいぐら)町と称している。町の中心にある四ツ辻は殊の外賑やかで、数人の棒手振(ぼてふり)が腰を下ろして客を引いていた。
その四ツ辻に、一人の男がやって来た。身の丈が六尺近くある武士で、笠の陰から無精髭が見える。主持(しゅうもち)の侍というよりは、無頼の武芸者のようだ。大男は初夏の日差しに目を細め、四ツ辻をぐるりと見回した。南北に延びる街道は前も後ろも下り坂だが、東西に横切る道は両側とも上り坂になっている。この辻は坂の天辺なのか、谷底なのか。
「ちと、お尋ね申す」
大男は、道端の棒手振に声を掛けた。売り物の大根を手にした棒手振が、ぎょっと身を引く。
「驚かせてしまったのなら、申し訳ない。四方八方、坂ばかりで迷っております。土器(かわらけ)坂とは、どの坂でしょうか」
強面(こわもて)の偉丈夫には似合わぬ優しい声音に、棒手振の頰が緩んだ。
「あっちの長い下り坂が土器坂でござんす」
棒手振が南に下る坂道を指差すのを見て、大男は頷きながら問い重ねた。
「伊文字屋(いもじや)という荒物屋を探しているのだが」
「その店なら、ちょっと下った左手にござんす」
大男は丁重に礼を述べると、土器坂を下っていった。
坂道の両側には、商家や仕舞屋(しもたや)が軒を連ねている。坂の名のとおり土器職人の家が多く、半裸の男が土間で轆轤(ろくろ)を回す姿が見えた。ほどなく、軒下に竹箒(たけぼうき)や手桶を並べた店が目に入った。看板は掛かっていないが、店先に溢れた日用の品々が荒物屋の目印になっている。旅人らしき客が足をとめて、軒から下がった笠と草鞋の束を手に取った。「いらっしゃい」と、店から小僧が出てくる。
「じょうせんも如何ですか」
良く通る小僧の声が耳に飛び込んできた。旅人が覗き込んだ先に、大男も釣られて目を向けた。重ねた笊(ざる)の横に、小さく折った竹皮包みが盆に載っていた。
「これが売り切れたら、もう秋まで作りません。暑くなると飴が溶けちゃうんで」
これで売り切りという言葉が効いたのか、旅人が飴に手を伸ばした。
地黄煎(じおうせん)――薬草入りの固飴だ。ねっとりとした甘味が口中に蘇って、大男は舌舐めずりした。先の客を送り出した小僧が振り向いた。
「いらっしゃい。お客さんも、お一つ如何ですか」
「いや、拙者は客ではない」
大男は笠を取って、小僧を見下ろした。
「こちらが伊文字屋さんとお見受けしたが、御主人はおられるか」
間口三間の店には、様々な道具がせめぎ合っていた。天井から吊り下がった鈴生りの小籠を潜って、大男はぐるりと店内を見回した。右手の板の間に、値の張りそうな鉄瓶が並んでいる。その向こうに帳場があって、主人と覚しき中年男が顔を上げた。大男は会釈しながら、帳場に歩み寄った。
「玉木屋さんから口を利いてもらった猫矢又四郎(ねこやまたしろう)と申します」
主人は、恵比寿顔に微笑んで頷いて見せた。
「猫又さんですね。ああ、失礼。猫矢さんでしたね」
閉じた帳簿を壁際の簞笥にしまいながら、主人は苦笑した。
「このところ猫又が気に掛かって、頭がそれで一杯になってましてね」
「ほう。この辺りには猫又がいるのですか」
年古る猫は、尾の先が裂けて化け猫になるという。そうなると、飼い主を嚙み殺す悪さも働くと聞く。だが、そう聞くだけで、大抵の者は目にしたことはない。それでも世間の多くは猫又の存在を信じて恐れている。武芸者たる者は狐狸の類いに怯えてはならぬと、又四郎は常々自戒していた。その一方で、猫又には親しみがある。是非一度会ってみたいとさえ思っていた。
主人は溜息交じりに首を振った。
「いいえ、これからそうなるかもしれないという話です。それはともかく仕事の話をいたしたく存じます。ここでは話しづらいので、いったん表に出て、横の路地を入って」と、主人は帳場の後ろにある障子窓の辺りを人差し指でちょいちょいと差す。「すぐ左手に裏口がありますから、中に入ってお待ちください」
又四郎は頷いて、店を出た。店先に立った老婆が「水飴をちょうだい」と持参の器を小僧に手渡した。小僧が固飴の後ろにある小桶の蓋を開けて、琥珀色の水飴に箸を刺す。この荒物屋では飴も商うのかと、又四郎は首をかしげた。
店の横にある木戸口から、人一人が通れるほどの細い路地が奥に伸びている。路地に入ってすぐに、教えられた裏口があった。引戸を開けて中に入ると、そこは三和土(たたき)の左側に一畳ばかりの板の間を設けた一間四方の小部屋だった。
やがて襖が開いて、狭い板の間に主人が入ってきた。襖の向こうに、先ほど主人が座っていた帳場が見えた。
「伊文字屋庄吉(しょうきち)と申します」と、主人は板の間に腰を下ろすと頭を下げた。「玉木屋さんとは遠縁でしてね。どちらも祖父が小田原の出でございます。あちらは北条家の侍でしたが、御家が潰れた後に江戸に出て材木屋になられました。手前どもは小田原城下で鋳物師(いもじ)を家業にしておりましたが、私の父の代に、ここに店を構えたんです。ですから、今でも金物は良い物を揃えておりますよ」
「それで屋号が伊文字屋というのですか」
「はい。ここから東へ行った芝増上寺の近くにも出店(でだな)がございまして、そちらは倅夫婦に任せております」
「手広く商いをされているのですね」
「ええまあ」庄吉が照れ笑う。「実はこの裏口で、質屋もやっておりましてね。質屋と申しましても、近隣の顔見知りにだけ金子(きんす)を用立てております。ただ、街道沿いですから、時折一見(いちげん)の客が参ります。身元の定かでない客は断っているのですが、金を出せと居座る輩もおりまして」
「それで、『防ぎ』が要るというわけですね」
「早い話、そういうことです。とにかく、街道沿いっていうのは物騒でしてね。戸締まりを固くしても、いつ何が起こっても不思議じゃない。腕の立つ御方がいれば安心です」
腕が立つ御方と言われて悪い気はしない。しかし又四郎は商家の警固という仕事に喜んで飛びついたわけではなかった。出来れば武家勤めがしたいのだが、「訳あり」の身の上では無理だろうと諦めていた。ただ、ここに長居をするつもりもない。とりあえず食い扶持を稼ぎながら、次の道を考えようと思っていた。その腹積もりを隠して、又四郎はにこやかに頷いた。
「事情は承知いたしました。拙者で役に立つのなら、尽力いたしましょう」
「是非、宜しくお願いします」
伊文字屋庄吉は微笑むと、急に声を潜めた。
「玉木屋さんから伺ったんですが、猫矢さんの御先祖は猫又退治をなさったそうですね」
「まあ、そういう言い伝えはあるが」
遠い先祖の話だから、真偽のほどは図りがたい。だが、今は亡き母から繰り返し聞かされたものだ。そんな勇敢な御先祖の血を引いたのだから、おまえも胸を張って生きるのですよ――母はいつもそう締め括った。
「もし猫又が現れたら、どうか退治してくださいませ」
「何と、この家に出るのか」
又四郎は思わず身構えた。同時に、期待に胸を躍らせた。先祖が退治したという猫又が如何なる面構(つらがま)えか、子どもの頃からずっと気になっていたのだ。
庄吉の目には怯えが浮かんでいた。
「いえ、まだ出ないと思います。そう思いたいのですが、万が一今夜にでも出たら、何卒お力添えをお願いいたします。事情は、追々お話ししますので」
庄吉は追々話すと言ったが、猫又の話はそれきりになった。どうやら伊文字屋の家族に絡んだ込み入った事情があるらしい。主人が口を開く前に、雇われ者のこちらから尋ねるのは無礼だろうと、又四郎は訊きたい気持ちをぐっと堪えた。
街道沿いに建つ町家は、間口のわりには奥行きが深い。荒物屋を兼ねた伊文字屋の細長い住まいは二階建てで、裏手には二間四方の土蔵があった。そのまた裏に三軒入った割長屋が続き、奥は武家屋敷の土塀で行き止まりになっている。
又四郎は、長屋の一隅に居を構えた。店賃(たなちん)は免除された上に、家財道具一切は質流れ品を宛がわれた。「防ぎ」の仕事は、暮れ六つに路地木戸に錠を掛け、裏口の板の間で寝不番(ねずばん)を務めた後、明け六つに木戸を開ける。人の動き始めた夜明けの街道に背を向けて、長屋に戻ると冷えた褥(しとね)に潜り込む。
そのまま晩まで寝ていればいいのかと思いきや、伊文字屋庄吉は無駄なく人を使う。又四郎は午刻(ひるどき)近くには起き出して、路地周りの掃除や小用の使いもこなした。細々とこき使われるわりには、給金は雀の涙だった。下女の稼ぎよりも少ないほどだ。
「朝晩の飯と汁物は、うちから出しますよ。一人前の飯を炊(かし)ぐのに薪を使うのは勿体ない」と、庄吉は言ってくれた。店賃と食い扶持が不要なら、これで充分だと又四郎は思い直した。掃除や使いっ走りの雑用には慣れている。今までの暮らしよりもずっと気楽に過ごせる毎日が、何よりも有難かった。
長屋には、又四郎を入れて三所帯が住まっている。隣は大工の夫婦と乳飲み子、その向こうが飴売りの家族で、舅と嫁、子どもが一人の三人家族だった。荒物屋にいた小僧は、この飴屋一家の息子だという。
「伊文字屋さんは今は随分と善人になりなさったけど、昔はひどく阿漕(あこぎ)だったんだよ」
大工の女房が、漬け物のお裾分けを持ってきたついでに話してくれた。
「五年前に娘さんが拐(かどわ)かしに遭ってね。金の貸し借りで恨んでいた男が掠(さら)ったんだよ。娘さんは無事に帰ってきたけど、傷物になったと悪い噂が立って、決まっていた縁談が壊れちゃってさ。同じ年に女将さんにも死なれて、あの年は伊文字屋さんには災難続きだったね」
その頃から、伊文字屋庄吉は人が変わったという。
「隣の飴屋さんの御亭主が急な病で亡くなった時、それまでの伊文字屋さんなら、店賃を取りっぱぐれるからって追ん出したんだろうけどさ。長男坊を上方の飴屋に修業に出してやって、小さい子に棒手振は辛かろうって、次男坊を荒物屋の小僧にしてやったんだよ。荒物屋の仕事をしながら、店先で爺さんの練った飴も売ればいいってね」
「なるほど。そういう訳で、荒物屋に飴があるのか」
「寡婦(やもめ)になった女将さんも女手一つで舅と子どもを養うのは大変だろうって、伊文字屋さんの奥で働かせてもらってるよ。あんなに因業(いんごう)親父だったのに、人っていうのは変わるもんだねえ。だけど、娘のお清(きよ)さんとは折り合いが悪いみたいだよ」
伊文字屋の娘お清は、今年で二十一になるが、「悪い噂」のせいで未だ嫁がずにいるという。二十一といえば、又四郎より五つ下だ。そんな年頃の娘がここにいるのかと、同じ独り身の又四郎は興味を覚えた。
二
又四郎の「防ぎ」らしい仕事は、今のところは不寝番だけだった。その他はほとんど小間使いと変わらぬ扱いだったが、気楽な暮らしではあった。長屋の住人は親切だし、取り立てて不平もない。それでも何か物足りなさがある。
その物足りなさの正体を考えながら路地の掃除をしていると、荒物屋の二階窓がことりと音を立てた。又四郎が見上げると、黒猫を抱いた娘が窓辺に立っている。長い髪を束ねもせず、虚ろな眼差しで遠くを見た娘は、ふと路地の又四郎に視線を落とす。二人の目が合った瞬間、娘の顔に怯えが走り、ぴしゃりと障子を閉めた。乱れ髪のせいで狂女のように見えたが、身なりを整えれば器量好しの娘ではないか。
井戸端で洗濯をしていた大工の女房が、二階の窓と又四郎を交互に見た。よいしょと立ち上がると、背中の赤子をあやしながら又四郎に近づいてきた。
「今のが、お清さんだよ。猫を抱いていただろう。あの雄猫は十年ばかり生きてるから、そろそろ猫又になるんじゃないかって噂でね。長い尻尾を切ると化けないらしいけど、お清さんが可愛がっているから旦那さんも手を出せないんだって」
伊文字屋の主人が恐れている猫又とは、あの猫か――又四郎は、ようやく得心した。
「驚かせてしまったようだな」
伸びた月代(さかやき)と髭を撫でながら又四郎が苦笑すると、大工の女房はくすりと笑った。
「猫矢さんだけじゃなくて、お清さんは男が苦手なんだよ。いつ襲われるかしれないからって、未だに表にも出られない。猫だけを話し相手に、ずっと閉じ籠もったまんま。拐かしの下手人が逃げちまって、それきりだから、きっと不安なんだろう。夜もよく眠れないって言うから、伊文字屋さんが心配して、それなら防ぎを雇おうってことになってね」
「ほう。拙者が雇われたのは、質屋の押し借りを追い払うためだけではなかったのか」
「それもあるだろうけど、お清さんを安心させるためでもあるんだよ」
「そうか。猫又の話はちらっと聞いたが、伊文字屋さんの歯切れが悪かったのは娘御の恥を晒したくなかったからか。確かに、ここへ来たばかりの男に打ち明ける話ではないな」
伊文字屋の内輪に立ち入りすぎたと思ったのか、話し好きの女房は話題を変えた。
「そういえば、猫矢さんが来る前にここにいた御浪人は急に出家するって言い出して、旅に出ちゃってね。ねえ猫矢さん、狸穴(まみあな)って知ってるかい」
「いや、存ぜぬ」
「土器坂の向こうに、もう一つ南に下る坂があるんだけど、その坂の途中に洞穴(ほらあな)が口を開けてるんだよ。狸の巣じゃないかって言われてるけど、ちょっと大きいんだってさ。先月、公方(くぼう)様が使いを寄越して中を調べさせてから、見物に来る者が増えてね」
徳川将軍家も三代目になって、江戸の町も年々広がっていった。中原街道を外れると、雑木林で鬱蒼(うっそう)としていた麻布の辺りも、土地を拓いて武家屋敷が建ち並んだ。山の斜面を覆っていた木々も伐られて、地元の者しか知らなかった奇妙な穴が露わになった。得体の知れない穴の話は将軍の耳にも届いたらしい。又四郎の前に防ぎを務めていた浪人も、その穴を見物に出掛けたという。
「帰ってきたら、お地蔵さんみたいに悟りきった顔になっちゃってさ。しょぎょーむじょーとか何とか、ぶつぶつ呟いて。ちょっとあれは、気味が悪かったねえ。ああいう所には、遊び半分に近寄らないほうがいいよ」
そう言われると見たくなるのが人情だが、その前に又四郎は行きたい所があった。
「赤羽橋の辺りに出床(でどこ)はあるかな」
橋の袂には、たいてい床屋が小屋を構えているものだ。
「あるよ。四ツ辻にもあるけど、橋の方が腕がいいらしい。まさか猫矢さんまで、坊主になるつもりじゃないだろうね」
そう言うと、女房はけらけらと笑った。背中の赤子がぐずりだす。又四郎があやしてやろうと覗き込むと、赤子は仰け反って泣き声を張り上げた。
「ちょっと出掛けてきます」
「ああ、行っておいでよ。今日はうちの亭主が休んでるからさ、伊文字屋さんで何かあったら代わりに飛び出すよ。酒にゃ弱いけど、腕っ節だけは強いからさ」
女の笑い声と赤子の泣き声が狭い路地に弾けた。又四郎は箒を片付けて、店の裏口に入った。襖を細く開けて、帳場の庄吉に半刻ばかり他出すると断りを入れる。
「念のために木戸を閉めておいてください」と庄吉の声が返った。
木戸口から路地の奥を振り返ると、大工の夫婦が二人して赤子をあやしていた。赤子は父親の顔を見て機嫌を直したらしい。その笑みに亭主が目を細め、女房が柔らかに微笑む。寄り添って立つ親子の姿を目の隅に残して、又四郎は木戸を閉めた。大工夫婦は長らく子宝に恵まれなかったが、今年ようやく男の子を授かったという。端から見ても幸せそうだった。
それに引き替え、独り身とは悲しいものだな――と、又四郎は空しさを吞み込んだ。同時に口寂しい思いに捕らわれる。気分を変える甘いものはないのかと、荒物屋の店先に目をやった。初めてここへ来た時に見た固飴はなくなっていた。売り切れたのかと、溜息が出る。
土器坂を下りていくと、先を行く遊行僧の後ろ姿が見えた。がっしりとした背中と、やや右足を引き摺る歩き方に覚えがある。どこで見た坊主だろう。はっきりと思い出せないが、その坊主のいる風景がどこか懐かしい。
坊主の知り合いなどいただろうか。又四郎は記憶を辿って、やっと思い当たった。たしか「兎心坊(としんぼう)」といった。数年前、兵法の師匠と常陸の鹿島大明神に詣でた際に、少しの間道連れになった遊行僧だ。荒れた堂宇で野宿をした夜、夜具代わりの蓑をそっと掛け直してくれた。そんな親切に不慣れな又四郎は寝たふりをしていた。その翌日の別れ際に、餞別と称して甘い干し柿を二つくれた。風花の舞う中で見送った後ろ姿が、目の前の景色と重なって消えた。
声を掛けようと、又四郎は足を速めた。だが先に坂を下り切った坊主は、赤羽橋の手前を右に折れていった。又四郎が橋際に来た時には、もう姿が見えなかった。
三
「えっ、猫矢さんなんですか。見違えちゃった」
奥の通り土間から裏口に出てきた荒物屋の小僧が、目を丸くして笑った。灯火を半身に受けながら、又四郎は剃り立ての月代と口周りをつるんと撫でた。
「些かむさ苦しいと思ってね。だが、肌寒くてかなわぬ」
「髭がないほうが優しそうに見えます」
「今日は随分と遅いんだな」
いつもなら又四郎が不寝番に来る頃には、小僧はとっくに長屋に帰っている。
「旦那様に算盤を教えてもらってました。兄ちゃんが修業から帰ってきたら、二人で働いて、いつか表店に飴屋を出したいんです。そしたら、帳面もつけなきゃならないでしょ」
「ああ、そうか。遠くに離れていても、兄弟揃って同じ夢を見て修業してるのだな」
小僧は笑って頷くと、袂を探って竹皮包みを取り出した。
「これ、一つだけ取っておいたから、召し上がってください」
なんと、一度は諦めた固飴が目の前に差し出されたではないか。飴にありつけた喜びもさることながら小僧の気遣いが嬉しかった。
「これは、かたじけない。しかし、いいのか。地黄を入れるから、元手も掛かるだろう」
「薬草は入ってません。爺ちゃんの話だと、昔は入れたけど、これは甘いだけだって。あ、嚙んだら駄目。ぺったりくっついて、口が開かなくなるから」
小僧は飴を手渡すと、「おやすみなさい」と会釈して、外に出ていった。
小半時後、伊文字屋庄吉が「御苦労様です。今夜も宜しくお願いします」と晩の挨拶に来た。短夜の季節になって、皆揃って早く寝る。人の気配が消えて、又四郎は明かり一つ灯る小部屋で一人きりになった。
飴を手のひらに載せたまま、しばらく眺めて楽しんだ。飴屋の家族は、働き手に先立たれても支え合って生きている。楽な暮らしではなくても、あの小僧の目は光に溢れていた。
「おれは家族には縁がないな。そんなものがなくても、生きていけるが」
独りごちながら竹皮を開く。一文銭ほどの平たい飴は湿気て、竹皮を膠付(にかわづ)けしたように貼り付いている。何とか剝がし取ったが、所々に皮が残ってしまった。まあ毒にはなるまいと、琥珀の塊を口に含む。
上顎と舌の間で飴がねっとりと溶けて、又四郎は甘みに酔いしれた。夜が更けていく。時折、犬の遠吠えが聞こえるほかは静かな晩だった。
がりっと、又四郎の背後で音が立った。振り向くと帳場を隔てる襖が五寸ばかり開いて、ぬるりと黒い生き物が滑り込んできた。灯火の光を宿した眼が、じっと又四郎を見上げた。
「何だ、猫又さんか」
お清が抱いていた黒猫だ。猫は長い尻尾を立てて、小さく「なっ」と鳴いた。漆黒の猫と思ったが、よく見ると尻尾の先だけ下ろし立ての筆のように白い。猫は又四郎の足先に鼻を寄せた。しばらく匂いを嗅いでいたが、やがて半眼になり、口を半開きにして恍惚とした顔になった。
「臭いますか」
猫は丸い目で又四郎を見つめた。物言いたげだが、もちろん猫の心の内まではわからない。
「おれには懐かぬほうがよいぞ。我が猫矢家の由緒を話して聞かせよう」
鎌倉将軍の頃というから、とんでもなく昔の話だ。ある時、又四郎の先祖は、鎌倉へ向かう主人の供をして杣道(そまみち)に入った。そこへ得体の知れぬ怪物が躍り出た。それが猫又であったという。先祖は弓の名人で、猫又を見事に射殺(いころ)した。それ以来、武勇を末永く子孫に伝えるために猫矢と名乗るようになったのだ。
「だがおれには、その猫又と猫がどうしても結び付かぬのだ。山中の怪物と言うなら、虎のようにでかいのではないか。おまえみたいに小さい奴が、凶暴な怪物になれるのか」
「うわおん」と、猫は低い声で答えた。
「そうか、おまえにも言い分がありそうだな。もし、おまえが猫又というものになるのなら、猫矢の名にかけて、おれが退治してやるぞ。ほれ、怖いか」
顎下を撫でてやると、黒猫はごろごろと喉を鳴らした。怖がるどころか、前足を又四郎の膝に掛けてよじ上ると、ころんと胡座(あぐら)の中に収まった。
「そうか。怖くないか。確かに先祖は立派だったが、おれの親父はろくでなしだったからな」
又四郎が生まれて間もなく、父はにわかに乱心して無二の親友だった男を斬り殺し、そのまま行方知れずになったという。その後、母は又四郎を連れて実家に戻った。実家は徳川の御家人で、母の弟が跡を取っていた。母は肩身の狭い思いに耐えて又四郎を七歳まで育てると、この世を去った。母を失った悲しみも癒えないうちに、又四郎も兵法家の内弟子になるために家から出された。武芸の道を極めて独り立ちせよと叔父は言ったが、体よく厄介払いされたのだ。
「師匠も流派を立てて弟子を増やせば、おれも一番弟子として食うには困らなかったろうに。何しろ変わり者で、勝手気儘な生き方を全うしたよ」
その師匠も昨年亡くした。行く当てもないので、また母の実家に転がり込んだ。叔父は一人娘に婿養子を取っていた。それが玉木屋の倅だ。かなり持参金を弾んだと聞く。商家に生まれても武家の婿養子になる者もいれば、武家に生まれても根無し草となる者もいる。
「運不運とは、あるものだな」
ぽつねんと座っていると、余計な思いに捕らわれてしまう。顔も知らぬ父親は、今も何処かで生きているのだろうか。
「乱心して、母を不幸にした男を父と慕う気はないさ。だが、ちょっと顔を見てやりたい、それだけだ」
闇を見つめていた又四郎は、ふと左手の板戸に目をやった。戸を隔てた通り土間から人の動く気配が伝わってくる。「かちん、何処にいるの」と、女の声が聞こえた。黒猫の耳が動くと、にゃんと虚空に鳴き声を放った。
「おまえ、かちんっていうのか」
「なっ」と、猫が頷くように見えた。鳴き声が届いたのか、人の気配が近づいた。板戸の向こうに立ちどまったのは、おそらくお清だろう。戸を開けるのを躊躇(ためら)っているようだ。
「猫殿なら、ここにおりますよ」
又四郎が努めて柔らかい声を掛けると、一呼吸置いて板戸ががたりと動いた。隙間から女の憂い顔が覗く。その目が又四郎の顔を捉えて「あっ」と声を上げると、膝に乗った猫に気付いてまた「あっ」と眼を見開いた。
又四郎の目は、娘の驚いた顔に吸い寄せられた。その瞬間だけ、気力の失せた面差しに本来の若さが蘇るように見えた。
「御主人様が捜しに来たぞ。さあ、行け」
又四郎が猫を膝から下ろそうとしても、かちんは爪を立てて袴にしがみついている。
「こんばんは……あの」と、お清はまじまじと又四郎を見つめた。「昼間、路地にいらした方ですか」
「はい。あの時は驚かせてしまって申し訳ない。むさ苦しい髭は剃ってまいりました」
「お髭を剃るだけで随分と人変わりするものですね」
お清の視線がこそばゆくなった又四郎は軽く咳払いをした。
「御挨拶がまだでしたな。拙者は……」
「存じております。父が雇った猫矢様でしょう。玉木屋さんの御親戚の」
「親戚か。拙者の母の実家に玉木屋の倅が婿養子に入ったから、そうなりますな」
お清の視線は黒猫に注がれている。猫は又四郎の顔を見上げると、お清に目を転じて「あむあむ」と意味ありげに鳴く。
突然、お清が小さく頷いた。ちらりと通り土間を振り返ると、敷居をまたいで小部屋に入ってきた。音を立てないように戸を閉めて、手にした手燭を又四郎の膝元に置く。明かりが二つになって、闇が薄らぐ。
お清が三和土に屈み込んで、又四郎を見上げた。切れ長の瞳にきらりと光が宿る。
「さっき、かちんと話していたんです。『どうしたら、おまえを守れるだろう』って。その後、私がうとうとした隙に姿が見えなくなってしまって。捜しに来たら、男嫌いのかちんが猫矢様のお膝に乗ってるんですもの。きっとかちんが、猫矢様を頼れって言うんです。そうよね、かちん」
又四郎の膝の内で、ごろんと仰向けになった猫が「なん」と一声返した。
この娘は猫と話せるのか。又四郎は、娘と猫を交互に見やった。板の間の縁に両手を乗せて、こちらを見上げる娘の顔が猫に似ている。もしかしたら、この黒猫は既に猫又の妖気を宿していて、娘を虜(とりこ)にしているのではないか。いやいや、そんなはずはない。
「すまぬが」又四郎は声の震えを抑えた。「おっしゃる意味がわかりません」
「あら、御免なさい。そうですよね。いきなり手前勝手に話を切り出しても、御理解を頂けるはずがありません。順序立てて、お話しいたします」
お清の目が黒猫に移り、悲しげに陰った。
「この子は、私が子ども時分に狸穴で拾ったんです。あの穴は近寄ったらいけないとは言われておりましたが、子どもが肝試しによく潜り込んでおりました。でも穴に入ると真っ暗で、急に親が恋しくなるから、どの子もすぐに家に帰ったものです。あの時もちょっと遊びに行ったら、この子が穴から出てきて、可愛かったからそのまま連れて帰りました。父は『狸穴にいた黒猫なんか気味が悪いから捨ててこい』って不機嫌になって。母が取りなして飼うのを許してはくれましたけど、父は端っからかちんが嫌いなんです」
筋道を立てて話すお清に、狂気は感じられなかった。それにしても狸穴の話を聞くのは、今日二度目だ。噂の狸穴とは、いったいどんな穴なのだろう。
「狸穴というのは、左様に気味の悪い所なのですか」
「いろいろ噂はございます。中に狸御殿があると言われてますけど、そんなに深い穴ではございません。だけど父は、あの穴には魔物が棲んでいると思い込んでいて、魔物の巣から出てきた猫が年を取ったから、きっと猫又になるって言うんです。そんなことはないって言っても、聞く耳持たずで。あの手この手を使って、かちんを私から引き離そうといたします。今朝も『捨てなくてもいいから、せめて尻尾を短く切らせておくれ』なんて言い出して。尻尾を切ったら死んじゃうかもしれないでしょ。おとっつぁんは、内心それを望んでいるのよっ」
話すうちに、お清の頰が紅潮してきた。よほど腹が立つらしい。
「父は根が狡賢いので、何をするかわかりません。かちんはずっと部屋におりますが、たまにお手水(ちょうず)を使うために表に出ます。そんな時、父が悪さをするのではないかと恐ろしくてたまらないのです」
「つまり、親父殿からこの猫を守れとおっしゃるのですね」
「はい。この子は決して猫又になんかなりません。ずっと一緒にいるから人の心がわかるだけで、在り来たりの猫です。私の話を聞いてくれるのもこの子だけ。この子がいなくなったら、生きていけません」
又四郎は猫を見下ろした。目が合うと、じっと見つめ返してくる。お清が来る前、又四郎も猫を相手に、人には言えぬ身の上話を語っていた。意味のある言葉は返らなくても、ただ聞いてくれるだけで心が和んだ。そう思えば、猫と語り合うのも、さほど奇妙ではないのかもしれない。
「わかりました。出来うる限り、お守りいたしましょう」
「有り難うございます」
用が済んだと気付いたのか、猫がくるんと膝から下りた。途端にすっと温もりが消えて、又四郎は思わず膝頭をさすった。お清は左肩に猫を抱え上げると、手燭を取って背を向けた。板戸をそっと開けて、又四郎を振り返る。
「夜中に一人で起きているのは、寂しくありませんか。私は夜になると、あれこれ考えてしまいます。何でこんなふうになってしまったのだろう、何も悪いことはしていないのに運が悪かったのだろうか、何故、どうしてって」
親の悪業の報いを我が身に受けた子の悲しみが、又四郎に雪崩(なだ)れ込んできた。事情は違えども、同じ心の疼(うず)きが脈打つように伝わってくる。
「その気持ち、わかりますよ」
ぽつりと返した言葉を耳にして、お清はこちらをじっと見返した。言葉に込めた真心を確かめるように黒目がちの瞳が動く。やがて頰を緩め、微かな笑みを浮かべた。又四郎の心に仄かな灯火が灯った。
-
『圧勝の創業経営』
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募締切 2025/07/26 00:00 終了 賞品 『圧勝の創業経営』5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。