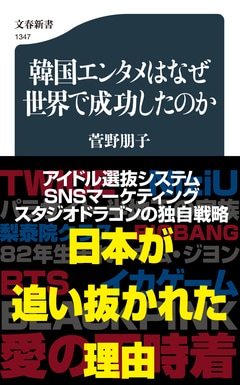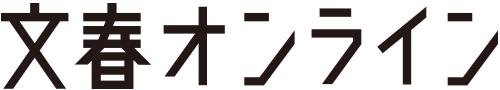バラエティ番組で「やらせ疑惑」、視聴者から抗議や苦情が殺到し…映像作家にフジテレビ退社を決意させた“きっかけ” から続く
『情熱大陸』(MBS・TBS系)や『ザ・ノンフィクション』(フジテレビ系)など、数々のドキュメンタリー番組を手掛けてきた、映像作家の大島新氏。そんな彼が『ドキュメンタリーの舞台裏』(文藝春秋)を上梓した。
ここでは、同書より一部を抜粋。『情熱大陸』や『ザ・ノンフィクション』の“知られざる制作秘話”を紹介する。(全2回の2回目/1回目から続く)
◆◆◆
取材における被写体との距離は「右手に花束、左手にナイフ」
取材における被写体との距離の取り方について、私は「右手に花束を、左手にナイフを」ということを心掛けるようになりました。『情熱大陸』に限らず、1人の対象を追う人物ドキュメンタリーは、どうしても「その人を称える」内容になりがちです。あるジャンルで功成り名を遂げた人を取材する場合は、余計にそうなります。
そもそも成功しているからその人を取材しているわけで、その成功の秘密を探ることが取材の常道になります。ただ、手放しにほめ称えると、プロモーションのような、ややもすれば気持ち悪い番組、観ている人からすると鼻白むような内容になってしまいます。
そこで、「花束とナイフ」となるのですが、まずは相手の懐に入らないと、良いものは撮れません。その為には、「あなたに好感を抱いています」あるいは「興味を持っています」あるいは「あなたの仕事を尊敬しています」と、表明することです。それが花束です。最初から「あなたを批判する目的で撮ります」と言って、心を開いてくれる人はいないでしょう。
時間をかけて「番組のディレクターさん」から「大島さん」に
とはいえ花束と言っても、過剰にほめたり、おべっかを使うのは逆効果です。成功者であればあるほど、そういう人は周囲に山ほどいるでしょうし、警戒感を持たれる可能性もあります。相手に敬意を持って接することはもちろんですが、大切なのは、その人のどういう部分に興味を抱いているか、取材者自身の考えをきちんと伝えることだと思っています。
その上で、信頼してもらえるよう人間関係をしっかりと作ります。時間をかけて「番組のディレクターさん」から「大島さん」に、相手の意識が変わるよう努力します。なかなかそこまでは達しませんが、「この人にだったらどこを撮られ、どう表現されても構わない」とまでなれば、最も良い状態と言えるでしょう。
そうした関係を築いた上で、今度はナイフです。これは、批評性と言い換えてもいいと思います。まず、完璧な人間はいません。人は誰しも、長所もあれば短所もあります。また著名人であればあるほど、賞賛の声もあれば、批判だってあります。その人の懐に入って普段は見せない素顔を撮っただけでは不十分で、その上で批評を加えることが重要です。その場合、後からナレーションで批評するのはいただけません。やはり現場で、自らの言葉で、その人への疑問点をしっかりとぶつけることです。
『情熱大陸』で秋元康さんにぶつけた質問
そうした私の「花束とナイフ」の姿勢が、最も色濃く出たのが2007年に放送した『情熱大陸』の秋元康さんの回でした。これは私の企画ではなく、プロデューサーから「大島に撮ってほしい」と言われた仕事です。その頃私は、番組の常連ディレクターの中では「やっかいな大物担当」のような感じになっていました。秋元さんは言わずと知れた希代のヒットメーカーであり、当時はAKBのプロジェクトをスタートさせ話題になりはじめていた頃でした。

しかし正直に言うと、私は秋元さんにあまり良い印象を持っていませんでした。「そんな僕がディレクターでもいいんですか?」と中野プロデューサーに伝えると、「大島くんはそう言うだろうと思っていたよ。でもだからこそ撮ってほしい」と言われました。そんな風に言われたら、がんばるしかありません。
私はある仮説というか、番組の裏テーマを考えました。それは、「ここ20年、世に出る表現物全般について、優れたもの=ヒットするもの(金が儲かるもの)と多くの人が感じるようになったのだとしたら、それは秋元康のせいではないか?」ということでした。理屈っぽいですね。さすがにこれをいきなり秋元さん本人には言えませんし、私の個人的な考えなので、ファクトとして提示することもできません。
放送後、メディア関係者から大きな反響が
だからこそ「裏テーマ」であり、私自身の中に常にその問いを持って取材をしました。この時のナイフは、インタビューでこんな質問をしたことです。「秋元さんは人間のタイプとして、どちらに近いですか? 1、ピカソ 2、広告代理店マン」これに対する秋元さんの答えは、「ピカソになりたい広告代理店マンかな。でも『なりたい』と思った時点でダメなんだよ」でした。見事なものです。
私は取材を経て、秋元さんのプロ意識の高さや勉強熱心さに頭が下がる思いでした。良い印象を持っていなかったのが、大きく変化しました。ただ、やはりマイナー界の住人たる私にとっては、距離のある人という印象は変わりません。
番組は、放送後に大きな反響がありました。一般の視聴者の方というより、テレビや出版など、メディア関係者からの声が多く届きました。そうした「プロ」からの熱い反響を聞き、なんとか30代で目標にしていた「大島印」の番組を作れるようになったと感じました。
ちなみに、秋元康さんとはその後もお付き合いが続き、仕事をご一緒する機会もありました。何度もお会いしていますが、あまり打ち解けた関係とは言えません。緊張感を保ったまま今に至るのですが、作り手としての私を認めてくれているような気はします。秋元さんご自身の仕事の領域は大メジャーですが、実は秋元さんはマイナーな映画やアートなどにも造詣が深いのです。
直近にご一緒したのは、2019年にNHKの番組のためにニューヨークで撮影をした時でした。美空ひばりさんの『川の流れのように』を作詞した時のことについて、秋元さんにインタビューをしたのです。そのロケの時の雑談の中で、秋元さんにこんなことを言われたのが強く印象に残っています。「大島くんがテレビでいいものを作るっていうのはもうわかったからさ、今後は原一男さんみたいにすごいドキュメンタリー映画を撮ってほしいな」
畏れ多くも、ありがたく受け止めました。

『ザ・ノンフィクション』の難しさ
フリーのディレクター時代の仕事でもう1つ触れたい番組は、フジテレビの『ザ・ノンフィクション』です。1996年に私がディレクターデビューした番組であり、2022年の今も続く長寿番組です。2021年には放送1000回を超え、毎年のように国内外のテレビアワードで受賞しています。固定ファンが多く視聴率も好調な、民放を代表するドキュメンタリー番組です。
しかし私は30代の頃、2つの点でこの番組に携わることを躊躇していました。1つは、フジテレビを辞めたわけですから、敷居が高かったということがあります。会社に残っている人から見たら、辞めた人間が出入りすることに違和感を覚えてもおかしくありません。上層部の中に、「大島は使うな」と言っている人がいると私に教えてくれた人もいました。真偽はわかりませんが、そうした空気に「望まれていない場所で作るのもなぁ……」と思っていました。
もう1つは、番組が持つテイストの問題です。『情熱大陸』が、各界で活躍する人や著名な人物のドキュメンタリーであるのに対し、『ザ・ノンフィクション』の取材対象者はほとんどが市井の人々です。それも、長引く平成不況と呼ばれる時代に、苦難の日々を送る人々にスポットを当てています。
2011年の東日本大震災以後は、社会がまとう空気と番組のテイストがマッチし、固定ファンを増やしていったと思います。それだけ、この番組にはある種の普遍性があると思うのです。
フジテレビ時代の先輩と7年ぶりに番組制作
だからこそ、取材では被写体のつらい状況や、厳しい現実にもカメラを向けなければなりません。貧困、家庭内不和、仕事のトラブル、病、死……現実世界で生きている人にとって、そうした困難こそが普遍性を有することです。
しかし、撮影をする側に立つと、番組の期待に応えるためには被写体の「不幸探し」をしなければならないような気持ちになります。もともとカメラの持つ暴力性に敏感だった私は、その部分が『ザ・ノンフィクション』の制作になかなか乗り気になれない点でした。
それでも、2003年に7年ぶりに同番組を作る機会を得ました。当時のプロデューサーだったフジテレビの味谷和哉(みたにかずや)さんの存在があったからです。
味谷さんは、私のフジテレビ時代の同じ部署の先輩です。それも、読売新聞大阪社会部の記者出身で、フジテレビに中途入社した珍しい経歴の持ち主。ディレクター経験も豊富で、新聞記者時代の知見と取材力を生かした『NONFIX』の「なんでやねん!西成暴動」や、FNSドキュメンタリー大賞に輝いた「幻のゴミ法案を追う」など、社会派のドキュメンタリーを手掛けていました。年は一回り離れて(私より12歳年長)いますが、よく番組について議論する関係でした。

映像制作会社である「蒼玄社」を設立
フジテレビ時代には一緒に仕事をしたことはなかったのですが、私が辞めた後も何かにつけて気にかけてくれて、味谷さんがプロデューサーの番組で、私の後輩がディレクターデビューするときなどに、「アドバイスをしてやってくれんか」と、私を構成作家として起用してくれたこともありました。
そんな味谷さんが『ザ・ノンフィクション』のチーフプロデューサーとなり、「大島もそろそろノンフィクションをやったらどうや」と声を掛けてくれたのです。さらに、「フリーだとお前の企画でもどこかのプロダクションを経由しなきゃいけなくなるから、会社を作れ」と勧めてくれたのも味谷さんでした。ディレクター個人だと「ギャランティ」になりますが、会社にしていれば「制作費」という形で、もっとまとまった金額で仕事を受けることができるからです。(リスクも生じますが)
味谷さんの助言によって、私は映像制作会社である蒼玄社(後のネツゲンの前身です)を設立しました。ネーミングの由来は、蒼(=素人)玄(=玄人)です。プロフェッショナリズムを持ちながら、この仕事に就く前の初心を忘れず、という思いで決めました。私1人の会社だった6年間はこの社名でしたが、2009年に仲間と一緒に新しく出発するときに「出版社、あるいは政治結社みたい」という声が上がり、ネツゲンに変えました。
『なぜ君』につながっていくドキュメンタリー
実は、味谷さんに最初に持ち込んだ企画が、小川淳也さんのドキュメンタリーです。小川さんと妻の明子さんは、私の妻の高校の同級生。妻から「小川くんっていう、野球部で、めちゃくちゃ勉強ができてさわやかな好青年が、東大を出て官僚やっとんたんやけど、あっちゃん(明子さん)の猛反対を押し切って出馬するんやって」と聞いたのです。時は小泉純一郎政権の時代、野党民主党からの無謀とも言えるチャレンジに興味を持ち、カメラを回しました。2003年の秋のことです。

しかし、味谷さんから「取材対象がひとりでは難しい」と言われ、小川さんだけでなく、旭川の無所属の男性と横浜の社民党の女性も取材することになりました。私は小川さんの取材をメインに3か所を回り、それぞれの候補者に知り合いのディレクターやカメラマンに張り付いてもらって密着するスタイルをとりました。番組のオンエアは選挙後だったので、放送法に抵触するということはありませんでしたが、やはり1人の候補者だけというのはバランスを欠くという判断があったそうです。
味谷さんから学んだ多くのこと
加えて、面白さという意味でも群像劇のほうがいいだろう、ということでした。番組は、2003年11月16日に放送されました。タイトルは『地盤・看板・カバンなし ~若手3候補者が見た夢と現実~』です。いずれも初出馬、親が政治家という背景を持たない30代の候補者たちは、全員落選しました。こうして一度小川さんの選挙を取材した番組を作った経験が、後の映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』や『香川1区』につながりました。
ちなみに味谷さんは実に多才な人で、番組のオープニング・エンディング曲『サンサーラ』の作詞・作曲をしています。一度耳にしたら頭を離れない「生きて~る、生きている~」という、あの曲です。本名とは別のペンネームを使っていましたが、番組のプロデューサーがテーマ曲を作るというのは稀有なことです。話芸が巧みな大阪のおっちゃんキャラですが、哲学への造詣が深く、時にずばっと本質的なことを語ります。
実は「右手に花束、左手にナイフ」も、味谷さんから聞いた言葉がきっかけでした。味谷さんのオリジナルは「花束とピストル」でしたが、私がそれをアレンジしました。事件記者としてならした味谷さんから、私は実に多くのことを学びました。