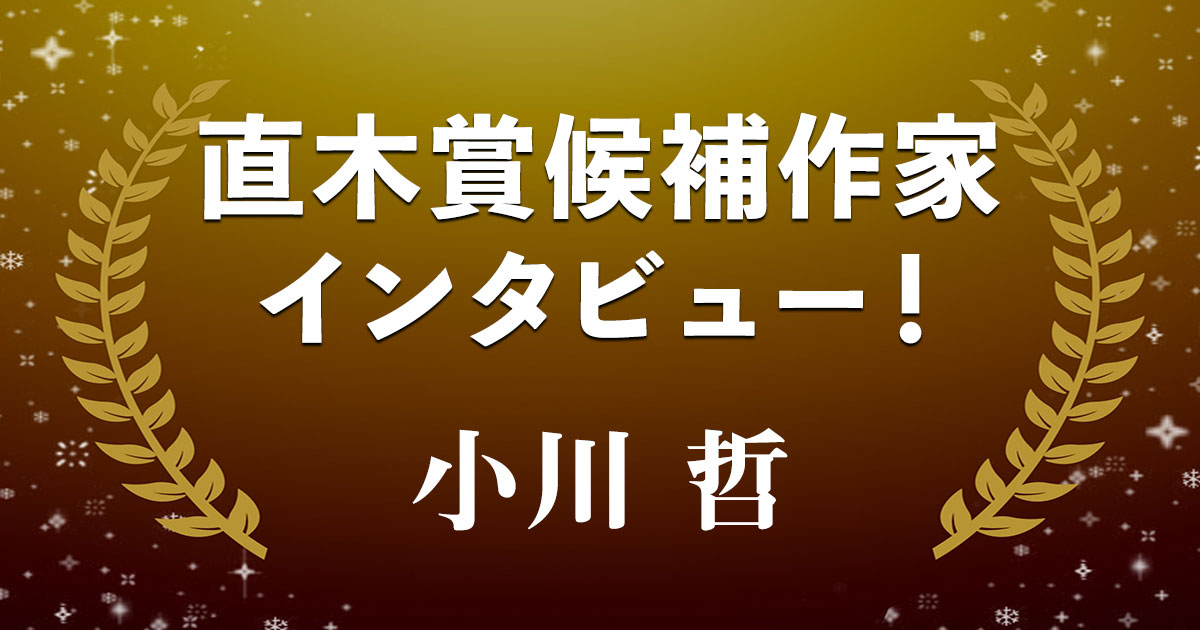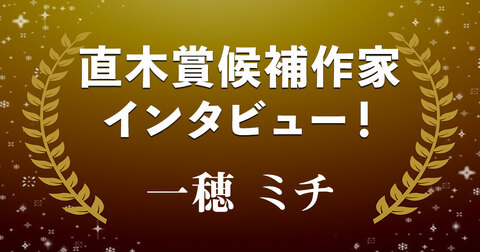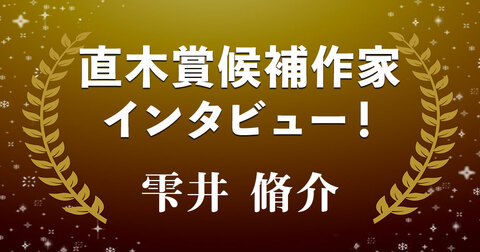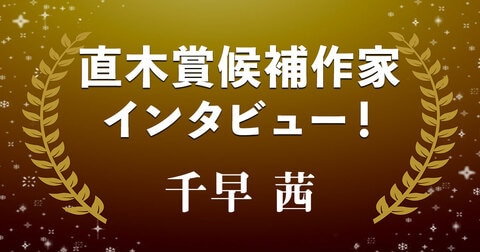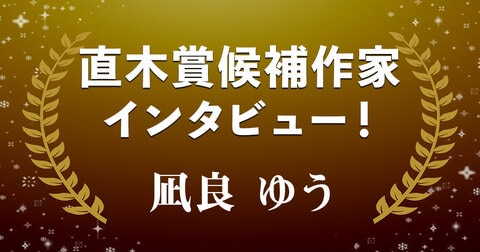日露戦争前夜の一八九九年から、第二次世界大戦終結後の一九五五年にかけ、満洲にある架空都市・李家鎮(リージヤジエン)(のちの仙桃城(シエンタオチヨン))が興り消えるまでを描いた『地図と拳』。六百ページを超す大作を通じて、それぞれの思惑を持った強烈な個性を放つ人物が現れては去っていく。
「小説執筆にあたって歴史を振り返るとき、『もっと最善を尽くせたのではないか』と、結果を知っているからこそ思うことが多くあります。小中学生の頃に教科書を読んで抱いた、どうして第二次世界大戦という無謀な戦いに日本は挑んだのかという疑問とも通じる感覚です」
本作で鍵を握るのは、密使に同行し通訳として満洲へ渡って来た細川という人物で、彼は十年後の未来を見定めようとする。
「SFと歴史小説は似ていると、これまで色々なところで話してきましたが、違いは、書き手としては史実の有無にあり、読者側からすると『ネタばれ』しているかどうかにあります。第二次世界大戦で日本が負けるという結末は誰もが知っていますよね。
一方で、その結果を当時すでに予想していた日本人たちがいた現実もあります。猪瀬直樹さんのノンフィクション『昭和16年夏の敗戦』は執筆前に読んでいて、そこから着想を得たのが、戦争構造学研究所の〈仮想閣議〉のアイデアです。なんとかならなかったのか、なぜ戦争をしてしまったのかという問いに、結果を知っている、いわば現代に生きる自分たちと同じ視点から戦争を描けたら、新しいものが生まれるのではないかと挑戦しました」
しかし、小川さん自身、もともと満洲や建築に詳しいわけではなかったという。
「担当編集者から満洲を小説のテーマとして提案されたとき、ほとんど知識がない状態だったんです。それでも、頭の中で空想のあらすじを描いてみたら、『この小説は自分でも読みたい』と感じて。裏を返せば、自分と同じくらい知らない人にも興味を持ってもらえるのではないか、と考えました」
半世紀を通して、「地図」と「拳」が都市に残したものを問いかけながら、終戦から十年後仙桃城で物語は幕を下ろす。
「戦争を語るときに使われる数字やデータは、感情移入しにくいものです。戦時下に自分だったらどう動いただろうかという想像は、戦時下に生きた個人を描くことで可能になると思うんです。戦争の難しさや怖さを考えるために、これは小説家がずっと取り組み続けるべきことだと考えています」

小川 哲(おがわ さとし)
一九八六年千葉県生まれ。二〇一五年『ユートロニカのこちら側』でデビュー。一八年『ゲームの王国』で山本周五郎賞、二二年本作で山田風太郎賞を受賞。
第168回直木賞選考会は2023年1月19日に行われ、当日発表されます。