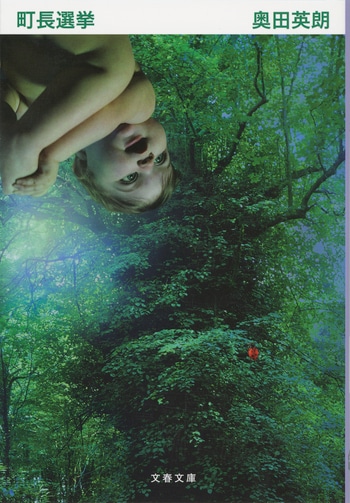奥田英朗さんは2004年に『空中ブランコ』で直木賞を受賞。トンデモ精神科医・伊良部一郎が暴走するこの作品は、〈伊良部シリーズ〉として累計290万部を誇る人気作だ。だが06年刊行の『町長選挙』を最後に、シリーズ刊行は途絶える。その理由と、17年ぶりの新作について著者が語る。

「〈伊良部シリーズ〉はもうやめようと、封印したつもりでした。そもそもルーティンで何かをするのは好きではないし、ヒット作は一度捨てたほうがいいという考え方なんです。ヒット作というのは諸刃の剣です。読者も出版社も続編を要求してくるけれど、それに応えていると自己模倣と縮小再生産が始まる。そうすると作家としてどんどん先細りするので、早い段階で捨てたほうがいいでしょう。
それに、読者の期待にいったん応えると、応え続けなければならなくなる。それが精神的に負担だったというのもあります」
とはいえ、直木賞を受賞した作品のシリーズであり、編集者も、何より読者も望んでいた作品を書かないというのは、徹底している。
「作家に限らず、クリエーターの心意気というのは、“catch me if you can”――できるもんなら俺を掴まえてみろ――なんですよ。
作家にとっては、読者も編集者も、ある意味で対戦者です。常に相手の想定外のことをしたい、という思いが僕の中にある。新しいことにチャレンジしないと面白くないでしょう。同じことはしないというのが、僕の以前からのスタンスです」
ではなぜ、その気持ちが変わって、伊良部の新作を書いたのだろう。
「そもそも『オール讀物』の周年企画だから書いてほしいと言われたのがきっかけです。それで、以前(2006年)書いたまま単行本に収録されていなかった『うっかり億万長者』を読んでみたら、面白かった(笑)。僕は自分の作品はめったに読み返さないんだけれど、恐る恐る読んだら、これやっぱり面白いな、じゃあもう1冊くらいやってもいいかな、と思いました。
久々に書いてみたら、伊良部とか看護師のマユミちゃんとか、昔の友人に会ったみたいでしたね。書くのが難しいとか苦労はなく、すぐ当時の感覚に戻れて、書いていて楽しかったです」
新作では、コロナも影を落としている。表題作「コメンテーター」では伊良部とマユミがテレビのワイドショーにコメンテーターとして出演し、コロナに関して放送事故寸前の発言を連発する。「パレード」では地方出身の大学生がリモート生活を強いられた結果、気づけば社交不安障害になっていた。
「現代人というか、いま生きている現役の人たちが体験したいちばん大きな出来事がコロナでしょう。戦争を体験した人たちはもちろん戦争がいちばんだろうけれど、大半の人の物心がついたのが戦後となったいま、世界的な大災害、大事件はコロナが初めてだと思います。死者が大勢出て、ロックダウンしたり、人の行き来ができなくなったり……。そんな中で、小説家として何か記録を残しておくべきだろうなという思いはありました。そして何より、伊良部はコロナに対してどう言うだろう、という茶目っ気のようなものもありましたね。
ただ、コロナもあくまでも借景として描いているだけです。コロナ自体をどうこうできるわけではないですし、コロナ禍で人はどうするのかというほうに興味があります。そういう意味では、コロナ前の時と小説を書く点においては同じスタンスですね。
そもそも僕は、テーマを書かない作家です。テーマを書かずにディテールを描け、と言ったロシアの戯曲家がいるそうですが、まったくその通りだと思う。テーマを書くと説教臭くなるんです。ディテールを描いてテーマを浮き彫りにする、というのが僕のやり方で、コロナなどの物事はあくまでも借景、背景です」

〈伊良部シリーズ〉では、伊良部も患者たちも登場人物が自由自在に動き、物語はまったく予測のつかない展開を見せる。患者たちの悩みは切実で読者は我が事のように感じ、伊良部の物言いは痛快だ。
「物語の展開は、まったく決めていません。登場人物の病気、症状を最初に設定して、あとはどうやって治すのだろうな、と考えます。このシリーズは、伊良部ではなくて患者が主人公です。患者が道に迷って、ふとしたきっかけで伊良部の病院に行き、そこで不思議な体験をするというのがこの小説の基本パターン。そして、異物と出会ったときその人物がどう変化するかを描く。病気の設定を決めればあとは何とかなる、と思っています。
この小説は人生相談みたいなものでしょう、かなり乱暴だけど(笑)。昔、今東光さんが『週刊プレイボーイ』で人生相談をやっていたんですが、それは痛快でした。常識ではそんなこと言えないということを、ユーモアでやっちゃえ、という感じで。〈伊良部シリーズ〉もそういうところがありますね」
昨年、長編の犯罪小説『リバー』を上梓した。その作品でも、最後の最後まで事件の真相を決めていなかった。「山を登る前に下山のルートを考えたことはない」という。
「自分の中でいくつか見せ場のシーンがあって、そこを通過して山頂に登るというのは考えていますが、どう降りるかはそう重要ではない。最近は、作中の伏線をきちんと回収しているかどうかが話題になったりするけど、僕はまったく意識しないですね。オープンエンドで構わないと思っているし、自分も映画などはそのほうが好きなくらいです。大団円でなくても、犯人が分からなかったり捕まらなくても、これだけ面白くしたならいいだろう、と思っています。
もちろん、うまく着地できるか、書いていて無茶苦茶怖いですよ。7割くらいは書いていて嫌で嫌でしょうがなくて、編集者にこれは失敗作だと打ち明けようかと思うこともしばしば。でも、毎回奇跡が起きるんです(笑)。
そして開き直りもあります。僕は出てくる人間たちが右往左往する様を描きたい。そして僕の昔からの読者も、それを楽しんでくれるんだろうと思っています。それさえ守っていれば許してもらえるんじゃないかな」
執筆は以前から、長編を1本手掛ける傍ら短編を時折り書く、というペースだ。『オリンピックの身代金』や『罪の轍』などの長編では、昭和30年代の事件を扱った。
「いま書いている長編も昭和を舞台にした大河小説です。『昭和』はライフワークですね。映画でも小津安二郎や黒沢明が断然面白いと思っているんですが、昭和のアナログは人間味があっていいなと思います。逆に“いま”を描くと、テクノロジーなんかはすぐに古くなってしまう。たとえば犯罪小説なら、連載している間にも新しい技術が導入されたりして捜査のやり方が変わってしまい、書きにくいです。
短編では、市井の人の、家族間の動揺などをおもに描いていて、事件も何も起きません。登場人物たちの心情のスケッチみたいなもので、ストーリーなんかいらない。どう心が揺れて、どう自分で納得させるか――それだけでも60~80枚は書けるし、そういうのが短編だと思います。無理やり起承転結を付けることに、あまり関心がないんでしょうね。そうすると、派手に設定を作って物語を動かすという〈伊良部シリーズ〉は、珍しいパターンですね」
さて、久々の〈伊良部シリーズ〉新作だが、またしばらく封印してしまうのだろうか。ファンは気になるところだ。
「マンネリ化とか縮小再生産の恐れは、いまはもうなくなりました。ここまで年齢やキャリアを重ねて、いろんなことをやってきて、皆さんの期待をはぐらかすように書いてきたから、もう何を書いてもいいという既得権みたいなものがあるんじゃないかと思ってます(笑)。〈伊良部シリーズ〉も、もう1冊くらい書いてもいいかな」