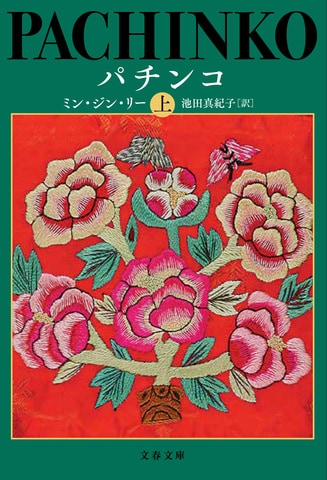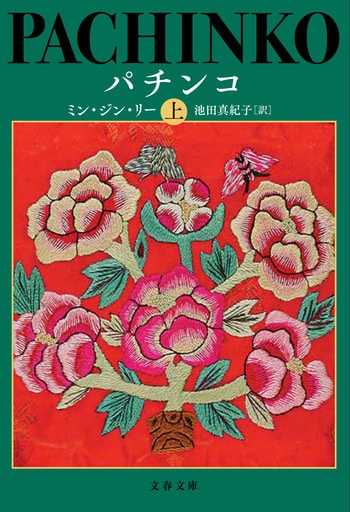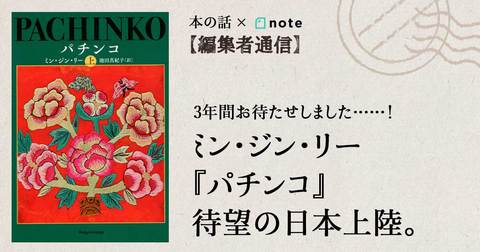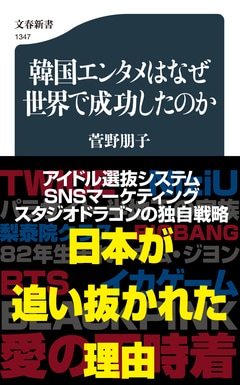私はバブル時代まっただなかの東京でアメリカ人ビジネスマンと知り合って結婚した。英国留学から戻り、日本に住みはじめたばかりの頃である。娘を出産後に夫の転勤で香港での生活を二年ほど経験したが、一九九五年からはずっとアメリカのボストン近郊に住んでいる。アメリカに来て困ったのは、日本語の本が入手しにくくて高いことだった。当時はキンドルどころかオンラインストアもなかった。『少年少女世界の名作文学』(小学館)のおかげで五歳の頃から活字中毒だった私は、読む本がないと生きていけない。そこで、必要にかられて英語の本を読むようになった。
アメリカ人の夫や義母よりも本をたくさん読み、しかも読んだ本について話さずにはいられない私は、そのうち周囲の人から「私にあう本を推薦してほしい」と頼まれるようになった。そして、二〇〇八年に、主に英語の新刊を日本語で紹介するブログ「洋書ファンクラブ」を始めた。そのブログの読者が増え、二〇一五年からは「ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト」で「ベストセラーからアメリカを読む」という連載コラムも始めた。このコラムは、単に本の感想や書評ではなく、「なぜこの本が、現在のアメリカでベストセラーになっているのか?」という視点から本とその背景にある社会的な事情を説明するものである。
ミン・ジン・リーさんの『パチンコ』も、この「ベストセラーからアメリカを読む」で二〇一八年にご紹介したことがある。
二〇一七年二月にアメリカで発売されたこの長編小説はまたたく間にベストセラーになり、その年の全米図書賞の最終候補になった。「出版業界のインサイダーによる、インサイダーのための賞」という批判もされているが、アメリカでは重視されている賞であり、最終候補になっただけでも話題性がある。しかも、『パチンコ』はこの年の受賞作『Sing, Unburied, Sing』よりも多くの読者の心を掴み、ベストセラー上位に長くとどまった。読者評価も異常なほど高い。
正直なところ、それにも関わらず、最初のうち私はさほど読みたいと思っていなかった。「在日コリアン一家の四世代にわたる年代記」という内容紹介を読んで、「アメリカ人読者には珍しさがあるだろうが、日本で育った私が得る新鮮さはないだろう」と思ったし、私は「パチンコ」を一度もやったことがないほど苦手なのだ。賭け事が好きではないというだけでなく、あの騒音に耐えられない。だから私は、『パチンコ』が自分の好みの本ではないだろうと勝手に「食わず嫌い」をしていたのだ。
しかし、周囲の人から「あの本読んだ?」と尋ねられることがあまりにも多くなり、無視していられなくなってきた。なにせ、私が出会ったころには本など読まなかったアメリカ人の義母までもが「あの本、良かったわ~。もちろん、ユカリのことだから、もう読んでいるわよね」と電話してくるのだ。最終的に背中を押したのは、アメリカ人と日本人のミックスである私の娘だった。「とても良い本だから読むべきだ」というのだ。
読んでみて、これまで「食わず嫌い」してきたのを後悔した。タイトルや内容説明から私が抱いていた期待を良い意味で裏切ってくれた、すばらしい読書体験だったからだ。
自分の人種や育った文化背景などをすっかり忘れてしまうほど登場人物に感情移入できるし、いったん読み始めたら最後までやめられなくなるほどのめりこんでしまうページターナーだ。そして、読後も彼らのことを考え続けてしまう。
小説は一九一〇年の釜山からスタートする。大日本帝国が大韓帝国との間で日韓併合条約を締結して朝鮮半島を統治下に置いた年だ。釜山の南にある影島の漁村に住む漁夫の夫婦は、その運命を黙って受け入れた。「盗人に祖国を譲り渡した」「無能な特権階級」と「無責任な支配者層」には、それ以前からすでに諦めの気持ちを抱いていたのだ。動揺するかわりに夫婦は身体に障害があるが利発なひとり息子フニの将来を考えた。夫婦は息子に学校で朝鮮語と日本語を学ばせ、仲人を使って見合い結婚をさせ、労働者用の下宿屋を経営させた。
フニの若い妻ヤンジンは何度も流産を繰り返した末にようやく健康な娘ソンジャを得た。そして、働き者のフニが亡くなった後も、未亡人は娘の助けを借りて評判の良い下宿屋を営み続けた。
ソンジャは働くことに生きがいを見出す生真面目な少女だったが、十六歳のときに年上の裕福そうな男コ・ハンスに誘惑されて妊娠してしまう。その後でハンスが既婚者だと知ったソンジャは、自分の過ちを恥じ、「結婚はできないが面倒は見る」というハンスの申し出を拒否して別れる。
田舎の漁村で未婚の女が妊娠するのは醜聞だ。結核で倒れたときに母娘に看病してもらったことに恩義を感じる若い牧師イサクは、これを神が自分に与えた機会だと考えてソンジャに結婚を申し込む。若い二人は、イサクの兄ヨセプの誘いで一九三三年に大阪に移住する。
イサクとヨセプの両親は裕福な地主だったが、韓国社会は不安定になっており、実家に経済的な余裕はなくなっていた。大阪に来たものの、韓国人牧師のイサクが得られる収入はほとんどなく、二組の夫婦は工場に勤めるヨセプの収入に頼ることになった。そのヨセプにしても、雇ってもらっているだけで感謝しなければならない状況で、どんなに働いても生活は楽にならなかった。
ヨセプが借金を抱えていることを知ったソンジャは、ハンスから受け取った唯一の贈り物である高級時計を内緒で売って返済したが、戦争前夜の日本の思想弾圧で牧師のイサクが逮捕されてしまい、一家はさらに窮地に陥る。ヨセプは男としての甲斐性にこだわって妻たちが外で働くことを禁じるが、ソンジャはヨセプの妻が作ったキムチを路上で売って家計を支える。
移民一世のソンジャたちは生活難で苦労するが、その二人の息子、特に学業優秀で真面目な長男は日本で育ったコリアンとしてのアイデンティティで苦悩する……。
異国に移住した一世と二世が異なる部分で苦労するというのは、実はどの国の移民にも共通している。この小説がアメリカで多くの読者に読まれ、高く評価されたのは、この部分にあるのかもしれない。
私がこの小説を読んでいるときに思い出したのは、二十世紀前半にアメリカに移住したアイルランド系やイタリア系移民が受けた差別や、紀元前からあるユダヤ人の迫害についてだ。ユダヤ系の人には金融業、医師、弁護士、科学者が多いのだが、それは古代のヨーロッパでユダヤ人の就業が禁じられていた職種が多かったからだという説を読んだことがある。また、アメリカのニューヨークやボストンでは、アイルランド系移民の警察官が圧倒的に多い。これも、アイルランド系移民が初期に受けた職業差別が少なからず影響している。二十世紀の日本での在日韓国・朝鮮人によるパチンコ店経営は、これらに似ているところがある。
アメリカは、先住民以外はすべて「移民」とその子孫だ。何世代か遡れば、必ず移民としてのこうした苦労ばなしに行きあたるはずだ。こうしたアメリカ人のDNAに刻み込まれた記憶が、小説への共感を生むのだろう。
日本統治下の韓国での日本人による現地人への虐めや、日本人による在日コリアンへの差別、そして単語こそ出てこないが「慰安婦」のリクルート、日本で在日コリアンが受ける差別など、日本人にとっては居心地が悪い部分もある。
けれども、これは日本人を糾弾する小説ではない。
ニューズウィーク日本版のコラムのための取材で、作者のミン・ジン・リーさんは「私の夫は日本人とのハーフで、私の息子は民族的には四分の一が日本人だ。現代の日本人には、日本の過去についての責任はない。私たちにできるのは、過去を知り、現在を誠実に生きることだけだ」と語ってくれた。
そういったリーさんの日本人への愛情は、この小説に登場する善良な日本人や在日コリアンの言葉からも感じ取ることができる。
むろん、良いことばかりではない。この小説に出てくる在日コリアンの一世、二世、三世が日本や日本人に対して抱く複雑な心理は、白人男性と結婚してアメリカで暮らす私にはとてもよくわかる。裕福で政治的に保守的な夫の家族は、悪気なく差別的な発言をするのだが、日米の血が混じったわが娘のほうが、私よりも過敏なところがある。それは、差別を覚悟で移住した一世の私と、祖国を自分で選ぶことができなかった二世の違いなのかもしれない。『パチンコ』を読んだ後で、娘とそんなことを話し合った。
けれども、多くの人にとっては、民族としての祖国よりも、暮らしている土地が「母国」になるものだ。そういった葛藤を鮮やかに表現しているのが、アメリカのコロンビア大学で教育を受けた三世のソロモンと、コリア系アメリカ人の恋人フィービーとの意見の対立だ。フィービーは日本人の上司に騙されたソロモンに同情して憤慨するのだが、ソロモンは、“日本人はみな悪”という思いこみを持つフィービーにかえって冷めた感情を抱くようになる。そして、「彼はたまたまいやな人間だった。たまたま日本人だった。もしかしたら、アメリカで教育を受けた結果なのかもしれない。たとえ百人の悪い日本人がいても、よい日本人が一人でもいるのなら、十把一絡げの結論は出したくない」と思うのだ。
こういうソロモンを「出来すぎの人物」と感じる読者もいるかもしれない。けれども、アメリカに長く住んでいる日本人の多くは、アメリカやアメリカ人に対して同じような気持ちを抱いている。そして、ソーシャルメディアなどで「アメリカやアメリカ人はすべて悪」といった十把一絡げの意見を流す日本人がいると、ついアメリカを擁護したくなる。
こういった複雑な心理をしっかりと描いているのも、『パチンコ』の優れたところだ。
けれども、『パチンコ』がアップルTVで連続ドラマ化されるほど人気が出たのは、純粋にドラマとして面白いからだ。私は、読んでいる最中に、若い頃に観たNHK連続テレビ小説の「おしん」を思い出していたのだが、人情と家族ドラマというのは、人種や国境を越えて、誰もが理解し、愛せるものなのだろう。
そんな素晴らしいドラマをこうして日本の読者にご紹介できるのは、光栄だと思っている。