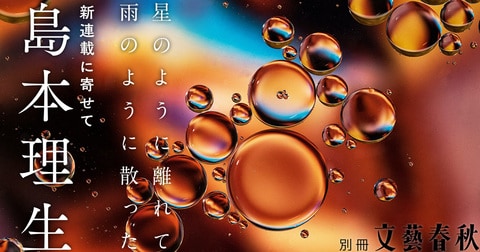小説は、大学院で文学を研究する二十代の女性、春のごく穏やかな一日を描いて始まる。
夏休み中の大学の光景、同級生との修士論文についての会話、美術館で待ち合わせた少し年上の恋人とのデート、互いに気遣いの感じられるやりとり……。コロナ禍一年目の夏で、大学には人の姿は少なく、行動に多少の制限がある様子以外は、論文が進まずに思い悩んではいるものの就職も決まっているようで、落ち着いた「幸せそうな」日々と、周囲からは見えるに違いない。
しかしその穏やかで気遣いのある言葉の隙間に、むしろ「気遣い」が重なるところに、不安や不穏な気配が潜む。そして、あるとき一気に春の感情が溢れ出す。
その暴発を引き起こしたのは、恋人の「愛してる」という言葉だ。「あなたが、私を愛してるって、どういうこと?」と、春は問う。繰り返すその問いは、春の呼吸の苦しさが伝わり、読む私の息も乱れる感覚が確かにあって、そして、この小説の問いが私自身の中から響いてくるみたいに感じて、読み続けた。
この十年か二十年か、男女間や恋愛における関係性の不均衡や難しさ、親密さの中で生じる暴力や支配的な欲望について、世の中ではだんだんと語られるようになってきた。その状態や不適切なありかたを表す言葉と解説を日常的に読んだり聞いたりすることが増えた。周囲の人間関係や、自分の過去の経験について、あれはそういうことだったのか、と考えることができるようになり、恋愛と呼ばれる関係やそれを描いた作品についても、「恋愛感情だから」だけでとらえられなくなっている。
かといって、では、恋愛や「愛」の介在する関係についてなにか困難が生じたときに、「それはこういう状態」「こんな支配関係」と切り分けてしまえるほどシンプルではないのが、人と人との関係であり、人の感情や記憶であると思う。
「恋愛」や「愛」の形で、ある人を取り巻いていく親密な関係、重なり合って絡み合った人々の欲望や関係性について、もっとも真摯に見つめて書き続けてきたのが島本理生だと思う。一読者として、また同時代の作家として、島本さんが書き続けてきたものはなにか、ようやく思い至るようになったのは島本さんの小説を読み始めてから何年か経ってからのことだった。
小説は、たいてい、すでにできあがったものとして読まれる。春がアルバイトに通う売れっ子作家吉沢樹が「ミステリーは細かい伏線張らなきゃいけないから」と言うように、結末や結果に向かってそれにつながる出来事や理由が示されていくはず、と。小説やドラマや映画、溢れる物語をたくさん読んできた私たちは、現実も、身近な人のことも、あるいはニュースで知った事件についても、物語としてとらえがちである。
恋愛の関わる親密な関係についても、それが破綻したり暴力や不適切な事態が起こったりしたとき、実は最初からだますつもりだった、善意だったのを誤解していた、みたいに意図や理由があって行動していたと思ったりする。それは時には、「見抜けたはず」「見る目がなかった」という非難につながりもする。だけど、愛と暴力は、対極にあるのではないし、そして紙一重でも裏表でもないのだと思う。それらはもっと入り交じって混沌としたものかもしれない。
春は、長らく二つの小説について考え続けている。
宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』と、失踪した父親が書こうとした小説である。
この小説の中で『銀河鉄道の夜』は、何度も読み直される。第一稿から第四稿まであり、よく知られている小説なのに実は未完であるこの小説について、春は何度か気になる場面を引用し、同じく文学を研究する友人たちと、恋人の亜紀と、信頼を感じる吉沢と、それぞれに話し合う。
いくつかの文学作品を読み直し、読み方について何度も語るこの小説は、恋愛の関係をめぐる物語としては、少々変わっているかもしれない。
夏休みに偶然会ってから話すようになった大学院で同期の売野は、「十代の頃にすごく売れた日本の小説」について話し(あの小説&映画のことだとすぐわかる人も多いと思うが、売野の「あらすじ紹介」は少し違った印象になっている)、春と過ごす一夜に『されどわれらが日々』『ノルウェイの森』について話す。そのとき語られるのは、作者の視点、登場人物の視点、売野の視点の三層から見えてくるなにか、そして売野の経験と結びついた男女と恋愛へのまなざしだ。「十代の頃にすごく売れた日本の小説」が「視点」が重要な仕掛けになっているのが示唆的だが、この小説の中で「誰かによって語られる小説」のバリエーションは、ミステリー的な仕掛けや、別の人から見ればまったく違った見方になる、ということではない。
語る彼ら自身が、その小説を通して表れてくるのだ。
吉沢は、春の語る『銀河鉄道の夜』を聞いて、春が書いた小説を読み、春と対話する中で、別れた妻や娘との関係を思う。篠田は、春が「好きすぎる」という福永武彦の『秋の嘆き』を読み、彼が春に語ることを通じて、春は自分の奥底にあったものに気づく。
読むこと、読まれること、話すこと、話されることが、春という一人の人を少しずつ変え、閉ざされていた心を少しずつ外の世界へと押し出していく。
この物語に至る前にも何度も読まれたのは、父が唯一残した手紙である。父の妹である叔母から届いた手紙、そして子供だった自分の書いた文章を読むことで、春は自分自身の謎を解いていく。
『銀河鉄道の夜』の改稿について質問する春に対して、いちばん始めに書いた部分は「動機」ではないか、と吉沢は言う。それは『ファーストラヴ』で父親を刺殺した女子大生が取り調べで言う、あの印象的な「動機はそちらで見つけてください」と響き合う。
人はきっと、最初から明確にわかっていてそのように行動するわけではない。自分の行動の理由を、理解しているわけではない。その人が言った「理由」がいつも真実とも限らない。そして真実ではないからと言って意図的な「嘘」とも限らない。
私は、この小説を単行本が刊行されてすぐに読んだ。二年近い時間を経て、私も「読み直し」「語り直す」ことを身をもって体験した。
最初に読んだときとは印象が違うところがあった。特に、春と売野のやりとりの場面では(二人の声がするすると聞こえてきて、どの場面も好きだ)、思い浮かべる経験や身近な人の顔が増えたり違ったりした。それは、二年という短くも思える年月のあいだに、個人的にも、世の中のできごととしても、違う経験をしたからだろう。
この小説が二〇二〇年の夏を描いていることも、二〇二三年の私にはいっそう深い意味があると感じられた。
人と会うことが困難であるからこそ貴重だった日々、大人数の飲み会では深く話すこともなかっただろう人との関わり、一人と向き合うからこそ交わされる言葉。二〇二〇年の夏でなければ、生まれなかったことかもしれない。
春と売野が宿泊する千駄ケ谷のホテルと周囲の光景は、オリンピックが延期されて空虚な場所であることが、春にとってはめずらしい、女友達と過ごす貴重な時間をより印象的にしている。
この小説が書かれた時にも、さらには単行本が刊行された二〇二一年の七月でさえ開会式の直前まで、「東京2020オリンピック」がほんとうに開かれるのか半信半疑だった人は多いのではないかと思う。文庫で読む今は、オリンピックがこの翌年に開催されたことを知っている。あの先の見えない日々の感覚を久々に思いだしたかもしれない。そこにもまた、時間を経て読むことで生じる「読み直し」がある。
二〇二三年に読んだ私は、この小説はなにより子供の無力さを書いたものだったのだ、と強く思った。
この原稿を書く直前に、私自身が子供のときの経験を書く機会があって、そうか、あれは無力だったから、無力であることを思い知らされたからあれほどつらかったのだと思い当たったことも大きい。
子供のころの春の周りにいた大人たちは、あまりに幼稚で身勝手である。もしかしたら、この小説が始まる前の時期、十代のころに、周囲に気を遣い感情をあまり出さない春のことを、彼らよりもよほど大人だよ、などと軽々しくわかったようなことを言う人もいたかもと想像する(子供、特に少女を「精神的には大人」と都合のいいことを言う大人はよくいる)。
断言したいのは、彼女はそのとき子供だったことだ。自分で生活することも、今日の夜にどこで誰といるかを選ぶこともできなかった。状況を理解して、ちゃんと助けてくれる人を探すこともできない、圧倒的に無力な子供だった。一人の子供を安心できる環境におくべき大人が、それをしなかった。その深い傷を、損なわれた心を、彼女自身が「読み直す」ことでようやく自分の生を生きていく小説なのだと思う。
春の父とその妹は、「救われたい」と思ったから「神さま」を求めたのだろうか。「神さま」に従えば誰かを救えると思ったのだろうか。
救われたい、救いたいという気持ちは、売野が千駄ケ谷のホテルで話した「そういう危うい女の子たちが本当に救われたら男の子たちはどうするのかなっていうことかもしれない」にも、亜紀が春にまだ話していない過去とも、つながっていく。
ほんとうは自分自身の傷を見なければならないのに、見ることが怖いから、それを誰かを救うことにすり替えてしまっている人は意外に多いのかもしれない。すり替えたいから、救うべき誰かを見つけたいのかもしれない。
それが恋愛の始まりだったとして、その先にはいくつか展開する可能性がある。どの可能性へ向かっていくかは、まだ、わからない。
小説の最後、春は亜紀との始まりを自分自身で語ろうとする。
いくつもの物語を読み直し、語り直す人たちの思いを受け取ったあとの春が、今の自分で、今の自分の言葉で、自分をどう綴っていくのか。
「文庫版あとがき」で島本さんが書いているように、改稿されたこの小説を読むことが、彼女の物語を受け取ることになるのだと思う。