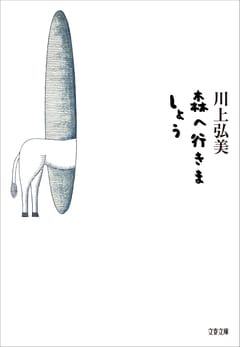幸田文の八十六歳の生涯は、ちょうど真ん中の四十三歳で、前半と後半があざやかにきりかわっている。父親の幸田露伴の死をきっかけに、家族の面倒に追われる日々から、ジャーナリズムでもてはやされる随筆家、作家へと立場が一変したのだ。
宮大工の意地を描いた小説「五重塔」が有名な幸田露伴は、尾崎紅葉、夏目漱石、森鷗外と並ぶ文豪であった。中国や日本の古典の知識が豊かで、歴史小説や芭蕉の俳諧の注釈にも力を注いだ。一方で、すぐれた都市文明論「一国の首都」を、すでに十九世紀末に展開する論理的な思考の持ち主だった。一九四七(昭和二十二)年に亡くなった時、「国葬に」という声があがったほど尊敬されていた。
幸田文は、そんな父親について後世の研究者の参考になればとつづった文章が絶賛されて、書き続けるうちに、内容は父親の回想記からはみ出て、エッセーや小説、ルポルタージュと活躍したのだ。苦労が続いた前半生が、後半生の執筆の土壌になった。
父親に教えられた、周囲を正確に観察する眼、世間にとらわれない思考、豊かな言語感覚。静かにためこんできたそれらが発酵し、独自の味わいの文章をはぐくんだ。
幸田文は、一九〇四(明治三十七)年九月一日、露伴の次女として生まれた。
暴風雨のさなかに生まれたと、幼いときから言い聞かされた。近所の男の子たちの先頭にたって遊ぶ元気のいい女の子は、大自然のエネルギーと一体化した荒々しい強さを自分の中に感じていたのだろう。
幸田家は、もとは徳川家に仕える幕臣で、江戸城で代々、坊主衆をつとめた。露伴の兄弟妹は、実業家、探検家、学者、音楽家と、幅広い分野で実績を残した。上の妹の幸田延(のぶ)は、日本の「楽壇の母」といわれたほどだったし、下の妹の安藤幸(こう)はバイオリニストで、「日本芸術院会員三兄妹」として知られた。才能と努力で道を切り開いたパワフルな一族の血が、文にも伝わっていた。
文が五歳のとき、実母が病死した。二年後に姉が病死、露伴は再婚する。教育者だった継母と露伴は不仲だった。家事が苦手な継母にかわって、父親の露伴は、女学校に通い始めた娘に、性教育から家事までの生活全般のことを自分で教えこんだ。
また、娘にカメラを与えて、周囲にある美を見つめるようにしむけたこともある。俳句も写生が大事と教えた。周囲を観察し、物事の本質をみきわめる姿勢を鍛えたのだ。
女学校のころから、文はほとんど家政を代行する。二歳年下の弟は、結核で十九歳で亡くなった。若いほど感染の危険が大きくなる。にもかかわらず文に看病がまかされた。冷たい家庭での、姉弟の交流を、のちに小説「おとうと」として書いている。
文は二十四歳で、文化的な仕事を敬遠して、酒問屋の息子と結婚する。翌年には、娘の玉が生まれる。夫とは心が行き違い、三十三歳のときに離婚。娘を連れて実家にもどったあとは、気難しく怒りっぽい父親の面倒をみるのに追われた。
晩年の露伴は、目が悪く、編集者らが口述筆記をしていた。文は、ふすまをへだてて話を聞いていた。夕食後、機嫌がいいときの露伴は、家族を相手にさまざまな話を興味深く語り、一時期は芭蕉の俳諧集の講義をしたこともある。
太平洋戦争末期。長野県に疎開しているとき、東京・小石川の自宅が戦災で焼失した。戦後は、千葉県の菅野の狭い住宅で、病気の露伴の介護をした。
文の最初の文章は、一九四七年、幸田露伴の八十歳記念号(「芸林閒歩」)のために日常を描いた「雑記」だった。雑誌の発行前に露伴は亡くなり、そのまま追悼号になった。続いて死の前後をつづった文章を発表する。父と娘の間に緊張感がはりつめながら、情愛がほとばしるさまが描かれた。
求めに応じて書いていくうち、父親の生活哲学だけでなく、自分の子供時代の思い出にまで、文章の内容は広がった。さすが露伴の娘と、もちあげられる一方で、悪口がまじるようになった一九五〇年春、人気のまっただなかで、突然、文は筆を断つと宣言し、仕事を連載中のものにしぼってしまう。
数年後に執筆を再開したあとは、芸者置屋に家事手伝いとして住み込んだ経験を生かして書いた小説「流れる」が高く評価され、自分が独自の世界をもつ作家であることを世間に認めさせたのだ。
五十代には、人気作家として、小説だけでなく、ルポルタージュや座談会、ラジオ出演など、活動の幅をいっそう広げた。
六十代になっても、エネルギーは衰えなかった。奈良・斑鳩(いかるが)の法輪寺三重塔の再建がとどこおっているのを知ると、寄付金集めに尽力し、現地に住み込んで完成を見届けた。露伴の「五重塔」の印税で暮らしてきたという思いが背景にあった。
宮大工から聞いたひのきなどの話から樹木全般へ関心を広げ、七十歳近くになってから、日本全国の巨木や樹林を訪ね歩いた。山地崩壊が目につくと、時には背負われてまで山奥に行き、各地の崩れのさまを自分の目で確かめた。
なにごとも力いっぱいで取り組む「渾身」を父親から教えられた幸田文は、気概と行動力の作家になった。そのパワーは、母親の死後、『幸田文全集』(岩波書店)発刊をきっかけに随筆を書き始めた娘の青木玉、小説やエッセーを書く孫の青木奈緖にまで受け継がれている。
父親の露伴が文をどのように教育したか、その土壌からどのように才能が開花したか。よくわかるのが、この選集第一部の「啐啄」「あとみよそわか」「水」「このよがくもん」など初期のものだ。座談の名人だった露伴から無意識に学んだ言葉遣いの呼吸が、ユーモアをにじませている。
露伴は、儒学の思想「格物致知(かくぶつちち)」を、とりわけ大事にした。物やできごとにそって知識を獲得する、周囲を観察し奥の原理をみつけていく。徹底した実践教育である。
父親が娘に性教育する「啐啄」は、露伴流の教育の始まりといってもいい。「啐」は、もとは卵の中のひなが鳴くこと、「啄」は親鳥が卵のからをつついて割ること、両方のタイミングがぴったりあって、ひなが誕生する。
女学校に入学したころ、十二歳の春のある日、露伴は、「おまえ、ほら、男と女のあのこと知ってるだろ」と問いかける。何気ないひとことがシュッとすられたマッチの火となって、授業で習った花の受精、鳥や犬の性欲と、近所の花柳街や道に落ちているゴム製品まで、さまざまなことが、一直線に人間の性欲とつながって照らし出された。
娘が性に関心を持ち始める時機をのがさず、親が肝要なことを伝える。それを「啐啄同時」とは、ぴたりとした表現ではないか。
露伴は猥談の小咄もときどき聞かせた。継母が処女の羞恥心がなくなると心配すると、なまの羞恥心ぐらいあぶないものはない、親の聞かせる猥談ほど大丈夫な猥談は、どこを捜したって無いと切り返した。本質から目をそらさず、「正直な態度でよく見ること」を、後年、今度は文が娘の玉に伝えている。
同じ年の夏には家事の訓練が始まった。
「あとみよそわか」では、まずそうじ道具をきちんと整えるという基本から取り組ませている。「水」では、水は恐ろしいものだから、根性のぬるいやつには水は使えない、と警告する。口だけでなく、自ら掃き掃除や雑巾がけをやってみせる。その身のこなしはすっきりとしていて、娘を感動させるのだ。やらせて見る、やって見せる、も一度やらせて見る。露伴は、そうして教え込んだ。
自分で教えられないときは、「このよがくもん」にあるように、学問にも世俗にも通じた人に、いわゆる社会見学を頼んだ。浅草の盛り場をあちこち歩きまわり、雷おこしの材料は何か、店員の給料はいくらだとか話していくのだ。講談や安来節(やすぎぶし)の舞台まで見た。
「金魚」は、出入りの魚屋さんの包丁さばきを真似して、金魚を料理してしまう話。何事も実行する実践教育が、解剖まがいの行為にまでつながったのかもしれない。
「あしおと」「ふじ」は、女学校時代の話。継母の紹介で入学した女子学院は、木造二階建ての洋館で、白いペンキ塗りに深緑の縁どりがあるしゃれたものだった。ここでの五年間は、文にとって楽園の時期だった。思春期の少女たちの友情や同性へのあこがれ、性の芽生えのようなものが、素直に回想されている。
「申し子」では、汽車の中で知り合った青年に誘われ、暇つぶしに乗客の職業などあてて遊ぶ。最後に互いを当てあうのだが、青年は彼女の正体がいいあてられない。しかし、青年のいった「蓮葉のようでいながら堅苦しく、ちゃんとした家庭のようなくせに野蛮」という印象は、若き日の幸田文の姿をほうふつとさせる。
「平ったい期間」は離婚後の時期をふりかえっている。出戻って落ち込んでいる娘に、露伴がお茶や踊りの虎の巻などについて学んできて、自分に教えるようにいいつける。しばらく稽古通いをするが、目的は果たさないまま終わる。あれは何の意味があったのかと不思議がるのだ。遊芸で娘を慰めようとする露伴の作戦だったのか。
「終焉」は、露伴の死の直後に書かれた一つだ。露伴は生死を達観して、空襲のときも防空壕がわりの押入に入るのをいやがった。「死なれたくない」一心の娘と、逃げるかどうかで厳しいやりとりをした。幼い時から「愛されざるの子」「不肖の子」だという劣等感をもっていた文は、自分の言葉を拒むのはそれゆえかと悲しんだのだ。
しかし、最期近くの日々に、父親の柔らかいまなざしに長年のこだわりは溶けた。
死の三日前、ふたりは最後の会話をする。「おまえはいいかい」と聞かれ、文が「はい、よろしゅうございます」と答えると、露伴は「じゃあおれはもう死んじゃうよ」と別れを告げるのだ。見事な最期といっていい。
そして幸田文は、愛(いと)し子としての自信を取り戻して、後半生に向かっていく。
露伴は多くの文化人との交流があった。それぞれへの父親の人物評を紹介しながら、柳田泉を回想した「堅固なるひと」、同じく斎藤茂吉の「はにかみ」、近所に住んでいた永井荷風を訪ねた「すがの」、いずれも、いい人間スケッチになっている。
第二部では、鋭い観察眼が、さまざまな対象に光をあてている。
「むしん」は、お金を無心に来て断られ、捨て台詞を残して去った男を、道にまで出て見送る話。無気力な背中の男が、道端でする行動が滑稽かつ哀しい。
「おふゆさんの鯖」には、傷んでいないか心配な魚もあえて食べる女性が出てくる。料理の要点はふたつ、まっとうな味を知ること、腐敗のものや毒のものを知ること。これは、料理以外にも通じそうだ。料理が手早く上手だった生活人としての随筆は多いが「二月の味」もそのひとつ。
「風の記憶」は、小さな竜巻に出会った話、「金魚」はおまけにもらった金魚の顚末。竹の生命力に驚く「いのち」、厠(かわや)にいたねずみをちょっとユーモラスに描いた「午前二時」、動物園でオランウータンを愛(め)でた「類人猿」、競馬のトップではなく二番手に共感する「二番手」など、観察対象の多種多様さも、特徴だ。
自分の知らない表情を撮影してくれた写真家とのやりとりを描いた「知らない顔」、別れた男の欠点と思った部分が、男のその後の成功にむすびついたらと考える「捨てた男のよさ」、次女の寂しさと強さをふりかえった「次女」は、いずれも自分自身と向き合っている。
「杉」は、晩年に全国の樹木や崩れを訪ねた時期のもの。鹿児島県の屋久島の縄文杉を見に行ったのは、七十歳の時だ。「縄文杉は、正直にいうと、ひどくショッキングな姿をしていた」。異様な樹容にも、長ければ七千二百年といわれる樹齢にも圧倒され、「目からも心からもはみ出していて、始末がつかなかった」という。
山地崩壊を見た「崩れ」という随筆に、同様に自然のエネルギーにおびえたような場面がある。剛毅といってもいい部分をもつ作家も、自らの老いや寿命を無意識に投影するようになったのではないか。
第三部の「週間日記」は、一九六四年の正月前後のもの。原稿に追われつつ、家事もこなす忙しさが見える。
人生相談「なやんでいます」への答えは、六十歳ごろのもの。店員がボーナスを無駄遣いするか心配する商店の主婦、太っているのが悩みの十五歳の女の子、ケチな夫に困った妻、夫と同じ会社の女性との交際に悩む妻に答えている。いずれも、質問者へ遠慮なく明快な答えを出している。気力、胆力のほどがうかがえる。
文庫化にあたっての付記
幸田文は、父親や経験から会得したものを、いったん体内に取り込んでから言語化している。そのためか、読みながら文章の呼吸のリズムが身体の奥底に共振し、体験を共有するような感覚さえ生まれる。
この十年余り。社会のデジタル化が加速して、あらゆる生活環境は激変しつつある。十九世紀生まれの幸田露伴が身をもって娘に伝えたような家事や生活知識は、動画付きの情報としてたやすく手に入るようになった。
与えられた膨大なデータからさまざまなコンテンツを作り出し、個別な要求に応えてくれる生成AIの時代とさえいわれる。しかし作り出されたものや答えが「まっとうな」ものかどうか、受け手には判断できない。ましてや、自然としての水を畏怖することから水掃除を教え始めた露伴のように、事象の奥をさぐる姿勢、生活哲学を鍛えてくれるとはとても期待しにくい。
科学によって薄く引き延ばされた「身体性」が、大きな疫病、地震などの自然災害、戦争などの危機に直面したとき、大きな混乱が予想される。そのとき、幸田文の文章は、世紀を超えて、生活の原点を考え直す手がかりを与えてくれるものではないか。
二〇二三年七月