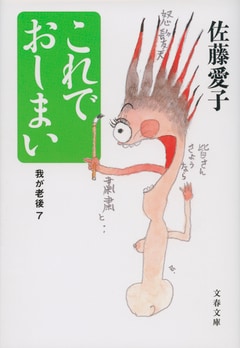オール讀物に「晩鐘」を書いたのが、私の最後の小説です。何年頃だったか思い出すのが面倒です。調べればいいのですが、なにも大作家じゃなし、そんなことどうでもエエやないの、といいたくなってしまいます。何もかも面倒くさい。億劫です。
秋になれば私は九十八歳になります。九十八という歳はつまり、そんな歳なんですね。何もかも面倒くさい。なるようになればよろしい、と思ってしまう。大雑把な記憶ははっきりしているけれど、細かいこととなるとわからなくなる。わからなくても別に困らないから、わからないままにほうっておく。人の名前なんて、覚える必要を感じないので覚えません。忘れるのではなく、ハナから覚える気がないのです。それでも以前は顔は覚えましたけれど、今は顔も覚えない。
「ごめんなさい。すっかりボケてしまって」
といえばそれですみます。家の者はそれに馴れて、すっかりボケ婆さんあつかいを心得ているのがいっそ気らくでいいのです。
「晩鐘」を書き終えた後、することもなくぼんやりしていました。そこへ小学館の女性週刊誌から七枚ばかりのエッセイの連載依頼が来ました。丁度、暇でしたので「エッセイ」なんて上等のものではなく、ただの身辺雑記なら気らくに書いてもいいという軽い気持で引き受けました。軽い気持で引き受けたので、連載の期間などは決めていませんでした。だらだらとつづけているうちに、驚いたことには七年の歳月が経っていて、ひと頃は軽く書けていたのが、次第に呻吟するようになって来ました。初めの頃は毎週書いていたのが隔週になり、隔週書くのも苦しくなって「今週はお休み」になり、それがつづいたりしているうちに「書ける時に書く」という至極身勝手な運びになりました。担当のKさんは寡黙な人物で、催促というものは一向にしないし、無理なようならやめにしますか、ともいわず、ただ、「原稿出来ました」という私の電話を待っているというあんばいで、作家としてはまことに有難い稀有なお方でした。しかし別の考え方からいうと、編集部では私の身辺雑記など「あってもなくてもいい雑文」になっていたからだろう、中止をいい出すと怒り出されると思っていえなかったのではという友達がいて、「あっ! なるほど」と思い、最後の原稿を渡した時、Kさんにそのことをいいますと、
「いや、そ、そんなことは決して」
と吃って、ひたすら恐縮しているのでしたが、そんな時に、「いや、実はそうでした」などという正直者の編集者はまずどこを探してもいないでしょうね。
そうして私の作家活動は終止符を打ったわけですよ。あの「締切」に追われるというやつ、あれは本当に寿命を縮めます。Kさんのような温和で寡黙な人は、一言も何もいいませんでしたが、いわれなくてもこちらとしては、頭の中でひねもす勝手に「締切締切」とひそひそ声が呟いているのです。こう見えても私は律儀なタチで、一旦とり決めたことは不眠不休で守らねばならぬ、という決意を持っているもので、およそ五十年か六十年を、「締切」に呪縛されて生きて来たといってもいいくらいなのです。
作家の中には締切無視をしても一向に寿命の縮まらない野坂昭如さんのような大人物もいましたが、私はこう見えて小心者なのです。
昭和何年頃だったか忘れましたが、毎日新聞に野坂さんが連載小説を書いていて、同時に私は雑文を連載していたことがあります。ファクシミリなんて結構なものがない時代でしたから、たいていの雑誌社、新聞社は担当かオートバイに乗ったお使いさんが原稿を受け取りに来ていました。