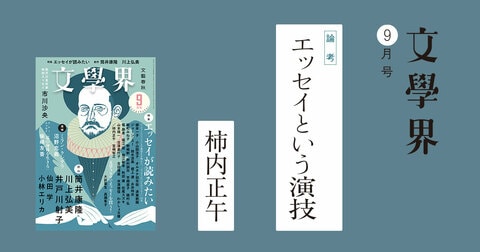子供がうつらうつらしはじめたところで、琴音は足を組み直した。太ももに手をのせ、ピアノの屋根の上、四つの写真立てを眺める。端から順に、子供の写真、家族の写真、子供の写真、子供の写真。メトロノームは隣の食器棚の中、ワイングラスの横に並んでいる。琴音は腕時計を見おろすとため息をつき、子供の横顔を見つめた。頭がゆらゆらと前に傾いて楽譜にあたりそうになると、子供はびくついて目を開いた。
「寝てたでしょ」
琴音が言うと、子供は目をつむったまま、にやりとした。
「疲れちゃった?」
子供は曖昧にうなずいて言った。
「走ったから」
「走ったの」
「体育で」
「そうなんだ」
「マラソン大会あるから」
「マラソン大会?」
「一月二十三日」
「そうなんだ」
琴音はバイエルに手を伸ばし、前のページをくりながら、
「寒いのに、大変だね」
と言った。子供はため息をつき、尻をもぞもぞと動かした。
「じゃあここ、ここからさっきまでのところ、続けて一回やってみようか。そしたら今日は、もうおしまい」
そのとき玄関のドアが開く音がした。子供はそろそろとピアノを弾き始め、途中でやめ、指で楽譜をなぞり、ひぃ、ふぅ、みぃと音符を数え、また弾き、中断し、ひぃ、ふう、みぃ、と数え、ひと息つくと鍵盤を押した。母親がそっとリビングの扉を開け、静かに部屋に入ってきた。琴音は振り向き、母親が手に下げているケーキの箱に目を走らせた。二人は声を出さずに笑顔を交わすと、会釈をした。
「それで、先生にお伝えしないといけないんですけど」母親は隣に座る子供の顔を覗き込んで言った。「ね、先生に言わなきゃいけないことがあるんだよね?」
子供はフォークをくわえながら首をかしげ、ぼりぼりと頬をかいた。そしてそのまま押し黙った。
「もー、自分から言うって、昨日約束したでしょ」
母親は笑いながら言った。
「先生、大変申し訳ないんですけど、先週お聞きした、来年の発表会、今回は、欠席させていただきたくて」
「えっ、そうなんですか」
琴音は目を丸くした。
「すみません……」母親は頭を下げ、ショートケーキにフォークをあてた。
「えー、そうなんですね……」琴音は鎖骨にかかる髪を二本の指で挟み、背中へはらった。「てっきり、参加されるんだと思ってました」
「私もそう思っていたんですけど」母親はフォークを口に運び、「ゆあなが急に、出たくないって言い出しちゃって」
皿に残るクリームをフォークでかき集める子供を、母親は憐れむような目で見た。
「ゆあなちゃん、発表会、いやになっちゃったの?」
琴音がテーブルに身を乗り出して言うと、子供は上目に琴音を見て頷いた。
「そうなんだ。どうして、嫌になっちゃったの?」
子供はフォークを口に入れたまま、うつろな目を宙に向けた。
「この間の発表会で、ゆあなよりずっと小さい子が上手に弾いてるのを見て、恥ずかしくなっちゃったみたいで」
母親が言った。
「ゆあなちゃん、そうなの?」
子供がフォークを口から離すと、その先端からよだれが糸のように伸びた。
「気にすることないのに」琴音は子供に笑いかけて言った。「発表会は三月だし、まだまだいっぱい時間あるよ。ゆあなちゃんの弾きたいなって曲をいまから練習していけば、全然間に合うよ。他の子のことなんか、気にしないでいいのに。ゆあなちゃんの弾きたい曲を弾いたら、それでいいんだよ」
「弾きたい曲、ないんだもん」
子供はふてくされたように言った。母親は短く笑った。
「そっかあ。弾きたい曲、ないのかあ」
琴音は明るく言い、母親と笑い合った。
「自分が練習しないのがいけないのにねえ。下手でもいいから、逃げないで、出て欲しいんですけどねえ」
「はい」琴音は力強く頷いた。「私も、出てほしいです」
「でもねえ、そうやって無理強いして、嫌な思い出を作ってしまうのも、違うのかなって……」母親は微笑みながら子供を見た。「それにこの人ガンコさんだから、一回言い出すと、何言っても聞かないんです。それで今回は……、すみません」
母親はケーキに向かって頭を下げてから、切り分けたそれを口の中にしまった。
「わかりました。じゃあ運営の方には私から伝えときますね」琴音は紅茶へ口をつけてから子供の方へ体を向けた。「でもゆあなちゃん、次は絶対に出ようね。いまから練習すれば、まだ一年以上あるから。一緒に弾きたい曲探して、次はそれを発表会で弾けるようにしよう?」
子供はフォークを皿の上に置くと、悠然とした足取りでリビングを出て行った。少しして戻ってくると、母親へ寄りかかって身をくねらせ、手に持ったノートを開いたり閉じたりした。
「なあに、聞こえない」母親は子供の口元に耳を近づけて言った。「見せてもいいかって? もー、そんなの自分で聞いてよ。すみません先生、ゆあなが、どうしても先生に見てもらいたいらしくって」
「私に? なんだろう、見せてー」
琴音が両手を広げると、
「ゆあなが描いたマンガなんですけど」母親は言った。「今回、自信作らしくて」
「さすが」
小林が言うと、琴音はスマホをスピーカーにしてテーブルに置いた。
「まじかと思ったよね。ふつう、ここでマンガ見せる? って」
「面白かった?」
「なわけないじゃん。子供のラクガキだよ。字が汚くて、セリフも読めなかった。おっ」
「どうした」
「や、いまネイル塗ってて、これ発色いいわ。安かった割に」
「好きだね。どうせすぐ落とすのに」
「そうなんだけど」琴音はテーブルに置いた右手の小指に顔を近づけた。「あーほんと、ピアニストより、ネイリストになりたかった」
「ピアニストでもないじゃん」
「ん?」
「ごめんごめん」
「てか、それはお互い様だよね」
「まあね、うちら無能コンビだから」
「は?」
「手塚に言われたじゃん、高校の、文化祭のとき」
「あー、手塚。よく覚えてんね」
「わすれらんないよ。一生覚えてるから」
「文化祭かあ、なつかしいね」
琴音は言った。
「うちらほど何もやらなかった子もいないって言われた、手塚に」
「えー、あたし手塚のこと、何にも覚えてない」
「うそでしょ」
「文化祭といえば、クラスでクレープやったじゃん。かっちゃんにクレープいっぱい作ってもらって食べたのは覚えてる」
琴音は右手をパタパタと動かした。
「かっちゃんね」
「あの日で、クレープ一生分食べたもん」
「元気かな、かっちゃん」
「ねー。まったく連絡とってない」
「まだ作曲、してんのかな」
「ああ、ね。なんだっけ。異名みたいな、あったよね……」
「いみょ?」
小林は聞き返した。
「あだ名みたいなの、あったじゃん」
「藪高のモーツァルト」
「そうだっけ。ショパンじゃなかったっけ」
「どっちだっけ」
「わかんない」
「いや思い出した、かっちゃん、自分ではグリーグがいいって言ってた」
「なんでグリーグ」
「恥ずかしいからグリーグにしてって言われた」
「えー」
「言われた、思い出した」
「ちょっと変わってたよね、かっちゃん」
「ちょっとじゃないよ、超変わってたよ」
「まあね」
「あと、ハローカティ」
「あー、はいはい。え? カトーキティじゃなかったっけ」
「どっちでもいいんだよ。どっちもあったから」
「そうなんだ」
「好きだったよねえ、キティちゃん。いまでも集めてんのかな」
「もう三十過ぎだよ」
「いや、関係ないっしょ」小林は言った。「三歳の時からキティ一筋だって言ってたし」
「いつ?」
「高一のとき」
「よく覚えてんね」
「入学したとき、あの子、クラスの子みんなに、サンリオキャラの中で何が一番好きー? って聞いて回ってたんだよ」
「そうなんだ」
「うちがマイメロディって言ったら、なんでみんなマイメロディなのー? もー、やだー、キティちゃんでしょー、つって。……でもさあ、一年とき、クリスマス会あったじゃん」
「うん」
「あんとき赤鼻のトナカイをワルツにしてきたの、あれはすごかったね。大高先生も感心してたし。大学行ったら作曲勉強したいって言ってたもんね」
「えー、でもかっちゃんて、大学行ったっけ。行かなかったよね」
琴音は言った。それから顔をうつむけて左手に取りかかった。
「だから、親が破産しちゃったから」
「えー、そうだったんだ」
琴音は手をとめ、顔をあげてスマホを見た。
「知らなかったの? リーマンショックで会社、潰れちゃったんだよ」
小林は言い、ごそごそと硬いものが擦れ合うような音がした。
「そうなんだ。それで行かなかったんだ」
「うちのクラスで就職したのって、あの子だけだよ」
「そうなんだ」
「なんか工場の、なんの工場か忘れたけど、なんか作ってる工場の事務やってるって言ってたよ。カメの結婚式のとき」
「えー」
「まじで知らなかったの」
「うん」
「へえ……」
「じゃあ大変だったんだ、かっちゃん」
琴音はせりふを棒読みするように言った。
「そうだよ。うちらが大学で遊んでた頃、あの子は働いてたんだよ」
「そうなんだ」
「いまは知らないけど」
「えー」
「そうですよ」
「うん……」琴音は塗り終えた親指を見下ろした。「じゃあまあ、そういうことなんで、市田ゆあなは、今回は出ませんから」
「オッケ。でもさ、そういう、ゆるい子の方がいいよね。めっちゃ気合い入って、コンクールがどうのこうの言ってくるのより」
「それはそうだけど、でもさあ、なんか過保護っていうか、あまいっていうか……。メトロノームの話、したっけ?」
琴音は人差し指を塗り始めた。
「してない」
小林は言った。
「ピアノの上にさ、普通、メトロノームって置くじゃん。ていうか、あたし一回、言ったんだよ。メトロノーム買ってくださいって。したら買ってくれたはいいんだけど、それずっと食器棚に入ってて、皿とかグラスみたいに仕舞われてんの。で、ピアノの上には家族の写真がずらーってあって」
「ふうん」
「おかしくない?」
「別に、めずらしくないじゃん」
「なんでよ。あたしなんか小さい時、メトロノーム以外の物置いたら、めっちゃ怒られたんだけど」
「お母さんに?」
「一回、ぬいぐるみ置いてたら、ぶん投げられて。ピアノが汚れるでしょって。ふざけるならピアノに触るなって怒鳴られたもん」
「こわ」
「めっちゃ怖かった」
「お母さん、そんなに怖かったの」
「中学くらいまではね。あたしに自分の夢かけてた人だから。でも全然才能ないってわかってから、言ってこなくなったけど」
「あー、わかる」
「だからあの家でゆあながグズグズやってんのみると、子供の頃思い出して、嫌なんだよね」
中指を塗りながら、琴音はわずかに顔をしかめた。
「でも終わったら、ケーキ食べれるんでしょ?」
「うん」
「じゃあ、いいじゃん」
「たしかに」
琴音は言った。
「そういや、お母さん元気?」
「うん一応。会えば、どこが痛いとかしんどいとか言ってくるけど」
「病気?」
「老化だと思う」
「大事にしてあげないと」
「うん」
「ひとり娘なんだから」
「えー……」
「話戻るけど、その子、そんなにやる気ないなら、そろそろやめるって言い出しそう」
「やめて、言わないで」
「時間の問題だな」
「やめてよ、自分でもちょっと思ってんだから」
「くっ。でもさあ、ほんとに辞めるかもしれないしさ、いまのうち稼いどいた方がいいよ。じゃっ、バイトする?」
「なに急に」
琴音は薬指を塗りながら言った。
「一日だけなんだけど」
「なんの?」
琴音は顔をあげ、スマホを見た。
「よし子の伴奏」
「よし子? よし子って、あの、ヤキソバ頭の?」
「そーそー。さっき連絡あって頼まれたんだけど、うち、その日ダメだからさ」
「いつ?」
「二十四」
「来月の?」
「今月」
「今月って……、イブじゃん」
「やっぱ無理? 用事あるんだっけ」
「それは二十五だから、いいんだけど……」琴音はブラシをボトルに戻し、テーブルの端の手帳を手のひらで引き寄せると、親指と人差し指でつまむようにしてページを開いた。「あっ、まって、友達と会うんだった」
「だれよ」
「中学の。優っていうんだけど、覚えてない? 高校の時、一回、電車で会ったことあるんだけど」
「わかんない」
「その子から、この間の誕生日にLINEきてさ、イブに予定ないって話したら、家来なよって言ってくれて」
「ふうん」
「もう結構、会ってないんだけどね。二、三年とかぶり。子供も一人いて、たぶん小学生になってる」
「何歳で産んだん」
「二十五とか。結婚はもっと早かったよ。あたしが大学出た年だから……、二十三か」
「ふうん」
「子供にクリスマスプレゼント、持ってったほうがいいよね?」
琴音は手帳を閉じて言った。
「そうなん」
「そうでしょ。何がいいと思う」
「何歳だっけ」
「六、七歳とか」
「小一?」
「たぶん」
「地球儀」
小林は言った。
「は?」
「地球儀」
「地球儀? なんで」
「知育グッズだし、見た目の割に安いし」
「そうなんだ」
「親ウケが大事だからね、そういうのは。で、何時から会うの、その日は」
「まだ決めてないけど、五時くらいじゃん」
「五時? いけるいける。一時から二時半までだから」
「えー、何曲やんの」
「八曲、だったような」
「そんなにあんの、やだ」
「まだ二週間あるし、いけるっしょ」
琴音はボトルのフチでブラシをしごきながら薄く笑い、いけないから、と言った。
「そんなこと言ってないで、ここで顔売っといた方がいいって。よし子、ちょいちょい仕事くれるし。それにいま、息子も歌手やってるから。気に入られたら、親子で仕事くれるよ」
「えー、ちゃんと話したことないんだよね、よし子」
「大丈夫、怖い人じゃないよ。ちょっと頭がアレだけど」
「なにそれ」
「なんか言われても、はーいって流せばオッケーだから」
「えー、場所は?」
「Hのケアホーム」
「どこそこ」
「茨城」
「えー、やだ」
「大丈夫、車で連れてってくれるから」
「だいたいなんで、コバ、行かないの。平日でしょ」
「まあ、結婚記念日だからさ、どっか行こうって話になって」
「なにそれ、新婚かよ」
「すみません、新婚で」
「許さん」
「お願いしますよ」
「えー」
「ピアノ、弾いてくれませんか」
「どうしよっかなあ」
「お願いしますよ」小林は言った。「クリスマスに家に帰れない老人たちのために、弾いてやってくださいよ」
「最低なんだけど」
そう言うと琴音は短く笑った。
(続きは、「文學界」2023年10月号でお楽しみください)