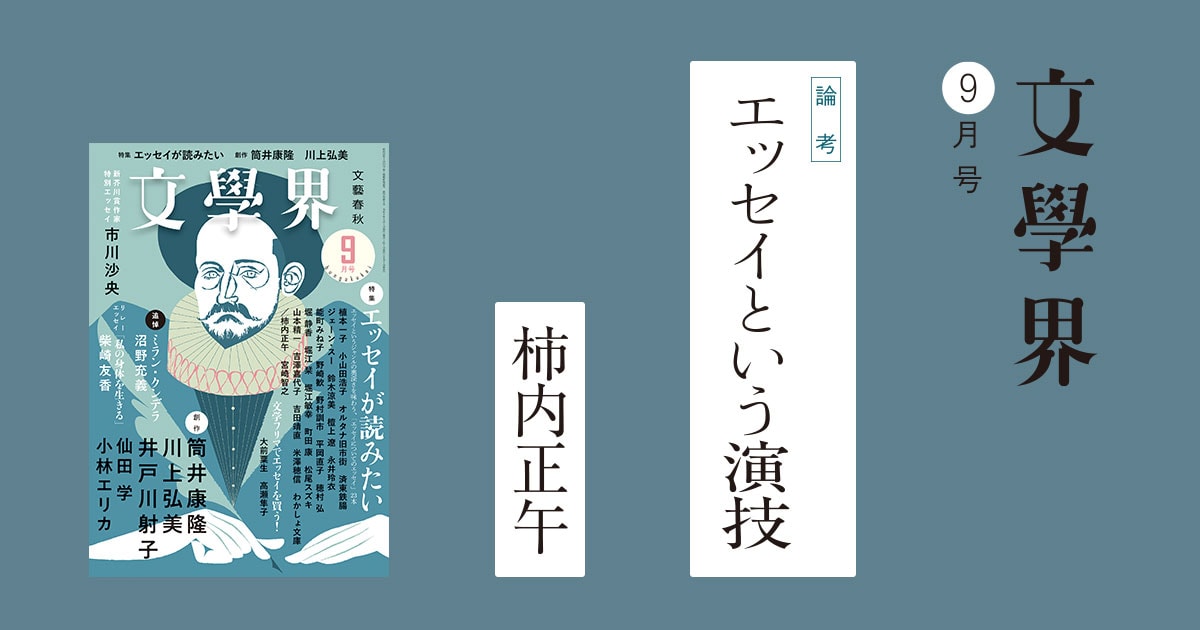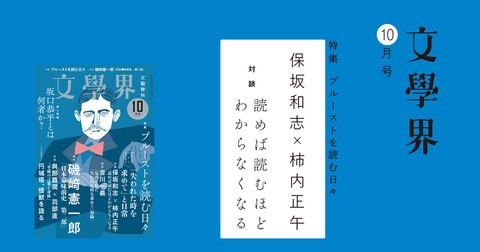二〇一八年一一月から毎日の日記をインターネット上に公開している。この日記を紙に印刷して、現在に至るまでに商業で一冊、自主制作で三冊発表までしている。僕はひとまず日記を公開し、販売さえする個人である。そのくせ僕は近年の日記ひいては随筆まわりの読書熱に対してどこか懐疑的である。読み手としての日記への不信と、書き手としての日記の使用。この一見矛盾するような事態をへっちゃらな顔で放置できてしまっているのはなぜだろうか。個人的な理路を解きほぐしていくなかで、エッセイという茫漠とした文芸ジャンルのぐるりを素描できればいいなと思っている。
日記や随筆、エッセイという言葉を僕はふだんあまり区別しないで使っている。後述するがとくに日本語文化圏においては物語も評論も随筆もすべて日記から派生していったものであると考えているからだ。もちろんすべての文芸の起源は日記であるとまでぶちあげるつもりはない。日記は一面であり、もう一面には歌があるのだが、この与太話は今度にしよう。ひとまず日記と随筆の話である。これらは一括して次のようなものと捉えてもいいと思う――書き手と作中主体とを同一視することを自明の前提として読むような文章形態。
さて、僕が違和を感じているのは、その良し悪しの判断基準だ。「ほんとうのこと」、「嘘がない」、「ありのまま」――随筆や日記を評価する際、このような言葉が肯定的な文脈で使用されることが多い。これは随筆や日記に限らないようにさえ思う。正直な人が好き、みたいな人物評から、魂を削って作っている、みたいな創作全般へのロマンチックな幻想まで、素材をそのままお出しした方がいいという価値判断は僕たちの生活の場にありふれている。僕は、これが好きじゃないのだ。
九〇年代生まれの僕が小学生の頃だ。テレビでバカという役割を引き受けたタレントたちが珍妙な解答を連発するクイズ番組を見ていたとき、珍しくその時間に家にいた父親が苦々しく溢した言葉を覚えている。
テレビっていうのはすごい人がすごいことをしてみせる場所で、こんなズブの素人が出ていいものではないのではないか……
共感ができて、親しみがもてる、そういう素人っぽさを褒めそやして増長させる雰囲気への異議申し立てであったと思う。幼い僕もべつにその番組が好きではなかったので素直に、そうか、と思ったのではなかったか。当時テレビは権威であり、権威というのはしかるべき優れた能力に応じて付与されるものであってほしい。そんな気分がまだありえたのだか、すでに当時からして時代錯誤であったのか。そこまではわからない。
さて、日本という文化圏はとにかく素人に甘い。なんでもない一個人が、飾らない「ありのまま」の姿をカメラの前で曝け出すことにいまだにはしゃいでしまうようなところがある。ある対象をそのまま書くということの称揚はこうした素人好きと同根なのではないかと疑っている。とにかく全部そのままぶちまけること。それでプレゼンスを高めて階級上昇を達成すること。そこにはアンダークラスから身一つでのし上がるというヒップホップ的な価値観との近似が見出せるかもしれない。無産階級のやりくりとしての日記や随筆というのもこの延長線上に置けるだろうか。しかし文筆一本で食っていけるような状況はいまこの土地にはないではないか。あぶく銭のために自らをなるべくそのままに曝け出そうと努めること、その割に合わなさがまずなにより気になる。暴露系の書き手や表現者は、多くのばあい精神の不調に帰結する。目先の小銭のために長期的に心身の健康を損なうような高いリスクをとることはなるべくよしたほうがいい。これは書き手本人の意思決定を責める意図は断じてない。手ぶらの相手に対して、とにかくぜんぶ脱いでしまえば耳目を集めて成功できるかもしれないよと唆しておいて、てきとうに楽しんだあとは誰も責任をとらないこの社会の構造がなんとも嫌だなあと感じているという話だ。プロフェッショナルな芸への敬意がなく、自分たちにもできそうな素人芸を次から次へと使い捨てるような風潮。僕はこの幼稚さはとても悪いものだと考える。
日記や随筆のように書き手と作中主体が等号で結ばれがちなテキストが読み手に喚起する欲望というのは、窃視的な性格を帯びずにはいないだろう。現代において随筆や日記の持つ問題とは、書き手が生活や人格を素朴に言語化しているという仮定のもと、読み手の覗き見への欲望に奉仕するという構図にあるような気がする。芸の巧拙よりも演者本人への野次馬的好奇心の満足が優位に置かれるような構造。とってもやな感じだ。
私生活を欲望の対象として流通させるというのはどこまでも資本主義の論理に回収されていくだけである。これは人物や企業の過去の言動に不適切なものがあった場合、不買運動を起こすという近年のキャンセルカルチャー的なものとの関係も気になるところだ。作品と人格があまりにも近接し、いつのまにか僕たちは作品ではなく人格を購入しているかのような錯覚を素朴に受け容れてしまってはいないだろうか。
そもそもの話として、素材をなるべくそのままに記述するという考えそのものにすでに欺瞞が感じ取れる。ここには言葉というものの道具性への鈍感がある。目の前の事物をそのままに書き尽くすことなどできない。言葉と対象は別物だから当然だ。ほんとうの意味で嘘なくありのままに記述しようとするならば、早々に言葉の物質性を前にその不可能を思い知るだろう。事物の、なんともいえないあの感じを文字の配置で再現しようと格闘すれば、自ずと文章はゴテゴテしたり、難解になっていく。しかしそのような、言語化不可能な実感の近似値を記述によって制作しようという無茶な試みの成果――レトリックは、「ありのまま」感を評価する日記や随筆の現場では「嘘くさい」と敬遠されてしまうのではないか。随筆に対して「これはほんとうだ」と感じるとき、それはせいぜい読みやすいということでしかないことが多い。要は余計な装飾なしに、淡々と事実を記述してくれているというような錯覚を覚えているのだ。読み易くて、何が書かれているかするする染み入ってくるようだなあ、という読み心地は、事物そのものへの接近を意味しない。単純に予め予想できたり知っていたことから大きく逸脱しない文字列が書かれているというだけのことだ。リーダビリティへの盲目的な信頼と、それに伴う文飾の失効。これはまた、この数十年で中流階級が消滅していく状況と相関関係にあるかもしれない。貧しい状況では貧しいテキストしか生産されないのだろうか。僕はこれに否と言いたい。
(続きは、「文學界」2023年9月号でお楽しみください)