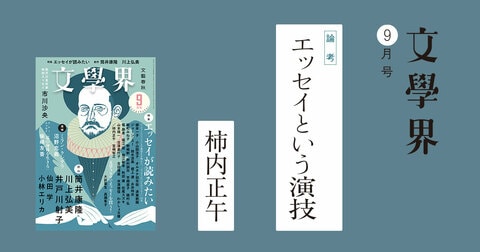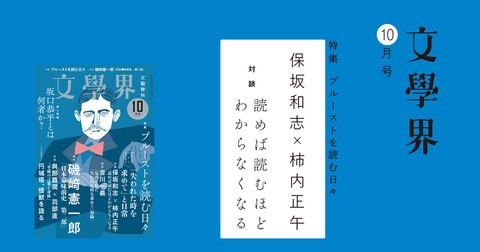ミラン・クンデラが七月十一日に九十四歳で亡くなった。亡くなったのはパリの自宅だが、生まれたのは一九二九年、現在のチェコ南部のブルノである。つまり彼はチェコ出身のチェコ人なのだが、フランスに亡命しフランスに帰化したという意味ではフランス作家でもある。彼を「チェコ出身のフランス作家」と見るべきなのか、「フランスに亡命したチェコ作家」と呼ぶべきなのか、いまだに批評家や研究者の間では揺れがある。
第二次世界大戦後から一九八〇年代にかけては政治的抑圧を逃れて旧ソ連・東欧圏から多くの作家・詩人たちが続々と西側に亡命した。ポーランドからは詩人のチェスワフ・ミウォシュ、ソ連からは小説家のソルジェニーツィン、詩人のヨシフ・ブロツキーなど。彼らの多くは共産主義体制に迫害されて亡命を余儀なくされたという「大きな物語」を引っ提げて西側に衝撃を与えたのだが、クンデラはそういった亡命作家たちの最後の大物だった。
一九六八年の民主化運動「プラハの春」がソ連の軍事介入によってあえなく潰されたあと、改革派の一翼を担っていたクンデラはチェコ当局からにらまれ、作品を一切出版できなくなった。そういう状況を逃れて彼がフランスに亡命したのは一九七五年のことで、ちょうどソ連から一九七四年に強制国外退去となったソルジェニーツィンが西側でセンセーションを呼んでいた時期と重なる。当時クンデラは、ソルジェニーツィンと並ぶ、東からの反体制作家の代表のように受け止められたと言ってもいいだろう。
実際、一九八〇年にフランスのテレビ局が彼の作品をめぐるパネル・ディスカッションを放送した時、ある批評家がクンデラの長編『冗談』(一九六七)を「スターリニズムに対する偉大な告発の書」と呼んだが、これに対してクンデラはとっさにこう反応したという。「いやはや、スターリニズムなんて、いい加減にしてくれよ。『冗談』はラヴ・ストーリーなんだから!」クンデラは自分の作品が政治的文脈の中で解釈されることを一貫してひどく嫌っていたし、まして彼は――ビロード革命の後に大統領にまでなった反体制作家ヴァーツラフ・ハヴェルとは違って――決して政治的な「反体制活動家」ではなかったのである。
そのことがよく分かるのは、クンデラの代表作『存在の耐えられない軽さ』(一九八四)だろう。時代は一九六〇年代後半。主な舞台となるのはチェコとスイスだが、背景にあるのは、チェコで「プラハの春」の後、共産主義体制に対して批判的な知識人への弾圧が強まっていったという歴史の流れである。このように『存在の耐えられない軽さ』は、チェコの重苦しい歴史を背景とはしているが、本質的には「柔らかな」愛の物語である。主人公トマーシュは二百人以上(!)の女性と関係を持ってきた色男。その彼に惚れ込み、嫉妬に苦しみながら、彼の「軽い」生活の重しとなる田舎娘のテレザ。そして、「存在の軽さ」に身を任せながら奔放な遍歴を続けて亡命者となる、トマーシュの以前の愛人で画家のサビーナ。読者の前で展開するのは、こういった魅力的な登場人物が時に引きつけあい、時に退けあいながら織りなしていく音楽のような世界に他ならない。そして、この音楽を通じて通奏低音のように響いてくるのは、政治的なメッセージでは決してなく、現代文明のあらゆる「俗悪なるもの」(キッチュ)を拒否するクンデラ独特の美学なのである。
その次の長編『不滅』(一九九〇)になると、クンデラはチェコの歴史を完全に離れ、パリを舞台に、あちこちに散りばめられたちょっとした挿話やイメージが意外なところで変奏されて互いに響き交わすような精妙な構成の名人芸を展開する。『不滅』の中で語り手自身が、「小説は自転車競走に似たものになるのではなく、たくさんの料理が出てくる饗宴に似たものにならなければいけない」と主張しているのだが、『不滅』こそはまさに小説の饗宴と呼ぶべき傑作だろう。
こういった小説を支えているのは、クンデラの確固たる小説観である。彼が常に意識しているのは、セルバンテスに始まりカフカやムージルに至る四世紀にわたる近代ヨーロッパ小説の発展の道筋であり、そして自分自身が中欧においてこの伝統を受け継ぐ者であるという立場から彼は、小説の精神と相いれないキッチュが蔓延する現代文明を批判する。クンデラによれば小説とは笑いの精神によって生み出された理性とアイロニーの芸術である。こうして本書の読者の前に現れてくるのは、ヨーロッパの文化に深く根ざし、時に時代に逆らってまでもその文化遺産を受け継ごうとする、先鋭的ながらも保守的な「ヨーロッパ人」の姿である。
クンデラはこういう立場に立って、自らをチェコという国の狭い歴史的文脈から解き放ち、ヨーロッパ文化という広い文脈の中に亡命するかのように、創作に用いる言語も『不滅』の後はチェコ語からフランス語に全面的に切り替えた。しかし、皮肉なのは、『緩やかさ』(一九九五)『ほんとうの私』(一九九八)『無知』(二〇〇〇)『無意味の祝祭』(二〇一三)といったフランス語で書かれた晩年の小説が、それ以前のチェコ語で書かれた作品を凌駕する魅力もエネルギーも獲得できなかったように見えることだ。やはり――少なくとも私にとって――クンデラはチェコを原点とする作家であって、チェコを捨ててフランス文学の中に亡命するのは容易なことではなかった。
(初出 「文學界」2023年9月号)