作家デビュー20周年を迎えた警察小説の第一人者・堂場瞬一さんが、オウム事件や和歌山カレー事件など難題の先頭に立ってきた伝説の科学捜査官・服藤恵三と語り合う。
堂場 はじめまして。今日は警視庁の科学捜査研究所で十五年間研究員を務められたのち、日本で初めて「科学捜査官」に任命され、数々の難事件と対峙された服藤(はらふじ)さんとお話しできるのを楽しみにしていました。
服藤 堂場さんはじめまして。ありがとうございます。
堂場 先日上梓された『警視庁科学捜査官 難事件に科学で挑んだ男の極秘ファイル』(文藝春秋)も拝読しました。地下鉄サリン事件をはじめ、和歌山カレー事件やルーシー・ブラックマン事件など一九九〇年代から二〇〇〇年代にかけてメディアを騒がせた多くの事件にかかわってらっしゃるんですね。まさに時代の生き証人というか。
服藤 依頼された鑑定や捜査をコツコツやってきて、振り返ったら多くの事件にかかわっていたというのが率直な感想です。私は科捜研時代から毒物や薬物事件を専門としていたんですが、バブルがはじけたあと、そういったものを使用した犯罪が増えたんですね。
堂場 僕は八〇年代から九〇年代にかけて新聞社で記者をしていたんですが、おっしゃる通りバブル後に犯罪の質が大きく変わった印象があります。不景気が襲ってきた結果、日本人全体のメンタリティも変質したのではないかと。たとえばオウム事件のような、一歩間違えば国家が転覆してしまったかもしれない犯罪って、八〇年代ではあり得ないと思うんです。極左グループでも、無差別な殺人はやってこなかったわけで。
服藤 オウム後も和歌山カレー事件など、従来なら「ここまでやらないだろう」という犯罪が平気で起こるようになりました。個々の事件で感じるのは、振り込め詐欺などもその典型ですけど、「自分のことが中心」という世の中になったと思います。モラルや道徳が消えていって。
堂場 やはりバブルの崩壊によってお金の価値観が変わったことに引っ張られたのでしょうか。インターネットの登場というトピックスも、これに近い時期に起こりましたし。
服藤 ちょうどオウム事件の頃からインターネットが発達したのも犯罪に大きな影響を与えていると思います。海外のネット上では、どうすればサリンを効率的に生成できるかなどの情報がオープンになっていたんですが、当時の日本人の多くはそんなこと全然知らなかった。
堂場 ネットと犯罪って、なぜかすごく相性がいいんですよね。八〇年代にも、盗品を売りさばくのにパソコン通信を使っていた事例がありました。誰でも利用できるということで、犯罪の垣根を下げてしまっている。
服藤 難しいのは、警察組織は発生事後にしかそれらに対応できない。つまりいままでの経験になかったことが起こったときに、準備ができていないと適切な捜査を行えないわけです。
堂場 具体的にどういった準備をするんですか?
服藤 オウム事件では化学兵器や銃火器が製造されました。これからは化学だけではなく電気電子や機械工学の専門家が必要となるだろうということで、民間からも人を集めて色んな分野の科学捜査官を作ったんです。私も参画したんですが、というのも、警察という組織では被害届が出されてから起訴するまでにどういう手続きや書類が必要かというのを知らなければ有効な捜査が行えない。科学に詳しいだけでは捜査はできないので、私みたいに元々捜査員ではなかったけれど組織にいた人間が先頭に立ちながら結果を出し、ノウハウを蓄積することが必要だったんです。
堂場 結局それって、人材育成の話ですよね。私も記者時代に取材していたから分かるんですけど、警察の世界って、技官以外は基本的に文系の人間の集まりじゃないですか。
服藤 そうかもしれません。だから、かつては数少ない理系の警察官をピックアップしたり、文系出身でも理系分野に興味を持っている人間を見つけて教育していました。警察という組織は警視庁だけでも四万人以上の職員・捜査員がいて、教育制度が非常に整っている。大事なのは、常に新しい知識を得ながら現場に出て経験を積むことだと思います。
堂場 ただでさえ警察官は忙しいのに勉強もしなくちゃいけないなんて、本当に大変な仕事だと思います。服藤さんの本を読んで最初に思ったのは「あなたたち、仕事しすぎだよ」ってことでした。
■事件は減った?
堂場 本に出てきた事件で個人的に興味深かったのが、二〇〇〇年の年末に発生した世田谷一家殺人事件でした。というのも、被害にあわれた宮澤さん一家の近くに当時、僕も住んでいたんですね。あれがなぜ未解決のままなのか、本当に謎なんですよ。
服藤 本にも書きましたように、私がかかわったわけではないのですが、初動がダメだったと言われています。資料はたくさんあったんですが……。
堂場 ブツの洪水状態ですよね。

服藤 詳しくは言えないんですが、初動捜査で詰めなきゃいけないことを、詰めきれてなかったということに尽きると思います。私は昔から政治家の後藤田正晴先生にお会いしていたんですが、当時お目にかかると開口一番「世田谷の事件はなんで捕まらんのじゃ」と言われました。続けて「警察の力はここまで落ちてしもたんか」とまでおっしゃられて。
堂場 後藤田さんは官僚時代、警察庁長官まで務めた方ですから。
服藤 やはり未解決にしてはいけない事件でしょうね。反省して次につなげなければなりません。ちなみに最近は事件そのものが減っているんですよ。私が捜査一課で係長や管理官をやっていた頃は特別捜査本部事件は年間二十から三十件あったのが、いまはひと桁です。
堂場 認知件数がそもそも減ってますし、最近は家族間の殺人事件が増えて、発生してもすぐに解決してしまうという事情もありますからね。じゃあ、多少は警察官の方も楽になっている?
服藤 そうなんですけど、経験が積めないから、刑事の捜査能力が伸びていかないんです。
堂場 ああ、現場で深夜まで頑張る経験があるのとないのとでは全然違ってきますか。
服藤 堂場さんもそうでしょうけど、人生のある時期、死に物狂いで何かをやって取り組んだ人と、そうでない人は生き方が全然違ってくると思うんです。
堂場 耳が痛いです(笑)。おそらく世の中の九〇%の人って、そんな大変な経験はしないんですよ。とりあえず普通に就職して、流されるように仕事をしてという感じで。僕自身、そういう生き方だったので。
服藤 いやいや、堂場さんは新聞社で働きながら小説家デビューもされて、それを両立されたというのは、死に物狂いで取り組んでこられた方ですよ。
堂場 いやあ、人生のターニングポイントはいつだったかって聞かれることがあるんですが、自分の中では正直そんなものどこにもないって感じなんですよね。シームレスに生きてきたから。服藤さんの場合は、やはりオウム事件に携わったときですか?
服藤 オウム事件は二度目のターニングポイントでしょうか。最初のターニングポイントは、科捜研に入ったものの挫折して、博士の学位を取るために大学で再び勉強したときです。
堂場 科捜研の主任昇任試験に二年連続で落ちてしまい、腐ってしまわれたんですよね。それをきっかけに科捜研の仕事をしながら東邦大学の医学部で勉強されたとか。
服藤 いまは仕事をしながら大学院で学べるコースもありますが、一九八〇年代はありませんでした。ただ、東邦大学医学部薬理学教室で出会った伊藤隆太教授が、「君は公務員で給料も少ないだろうから、今日から僕の無給助手だ」と、学費を取らずに勉強させてもらったんです。

堂場 結果、博士の学位を取得されるんですよね。
服藤 ええ。ただ、学位を取りたい取りたいと焦っていた私は、ある日伊藤先生から「博士は取ったら終わりではなく、そこから始まるんだ」と叱られたんです。以来、なんとか社会のために貢献しようと思うようになりました。もし伊藤先生のもとで勉強して毒物の専門家になっていなければ、オウム事件が起きた際に声もかからなかったでしょう。
堂場 それは大きなターニングポイントですね。いまお話を聞いて、自分の場合、記者時代に身体を壊してしまい、異動させてもらった時が転機になったかなと思い至りました。それで時間ができて小説を書くようになったんです。
服藤 身体を壊すくらい働いてらっしゃったんですね。警察官でもそうやってがむしゃらに働く世代というのは昭和の中頃生まれの人に多かったです。私も同じようにがむしゃらな時期があったからこそ、様々な事件を任されるようになりました。おかげで退官した現在も、経験を活かして、広域技能指導官という役目をいただいて全国の警察官にノウハウを伝えているんです。
堂場 ただ、捜査技術って、聞き込みや自供を取るなど、マニュアル化できない職人芸が多くないですか?
服藤 言葉だけではどうしても伝えられません。一緒に経験しながら、個人個人が自分の手法を見つけていくしかないんです。
堂場 僕は服藤さんの本を読んで、科学捜査の将来に関しての見通しは明るいんじゃないかと思いました。というのも科学的に捜査したものは記録に残る。だから今後も積み重ねることによってどんどん蓄積されるんじゃないかと。
服藤 私は逆に不安なんですよ。今後5Gをはじめ、様々な新しい技術が出てくるなかで警察では解析できない、犯罪に利用できる高度な技術が出てくる可能性があります。もしかしたら既に登場していて、警察がいまだに発生にすら気づいていないかもしれない。
堂場 たしかにあり得ますね。
服藤 常にそういう可能性があることを捜査員ひとりひとりが念頭に置いて仕事することがより大切になってきています。警察内でも「情報を取れ」と言う人はいっぱいいるんですけど、取っただけではダメで、それを解析したり自分の頭で考えて物事を構築していかなければいけない。
堂場 言われたことをやるのは楽なんですよね。でも、新たなことを考えるというのは、警察に限らず、どんな業種でも一番難しいことだと思います。
服藤 個人の資質が大きく関係してきますよね。本の中で、イギリスのプロファイラーのデヴィッド・カンター教授とのエピソードを書きましたが、彼が言っていた「センスは天命である」というのはほんとにその通りじゃないかと思います。
堂場 そう言われちゃうと教育だけでは難しいですよね……。
服藤 そしてセンスがあったとしても、組織を俯瞰的に見られないと活かせない。警察組織でいうと、警視になってはじめて警視総監に直接決裁を仰ぐことができるようになり、各部とも折衝がしやすくなるんです。つまり、刑事課長や副署長を経験していくことで幅が広がって、センスが開花していく。全体像がわかると、どこに問題があってどうしたらいいのかというのが見えて、組織をより良いものに改革できるようになるんです。
堂場 僕ら日本人は「現場で刑事一筋三十年」みたいな方をすごく尊敬してしまうんですけど。
服藤 もちろん、そういった方は組織の宝ですし、絶対に必要な人材です。
堂場 加えて、鳥の目を持つ人間をどう育てていくかが今後の課題なんですね。
■本職から見た警察小説
服藤 本日お目にかかるにあたって堂場さんの新刊『赤の呪縛』(文藝春秋)を拝読しました。ひとつの放火事件がきっかけとなって、大きな闇が暴かれていく警察小説で、すごく面白かったです。「次どうなるんだろう、次どうなるんだろう」とワクワクさせられました。
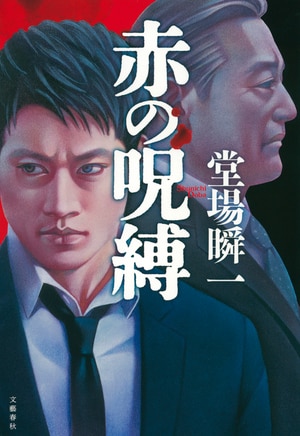
堂場 ホッとしました。警察小説を書いている身として、現役の警察の方やOBの方に読まれるのが一番怖いんです。特に警察官の動きはリアルに描きたいと思っているので、「今はこんなことしないよ」と言われると、謝るしかありません(笑)。
服藤 いえいえ(笑)。読んでいて情景が鮮やかに映像で浮かんできましたよ。たとえば序盤の火事現場で、消火のホースが出てきたときに……。
堂場 ホースが道路上でうねり……と表現したところですね。
服藤 はい。私は火事現場に何度も行ったことがありますが、現場に向かうときによけながら歩かなきゃいけないんですよね。そういった情景を一瞬で思い出しました。あと、火事場って結構湿気があって、においも独特じゃないですか。そういった細かいところの描写力も素晴らしいと思いました。
堂場 私も記者時代に火事現場にさんざん行きましたから。
服藤 警察OBとして気になったところがあるとしたら、視点人物が観ている景色でしょうか。警察関係者って、事件に関連したものを見つけようという習性があるので、実は全体の情景って頭の中に残らないんですよ。
堂場 なるほど。それは記者的な視点が入っているのかもしれませんね。ただ、個人的にすごく視野が広い刑事がいたらどうなるんだろうということに最近は興味があるんです。おっしゃる通り、普通刑事は余計なものを見ないようにするけど、それが見えちゃう人がいたらどうなるのかなと思って。
服藤 ああ、それは面白いですね。
堂場 主人公の刑事・滝上のように、上司に対して嘘の報告をして独自に動く人間というのはなかなか現実にはいないでしょうね。
服藤 いまはほとんどいないと思います。ただ、昭和の時代はいましたよ。上司に別の報告をしても、自分の考える方向に走って捜査をする人間が。そういう刑事は結果を出してくるんですよね。
堂場 勝手に動く人間のほうが、当たったときは大きな手柄を挙げますからね。ただ外れるときは大外れというケースもあるからなかなか難しい。
服藤 これは持論なんですが、私は自分のチームの中に、きちんと反論できる人を必ず入れたいと思ってやってきました。イエスマンばっかりだったら、必ずその組織は失敗するんです。
堂場 それはあらゆる上司が欲しい人材ですよ。なかなか居ないんですけど。
服藤 私がかかわっていた平成の初期の捜査一課にはそういう人間がいたんですよ。会議でも管理職に食って掛かるような。彼に対して上司がちょっと注意したところ、「階級で事件の捜査をやるんだったら警視総監を連れてこい。そうすればみんな解決するだろ」と言い放ったんです(笑)。
堂場 いい話ですね(笑)。捜査一課はそうあってほしい。僕は小説では人間のエゴを描きたいなと常々考えてまして。
服藤 エゴですか?
堂場 はい。自分の仕事を全うするために余計なものがあれば排除するし、場合によっては人の邪魔だってする。手柄を立てることって自己満足でしかないけれど、実際のところ他者のために仕事ができる人ってほとんどいないとも思うんですね。だから僕の小説にはエゴ満載の刑事が登場してしまうんです。また、そういう人のほうが求心力があったりしますし。
服藤 エゴにつながるかは分かりませんが、刑事の場合、事件の裏には必ず被害者がいるわけです。結果を出すことは被害者のため、あるいは同じような犯罪を起こす人間を絶つことに繋がります。そこに自己満足や自己実現を感じながら生きている刑事はたくさんいますよ。
■公務員人事は書きにくい
堂場 『警視庁科学捜査官』の後半は、服藤さんがよりよい捜査のために組織を改革していこうとするけど、抵抗にあう様も書かれています。なかなか辛かったのではないですか。
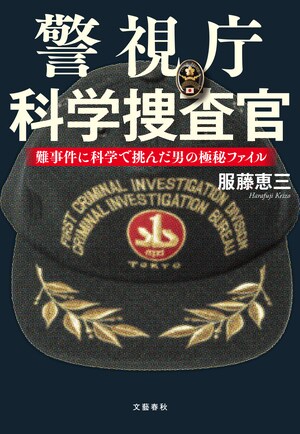
服藤 (苦笑)
堂場 警察に限らず、組織をいじろうとして声を上げる人って、だいたいひどい目に遭うじゃないですか。
服藤 そうですね。これまでの環境が心地よいと思っている人がたくさんいるし、その中である程度結果を出してきたという自負を持っている人は、「どうして変えなければならないんだ」となる。
堂場 服藤さんは上司にはすごく恵まれてきたと思うんです。「とにかくやってみなさい」という人がほとんどで。ところが、服藤さんの立場が上がってくると、足を引っ張ろうとする人が出てきて。
服藤 日本の社会って不思議で、ポジションが低いうちは軋轢が少ないんです。ただ立場が上になると、こちらはそう思っていなくても、自分のことをライバル視して邪魔をしてくる人間が出てくる。私は科学捜査官だったので、どちらかといえば捜査を指揮する人間のサポートができればと考えていましたし、だからこそ皆と同じ目的に向かって進めると思っていたんですが……。
堂場 想像ですけど、下にいるうちは「服藤って便利なやつだな」くらいに見られていたんだと思います。ただ、階級が上がっていくと警戒される対象になってしまった。特に警察官は人事をすごく気にする組織じゃないですか。
服藤 振り返ってみると、私自身にも問題があったと思うんです。良かれと思ってやってきたことですが、反発する人に対してもう少し丁寧に対応するべきだったなという場面が多々あって。
堂場 そこで理系と文系の壁ってありませんでした?
服藤 ありましたね。
堂場 「名張毒ぶどう酒事件」の章を読んでそれを感じました。服藤さんは昭和三十六年に起こった事件の再審請求にかかわっていて、非常に熱心に取り組まれてましたよね。他の事件とは熱の入り方が違う感じがしました。その後の組織内での服藤さんの処遇も悲しいものでしたが、あの章では説明がかなり専門的になっていて、文系の人には伝わりづらかったんじゃないかと。僕も調べながら読みましたが、理解できたかどうか。
服藤 私もあの部分を読み直してみて、もうちょっと丁寧な書き方をしたほうが良かったなと感じました。
堂場 つまり、理系の方は数式で説明したほうが確実だし早いと考えるでしょうけど、文系の人間からすると「分かる言葉で言ってくれよ」という思いがどうしても出てしまう。そういった部分で壁があって、服藤さんがどれだけきちんと仲間に説明しても理解されにくかったんじゃないかと想像してるんです。
服藤 なるほど、そういう意味でしたか。
堂場 僕も小説の中で天才的な分析官を出してみたいと思うときがあるんだけど、必ず最後は数式を出さざるを得なくなる。でもそれを書くと、多くの読者にとって読みにくいものになってしまうんですよね。自分が理系の人間を書けるとしたらプロファイラーくらいかな。プロファイリングは一種の統計学だから数式があまり必要ないし。
服藤 そうかもしれませんね。日本の場合は地理的プロファイリングが一番伸びる可能性があると思っています。
堂場 本の中でも、同一犯と思われる事件が複数の場所で多発した際、現場を繋げてそこから等距離の地域に犯人が住んでいる可能性が高いと考えて実際に逮捕できたという話がありましたよね。あれは非常に面白かったです。
服藤 (笑顔で)それは良かった。
堂場 お話ししているように、『警視庁科学捜査官』の後半は、組織と人事のシビアな話がたびたび出てきますが、実は警察小説でその手の話って書きづらいんです。企業小説だと人事抗争の話が好まれるんだけど、公務員の場合は実像が外に出てこないこともあって、リアルなものを書くのが難しいと思います。分からないなりに公務員の人事をフィクションで描くとキャリア官僚同士の暗闘みたいな話になりがちで、現場の方の話はなかなか書けなかった。そういう意味でも、こういう形で経験を本に残して下さるのは資料的価値も含めてありがたいです。もちろんこの二十年くらいの科学捜査の最前線も分かりますし。
服藤 ありがとうございます(笑)。
堂場 これから理系の勉強をし直して、自分の小説に取り入れていければいいなと思いました。
服藤 少しでも科学捜査のことを知っていただけて嬉しいです。もう警察だけでは対応できない時代が来ていて、実際に警察は企業と協力して、捜査のための資機材やソフト、手法の開発などをやっているんです。私は既に現役の警察官ではありませんが、官と民が一緒になって共同で色んなことができるような仕組みづくりのお手伝いができればいいなと考えています。そのためにも思い切った情報の開示から始めなきゃいけないでしょうね。
堂場 今回のご執筆も、ある意味その一環なわけですね。
服藤 あとは漫画なりイラストを使った本なりで、子どもたちに鑑識のことなど警察の仕事について教えられないかと考えています。自分では描けないので、どなたかの力をお借りして。
堂場 さっき天才的な分析官を小説で書くのは難しいという話をしましたが、実は映像や漫画といったビジュアルで見せると分かりやすいんですよ。
服藤 そうですよね。今後チャンスがあれば映像などもぜひやってみたいです。
堂場 服藤さんのように、色んな困難な状況がある中で、それを変えていこうとする方がいらっしゃるので、僕はそういった姿をきちんと小説に残していきたいと思いました。僕は今年でデビュー二十年なんですが、長く書くということはそれだけ時代に寄り添っていくということになる。テーマは変わっても、世の中の動きをちゃんと見て小説という形で記録に残していきたいですね。
服藤 楽しみにしています。

どうばしゅんいち 一九六三年生まれ。二〇〇〇年「8年」で小説すばる新人賞を受賞。警察小説の旗手として知られる。『赤の呪縛』など著書多数。作家デビュー20周年の記念イベントなどは公式サイトへ。
はらふじけいぞう 一九五七年生まれ。東京理科大学卒業。警視庁科学捜査研究所研究員を経て、初代科学捜査官に。著書に『警視庁科学捜査官』がある。




















